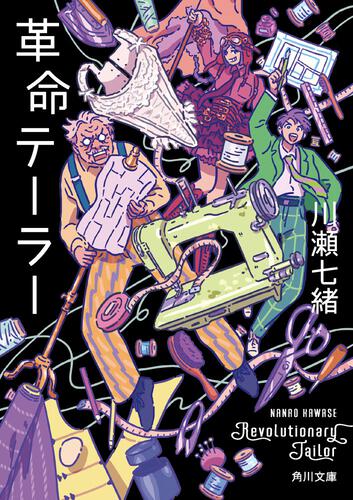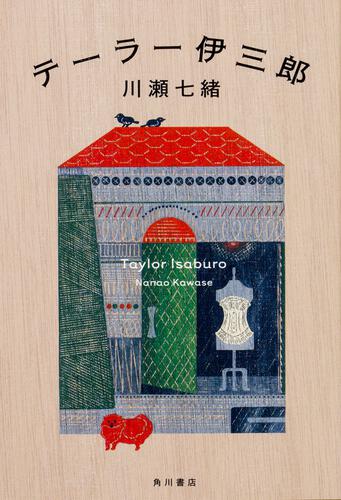3月1日に刊行された川瀬七緒さんの書き下ろし長編小説『四日間家族』。帯の「徹夜必至」という言葉どおり、圧倒的一気読み小説だと評判になっています。
好評御礼企画として、第一章「最悪への扉」を全文公開!
『四日間家族』第一章公開#03
3
ざわざわと木々が風で揺れる音に混じって、時折り甲高い音が耳に届けられる。気のせいではなく、どこか逼迫を感じさせるような抑揚だ。動物の鳴き声? わたしは窓に顔を近づけ、不安定な音に集中した。こもったような音は途切れることなく続いており、どことなく不気味な響きがある。さらに意識を向けようとしたが、どうにも長谷部のがらがら声が邪魔でわたしは小さく舌打ちした。
「ひきこもりの甥はな、俺にだけは心を開いてんだ。要は男親の愛情に飢えてんだな。あいつも俺がいなくなりゃあ、はっと気づくことが……」
「静かにして」
わたしは誇張されているであろう長谷部の話を遮った。
「外から声がする」
わたしがじっと耳を澄ますと、怪訝な顔の長谷部と千代子は話をやめて動きを止めた。風が草木をなぶる音がことのほか大きく感じる。どこかから飛ばされてきた葉っぱがフロントガラスに当たった。音は無機質なものがほとんどだが、また不安定な節のある声が微かにまぎれ込んでいた。
「ほら、今聞こえたでしょ?」
「ああ? 風の音しかしねえよ」
長谷部と千代子は同時に首を横に振った。
「いや、聞こえるんだって。ちょっと気持ち悪い叫び声みたいなものが」
そう言ったとき、隣で陸斗が「確かに」とつぶやいた。
「ホントに聞こえてんのか? 今さら死ぬのが怖くなって幻聴でも聞いてんだろ」
「幻聴じゃない。年寄りには聞こえない周波数なのかもしれない」
陸斗の真面目な切り返しに、長谷部は唇を歪めて腹立たしさを表現した。わたしは少年に目を向けた。
「それほど遠くはないように聞こえるんだけど」
「うん、わりと近い。ネコの鳴き声に聞こえる。さっきの危険運転女、もしかしてネコを捨てにきたのかも」
ペットショップや悪質なブリーダーが売れ残った動物を持て余し、捨てているという動物虐待の嫌な記事を読んだことがある。しかし、動物の声には聞こえなかった。
「よく聞いてみて。わたしには赤ちゃんの泣き声に聞こえる」
自分で言っていながら背中がぞくりとした。さっきの女は赤ん坊を捨てにきたのではないのか。黒いリュックサックに入れて、山の中に置き去りにした?
みな耳をそばだてて押し黙った。そしてしばらく経ったとき、わたしの隣で陸斗が口を開いた。
「言われてみればそうかもしれない。赤ん坊だ」
「ちょ、ちょっと、本当なのかい? うそはなしだよ。間違いなく赤ん坊なのかい?」
千代子が体ごと後ろを向いて問い、わたしと陸斗は無言のまま頷いた。
「……まいったな」
長谷部がごま塩の角刈り頭を撫で上げると、千代子は慌てたように声を上ずらせた。
「たいへんじゃないか! 今は五月でいい陽気だけども、夜はまだまだ冷えるんだぞ! 今すぐ助けなきゃ命にかかわるよ!」
「まあ、本当にガキが捨てられてんならそうするしかねえだろうが」
「待って」
目張りしたテープを剝がしにかかっている二人に、陸斗は淡々と声をかけた。
「これから死ぬんだから、助けても意味はないと思う」
「何言ってんだい! こんな真夜中の山ん中で、赤ん坊が必死になって泣いてんだぞ!」
千代子が長谷部に目配せをすると、男も即座に加勢した。
「おまえは本当に血も涙もねえガキだな。俺らは死にたくて死ぬが、捨てられた赤ん坊は生きてえから泣いてんだ。これを見捨てられるようなやつは人間じゃねえ」
「まったくだよ! あんたもそう思うだろ?」
千代子が急に話を振ってきた。この二人が言っていることはしごく真っ当だが、手放しで賛成できない気持ちがある。わたしは後れ毛を耳にかけて顔を上げた。
「正直言って、面倒っていう気持ちのほうが大きい」
「正気かい? あんた、女のくせに赤ん坊を見殺しにするつもりか?」
「いや、助けてあげるべきだとは思う。でも赤ちゃんを保護したら警察へ行かなきゃならないし、事情聴取とか現場検証とかいろいろあるでしょ。それに、なんでここに四人で集まってたのか聞かれるよ。単純に考えてめんどくさい。なんせ未成年もいるからね」
隣にちらりと目を向けると、陸斗は長めの前髪に触れながら口を開いた。
「僕はこの車に自分の意志で乗ったけど、保護者の許可がない。こういう場合、世間一般では未成年者略取になるみたいだよ」
他人事のような言葉を受けて、二人は一瞬だけ口を閉じた。が、すぐ赤ん坊を見捨てるなどできないという結論に達した。当然といえば当然で、わたしも進んで小さな命を見捨てたいと思っているわけではない。ただ自分のことだけでせいいっぱいなのだった。
それから四人は窓に貼られたテープを剝がして車の外に出た。西からの乾いた風が吹き荒れ、久しぶりに吸った新鮮な空気が現実に引き戻してくる。雲ひとつない夜空にはわずかに欠けた月が浮かんでいるのが見え、急に息苦しいほどの切なさが込み上げた。雑多な感情があふれ出す前にこの世を去る計画だった。それなのに、よりにもよって赤ん坊という最高に厄介な存在にかかわろうとしていることが信じられない。
わたしは気持ちを切り替えようと土や木々の匂いを胸いっぱいに吸い込み、スマートフォンのライトを点けて木立のほうを照らした。陸斗も同じようにスマートフォンを森に向けており、風に乗って届けられる弱々しい声に耳を傾けていた。長谷部はダッシュボードから取り出した錆だらけの懐中電灯を点け、木々の間に光をまっすぐ向けた。
「さっきの女が入ってったのはここだな。俺は工場でパンチプレスの騒音を何十年も聞いてっから、耳がイカれてんだ」
長谷部は耳に手を当て、声のする方向を探っている。ここからでは赤ん坊の姿は確認できないが、そう遠くはないはずだった。わたしの隣では、頭二つぶんほど小さい背丈の千代子がしきりに足許を気にしている。見れば、黒いスパンコールの縫いつけられた五センチはありそうなヒールを履いていた。
「その靴で森に入るのは無理ですよ」
当然のことを指摘するなり、千代子はかぶりを振った。
「こんなとこにひとりで残されるなんて薄気味悪くてたまんないよ。外灯ひとつありゃしない」
わたしは千代子の全身に目を走らせた。靴もそうだが、ドレスと見まごうばかりの丈の長いワンピースが強風を受けてはためいている。なぜこのなりで森へ入れると思うのか。説得するのもばからしくなったとき、後ろから感情のない陸斗の声がした。
「これ以上ないほどの足手まとい」
わたしの気持ちを的確に代弁してくれた。すると長谷部はハイエースのドアを開け、腰を屈めて汚れた長靴を取り出した。千代子のほうへ無造作に投げてよこす。
「これに履き替えろ。それにそのひらひらの服。木に引っかかって破れても知らんぞ」
そして陸斗のほうへ向き直る。
「はっきりさせておく。リーダーは俺だ。すべての決定権は俺にあるから覚えておけ」
「……リーダー」
「この会の発起人も俺だし車を出したのも場所を決めたのも俺だ。そもそも、年長者の男が場を仕切るのは常識だ。おまえらは黙って従ってりゃいいんだよ」
長谷部は顎を上げてすごんで見せた。この状況下で、お荷物にしかならない老女を連れていくと宣言するリーダー。しかも、千代子自身の負担になる事実をまるで考えてはいなかった。信じられないことに、長谷部はこれを決断力や優しさだと履き違えている。自社が経営難に陥ったのも、ウィルスのせいだけではないようだ。
わたしは次々と噴出する問題の多さにため息をついた。ここに集まった四人の相性は稀に見るほど最悪だ。みなを結びつけていた命を絶つという目的も、この面子で達成できるのかと問われれば疑問だった。
長谷部はふんぞり返って存在感を示してから、さっと翻って森へ足を向けた。少年は男の後ろ姿をしばらく見つめ、あいかわらず無表情のまま木々の間に入っていく。そのすぐあとに千代子が続き、わたしは後ろからのろのろとついていった。
車を駐めた空き地も目が利かないほどの闇だったが、雑木が繁る森はその比ではなかった。スマートフォンのライトはせいぜい五十センチ先ぐらいまでしか届かず、体の左右には暗幕が張られているかのような圧迫感がある。加えて土の上には枯れ葉が積もり、脚を一歩出すたびに沈み込んでバランスを取るのが難しいほどだった。長靴に履き替えたとはいえ千代子はたびたび脚を取られ、木にぶつかりそうになっていた。
「長靴が大きすぎて抜けそうだよ。そのうえ息が切れてね。あたしは狭心症で血管にステントを入れてんだ。それほど距離もないだろうからおぶってくれないかい?」
千代子はいささか大げさに肩で息をし、眉尻を下げた弱々しい面持ちでわたしの顔を見つめた。だから待っていろと言っただろう。その言葉はすんでのところで吞み込んだけれども、大丈夫ですか……などという気遣いをわたしは見せなかった。千代子には助けてもらって当然という態度が見え隠れしているし、心優しい気配り上手と見せかけて実際のところはかなりの傲慢かつ強情だ。どこか小馬鹿にした態度でわたしを下に見ているのは思い違いではないはずだった。
わたしは顔色ひとつ変えずに口を開いた。
「行くと決めたんなら自力で歩いてください」
千代子は浮かべていた弱々しい笑みを消してたちまちむっとした。
「目の前で年寄りが苦しんでるのにその言い種とは、恐ろしい女だよ。あんた、嫌われ者だっただろ。思いやりの欠片もない」
千代子は悪態をついた。車にいたときとは顔つきもまるで変わっており、たるんだ瞼の下にある目には激しい敵対心があった。
「その若さで死ぬしかなくなるなんてのは、よっぽどの毒婦なんだろう。女なら、どれほどの醜女だろうがひとりぐらいは助けてくれる男がいるもんだ。それもいないなんて、女としてなんの価値もない」
「それが本性なわけですね」
わたしは冷ややかに千代子を見下ろした。
「七十三になっても若い女に対する嫉妬がある。そう見えるけど間違ってます? わたしなんて孫ぐらいの歳だろうに、同じ土俵に立つ気満々で正直ぞっとした」
「うるさい! 初めからあんたは目障りなんだ! 若いってだけで勝ち誇った顔しやがって! おとなしそうな素振りをしてるが、ホントはろくでなしの売女だろ!」
ここまで真正面からの罵声というのは初めての経験だ。ことのほか気性の激しい千代子に探るような目を向け考えたが、すぐに納得する答えが見つかった。
「たぶん、あなたはいわゆるオタサーの姫なのかな。男にちやほやされるのに慣れている。長年のスナック経営はまさにそれだったはずだしね」
千代子はくすんだシワだらけの顔に疑問符を浮かべた。
「説明はややこしいからパスするけど、あなたの気持ちはわかりますよ。でも、死に際まで引きずることじゃない。じゃあ、そういうことで」
「待ちなよこの性悪女! 見捨てる気か!」
「正直、あなたのことは最初から見捨ててる」
わたしはそう言って踵を返し、木につかまりながら緩やかな小山を上りはじめた。後ろから千代子のわめき声が聞こえているけれども、上るよりも戻るほうがはるかに楽なはずだ。それからは真っ暗な木立の間を大股で歩いていったが、先ほどから赤ん坊の泣き声は聞こえなくなっていた。歩くペースを上げると、少し先に明かりが見えてくる。男二人は上り坂の途中で立ち止まっており、ライトを周囲へ向けていた。
「赤ちゃんは?」
ようやく追いついて声をかけると、長谷部が振り返ってすぐ訝しげに反問した。
「ばあさんは?」
「見捨てた」
とたんに、今まで表情を動かさなかった陸斗が噴き出した。
「鬼だ」
「だれが考えても戻ったほうが安全でしょ」
仏頂面の長谷部に目をくれ、わたしは話を戻した。
「それより赤ちゃんは?」
上がった息を整えながら問うと、長谷部は小さく舌打ちしてから首を横に振った。
「気配がねえ。この辺りから声が聞こえたはずなんだがな。さっきからうんともすんとも言わなくなっちまってよ」
わたしも周りにスマートフォンのライトを向け、赤ん坊らしき影を捜した。
「もっと奥にいるのかも」
「それはない」と珍しく陸斗が即答した。「あの女が山に入って出てくるのにかかった時間はだいたい十分。片道五分としたら進める距離は三百メートル未満。これより奥には行ってない」
わたしは暗がりのなかで少年の顔を凝視した。陸斗は時折りすべてを見通したようなことを言う。口先だけの言葉とは違って自信が透けて見えるものだから、なおさら警戒心が煽られるのだ。
わたしはしばらく陸斗を窺っていたが、少年はそれをかわすように周囲へ目を向けた。それに倣って自分も捜索を開始した。しかし、ライトの届かない繁みがあまりにも暗すぎて、捜し終えた場所すらわからなくなるようなありさまだ。緩やかな傾斜があるから帰り道はかろうじて判別がつくが、視界が利かずに方向感覚はすでになくなりはじめている。しかし陸斗だけは先ほどから同じ場所にしゃがみ込み、そこから動こうとはしなかった。
「おい、ガキ。さぼってんじゃねえぞ。さっさと上のほうを見てこい」
陸斗は今にも地面に顔がつきそうなほど近づいており、ライトで落ち葉の隙間を照らしたままくぐもった声を出した。
「地面についた新しい足跡はここから上には行ってない。たぶん、赤ん坊がいるのはこっから左側のほう」
「おまえなあ、さっきから適当なことぬかしてんな。枯れ葉がこれほど積もってんのに、人の足跡なんざ残るわけがねえだろうが」
すると陸斗は立ち上がり、華奢な肩をすくめて見せた。
「足跡って地面にべったりとついてるものだけじゃないから。湿った枯れ葉は、踏まれると葉っぱの繊維が潰れて少しだけ表面が滑らかになる。光を当てると、微妙に光って見えることがあるんだよ。この辺りは雑草とか葛にもかきわけたような跡が残ってる」
長谷部はせせら笑ってはなから相手にしなかったけれども、わたしは陸斗の言葉が口からでまかせだとは思えなかった。夜の森をあてどもなく捜しているわたしや長谷部とは違い、みずから導き出した予測のもとに捜索範囲を絞っている。相当の自信がなければできないことだった。
わたしは翻って陸斗に近づき、彼が探っている方向へスマートフォンのライトを当てた。彼は斜面の左側を重点的に捜索しており、そこらじゅうにはびこっている葛をむしり取っている。そしてほとんど寸刻みで斜面を移動していた陸斗は、青々と葉を繁らせた巨大なミズナラの木の脇でびくりと肩を震わせた。
「これ……」
陸斗はヘビのように飛び出した根っこのあたりを凝視している。わたしも近づくと、おびただしい葛の葉に埋もれるような格好で、黒いリュックの背負い紐が見えた。陸斗はゆっくりと立ち上がり、若干怯んだような顔を向けてくる。
「……リュックのファスナーが閉まってる。声も聞こえないし動きもない。もう生きてないかも」
生きていない? その言葉を聞いてよろめいたとき、わたしを押しのけるようにして長谷部が脇を走り抜けた。
「見つけたのか? おまえら! 何ボケッとしてやがんだよ!」
突き出たビール腹を揺らして、リュックの脇にどすんと膝をつく。そして険しい面持ちのまま滑りの悪いファスナーを開けはじめた。初めて見せる真剣なまなざしは、今までの印象をがらりと変えるほどの迫力があった。
長谷部は、なかなか開かないファスナーの引き手を太い指でつまんだ。
「五分ぐらい前まで泣いてたんだ。まだ死んじゃいねえ。子どもってのは見かけによらず強いからな。大丈夫だ」
自身に言い聞かせるようにそう言い、長谷部は少しだけ開いた隙間にむりやり太い指を突っ込んだ。そして力まかせに開いた瞬間、わたしたち三人は同時に動きを止めた。
そこには本当に乳児の姿があった。水色の産着を着せられ、バスタオルがぞんざいにかけられている。想像していたよりもずっと小さく、まるで赤ん坊を精密に象ったビスクドールのようだった。
わたしはぴくりとも動かない赤ん坊を見て及び腰になっていたけれども、長谷部はごくりと喉仏を上下させ、リュックの周りに繁っている葛を無造作に引き抜きはじめた。続けざまに動かない赤ん坊を抱き上げ、枯れ葉が堆積している地面に寝かせる。そして小さな体に耳をつけたが、すぐに勢いよく顔を上げた。
「駄目だ、心臓の音が聞こえねえ」
長谷部は掌の付け根を小さな赤ん坊の胸に当て、急くように心肺蘇生を試みようとした。真上から力を加えようとしたそのとき、陸斗が長谷部の手首を摑んで心臓マッサージを止めた。今さっきまでの怯えは消えており、きっぱりと力強い声を出した。
「そのやり方じゃ赤ん坊の胸骨が折れる。そこどいて」
「俺は工場で心肺蘇生の講習を受けてんだよ! おまえこそどいてろ!」
「いいから、言い争ってる時間が惜しい」
陸斗は長谷部を押しのけるようにして膝をつき、赤ん坊の小さな素足を掌で軽く叩いた。そして指で顎を上げて気道を確保し、顔に耳を近づける。そして胸に耳をつけて心音を確認した瞬間、わずかに脱力して表情を緩めた。
「生きてる。眠ってるだけ。心音も呼吸数も正常」
「ホントかよ!」
長谷部もあらためて赤ん坊の胸に耳を当て、心音を確認したとたんに相好を崩した。
「驚かせやがって。この騒ぎのなか眠ってるとはいい度胸だ」
その横では陸斗がリュックサックを隅々まで見分し、ストライプ柄のタオルを持ちながらすっと立ち上がった。
「このリュックの中身は赤ん坊とバスタオルだけ」
「本気でガキを殺すつもりだったわけか。とんでもねえゲス野郎だな」
長谷部は鼻梁の太い鼻の付け根にシワを寄せた。
「とにかく戻るぞ。こうなった以上は予定を変更するしかない」
今日じゅうに集団自殺を決行することは確実に不可能だ。不本意だが、まずは赤ん坊の安全を確保する必要があった。
(つづく)
作品紹介
四日間家族
著者 川瀬 七緒
定価: 1,870円(本体1,700円+税)
発売日:2023年03月01日
誘拐犯に仕立て上げられた自殺志願者たちの運命は。ノンストップ犯罪小説!
自殺を決意した夏美は、ネットで繋がった同じ望みを持つ三人と車で山へ向かう。夜更け、車中で練炭に着火しようとした時、森の奥から赤ん坊の泣き声が。「最後の人助け」として一時的に赤ん坊を保護した四人。しかし赤ん坊の母親を名乗る女性がSNSに投稿した動画によって、連れ去り犯の汚名を着せられ、炎上騒動に発展、追われることに――。暴走する正義から逃れ、四人が辿り着く真相とは。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001445/
amazonページはこちら