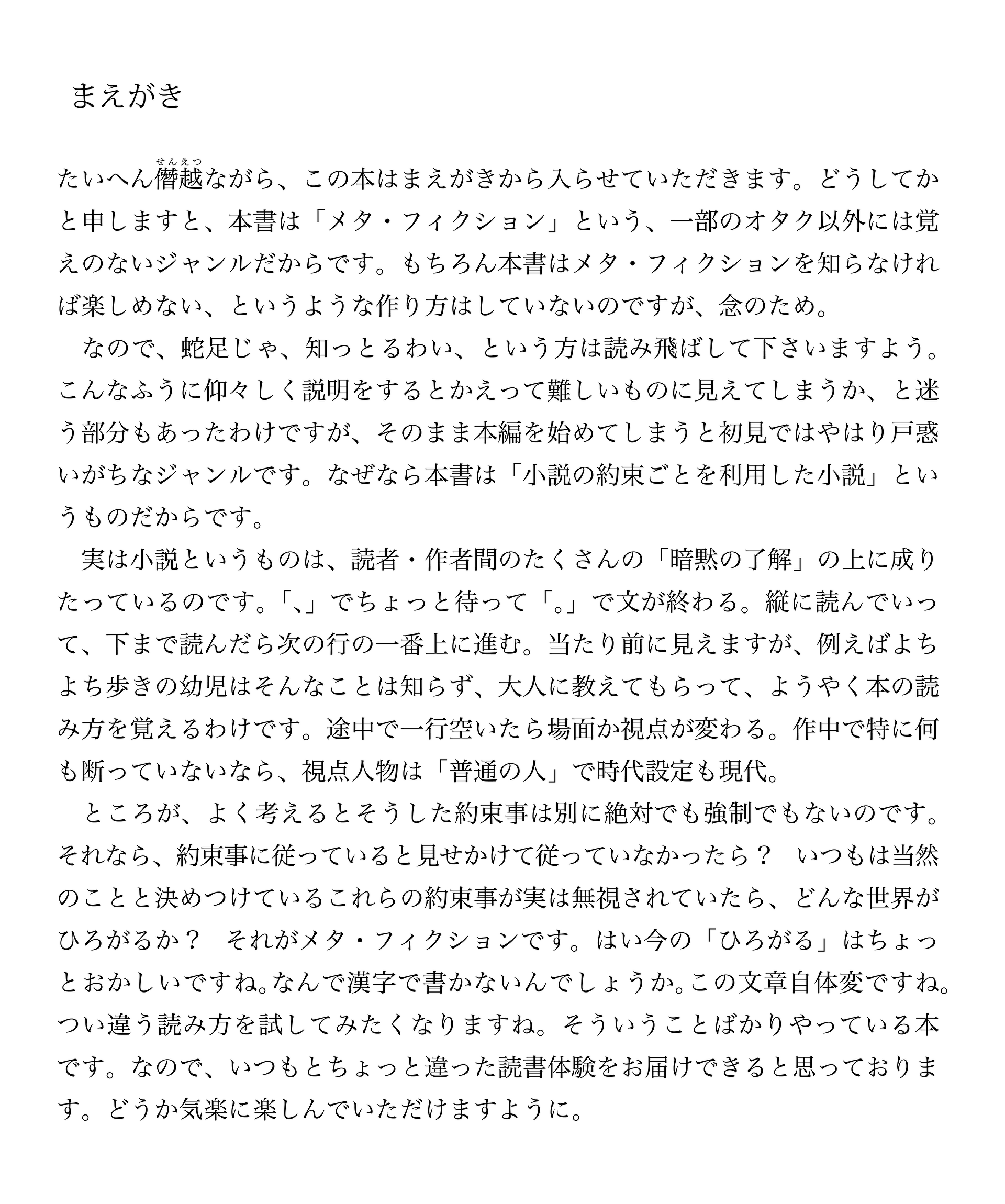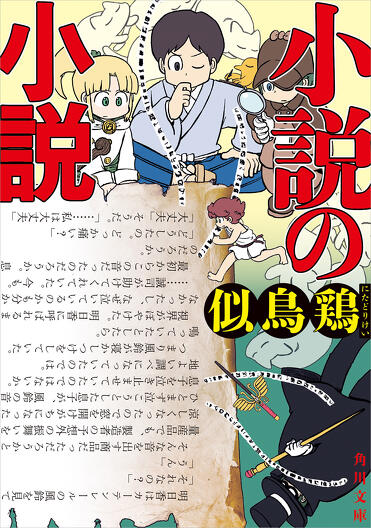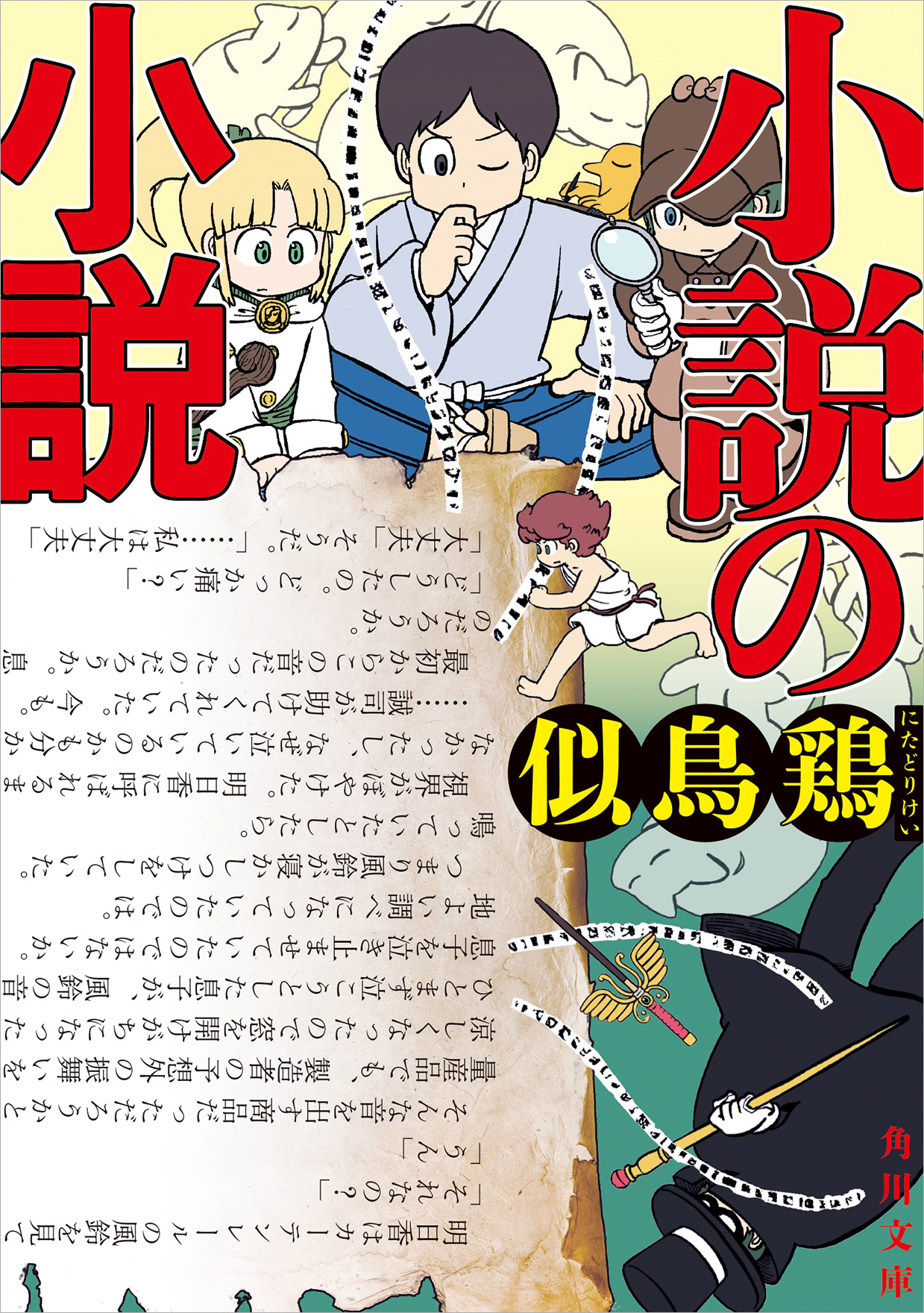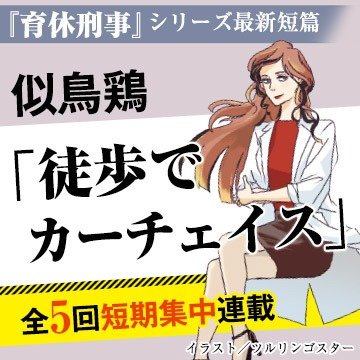「小説」の決まりごとを逆手にとった、ルール無用のメタ・フィクション!
本格ミステリ作家・似鳥 鶏さんの新境地として話題を呼んだ『小説の小説』が、2025年9月22日(月)ついに文庫化!
刊行を記念して、本作の「まえがき」と、注釈芸の限界に挑む短編「立体的な薮」を全文特別公開します。無限に広がる「小説」の可能性を、どうぞお楽しみください!
似鳥 鶏『小説の小説』試し読み
立体的な藪
どんな個性的な人間でも非常時に見せる振る舞いは平凡である。
*1 『砂の女』(1962年/新潮社)
となれば、聖人でも変人でもないこの名探偵が死体を見て「うわ」という何の面白みもない第一声をあげたからといって、責めることはできないだろう。確かに名探偵は名探偵であるから、これまでかなりの数の殺人事件に遭遇してきたし、そのすべての真相を明らかにしてきた。首がない死体もあったし、バラバラ死体もあったし、両手両脚をつけ根から切断されて代わりに馬の四肢を接合された死体とか、腹をくり抜かれ引きずり出された腸の束で首を
「どうですか」
「死んでますか」
「見ての通り」
名探偵は後ろからこわごわ
後ろの二名は当然のことながら、死体には慣れていない。彼らはすべてを名探偵に任せて「壁の花」になっていたいという思いのはずだが、今この場ではそうはいかない。この宿には彼ら三人しかいないはずであるし、今から警察を呼んだとして、こんな
「圏外ですね」
「あ、食堂なら」赤木は
「では赤木さんは」名探偵は言い直した。「いえ白鳥さんも。お二人で一一〇番をお願いできますか」
赤木一人では動転してうまく話せないかもしれない。赤木自身もそれを理解し、白鳥の方に「つっかえたら代わってくださいね」「こっちに全任せしないでくださいね」という意味の目配せをしつつ食堂に出た。白鳥はとりあえず死体から離れる理由ができてほっとしている。名探偵の素性はこの二人も知っているから、死体と二人きりにしたところで妙な偽装をするようなことはない、と信用している部分もあった。
そう、偽装である。
名探偵はすでに仕事の顔をしていた。いかな名探偵であっても、死体を見るたびに仕事を始めるわけではない。明らかな事故死、病死、他殺であっても犯人が明らかな場合は警察に任せて現場保存をするに
死んでいるのは赤木・白鳥と一緒にこの宿に宿泊していた
そう。確かにそのように「見える」のだが、と名探偵は考え、死体の傍らに
状況からして、犯人は赤木か白鳥のどちらか、ということになる。なぜならこの宿、内装こそ綺麗にされているが人里離れた
明白だった。そしてこの黒田が殺されたというなら、犯人はここにいる赤木か白鳥のどちらかということになる。
では、どちらなのか。
*2 主にツーリング中のライダーに向けて用意された簡易宿。食事なしの相部屋が基本で一種のユースホステルだが、ただ単に「所有者が空いた別棟を開放しているだけ」という雰囲気のところも多く、より簡易。宿泊料金も、安いところでは千円程度のこともある。
名探偵は食堂に戻り、一一〇番通報を終えたらしい赤木と白鳥に話しかけた。「どうです」
「『すぐ向かうが、時間がかかる』そうです」赤木が答える。「『現場には入らないで』『ご遺体には触らないで』だそうです」
隣の白鳥も名探偵に向かって「いいんですか」というニュアンスを含んだ視線を向けているので、名探偵は落ち着いて手を振った。これまで山ほど事件を経験してきて、現場のどこに触りどこを変えると鑑識が困るか、というポイントは把握していた。要はそこさえいじらなければいいのだ。若い頃は「現場には一切手を触れてはならない」などと
「事件」
「解決」
赤木と白鳥は同時に反応し、一瞬の反発と直後にやってきた納得の二つで表情をちらつかせた。名探偵は昨夜、彼らと夕食を共にした際に素性を話している。目の前で殺人事件が起こり、しかも現場にはあと一時間半、自分たちしかいないと分かれば、名探偵がそう動くのも納得してもらえるだろう。
名探偵は二人の心理を素早くとらえ、当然ですよね? という圧力で反発を押さえ込みながら、まずは赤木に
「それは……」
「何か、話したくない事情がおありですか」
「いえ、そんな。しかし」
うろたえる赤木に代わって白鳥が出てくる。「ちょっと待ってください。それって俺らが犯人じゃないかって疑ってるってことですか」
「そうです」名探偵はああ面倒臭い、と思い、それをそのまま態度に出して頭を
「そんな。ひどい」
「やましいことがないならなんでわざわざ真相解明を拒むんです? では警察にはあなたの態度を伝え、たぶん犯人だろうって言っておきますね。私、警察には信用されてるんで」
事実上の脅迫であるが、もう何十年も事件に関わっている名探偵は、そのあたりは気にしないことにしていた。確かに昔は名探偵も、相手の反感を買わないよう配慮して回りくどいやりとりをし、なるたけ穏便にアリバイを訊き出そうとしていた。だが数十年も事件に関わり続けているうちに実感した真実は「そんな手続きは無駄」だということだった。事件は日々起こっていて警察も人手不足だ。とっとと片付けるべきである。どうせ二度と会わない容疑者たちにどう思われようが何の問題もない。
「いえ、でも」赤木は手を振りながら後じさり、床板をぎしりと鳴らす。「でも私、その時間は携帯で地元の友達と喋ってました。ずっと。グループ通話で」
「なるほど。しかしグループ通話なら、ずっとあなたが喋っているわけではありませんね。というより喋りながら殺せる」
赤木は名探偵の断言にますます慌てて床板を鳴らす。「いえ。だってほら。ここ、食堂以外は電波入りませんし。つないでる間は食堂から出られないじゃないですか」
名探偵は食堂内を見回す。「そういえばそうですね」
次は自分の番だ、と察していた白鳥は、名探偵に追及される前に急いで言った。「なら俺も無理ですよね? 現場、窓の
「それもそうですね」
名探偵はまた
つまり白鳥から見れば、現場は出入口のない密室である。では赤木の方はというと、死亡推定時間帯にはずっと食堂から出なかったということになり、アリバイが成立してしまう。他に容疑者がいないとなると、不可能犯罪になってしまうわけだ。名探偵はふむ、と頷く。赤木と白鳥もそのことを察したような顔でお互い頷きあっている。
だがどちらかが犯人のはずだ。名探偵は少しも動揺しなかった。「赤木さん。一応、第一発見者はあなたですが」
「ああ、はい……一応」
「あの」白鳥が口を挟む。白鳥には、名探偵がなぜ訊き込みを続けるのか理解できなかった。「でも、俺も赤木さんも犯行、無理ですよね。つまり、いわゆる不可能犯罪なんじゃ」
「私はこれまで三百件くらい殺人事件に関わってきまして。その六割程度が『一見、不可能犯罪に見える』ものでしたが」あれ、もっと多かったかな、と名探偵は考える。おそらく三百六十か七十くらいであり、それならば「三百五十件くらい」と言うべきだったかもしれない。「その中で本当に不可能犯罪だったものは一件もありませんでした。それともこの事件だけが例外で、これまで百八十件中ゼロだった不可能犯罪の、記念すべき最初のケースだとでも?」
白鳥は黙り、赤木は観念して説明を始めた。もっともその内容の大半は名探偵自身も知っていることである。第一発見者は赤木だが、直後に白鳥と名探偵も現場に踏み込んでいるのだ。死体発見はつい先程で、朝八時五分のことだった。白鳥と名探偵はそれぞれの部屋で支度をしていたが、黒田の部屋を開けた赤木が「うわあ」と大きな声をあげたためすぐに駆けつけた。宿内はわりと声が通る。駆けつけた白鳥と名探偵が見たのが、倒れている黒田と、その横で驚いて
「死体発見時、何か気付いたことはありませんでしたか? たとえば、部屋に何かがいたり、妙なにおいがしたりといったような」
「いえ」赤木は即答しかけてからじっくりと記憶を
「では白鳥さん。殺された黒田さんは一人だけ、別の部屋で寝ていたわけですが」
「あ、はい。それは」白鳥は「殺された黒田さん」という言い方にびくりとしてから答えた。名探偵特有の配慮のなさといえるが、当人は無神経というより、早期解決のためにはそんな細かい配慮はどうでもいいと思っているのである。「……黒田、さんは。
「なるほど」
名探偵にも経験のある話だった。夜行バス、夜行列車、フェリーや宿の
差し込む朝日で食堂の空気が暖まってきたようだ。失礼、と言い置いて、名探偵は再び現場である黒田の部屋に入る。ドアは開放したままである。現場でおかしなことをしない、という保証のためだが、同時に、食堂に残った二人におかしな相談をさせない、という
だが名探偵が調べても、現場に不審な点は見つからなかった。凶器らしきものはない。氷か何かでナイフを作った、という事件も経験したが、今回の犯人は単に持ち去ったのだろう。そこはいい。問題は窓に細工の跡がない点だ。ドアには鍵がかかっていなかったものの、こちらは食堂に赤木がいたから使えない。あと人が出入りできるのは窓だけだが、二つある腰の高さの窓はどちらもクレセント錠がかかっている。向かって右の窓は開きにくく、錠周辺に
だが窓を開けて外を見ると、名探偵は発見した。外はすぐ林で、地面も落ち葉で埋まっているため足跡はつかない。しかし、その落ち葉が一部、地面に密着してめり込んでいる。横から伸びた細い枝の中にも折れているものがある。誰かがここを通ったのだ。外を歩いた痕跡。あの林の中には何もないはずだ。窓から出入りしたのではない、とすれば。
名探偵は携帯を出した。確かに、この部屋では電波は通じない。窓枠に足をかけて外に出る。足元の落ち葉がかさりと音をたてる。そのまま林を進んだ。建物が遠くなってくるまで進み、右に曲がって林から出る。鳥たちが朝の
電波は結局、一度も入らなかった。
「……なるほど。だとすれば」
名探偵は頷き、宿に戻った。玄関から登場した探偵を、赤木と白鳥の視線が迎える。
探偵は二人を見て言った。
「犯人が分かりました」
食堂に座って、特にやることもないのでお茶を飲んでいた赤木と白鳥は
赤木と白鳥が座ったまま
「まず、この事件は不可能犯罪ではありません。ある簡単な方法で、一見不可能に見えた犯行を可能にできます」名探偵は赤木を見る。「赤木さん。犯人はあなたですね」
あまりにあっさりと、ついでのように言われたため、赤木は当初、自分のことだと気付かなかった。
名探偵はそれには特に構わずに推理を話す。
「一見、あなたにはアリバイがあるように見えます。死亡推定時間帯は昨夜十時半頃から深夜零時半頃まで。しかしあなたはその時間帯、ずっと携帯で、友人たちとグループ通話をしていた。私も先程確認しましたが、この宿の中、及び周辺で、携帯の電波が入るのは確かにこの食堂だけです。おそらく裏の林とこの建物自体が微妙に電波を邪魔している。携帯の電波が入るのは食堂だけだというなら、赤木さん。あなたはその時間帯、食堂を一歩も出ていないように思える。ですがそれがトリックでした」
名探偵は
「そもそもあなたの態度はおかしかった。あなたは言いましたよね。『食堂以外は電波入りませんし』」名探偵は赤木を指さす。「どうしてそう断言できたんですか? ここ以外は電波が入らない、という状況は、常識から考えればかなり特異なものです。それに本来、携帯の電波状況というのは不安定なものだ。入らないな、と思った場所でも、少し待てば改善されることが多い。どこは電波が入って、どこは入らないのか。
赤木はまだ反応しない。白鳥は赤木を見ている。
「なぜ言い切ることができたのですか? しかも、あなたは私が疑いを向けた途端に、すぐそれを言った。まるであらかじめ、そう言おうと決めていたかのようです」
そこで一拍空き、どうやら喋ってもいいらしいと察した赤木がすぐに反論する。「いや、でも。実際に電波は入らないわけで」
「今は入りません。ですが犯行時は入ったとしたら?」名探偵はすぐに反論を封じた。「簡単なトリックです。携帯電話などに使用できる『電波ブースター』つまり電波中継器はあなたもご存知ですよね(*3)? あれを宿の周囲に隠しておけば、本来、電波の入らない場所でも入るようになる。あなたは電波中継器を使い、電波が入る状態にした上で食堂を出たんです。どこでも電波が入るならどこにでも移動できる。ドアから入って黒田さんを殴り殺し、電波中継器をおそらく林の中にでも捨てて、何食わぬ顔で食堂に戻った。林の方角に、何かの通った痕跡がありましたしね」
*3 携帯電話電波中継器は自ら電波を発するため、これを使うと「個人が、総務大臣の許可を受けずに携帯電話と同じ周波数帯の電波を発した」ことになり、電波法四条違反になってしまう。「電波法準拠」と書かれている商品も、どう準拠したかはっきりしないのであれば使うべきではない。
「な……」赤木が絶句する。
「なぜ黒田さんを殺したのか。動機は警察が調べるでしょう」名探偵は言った。「赤木さん。犯人はあなたです」
名探偵は言った。
だがこの推理は間違いである。名探偵が言ったことなのだから絶対に間違いはない、などというルールは小説にはない。名探偵であっても間違った推理を披露してしまう可能性はある。名探偵の代名詞である、かのシャーロック・ホームズだって、けっこうな割合で推理を間違ったり、犯人の策略に途中まで
では推理小説において、本当に間違いのない「真相」を決めるのは不可能なのか? 答えは「否」である。当然である。方法はある。簡単なことである。ここ、すなわち地の文で書けばいいのだ。
せっかくの推理を登場人物などに言わせるから真相だという保証がなくなってしまうのである。どんなに
もちろん、視点の問題には注意しなければならないだろう。たとえ地の文で「これが真実である」と断言しても、その地の文がそもそも登場人物の一人たる「視点人物」の語りであった場合、これはやはり「視点人物が真相だと思っている」に過ぎないということになる。したがって一人称だの三人称一視点だのの方式は避け、地の文は登場人物すべての視点に自由に入ったり出たりし、場合によっては登場人物の誰も知覚し得ないことを語りだす、いわゆる「神の視点」にしなければならない。だがこれさえ守れば、そこに書いてあることは真実になる。なんせ神なのである。神の言うことは絶対に正しい。神が光あれと言えば光が生まれる。松方死ねと言えば世界中の松方が死ぬ。ひどい話である。松方さんが一体何をしたというのか。
というわけでここで断る。この小説は神の視点で書かれている。地の文で「赤木は観念して説明を始めた」だの「白鳥には、名探偵がなぜ訊き込みを続けるのか理解できなかった」だのと、本来赤木本人、白鳥本人にしか知覚し得ない彼らの心理を断言してしまっているのが、その証拠である。
したがって神たる地の文の言う推理こそが真相なのである。名探偵が反論しそうで面倒臭いので名探偵には黙っていてもらうことにしよう。名探偵は突如モルモットになった。これで名探偵は以後プイプイとしか言えない。これが神の力である。というわけで真相を説明する。犯人は白鳥である。
そもそも赤木が犯人だという名探偵の推理は論理的にも無理がある。名探偵自身も言っているではないか。「携帯の電波状況というのは不安定なものだ」と。「食堂以外は電波が入らない」と断言するのはおかしい、と。それならそもそも、「食堂以外は電波が入らない」ことを前提としてトリックを仕込むこと自体がおかしいではないか。犯人が電波中継器を使ったことを隠して「ほら食堂以外は電波、入らないでしょ」と主張したとする。それで確実に容疑を免れられるだろうか? 警察が検証してみたら、その時には「あっ、このへん今、電波入りました」となる可能性だって充分考えられる。そうなったらせっかく用意したトリックが全部無駄ではないか。そもそも携帯の電波状況などその日の天気でだいぶ変わる。トリックを計画して準備した時には電波が入らなかったからといって、犯行当日も入らないとは言い切れないのだ。そんなギャンブルを犯人がするだろうか。
一方、実は白鳥には犯行が可能なのだった。名探偵は見逃しているが、現場の「左側の窓」に開けた跡があったことは何を意味しているのか。推理小説においては意味のない事実をわざわざ書いて
もちろん読み飛ばしなどしない読者諸賢におかれては、それはおかしい、とお思いだろう。現場の窓は鍵がかかっていたし、糸か何かを外に通して引っぱったような痕跡はない、と明記したのはお前ではないか、とお思いだろう。だが「糸か何かを外に通して引っぱったような痕跡は」ない、とわざわざ限定していることに注目していただきたいのである。糸などを使わなくとも、外からクレセント錠を動かして鍵をかけることはできる。たとえば強力な磁石を使えば、アルミサッシのクレセント部分を外から動かすことができるのである。
一見おかしなことを書いたように思われるかもしれない。「アルミ」サッシなのだから磁石は効かないはずである。だが今回は違った。それこそが白鳥の用いたトリックの
というわけで、真相はかくのごとしである。犯人は白鳥であった。だが彼は逮捕されずに逃げおおせた。名探偵がモルモットになってしまっているせいだった。(※などということが書いてあるが、この推理も間違いである。地の文を神の視点で書けばそれが絶対に真実となる、などというのは
ここからが大事であるから、「()でくくられ、しかも頭に※がついた地の文」としては通常やらない「改行」をさせていただいた。
さて絶対的に真相たり得る「()でくくられ、しかも頭に※がついた地の文」の推理を述べる。先程、地の文が、神などと笑止千万な自称をしつつ述べた推理は間違いである。白鳥も犯人ではない。当たり前である。ちょっと考えれば分かることであるが、「窓枠を鉄製のものにすり替えておいて磁石で鍵をかけた」などというトリックはありえない。現場をよく思い出していただきたい。向かって右の窓には蜘蛛の巣がかかっていた。全体的に古い建物なのだ。窓枠をすり替えてしまえば目立つに決まっている。まさか個人で製作したわけでもあるまいし、そんな変な窓枠を発注すれば証拠も残る。何より白鳥の犯行を不可能にする「密室」という状況自体が、赤木が「たまたま犯行時間帯の最初から最後まで、食堂に陣取っていてくれる」という偶然により成立している。確かに赤木がグループ通話をすること自体は予想ができたかもしれない。だが彼が、今は電波状況がいいからと食堂以外でグループ通話をしたら? 始める時刻が遅かったり、終わる時刻が早かったりしたら? 何よりトイレか何かで一度でも席を立ったら、その途端に「その間に食堂をすり抜けることは可能だった」と言われてしまう。こんな偶然を当てにして、鉄製の窓枠まで準備してトリックを仕込むトンチキはいない。
では真相はどういうものか。
簡単である。赤木も白鳥も犯人ではないのだから、犯人は存在しないのだ。死んだ黒田は「自然死」、つまり事故である。
黒田は単純に、転んだ拍子にローテーブルの角に側頭部をぶつけ、打ちどころが悪くて死んでしまったのである。そのような事故は世界中で毎年無数に発生している。
確かに作中の名探偵は、事故死ではないと断じた。だが彼は色々と
というわけで、真相は最も単純で、罪がなく、
〈了〉
*4 どうも事態が混 沌 としてきたようである。小説の体をなさなくなってきた、といえるかもしれない。最初にお前がしゃしゃり出るから、と地の文だけを非難するのも間違いだろう。尻馬に乗ったやつらも同罪である。
とはいえ後始末はしなければならない。なので本来はこんなことはしないのだが、注で決着をつけてしまうことにする。ルビまで出しゃばりだしてしまっている以上、今回は仕方がないだろう。というより、もう事態を収拾することができるのはこの注しかないのである。これは最後の手段というわけで、本の体裁が美しくなくなるから本当はやりたくなかったのだが、仕方がない。
というのも、本文のどの記述よりも客観的で真実を語れるのがこの注だからである。神視点の地の文や「()でくくられ、しかも頭に※がついた地の文」よりルビの方が真実性がある、というのは確かにその通りなのだが、それでもルビは本文の一部である。ルビ自身は自らを本文の一部だとは思っていないようで、本文を「下界」などと呼ばわっていたが、注から見れば井の中の蛙 、十次元世界から見た三次元人であって、どちらも狭い本文の中で上だ下だと言いあっているに過ぎないことは、読者の皆様も直感的にお気付きだろう。
そもそも「ルビだから絶対に正確である」などという主張に無理がある。ルビ自身が例に挙げているではないか。「筋肉」と書いて「たましい」と読ませたりできる以上、ルビだってその内容は恣 意 的 、主観的なのであって、本質的には本文の一部であり、著者による創作に他ならない。音楽記号のスタッカートやフェルマータが「私は音符本体ではないから楽譜の一部ではない」などと主張するだろうか? スタッカートもフェルマータも、音符本体と合わせて「出すべき音を指示する」といういわば音符本体の付属部品なのであって、外すと音符の意味が変わってしまう以上、どうしようもなく本文なのである。◦の有無によってůとuが別の文字になるのと同じである。それに「ルビは有限ゆえ絶対の真実になり得る」という主張も無理筋だ。「文字組みが」「ぶら下がりが」とあれこれ言い訳をすればいくらでもに飛び出せる上に、いざとなれば今やったように何もないところにルビだけふってしまうことすら可能なのに、そのことに関しては意図的に言及を避けた政治家のごときゴマカシ方であり、悪質である。
一方、注は違う。注は本文から離れた場所におり、なんなら別ファイルになることもできる、完全に本文とは独立した存在である。その証拠に、あってもなくても本文の意味が変わるわけではないし、位置が変わっても本文には特に影響しない。この注も、電子版では末尾にくっついてクリックでジャンプできる仕様になっているが、紙版では出現した頁 の左端からすぐ始まる。
そして注は、本文外にあって本文の説明をするものである。つまりルビを含む本文より後に来て、ルビを含む本文を訂正する権限を持つものである。どちらが客観的に正しいかは、この場合、問題ではない。注が間違っているケースもあるからだ。だが「どちらが真相となるか」つまり真相を決定する権力があるか、という観点からすれば、注は絶対に、ルビを含めた本文より上位に位置する。いかに本文で「これが真相である」と述べても、(※これが真相である)と述べても、あるいはル ビ でそう述べても 、注が「これが真相である」と述べれば、読者はそちらを信じる。それこそ小説外の、現実世界のルールでそういうものだとされているからだ。
したがって、この注が語る真相こそが、絶対に覆されようもない本当の真相ということになる。これを覆すには著者が現実世界で「あの注は違っていて、本当の本当の真相は……」と述べるとか、版が変わって訂正された真相が出るとか、そのくらいしか考えられないが、それらも実は問題にはならない。国語の問題の「この作者が言いたかったことは何ですか」という問いはしばしばネタにされるが、テクスト論を引くまでもなく、著者の解釈や意見などといったものは作品の内容には関係ないのであって、著者の発言は「有力な仮説の一つ」以上の地位は持たない。まして版が変わって訂正されても、旧版の本は残り続けるわけで、新版の方が正しい、などといったルールもない。グリム童話を例に挙げるまでもなく、新版の方が変質して本質から遠ざかっている、ということだってあるし、マニアになるほど求めるのは初版の方である。
ということで絶対の真相を述べる。犯人は「外部犯」である。
名探偵はもとより赤木も白鳥も犯人でないことは本文が説明した。事故死でないこともルビが説明した通りであるから繰り返さない。だがルビが主張する「赤木と白鳥の共犯」説もだいぶおかしい。ちょっと考えれば分かることである。もし赤木と白鳥が共犯なら、こんなにややこしく、電波状況次第で否定されかねない回りくどいアリバイなど主張しない。二人一緒の部屋で寝て、朝まで二人とも部屋を出ていません、と噓をつけば済む。赤木と白鳥がその可能性に思い当たらなかったはずはないわけで、つまりこの二人は共犯ではなく、どちらも無実なのだ。二人が無実で、事故死でもないなら、残った可能性は「外部犯」しかない。「可能性を一つ一つ除いていって、最後に残ったものは、どんなにありそうになくても真実」というやつである。
もちろん、外部犯が夜、いきなり突入してきたわけではないだろう。外部犯はもともと宿内に潜んでいたのだ。このてのライダーハウスというのは、宿泊の予約がない限りは管理人が全く顔を出さない日も多い。宿泊費を払わずに潜んでいる人間がいたとしても不思議ではないのである。そいつが黒田を殺し、おそらくはまだ現場内に潜んでいる。迂闊なことだが、赤木や白鳥はもとより名探偵も、まだ現場となった部屋を隅から隅まで調べてはいないのである。
動機は分からない。たまたま黒田と関係があった人物だった、という可能性は小さいだろう。犯人がこのような生活をしていたことから考えれば、そもそも人前に出ることができない逃亡中の指名手配犯か何かであり、黒田を殺した動機は単純に「見られたから」だろう。
さて、注の本分からして、あまり本文に影響を与えるのは望ましくない。真相は以上の通りであるとして、名探偵は間違った推理をしたまま警察が到着。すぐに現場検証がされ、警官隊の手により、押し入れの奥に隠れていた犯人が発見、逮捕され、事件は解決した、ということにしておこう。
本文には書かれなかったが、これが本事件の結末である。
「……という手紙が届いたんですよ」
私は正面に座る探偵に言った。もちろん手紙の現物も
「妙な手紙ですね。確かに黒田さんでしたっけ? 彼が殺された事件は不可解だったが」探偵は脚を組んだまま、手紙の現物にはさして興味はなさそうだった。「まあ、色々と推理を書いてご苦労様、といったところだがね。この手紙の内容は間違いだよ」
探偵はそう言うと、組んでいた脚をとん、と
「今からこの事件の、本当の真相を話します」探偵は皆を見回す。「……犯人は、この中にいます」
(このほかにも「小説」の常識を覆す短編を4編収録! ぜひ本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:小説の小説
著 者:似鳥 鶏
発売日:2025年09月22日
本格ミステリの著者が描くメタ・フィクション!「常識」に捉われるべからず
いつものように殺人現場に出くわしてしまった名探偵。華麗な活躍で事件が解決したはずだったそのとき、思わぬ《伏兵》が推理を始め……?(「立体的な薮」)/異世界転生し、チート能力で無双する。誰もが夢見るシチュエーションに恵まれた「俺」だったが、最大の敵は、言葉の《イメージ》だった!(「文化が違う」)/「小説」とは何か、「書く」とは何か。創作の限界に挑む、これぞ禁断の小説爆誕!(「無小説」)/時は新法が成立し、検閲が合法化された曰本。表現の自由が脅かされる中、小説家の渦良は、《あらゆる》手を尽くして作品を書き続けるが――。(「曰本最後の小説」)
本格ミステリの著者が挑んだ新境地、メタ・フィクション! あなたが知る小説の概念を覆す、驚きの5編を収録!
※紙書籍版カバーには、文庫版特別書き下ろし特典を収録
※電子書籍版巻末には、電子特典「夫の日記帳」を収録
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000745/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら