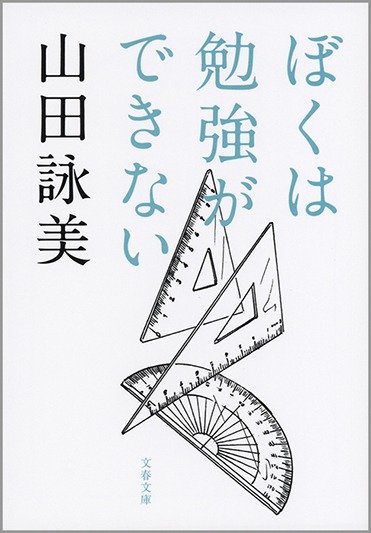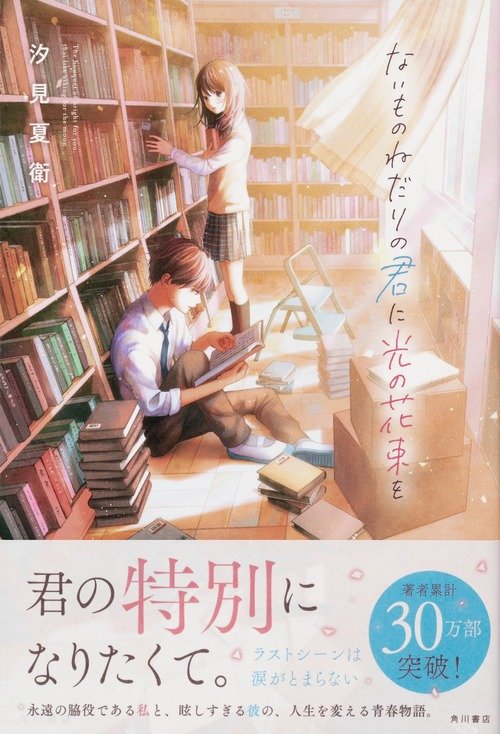6月18日(木)に発売された『ないものねだりの君に光の花束を』の刊行を記念して、6回に分けて試し読みをお届けします!
平凡であることにコンプレックスを抱く女子高生が、クラスの人気者でアイドルとしても活躍する男の子と出会い、「普通」や「特別」とは何かを考える物語です。汐見夏衛が描く、読後世界が輝いて見える希望の小説。
◆ ◆ ◆
>>前話を読む
放課後、羽奈から「お茶しようよ」と誘われて、一緒に学校を出た。
駅前のファストフード店に入り、レジでフライドポテトとジュースのセットを買って、混み合う店内でなんとか見つけた空席に陣取る。
「それにしてもさ」
しばらくとりとめのないおしゃべりをして、先週の実力テストについての話が一区切りついたとき、ふと羽奈がそう言った。
「影子にはもう何回も言ってるけどさ、クラスに芸能人がいるとか、ほんとケータイ小説もびっくりの展開だよね」
私は笑って「そうだよね」と頷く。
彼女が少女漫画やドラマと言わずケータイ小説と表現したのは、私たちの接点がそこにあったからだ。
私と羽奈は、一年生のときにケータイ小説をきっかけに親しくなった。クラスは違ったけれど、たまたま学校の図書室で同じ棚を物色していたときに、『こういうの、よく読む?』と声をかけられたのだ。
雑食で本ならなんでも読む私が頷いて『あんまり詳しくはないけど』と答えると、彼女は
私の周りには、ケータイ小説に限らず本を読む人自体いなかったので、私にとっても嬉しい出会いだった。二年生になって同じクラスになったときは、手を合わせて喜び合ったものだ。
出会ってすぐのころ、羽奈が《アメジスト》という小説サイトを紹介してくれた。私もすぐに彼女に教えてもらいながらユーザー登録をして、この小説が面白かった、あの作家が好みに合いそうだよ、などと毎日のように情報交換をしてきた。ついでにアメジスト用のツイッターアカウントも作り、他のユーザーともネット上で交流している。
私は小説の執筆はせず、気ままに好みの作品を
「もし鈴木くんを小説にするとしたら、どんなストーリーにする?」
ふと思いついて
「そうだな、まずはタイトル、『みんなの王子様に、なぜか
羽奈は楽しそうに頰に手を当て、声を上げて笑った。私も笑いながら、拍手をする。
「よくそんなにどんどん言葉が出てくるね。すごい、さすがだね」
私の言葉に、彼女は照れたように首を振った。
「いやいや、普段はなかなか思いつかなくて、めちゃくちゃ悩みながら書いてるんだよ。今のは、モデルが圧倒的にすごいから、真昼くんのこと考えたらすらすら出てきたってだけ」
「へえ、そういうものなんだ」
「だって、真昼くんって本当にすごくない? 漫画にもなかなかいないよ、あんな顔も中身も誰が見ても完璧な王子様なんて!」
完璧な王子様、という言葉は、確かに鈴木真昼を表現するのにいちばんしっくりとくるものだと思う。
彼はデビュー当時から『天然記念物級イケメン』と騒がれ、SNSなどでも『一生眺めていたい顔』だとか、『眩しすぎて直視できない』だとか言われているのをよく見る。
それは世間一般のイメージだけれど、学校でも彼の評価は変わらない──どころか、それ以上に
もちろん顔もスタイルも抜群な上に、勉強もできてスポーツ万能、さらに性格もよくて人当たりまでいい、と誰もが口を揃える。男女問わず、上級生にも下級生にも人気があった。
こんなに何でも持っている人間が本当に実在するのか、と何度見ても自分の目を疑ってしまう。
でも、いるのだ。同じクラス、しかも私の隣の席に。
「そんな大人気の王子様な彼と、地味子な私、一生話すこともないと思ってたのに、なぜかある日突然彼に呼び出されて、しかも告白されて……!? って感じであらすじ紹介して、本文スタート!」
羽奈が人差し指を立ててにやりと笑った。
「主人公は本当はみんなと同じで彼のことが気になってるんだけど、わざと彼のことなんて全然興味がない、って顔してるの。だって、絶対いつかめちゃくちゃ可愛い子と付き合っちゃうんだから、そのときショック受けたくないじゃん? だから彼のことは好きにならないようにするの。でも、急に彼のほうから主人公に近づいてきて、『なんでお前、他の女みてえに俺のこと好きじゃねえの?』って
羽奈が紡ぎ出す物語が、鈴木真昼の顔で再生される。相手役は私みたいに地味で平凡な女の子。
脳裏にその映像が
それでも彼女はめげずに顔を輝かせて続ける。
「いやー、分かんないよ? 人生は何が起こるか未知数なんだから。私にだって影子にだって、ドラマみたいにロマンチックなことが起こる可能性はあるんだから! それこそ真昼くんに溺愛されちゃうとかさ。なんせ隣の席なんだし!」
「いやいや、私に限ってはそれはない、それだけはない、あるわけない、百二十パーセントない」
思わず全力で否定してしまった。
羽奈が気を悪くしたのではないかと焦ったけれど、彼女はけらけら笑いながら「どんだけ必死やねん」とおどけてくれて、ほっとする。
「でもさ、まあ、アイドルと恋なんて夢のまた夢って分かってるんだけど。そりゃあ好きになっちゃうよね、真昼くんみたいな完璧な人が身近にいたらさあ」
「……んー」
正直なところ、全く共感できなかった。
彼を見ても私の心は暗い感情に支配されるだけで、どきどきだとかときめきだとかいう可愛らしい気持ちなんて、一ミリも湧いてこないのだ。
鈴木真昼に限らず、私が王子様のような男の子から好かれる可能性なんて
誰もが憧れる格好いい男の子なんて、私は隣に並ぶのも嫌だ。遠くから見るぶんにはいいかもしれないけれど、絶対に近くにいたくない。きっと見比べられて、隣にいる自分がひどく惨めになるから。
もしも万が一、絶対にありえないことなのだけれど、たとえば神様の手もとが狂ってとんでもない奇跡が起こり、なぜか彼が私のことを好きになって、付き合うことになったとして。
そのとき私はきっとこう思う。《特別》な彼は、《普通》な私のことを、どんな目で見ているんだろう。周りの人たちは、当たり前のように彼の隣にいる私を、どんな目で見ているのだろう。多分、よくもまあその顔で当然のように彼の隣に立てるものだ、と
私のような平凡な人間が、彼のような人のことを格好いいと騒いだり、好きだと言ったりするなんて、たとえ直接伝えるのでなくても無理だ。思うだけでも恥ずかしい。自分が彼に好意を持っていると誰かに知られることすら恥ずかしい。
だから絶対に好きになんてならない。なれない。
でも、それは私がひねくれているからで、羽奈のように素直な女の子ならみんな彼に惹かれてしまうのは、頭では理解できていたから、今度は「そうだよね」と頷いた。
何度かぱちぱちと
「前も言ったけど、影子もアメジストで小説書いてみたらいいのに。すごく分かりやすくて簡単だよ。影子は私よりもたくさん本読んでるし、ケータイ小説以外の難しそうなやつも読んでるし、すごくいいの書けそうじゃん」
「いやー、いやいや」
私は慌てて手を振った。
「私には無理だよ……。そりゃ本は好きだけど、読むのと書くのじゃ全然違うだろうし」
えー、と不服そうな顔の羽奈に笑いかけ、それに、と続ける。
「私みたいな平凡人間、みんなが読みたくなるような面白い話なんて書けないよ」
彼女はおかしそうに笑った。
「何それ、私だって超平凡だよ」
私はぶんぶんと首を振る。
「いや、羽奈はそもそも普通にしててもめちゃくちゃ面白いから。平凡なんかじゃないよ、話してるだけで楽しいもん。羽奈が書いた小説も絶対面白いと思う」
さすがに照れくさくて面と向かっては言えないけれど、彼女のあっけらかんとした明るさや素直さ、屈託のないテンションの高さは、まるでラブコメの登場人物のようだ。そんな彼女が自分の気持ちをそのままぶつけた小説なら、きっとものすごく面白いに決まっている、と常々私は思っているのだ。
だからぜひ彼女の作品を読んでみたいのだけれど、以前「ペンネームを教えて」と頼んだら、真っ赤な顔で「恥ずかしいから無理!」と言われてしまった。でも、そのあとぽつりと「ファン数が千人超えたら、記念に教える」と言ってくれたので、いつかその日が来るのを待っている。
「私も影子と話してたら楽しいよ」
羽奈は優しいので、そんなふうに言ってくれる。
でも、私自身がいちばんよく知っていた。私はとても平凡で、普通で、いくらでも代わりがいるような、取るに足らない存在だということを。
そんな私の考えに気づくふうもなく、彼女は続ける。
「それにさ、誰かが読んで面白がってくれるとかじゃなくて、自分が楽しく書けるものでいいんだよ。ネット小説って、自分の夢とか妄想を書き散らしても許される世界なんだもん。影子と創作の話ができたら楽しそうだし、書いてくれたら嬉しいなあ」
「うん……そうだね。でも、私には人を楽しませられるような夢も妄想もないからなあ……」
自分の思いのままを口に出してしまってから、せっかく励ましてくれた羽奈に対して失礼な反応だったと気がついて、慌てて笑みを貼りつけた。
「いつか面白そうな話を思いついたら、書いてみようかな」
そうでも言わないと、誘いをかけてくれた羽奈の顔を立てられないと思った。彼女はにこりと笑って、「楽しみにしてる!」と言ってくれた。
(つづく)
▼汐見夏衛『ないものねだりの君に光の花束を』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000671/