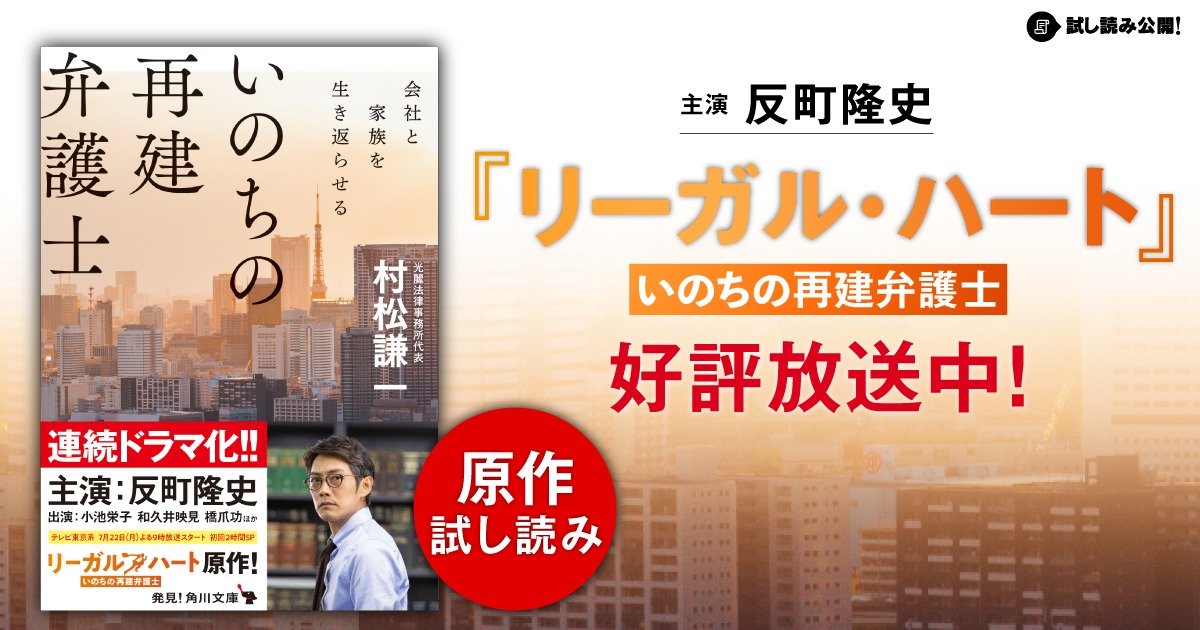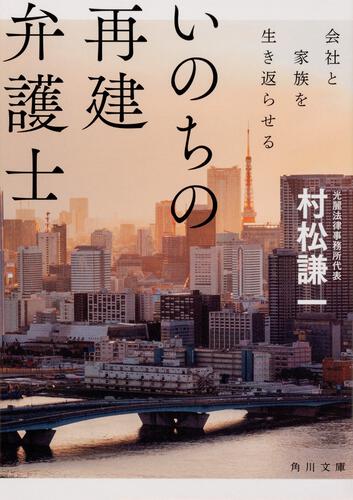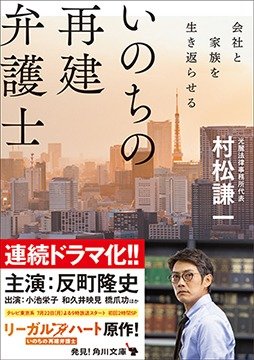「企業再生こそ日本の再生だ」会社を生き返らせる男が修羅場で見た物とは!
テレビ東京系で放送中のドラマ「リーガル・ハート~いのちの再建弁護士~」。
反町隆史さん演じる再建弁護士・村越誠一が、倒産の危機に瀕した中小企業を救うことに心血を注ぐ、熱きヒューマンドラマです。
カドブンではドラマの放送開始を記念して、現役弁護士・村松謙一(構成協力:石村博子)による原作『いのちの再建弁護士 会社と家族を生き返らせる』(角川文庫)の試し読みを実施。
「まえがき」につづき、第2章「ふたつの死が私を変え、支えている」を3回にわけて全文公開いたします。
▷2章を最初から読む
参議院で再認識した、己の使命
二〇〇〇年、私は事務所の名称を「村松謙一法律事務所」から「
だが、再建の相談は受けても、実際の受任には至らないという日は続いた。再建事業と取り組むには、体力気力、何より覚悟が必要である。その覚悟を決める力がどうしても湧いてこないのである。お前にこれができるのかと思うと、怖くてならなかった。
弁護士をやめて生まれ故郷の静岡に帰り、静かに暮らそうか……など、浮かぶのは後ろ向きのことばかりだった。
二〇〇一年の暮れ、そんな私に思いがけず、「参議院財政金融委員会」から参考人としての呼び出しがかかってきた。その委員会では破綻企業の処理についての審議が行われており、企業倒産の現場を歩いてきた専門家の意見が聞きたいというのだ。委員の誰かが、それまでに出した私の本を読んで、白羽の矢を立てたのだろう。
「創造的破壊」という言葉がもてはやされている風潮に危機感を持っていた私は、「出席」と返答した。だが、返答してすぐに、そんな資格が自分にあるのかという迷いがこみ上げた。人前には出たくないという気分も強く残って、出席すべきかどうか前の日まで揺れ続けた。
それが、委員会の当日である。目を覚ますと「もう一度立ち上がれ!」という声がどこかから響いてくるのを感じたのだ。その日は一二月五日。もしかしたら亡くなった天国の麻衣からの少し早いクリスマスプレゼントだったかもしれない。私はもう一度リングに上がるボクサーのような気持ちで、委員会の席に座った。
委員会の席上、議員の一人が「体力の弱っている会社は、救済よりも消滅させた方が経済にとって良いのではないか。先生は倒産寸前の会社でも救済すべきとお考えか」と私に質問を投げかけてきた。
瞬間、自死した社長の姿が脳裏に浮かんだ。今の言葉は社長の苦闘を侮辱するものではないか。私は手を挙げ、返答した。
「結論から言うと、一〇〇%再生し続けなければいけないと思います。なぜなら、人の命がかかっているからです」
議員は一瞬驚いたように目を
約一〇分、意見を述べながら、社長と麻衣の存在をありありと感じていた。たったひとつの命でも大事にすべきであることを訴えなければならなかった。もしかしたら、この社長や麻衣が私の口を借りて「命の大切さ」を言いたかったのかもしれない。
あわせて、怒りが、長い間眠っていた心を目覚めさせた。私の正義感に再び火がついた。自分には救うべき人たちがいる。社会の無理解によって奪われてしまう命をひとつでも救うのが使命であると、私は自分に言い聞かせた。
再生の仕事、落合楼の再建に取り組む
国会で意見を述べた約半年後、二〇〇二年五月のことだった。見知らぬ旅館経営者の老夫婦が、私の事務所にやってきた。老夫婦は何人もの弁護士に頼んだけれどみんな断られ、やっと探し当てた村松先生しかいませんと力なく頭を下げた。
旅館は
落合楼は明治から戦前にかけて、
それほど高い格式をもった旅館が、一〇億円の負債を抱えて沈没寸前であるという。公共料金はもとより租税公課、取引先の支払いも数カ月分滞納のまま。従業員の給料も半年以上も払われず、従業員はお客からの〝心づけ〟で、何とか
銀行にも一年以上返済が滞っている、いわゆる「実質破綻先」で、これ以上の貸し出しは不可能である。民事再生を申し立てたくとも、裁判所にその費用も出せないという惨状であった。
ところが驚いたことに、その返済の滞っているメインバンクがプロジェクトを組んで、旅館再生に取り組んでいるというのである。そんなことは異例中の異例のことである。銀行の担当者によれば、落合楼は建物はもちろん、宿泊の部屋、階段に至るまで、七つの建造物が文化財としての指定を受けている。これほどの旅館は全国的にも
「もう一度前に」と思った私であったが、あまりの難問に返事を渋った。再起第一戦とするにはこちらが
「お父さん、この建物を壊さないで」
という声が聞こえたような気がした。
巡り巡ってこの案件が私のところに
「お父さん、そろそろ立ち上がって、仕事をしなさいよ」
その声に応じようと、「やりましょう」と私は返事をした。
この落合楼再建事件は、「これまでにないこと」への挑戦の連続となった。銀行側も実質破綻先に融資するという大英断を敢行。担当者は、クビを覚悟で取り組んでいた。私は弁護団を結成し、民事再生手続きなどに奔走した。税金の徴収官とやりあい、電気料金の取り立てに抗議し、各地の旅行代理店をまわって倒産という風評被害を潰していった。緊迫したやり取りを交わすうち、バリバリやっていたころの感覚が
私たちの動きに歩調を合わすように、掃除が行き届かずに荒れていた旅館内部も、次第に整えられていった。往時の風格が次第に蘇る様は感動的なものがあった。
「出会い橋」で麻衣が見せてくれた蛍の舞
大きな山場だった債権者集会も混乱なく終わり、数々の困難な出来事にも出口が見えてきたころ、私たち弁護団は落合楼に一泊して、ひととき労をねぎらうことになった。川のほとりにある野趣あふれる露天風呂は、私にとって何年ぶりかの温泉だった。
蛍の季節だというので、私たちは見物を決め込み浴衣着のまま、旅館のわきを流れる川へと向かった。川には橋がかかっている。欄干に刻まれた橋の名は「出会い橋」。「出会い」という名に、思わず胸が詰まった。
背後には深い森を抱えて、あたりは漆黒の闇である。闇の中、川の岸辺では数万匹の蛍が乱舞して、幻想的な明かりを放っていた。私たちは、渓流の音を聴きながら、蛍の舞に無言で見入った。
私は蛍の様子に、麻衣の姿を感じていた。亡くなる二週間前、麻衣は学校の文化祭のダンスに出演した。私が見られなかったダンスを今ここで、見せてくれるような気がしてならなかった。
不意に雨粒が落ちてきた。あっという間に雨粒は強まり、みな声を上げ、
すると一匹の蛍が群れを離れて、私の方へと近づき、上へ下へと舞い始めた。「麻衣か?」と呼びかけると、
「ごめんな。お父さん、何もしてやれなくて」
「気にしなくていいよ。誰のせいでもないよ」
どしゃ降りの雨の中、私は麻衣と懐かしい会話を交わし、思い切り泣いた。
間もなく、日本政策投資銀行による旅館再生ファンドが成立。旅館再生ファンドの第一号という快挙であった。
落合楼は若き経営者を迎えて「落合楼
命を守る弁護士になる
落合楼の再建を機に、私は再び新たな再建を引き受けるようになった。私のもとを訪れた人々を守り抜こうという気持ちは以前と同じだ。しかし、何を守るかというと、究極は「いのち」だと思うようになった。財産はなくなっても、頑張ればまた元に戻すこともできる。でも、命は
落合楼以後、麻衣はしばしば私にメッセージを送ってくれるようになった。メッセージの送り方は、私にしか分からない方法である。落合楼のときのように、偶然と思えるなかに、深い意味が隠されているという出来事を、私は何度も何度も体験した。それらは出来事というにはあまりにささやかで、説明してもうまくは通じないだろう。初めて受け入れた女性司法修習生が麻衣と同じフェリス女学院出身だった、依頼主の車のナンバーに娘の誕生日が込められていた、命日にたまたまひもといた法律雑誌に懸案中の難問の解答事例が載っていた……。数え上げたらきりがない。
そのたびに私は、麻衣の存在を感じる。私の力になってくれていることを感じとる。麻衣はいつもそばにいて、何かがあると「メッセージ」を送り、私を守ってくれている。目で見ることはできないが、きっと私たちの魂はつながり続けている。いつも一緒に歩いているのだ。
科学では立証できないことだが、心の現実として確かに「存在」するのである。
メッセージを実感するには、何年もの歳月を経なければならなかった。不思議な偶然を何度か体験した後、やっとその意味に気がつくときが来る。
「ああ、これだけの偶然があるなら、彼女はそばにいるのだろう」
その実感を持つことが、立ち直るということなのだろうか。
以前、あるところから受けたインタビューに、私はこう答えている。
「娘を亡くしてから、仕事への打ち込み方が全く変わりました。彼女が存在した意味を、この仕事の中に込めていこう、倒産という闇に
だから、死ぬまで私は彼女と一緒なのだ。今、そこに、娘はいてくれる。いつか私が天国に行くときは、迎えに来てくれるだろう。それまでは「多くの人に出会って愛を分けてあげて」という娘の願いを胸に刻んで、自分がなすべきことをなしていきたいと思っている。
魂を賭けた医療裁判
ここで麻衣の死の原因と、その後の展開について述べたいと思う。
麻衣の死は医療関係者にとっても予想外の出来事だったようで「このような症例はめったにない」と言うばかりだった。当日の昼過ぎまでは、元気だった、回復に向かっていたという。それがなぜこれほどの急変が起きたのか。
葬儀が済むと、私は病院側に死因に関するデータ提出を求めた。だが何度も請求した末に渡されたのは翌年三月で、しかもそれはコピーの一部を切り張りしただけというずさんなものだった。
あまりに誠意のない態度に、私の疑念は深まった。「病院側は、何か隠しているのではないだろうか?」さんざん悩み、考え抜いた末、私は病院側を相手取って訴訟を起こすことを決意した。法廷闘争になれば事実が洗いざらいさらされ、再び辛い思いをしなければならないことは、弁護士である私がだれよりも知っている。それでも、「拒食症」は死に至る病との認識を病院側にしてもらい、同じ過ちを他の患者、子どもたち、そして親御さんに繰り返させないためには、真相を明らかにする必要があると考えた。これによって多くの拒食症の患者の命を救済することができれば、娘が命をもって行った問題提起の意味を見いだせるとも思った。
(この間、病院側でも麻衣の死因に関する検討会が行われ、敗血症や脳内出血など、いろいろな意見が出されたそうだ。しかし、究明するには至らなかったという)
二〇〇一年五月、私は医療裁判に詳しい弁護士二名に弁護を依頼し、横浜地裁川崎支部に訴訟を提起。それは「拒食症訴訟」として、地元の新聞にかなり詳しく載った。
妻はそのときも、
およそ二カ月に一度の、地裁通いが始まった。当初は「入院時期を早めるべきであったか否か」をめぐるやり取りだったが、医師への証人尋問が続くうち、驚くべき事実を知ることになる。
亡くなった一一月一八日の昼過ぎまで、麻衣は元気でいた。それがオレンジジュースと牛乳を一緒に飲んで間もなく、容態が急変して死に至ったというのである。
経過は以下のとおりである。
当日、三時ころ、昼寝から覚めた麻衣は、ベッドのそばにオレンジジュースと牛乳の紙パック(合計四〇〇CC)が置かれているのを認めた。その日から「経口摂取」を決めた主治医が栄養部に連絡して届けさせたものであった。飲み方に関する注意はなく、麻衣はその二つを一気に飲み干す。しばらくして嘔吐と下痢が起こり、急速に脱水症状を招いて、心臓がショック状態を起こしてしまった。
拒食状態で半年以上オレンジジュースを飲まなかった子に、それもこの三日間点滴治療で何も食事をとっていない子にいきなり嘔吐と下痢を誘発しやすいオレンジジュースと牛乳を与えたこと自体、驚きであった。飲み方も〝一気〟に飲んではいけないなどの指示はなかった。加えて初めての経口治療の開始時で、何が起こるか分からない大事な場面に主治医も研修医も不在だったので、迅速な救命措置ができなかった。主治医は「【画像】、今回のようなことにならなかったかもしれない」と証言した。これが事実なら、麻衣は病院側の医療ミスによって命を亡くしたことになる。
だが一審では、途中から明らかになったこの事実に比重を置こうとはせず、入院時期に焦点を当てたので「病院側に過失はなし」との判断が下された。
どうしても納得のいかない私は、二〇〇四年九月に控訴した。争点は「食材の誤り、与え方、後の処理」の三点に絞られ、再度の検証が行われた。
最後に分かってくれる人がいた
私は「証人」として出廷した。
裁判中、いかに真実に迫るためとは言え、娘の最後の苦しみを聞かねばならないのは辛いことだった。医者にとっては数年前に起きたことゆえ「記憶にありません」といえるものでも、私の脳裏には一つひとつの情景が昨日のことのように鮮明に思い出されてくる。というよりも、その場面が脳裏に焼きついている。証人としての発言の最中、声が震えてくることを何度か感じた。「生きていれば麻衣さんは今年、成人式だったのですね」と弁護士に問われた時は胸が詰まって声が出ず、絞り出すように「はい」と答えるのが精一杯だった。
それでも私は最後まで闘わなければと、気力を振り絞った。悲しみに浸るだけでなく、娘の死を意味のあるものにすることが父親であり、弁護士である私の役割と思った。この事件をきっかけに、患者の気持ちになって行う医療を目指してほしいとも訴えた。そしてM大学病院に対しては、「謝罪」の言葉がひとことだけでもほしかった。
高裁での審理は、的を射たスピーディなものだったと思う。二〇〇五年一一月、結審。裁判所の心証は「非は病院側にあり」であった。事実が承認されたことに、肩の荷が下りる思いだった。
裁判所は勝訴的和解を勧告した。争いごとを好まない、温和な麻衣の顔が浮かんだ。私も病院側もそれに応じることになった。和解文を作成するに当たり、私はそこに病院側の謝罪の言葉を入れることを、特にお願いした。通常の和解では「お
その裁判官室での話し合いの席上、思いがけないことが起きた。担当の裁判官が、私に穏やかな口調でこう言ったのだ。
「私にも同じくらいの年の娘がいます。ですから先生の気持ちはとてもよく分かります」
その瞬間だった。私の固く凍っていた体の中に、ひとすじのお湯の糸が注がれたような温かさが広がり、涙が一気にあふれてきた。
娘の死によって、私は「生と死」という究極のものにつきあわざるをえなくなった。
生きることより死ぬことを考える時期もあった。
でも、どんなに耐えられないと思う苦しみや悲しみも、時間と共に少しずつ和らぐものが生まれてくることを知った。そして今は彼女がそばにいることを感じる。一緒に歩いて行こうと思う。
「悲しみを乗り越えて」とよく言うが、子を失った悲しみを乗り越えるなどできるはずもないし、乗り越える必要もない。
悲しみを抱えながらも、共に生きていく。それが「再生する」ということかもしれない。そして人生は再生できるからこそ、尊いのではないだろうか。
再生し、また前に向かっていくことの命の強さと意味深さ──今も娘はそれを教えてくれていると感じている。
(つづきは製品版でお楽しみください)
ご購入はこちら▶『いのちの再建弁護士 会社と家族を生き返らせる』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
おすすめ
▷構成協力・石村博子特別寄稿「私が見た再建弁護士」
▷誰もが見放した“命”を救え! 100社以上の会社を立て直した男が見た修羅場とは?『いのちの再建弁護士』