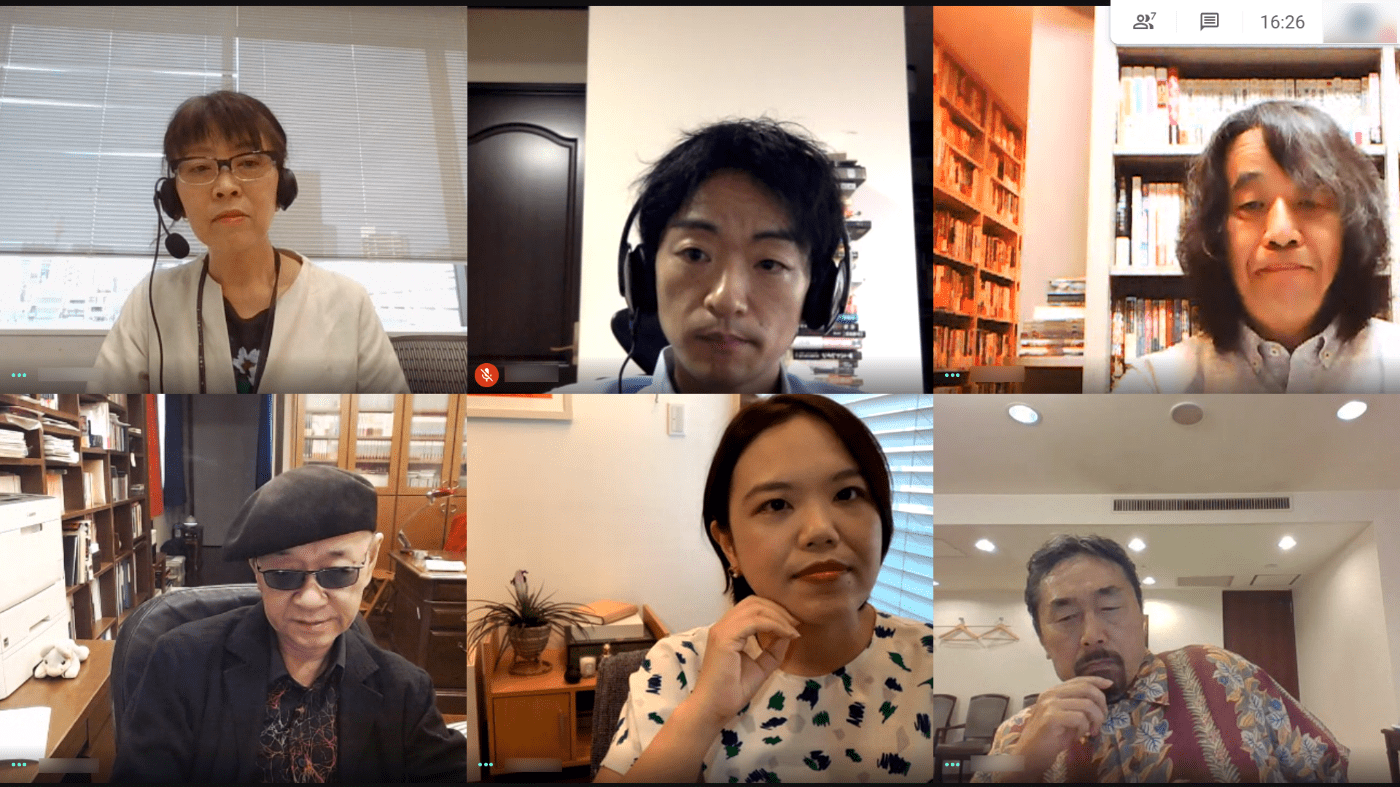KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
>>試し読み⑧へ
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み⑨
潜伏中に他の人間と接触した記述はこれが初めてだ。貞市たちの隠れ場所が知られるきっかけとなったのかもしれない。
五月十八日
待機所で日中過ごす
ネツサガラズ ゲリ
トリはアラワレズ
五月二十日
発熱 終日ウゴケズ
もしトリをシトメタラバ
どう調理するかを三人で協議 タノシミ
六月三日
イヨイヨウゴケヌ
ネツサガラズ
六月五日
食欲ナシ ウゴケズ
何も食いたくない
ニクデモ クイタイ
日増しに貞市の火喰鳥に対する執念は強まるばかりだった。そもそも食欲無しと書きながら、肉が食いたいとは妙な話だ。
そして昭和二十年のこの日、ついに日記は唐突に終わる。
六月九日
という記載が最後だった。日付のみで本文が無い。後から本文を書こうと思ったのか、あるいは書きかけのまま中断を余儀なくされたのかはわからない。とにかく、これが最終頁だ。この頁の下半分は汚れていて、くすんで色褪せたえんじ色の染みが散っている。大小三つの染みは所々かすれていて、その形は角度によっては歪んだ人の顔にも見えた。泥水が飛んだのか、あるいは貞市自身の血かもしれない。
「この日、貞市兄貴は撃たれて死んだんだ」保が日記を手元に寄せ、日付を指でなぞる。
「昭和二十年六月九日。日付も聞いてた通り?」私が尋ねると、保は仏壇の奥から一つの位牌を持ち出して卓上に置いた。漆塗りに沈金が施されたその位牌は、それなりに古びていて、黒い塗りの光沢も鈍い。
「これが兄貴の位牌。藤村さんが復員されて、戦死を伝えてくれたもんで、没年も入れられたんだ」
位牌の裏側に「俗名 久喜貞市 行年 二十二歳」と記されている。それを表側に返すと、中央の戒名の横に「昭和二十年 六月九日」と死亡日がある。終戦の直前。たしかに、この日記の最後の日付と同じだ。覚えてはいないが削られた墓石にもこの日付が刻まれていた筈だ。
玄田記者が卓上に開かれた日記と、小さな位牌をでかいカメラのファインダーにおさめる。
保がしわがれた声を絞り出した。
「この日、兄貴は具合悪くして寝込んでいたらしいでな。藤村軍曹と伊藤軍曹が食料探索に出かけて留守の間に敵に襲われたらしい。探索に出てた二人も如何ともし難かったろう」
私は久喜貞市の位牌を手にした。戒名をつるりと撫でてみる。今まで気にかけたことは無かったが、日記を読んだためか、以前よりもこの位牌に身近なものを感じた。
日記に記された最期の日。貞市は何を思っただろうか。日本に帰ることができていたら、穏やかに暮らせたろうに。そればかりか、今もこの家にいたかもしれないのだ。
「火喰鳥を食べることができていたら、大伯父は死ななかったかもしれないな」
気づけば私はそう口に出していた。
夕里子がお茶を淹れなおすと言って席を立とうとしたが、母がそれを制して出ていった。
保は手にした日記をくぼんだ目でじっと見つめている。
「いかがですか」与沢記者が口を開いた。記者としては保のコメントが欲しいのだろう。しかし日記の主の実弟は言葉少なだ。
「……うん」と言ったきり、黙り込んでしまう。
「感慨深いものがあるんだよね?」居心地の悪い沈黙に耐えかね、私は祖父の気持ちを代弁するが、保は答えない。涙でも堪えているのかと思った矢先、ようやく口を開いた。
「妙な日記だわな」
「妙……、ですか?」与沢が大きな目をぱちくりさせた。
「それは、どういったところがでしょうか?」そう問いかけたのは、終始寡黙だった夕里子だ。
その声にどこか違和感を覚えた。寡黙なのはいつものことだが、今の夕里子には思い詰めたような気配がある。私は妻の顔を見つめたものの、表情からは理由を読み取れなかった。
「どうというか……、妙な感じだわな」
与沢がメモ帳を開いてペンを握る。
「お兄様が亡くなられてから七十年以上は経ちます。今になってこうした生々しい記録が出てくるというのは、やはり不思議な感覚でしょうか?」
「いやあ、そういうことでなくて」
煮えきらない祖父の言葉に私も与沢も首を傾げた。
保は白い眉をひそめ、少し考えると、全く別のことを話し出した。
「兄貴は高等小学校卒業後、十四で陸軍に志願入隊したんだよ。兵隊さんに憧れがあったらしいわ。長男だけえど、当時うちは裕福な農家で人手も余裕あったしな。まあ精神修養の場にもなるし、時期が来たら除隊すりゃいいってことで、父も入隊を許可したんだ。ほいだけえど、こういう大きな戦争になったもんで……」
保は老眼鏡を外すと、閉じた日記を座卓の端にぽんと置く。
「跡継ぎの責任もあるしさ。兄貴は何としても日本に帰りたかったと思うわ。異国の地で死ぬなんて考えもせなんだろう。この日記を読むとさ。帰らなきゃならん、生きなきゃならんという、何か匂いみたいなものがあるわな」
自分の言うことがしっくりこないのか、保は言い終えても首をひねっている。
匂い。
それが「妙な感じ」の答えなのだろうか? 祖父にしてはやや詩的な表現だ。質問への答えにはなっていない気がする。与沢記者も戸惑った面持ちで祖父を見つめる。
「そうですね。文脈から貞市さんの必死な思いみたいなものは感じられるかもしれません……。そういえば、玄田もこの日記を初めて目にした時は感じ入ってました。ね?」
与沢の問いかけに玄田は手帳を見据えたまま答えなかった。しかし、一瞬だけ視線をゆるがしたあとに、思わぬことを言った。
「久喜貞市は生きている」
玄田の言葉にその場の空気がしんと凍りつく。
低い声色は奥座敷にじわりと染みついた。
「生きている」 玄田はもう一度、単語を擦り込むようにゆっくりと言った。
一瞬、稲光に照らされるように、久喜家の墓石が私の脳裏に浮かび、消えた。
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/