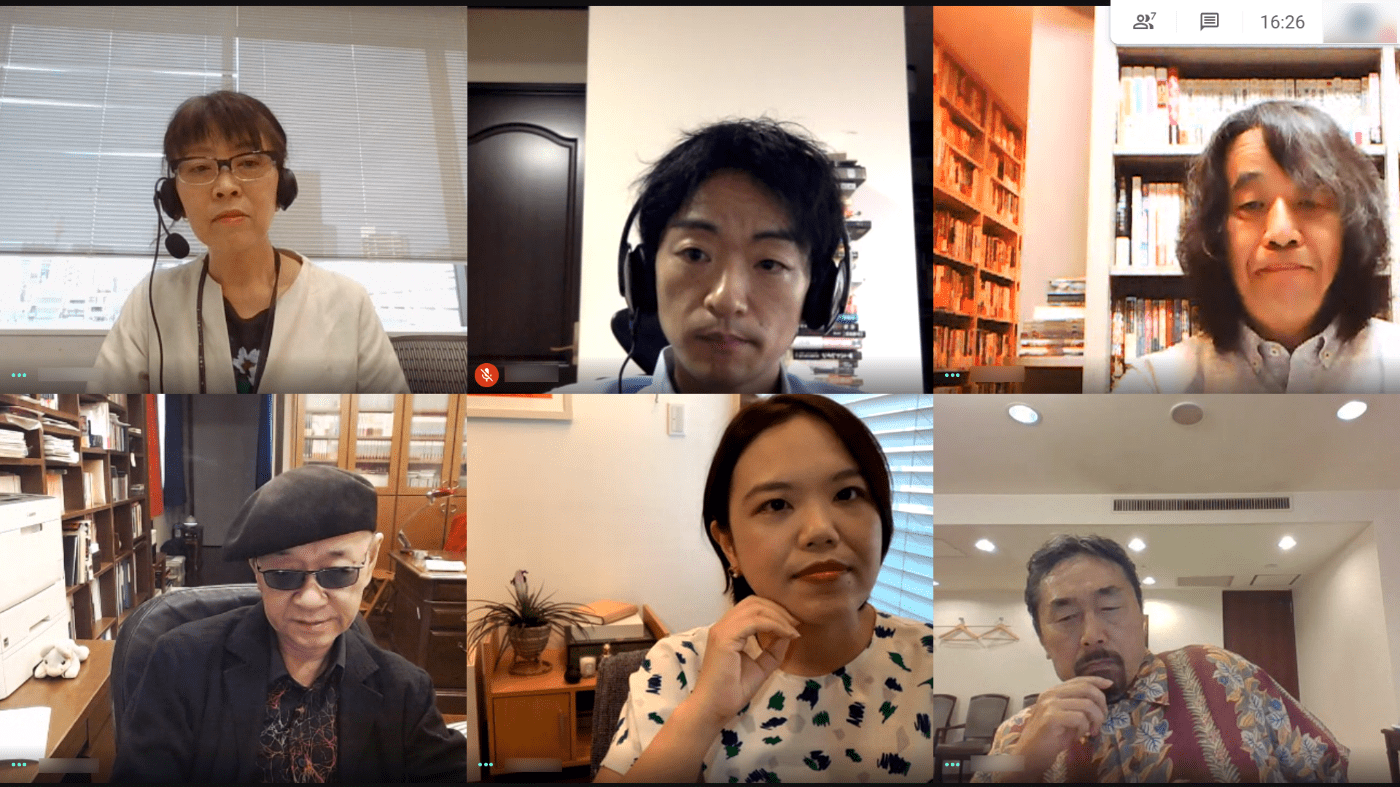KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
>>試し読み⑨へ
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み⑩
誰かに削られた墓石。生への執着が滲む日記。
日記の帰還と共に貞市が蘇り戻ってきた。
そんな幻想が駆け抜けた。気圧が変化したような奇妙な感覚に襲われる。
「ちょっと、玄田さん。一体何を……」
与沢が戸惑った様子で咎めると、玄田は頭を下げた。
「申し訳ない……。雄司さんの言うとおり、彼が、生き延びていればと」
私は夕里子と顔を見合わせた。彼女の表情は、心なしかいつもより強張っているように感じられる。保も困惑しているようだった。
エレベーターが急降下するような気持ちの悪さが続いていて、尻の下で座布団がぞわりと逆立った気がした。不穏な気配を感じたのは私だけではないのか、その場の全員が口を閉ざしたまま何の言葉も発さない。
一方で当人の玄田は何事も無かったかのように、むっつりした無表情に戻って手元のカメラを弄んでいる。なんだこいつは、と少し腹が立った。
私はふと奥座敷の暗がりに視線を走らせた。
何かがぱちりと目を覚まし、私たちを見つめているような錯覚に囚われたからだ。勿論そこには何もいやしない。
その時、
「亮?」
夕里子が小さく呼びかけた。夕里子の視線の先には、いつの間にか皆に背を向けて、縮こまって座りこむ亮の姿があった。
一目見て、ぎくりとした。
亮の頭部が消えているように見えたからだ。しかし、すぐに首が落とされたわけではなく、座したまま首が折れるほど俯いているのだと気がついた。しかし認識が追いついても、やはりそれは異様な姿だと思えた。
「亮、どうしたの?」
夕里子が再び呼びかけるが、反応は無い。
「亮!」
いつにない夕里子の大声に、その場の者は皆、夕里子を見、次に亮を見た。
亮はゆっくりと垂れた頭を持ち上げると、機械仕掛けの人形さながらに、じりじりと顔だけこちらに向けて皆を見た。ビー玉みたいな真っ黒い目玉には感情が浮かんでいない。
夕里子が重ねて問いかけた。
「何をしているの?」
亮の手にはいつのまにか貞市の日記があった。左手におさまっている日記は、頁が開かれている。右手には鉛筆を握っていた。亮は自らの手元に目を落とすと、夢から覚めたかのようにしげしげと貞市の日記を眺めている。
「もしかして、それに、何か書いたの?」
夕里子が当惑の声を上げた。
「え? ああ ……」
亮は呆けたように手の中の日記を見つめたままだ。自分自身の行動に戸惑っているようにも見えた。
「書いた?」
私が亮の手の中を覗き込むと、そこにたった今書き込んだのであろう記述が読めた。
開かれているのは貞市が最後に記した、日付だけ残された日記の最終頁。その六月九日という記載の隣に片仮名の一文が追記されている。
ヒクイドリヲ クウ ビミ ナリ
私はその文字列を口にした。
「火喰鳥を、喰う……、美味、なり……?」
声にした途端、じわりと背中に嫌な汗が滲むのを感じた。
亮はどうしてこんなことを書いたんだ?
亮の顔を見る。一瞬前まで黒く塗りつぶされていた瞳には光が戻ってきたように思えたが、日記を持つ彼の手は震えていた。
夕里子がひったくるように日記を取り上げた。
「どうして?」
姉のもっともな問いに、弟は狼狽したように首を振る。
「いや」
「どうして、いたずら書きなんて」
亮は口元を歪めた。
「自分でも……、よくわからない」
「わからないって……」
夕里子はまじまじと弟の顔を見つめた。どう考えても様子がおかしいが、亮が嘘をついているようには思えない。
亮は膝の上で拳を握り締めている。まだわずかに震えているようだ。
「腹が減ったら……、死ぬから、だから……」人ごとのように呟き、慌てて私に詫びた。「すみません。貴重な日記に……。ぼうっとしていたら、気づいたら書いちゃって」
私は返答につまった。与沢がとりなすように言葉を足した。
「壮絶な内容ですから。毒気のようなものに当てられてしまったのかもしれません。若い方には刺激が強いといいますか、きつい内容ですし。ね? 玄田さん」
振られた玄田記者は、髭を撫でると、同意したつもりか、む、と一言返した。
そんなことがあるものなのか。亮は軽口を叩き、場の空気を読めない傾向の青年だが、決して非常識ではない。彼の様子は自分の意思というよりも、何かに憑かれているように見えた。
久喜貞市は生きている。
玄田の一言から訪れた、空気が色を濁らせたような異様な気配が抜けない。
私はまた座敷の闇だまりに視線を走らせた。
奥座敷は風通しもよく陽当たりも良い。それでも和室の最奥には常に濃い暗がりがある。その一角だけが子供の頃から怖かった。よくわからない何かが、暗がりからニタリニタリとこちらを見つめている。そんな空想に囚われていたからだ。
今、その感覚が蘇っていた。背筋を冷えた汗が垂れていくのを感じる。
保は夕里子の手にある日記を黙然と見つめていたが、やがてのそりと腰を上げた。
私は声をかけようとして言葉を飲み込んだ。保の顔色は白く乾き、極度の疲労に困憊して見えたからだ。黙ったまま座敷を出ていくその背中に、誰も声をかけられなかった。
夕里子は道具箱から消しゴムを取り出すと、亮が書き込んだ部分を擦り始めた。
「いいよ、そのままで。破れちゃうよ、古い紙だから」
私は制止するが、夕里子は無視して紙面を擦り続ける。まるで何かに焦っているようだ。夕里子の様子は先程からやはりどこかおかしい。彼女の示す感情の起伏がいつもより激しいのだ。
やがて、少しばかり筆圧による跡が残ったものの、「ヒクイドリヲ クウ」の一文は綺麗に消えた。
(気になるつづきは本書でお楽しみください)
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/