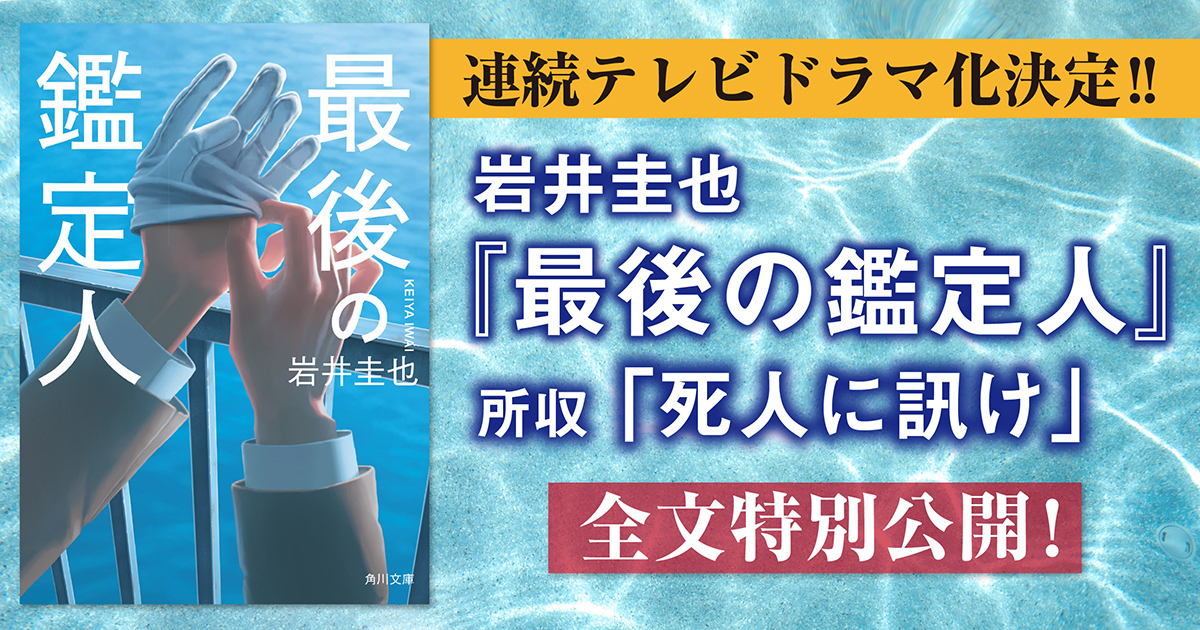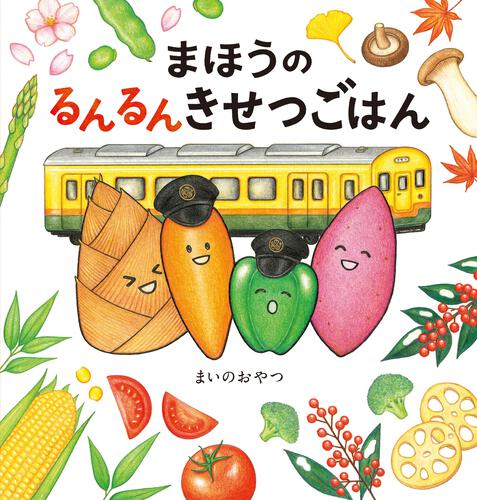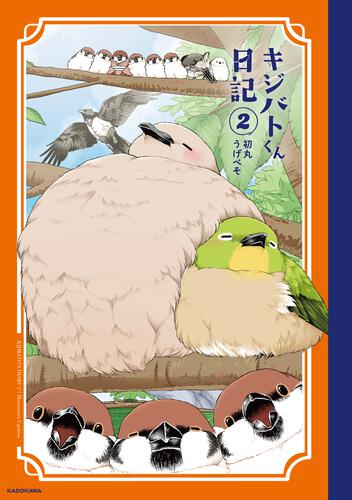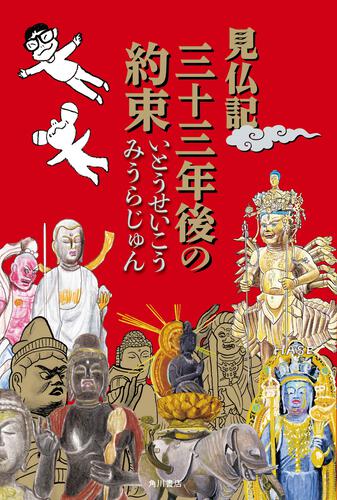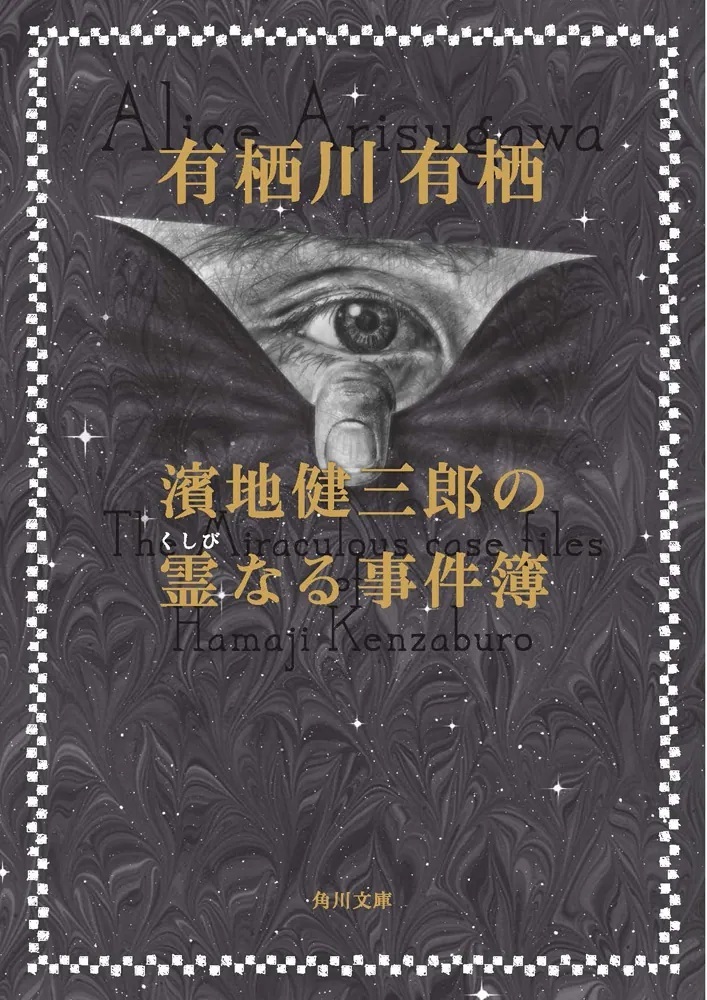岩井圭也さんが手掛ける、心揺さぶるサイエンス×ミステリ『最後の鑑定人』。
連続テレビドラマ化決定&待望の文庫化(2025年6月17日発売)を記念して、ドラマ第1話の原作にあたる「死人に訊け」を全文特別公開します!
「科学は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつだって人間です」
孤高の天才鑑定人・土門誠の華麗なる事件簿を、どうぞお楽しみください。
岩井圭也『最後の鑑定人』試し読み
死人に訊け
薄灰色の空を背負った三階建てのビルは、鼠色に塗装されていた。装飾は一切なく、建物というより大きな箱に見える。
都丸勇人は自分の心境を反映したような空模様を見上げ、ため息を吐いた。手に提げた鞄はずしりと重い。捜査資料のコピーが限界まで詰め込まれているせいだ。
――厄介払いか。
そんな言葉がよぎった。
高校を卒業し、Ⅲ類で警視庁に入ってからずっと刑事に憧れていた。二十六歳でようやく刑事部門に配属され、前任の署と合わせて経験は四年半。現在の所属である大田署強行犯捜査係に異動してからは一年と少し。三十一歳の巡査部長ともなれば、脂は乗り切っている。実績も同年代の連中に負けていると思わない。そんな都丸が使い走りに出されたのだ。しかも、都内とはいえ遠方にある民間の鑑定所にまで。
面白いわけがない。
事件そのものは重大だ。都丸だけでなく多くの捜査員が動いている。解決への意欲は高い。しかしよりによって、与えられた任務がこれでは意欲も萎えるというものだ。
係長の三浦との会話を思い出す。
「都丸。こっち来い」
会議後、捜査員たちが解散した直後に呼ばれた。身長百八十五センチ、体重百キロ超の三浦が放つ威圧感は並大抵ではない。すかさず飛んで行った都丸に、三浦は「お前に仕事だ」と言った。煙草の臭いが混ざった息が顔にかかる。
「鑑定は外部に頼むぞ。科捜研や科警研は時間がかかる。お前、依頼に行け」
反感が露骨に顔に出ていたのだろう、三浦の強面がさらにいかつくなっていく。
「なんだ、その顔。任された仕事一つ満足にできねえのか」
「できます」
「だよな。こっちはお前が適任だと思って呼んでるんだ。しっかりやれ」
そう言って三浦が懐から取り出したのは、古びた名刺だった。〈土門誠〉という名前が記されている。肩書きは〈土門鑑定所代表〉。科捜研以外の分析機関に依頼をした経験はあるが、初めて聞く名だった。
「有名な方なんですか」
「元科捜研だ。昔は世話になった……いいか。十二年も経った事件を掘り返すには、普通の方法じゃ無理だ。お前の役目が鍵だぞ。しっかりやれ」
名刺をしまった三浦は都丸の背中を叩き、さっさと会議室を出て行った。気乗りはしないが、上司の命令に背くほど向こう見ずではない。都丸はさっそく、土門鑑定所のウェブサイトから面談を予約した。
一見して、建物の外観は民家のようでもある。知らなければ、まず科学鑑定の事務所だとは気づかないだろう。約束の三時より十五分ほど早いが、周囲には時間を潰すような場所もない。呼吸を整え、インターホンを押す。
「はい、土門鑑定所です」
女性の声が返ってきた。
「警視庁の都丸ですが」
「少々お待ちください」
すぐにドアが開いた。現れたのは同年代の女性である。白のシャツに黒のパンツという地味な服装だが、顔に浮かんだ笑みは朗らかな印象を与えた。
「助手の高倉といいます。どうぞ」
都丸は一礼を返す。
高倉の案内で廊下を抜けた先に応接間があった。部屋の中央にはソファセットが置かれている。都丸は奥にあるスチールの扉を背にする恰好で座って待つよう、案内された。腰を下ろすより先に、天井付近に設置されたカメラに気が付いた。
「防犯ですか」
「ええ。気になさらないでください」
高倉はにこりと笑ってみせるが、カメラへの違和感は拭えない。公共施設ならともかく個人の事務所に、しかも、応接室に堂々と設置するものだろうか。
カメラから目を逸らしつつ待っていると、水の入ったグラスを出された。礼を言って口をつけると、猛烈な青臭さが鼻に抜けた。雑草を煮詰めたような風味に襲われる。うっ、と呻き声が漏れたが、どうにか吐き出すことは耐えた。
「よければ、感想いただけませんか。これ、私がブレンドしたハーブ水なんです」
「……面白い味ですね」
「おいしかったですか?」
「まあ、一応」
答えると、高倉は都丸の顔をじっと覗き込んできた。噓だとばれているのだろうか。都丸はスチール扉を振り向くふりをして、顔を背ける。しばらくすると彼女は「なるほど」とつぶやき、部屋の片隅にあるデスクへと去っていった。
――どうなってんだ、ここは。
カメラと言い、高倉の応対と言い、普通の事務所とは思えない。これは相当な変わり者が出てくるかもしれない。三浦は若い頃からやり手で有名だったと聞いているが、その三浦が世話になった、と言うほどの人物なのだろうか?
勘繰っているうちに、約束の時刻となった。同時に背後の扉が開く。
現れた男は、一見してどこにでもいる会社員のような見てくれだった。四十代半ばくらいの瘦せた風貌。三浦ほどではないが背は高い。ベージュのジャケットとパンツに無難な髪形。能面のような無表情でこちらを観察する態度からは、取っつきにくい印象を受ける。
都丸は、黙って向かいのソファに座ろうとする相手にすかさず近づき、名刺を差し出した。
「大田警察署の都丸勇人です」
「土門です」
そう言って、思い出したように名刺を手渡してくる。元警視庁の先輩ではあるが、それにしても愛想のない反応だ。都丸は勢いをつけ、再び尻を落とした。ソファのスプリングがきしむ。
「土門さん、以前は警視庁にいらっしゃったとか」
まずは相手の過去を知るのが先決だ。自分が名前を知らないということは、すでに警視庁を辞めて相当の時間が経っているはずだった。若手とはいえ、こちらは現役である。立場の違いを思い知らせて、主導権を握るのだ。意気込むほど都丸の眼光は鋭くなる。
「ええ。科捜研に」
「当時から三浦係長とは知り合いで? 係長は昔、世話になったと……」
「前置きは結構。本題をお願いします」
土門の低い声音に、都丸の瞼が小刻みに痙攣する。深呼吸で気持ちを落ち着ける。ここでペースを崩せば、相手の思う壺だ。
「ご相談したいのは法医学鑑定です。先日、相模湾から遺体が引き揚げられました」
語りだした都丸の顔から、土門は視線を外さない。
潜り漁を行っていた神奈川県の漁師が、海底に沈んでいる軽自動車を発見したのは十月二日だった。
車内には白骨化した遺体があり、通報先である神奈川県警が車を引き揚げた。警察は遺体の人物特定をはじめたが、相当古いものであり作業は困難を極めた。車内の所持品もほとんどなく、遺体そのものも白骨化しており身元は不明。ナンバーなどの情報から、車は十二年前、新宿の営業所で借りられたレンタカーであることまでは突き止めた。だがレンタカー会社がすでに倒産し、資料が散逸していることから、借り手の名義などは特定できなかった。
唯一の手掛かりは、後部荷室に詰め込まれていた大量の宝飾品である。車内に財布すら残されていない状況でありながら、荷室には貴金属の指輪やネックレスといった高価な宝飾品が多数収納されていたのだ。
出所を探ったところ、これらはすべて大田区内で十二年前に発生した強盗殺人事件の盗品であることが判明した。当夜盗まれた品物は一つ残らず揃っていた。
事件の被害者は質店を営んでいた男性とその妻で、いずれも刺殺されている。防犯カメラの映像には一部始終も収められていた。深夜、防犯設備を破壊して侵入した三人組の犯人は、すぐさまショーウインドウを叩き壊して商品を強奪。現場に駆け付けた店主夫婦をその場で殺害した。被害総額は約二億円に上る。
当時、警視庁はすぐさま大々的な捜査を展開した。映像記録をはじめ、手掛かりが多数残されているため、犯人逮捕は時間の問題と思われていた。だが、予想に反して捜査は難航。頼みのカメラ映像は画質が悪く、犯人たちは三人ともマスクにニット帽という出で立ちで、顔つきは見てとれない。犯人の足取りはつかめず、成果を挙げられないまま捜査本部は解散した。
レンタカーの白骨遺体は、この事件と何らかのかかわりを持っていると見て間違いない。仮に犯人の一人だとすると、身元が割れれば、残る二人へとつながる重大なヒントになる。
十二年前の未解決事件がにわかに動き出した。事件を管轄していた大田署強行犯捜査係では多数の捜査員が投入され、遺体の身元特定を急いでいる。
「科捜研の見立ては? DNA鑑定はやったんでしょう」
事件の概要をまとめた書類に目を通しながら、土門が尋ねた。都丸は首を横に振る。
「衣類から、中肉中背の男性ということは推定されています。DNA鑑定では、血液型がB型ということ以外わからなかったようで。遺体が古いものですから」
「条件は?」
即座に返ってきた質問が何を問うているのか、都丸には理解できない。ぽかんとした顔で見返すと、土門は「鑑定の条件ですよ」と付け加えた。
「DNA鑑定にも色々やり方があります。結果なんて、手順一つでいくらでも変わりますから。できればプロトコルまで示されているものがよいですが」
そんな細かい内容を気にしたことは、一度もなかった。都丸は慌てて鞄の中身を漁る。相手が鑑定人ということで、鑑識や科捜研の鑑定結果に関する資料は一通り持参していたが、そもそもどれが求められているものか判断がつかなかった。仕方なく資料の束を丸ごと手渡す。
土門は能面のように感情のない顔つきで資料をあらため、しばらくすると「これですね」とつぶやいて薄い冊子を抜き取った。科捜研が作成した報告書か何かだ。熟読している間、都丸は手持ちぶさたな思いで待つしかなかった。
「うん、なるほど」
十分ほど書面を読んでいた土門は、冊子を閉じて断言した。
「DNA抽出の方法に検討の余地があります」
「……つまり、科捜研のやり方に文句があると?」
あえて怒りを煽るような言葉を選んだのは、土門の本心が見えないせいだった。心の揺れがなく、あまりに淡々と話を進める土門は、冷静を通り越して不気味だ。挑発すれば多少は気分を害するかと思ったが、土門はまったくぶれのない口調で「わからなければ説明します」と、さらに都丸の神経を逆撫でするようなことを言う。
「説明ね。ええ、ええ、お願いしますよ」
瞼がさらに痙攣する。
「白骨化した遺体の場合は必然的に試料が骨や歯となり、これらは脂肪や筋肉のような軟部組織に比べて抽出が困難です。抽出方法にもいくつかありますが、なぜかフェノール・クロロホルム法とプレップ法を選んでいます。近年はキアゲンのキットを使うのが常道なので、まずは手法自体を見直すべきでしょうね。DNA濃度の検討も不十分です。これは憶測ですが、別の鑑定と重なったため、まとめて実施されたのかもしれません」
大学の講義でも聴いているような気分だった。話の半分も理解できない。
「要するに、うちのやり方は甘いってことですか」
「今の科捜研がどんな手法を採用しているのか知りませんが、この報告書に関して言えば、検討が甘いと言わざるを得ません」
平板な口調で言いながら、土門は報告書をローテーブルに置いた。
「他の資料も拝見して構いませんか」
気づけば土門が会話をリードしている。都丸は奥歯を嚙みしめながら「どうぞ」と応じるのが精一杯だった。
しばらく、土門が資料を精査する時間が取られた。都丸は時おり投げかけられる質問に答える程度で他にやることはなかった。高倉と話して退屈をしのごうと思ったが、彼女も忙しなくキーボードを叩いており、気安く話しかけられる雰囲気ではない。二十分ほど待ったが、それ以上留まっている意味はなさそうだった。
「今日はお暇します。コピーはいったん預けますんで」
ソファから立ち上がった都丸を一瞥し、土門は「一つだけ」と言った。
「復顔は、もうされましたか」
復顔とは、頭蓋骨の形から生前の顔つきを復元する方法である。都丸の記憶では、そのような試みはしていない。
「その、復顔っていうのをやれば、元の顔がわかるんですか」
「簡単ではありませんがね。頭蓋骨だけでは、軟部組織の情報が一切ありませんから。瘦せているか、太っているかもわからない。ただ、最近は3D復顔法が発達して、精度も上がってきました」
「へえ。なら、科捜研もさっさとやればいい」
「誰でもできるわけではありません。正確な復顔にはデータが必要です。特に、顔面の軟部組織の厚みを計測したデータが。たとえば、鼻や頰の厚みなどですね。それは私の手元にもない。あるとすれば、科警研ということになりますが……」
断定的だった土門が、そこで言葉を濁した。
科学知識に疎い都丸でも、科捜研と科警研の違いは知っている。科学捜査研究所(科捜研)が都道府県警察の附属機関であるのに対して、科学警察研究所(科警研)は警察庁の附属機関だ。科警研では、科学捜査に関する研究や機器開発、高度な分析や鑑定、全国にある科捜研への指導などを担当している。
「つまり、土門さんでも復顔はできないということですか」
都丸は再び挑発するような台詞を吐いたが、答えは返ってこない。眼中にない、と言われているようでまた腹が立つ。
去り際、玄関で高倉が見送ってくれた。
「いつもああいう感じなんですか、あの人」
問いかけに、高倉は困ったような笑みを見せた。
「今日はましなほうですね」
呆れた都丸は軽くなった鞄を提げ、土門鑑定所を後にした。三浦の推薦だが、もうここへ来る必要はなさそうだ。資料のコピーは郵送で返却してもらおう、と気の早いことを考えていた。
翌日、大田署のデスクにいた都丸の携帯電話が鳴った。反射的に電話に出た都丸は「土門ですが」という声を聞いて、思わず顔をしかめた。
「お世話になります。資料の返却ですか」
「いえ。DNA鑑定の準備が整ったので、検体を送ってください」
土門は淡々と語る。まるで、依頼することは決定事項だと言わんばかりだった。都丸は「ちょっと」と慌てる。
「待ってください。あなたに頼むとは一言も……」
「待つのは結構ですが、いいんですか。早々に着手したほうがよいのでは」
視線を上げると、離れた席にいる三浦と目が合った。三白眼が細められる。今にも怒鳴られそうだった。躊躇している暇はない。都丸は携帯電話から顔を離し、舌打ちをした。
「わかりましたよ。手配します」
「もう一つ」
「まだあるんですか」
「資料に骨の緻密質写真がありますが、不鮮明なのでこちらで撮影し直します。観察用の資料が残っていれば送ってもらえますか。依頼書もお願いします」
用が済むと、電話はあっさり切られた。事務所で会った時と同じく、どこまでも自分勝手な態度である。土門の指示を聞きながら書いたメモを見直していると、席を立った三浦が近づいてきた。立ち上がった都丸に凄みの利いた声音で話しかける。
「今の電話、土門さんだろう」
「そうです」
「変わった人だが、腕は信じていい。勉強させてもらえ」
それだけ言い残して去っていく。
実際、鑑定人としての腕はいいのかもしれない。飲み込みも早く、頭の回転は速そうだ。だが、都丸に与えられた役割は所詮メッセンジャーに過ぎない。新人にでもこなせる雑用のはずだ。厄介払いされたのだという意識は変わらなかった。
その日は署で溜まりに溜まった書類仕事を片付けた。全部は終わらなかったが、あらかた処理した午後十一時、ようやく帰途についた。
退勤後の都丸は疲れ果てた身体を引きずって歩く。深夜の町は寂しい。
アパートの扉を開けると、視界に飛び込んでくるのは散らかり放題の我が家である。恋人と別れてからのこの一年、特にひどい。流しはカップ麵の容器や割り箸、発泡酒の空き缶で一杯になっている。床には洗濯前後の衣類がいっしょくたになって散乱していた。
ワンルームの照明をつければ、惨状はより明らかになる。雑誌や書類、脱ぎ散らかした靴下、使っていない鞄、カードにレシート、その他雑多な小物たちがフローリングの上に乱雑に配置されていた。
――荒んでるな。
そう思いつつ、片付ける気力は湧いてこない。座卓の上にスペースを作り、コンビニ弁当と発泡酒のロング缶で遅い夕食をはじめた。物音がしないと寂しいため、スマートフォンで適当に音楽を流す。
独身寮の頃は、こんなところ一日でも早く出てやると思っていた。しかし不思議なもので、アパートで一人暮らしをしていると、ごくたまに寮が恋しくなる。同じ屋根の下に職場の仲間がいて、言葉を交わさずとも互いの頑張りが感じられる。もがいているのは自分だけではない、と思える。
早食いの習慣がついているせいで、食事はあっという間に終わる。飲みかけの発泡酒を口に運びながら横になった。
家にいても、考えるのは事件のことばかりだった。抱えているいくつかの案件が頭をよぎる。日中は膨大な書類仕事に追われてじっくり考える余裕がない。むしろ私的な時間のほうが、捜査の背景や些末な事柄にまで考えが及ぶ。
真っ先に浮かんだのは、やはり十二年前の強殺事件だった。
店主夫婦は刃物で刺殺されている。つまり、犯人たちには最初から危害を加える意図があった。そんな凶悪犯が司法の手を逃れ、今も平然と暮らしていることに憤りを抑えきれない。相模湾の底から見つかった車は、連中を裁く最大にして最後のヒントだ。
昨日面談した土門の無表情が浮かぶ。愛想がなく、不遜な態度の鑑定人。本当に彼を信じていいのだろうか。もっと、他にやるべきことがあるのではないか。
だんだん心がささくれだってくる。捜査の本流から外された自分が情けない。苛立ちを紛らすためにシャワーを浴びた。
例の強殺事件が起こったのは、都丸が警視庁に採用されたのと同じ年だ。警察学校で訓練を受け、初の交番勤務に緊張しながら一夜を過ごしたあの年、盗品を載せた車は海底に沈んだ。そして今、当時の新人だった自分が引き揚げられた車の遺体を特定しようとしている。縁とも呼べない偶然の一致だが、そう考えるとなぜか十二年という時が短く感じられる。
警察官を志したのも、刑事への憧れがあったからだ。最初は単純に、その恰好良さに惹かれた。ドラマやマンガで活躍する刑事は颯爽として、いかにも警察の花形部門に見えた。採用されてからは事務仕事の多さや過酷な勤務形態を知ったが、熱意が薄れることはなかった。刑事部門への配属を伝えられた時は、人生で一番嬉しかった。
捜査員になる前は交番勤務や内勤も経験した。それらの仕事には終着点がない。治安を維持すること、あるいは組織を回すことが目的だ。だが刑事の仕事には一応のゴールがある。それだけに、ゴールできなかった時の無念は計り知れない。
都丸の肩に、十二年前の捜査員たちの未練がのしかかっている。
浴室を出た都丸は、洗濯したのかどうかもわからないスウェットを身に着け、髪も乾かさずベッドに潜り込んだ。明日の朝も早い。直前まで事件のことを考えながら、気絶するように眠りに落ちた。
それからの一週間、新たなヒントは得られなかった。
レンタカーの借り手は依然見つからず、目撃情報もない。十二年前の事件の目撃者を探すこと自体、無謀ではあった。遺体の線も手掛かりは少なく、歯型の照合も該当なし。衣類も全国の量販店で販売されていたものであり、生前の行動特定にはつながらない。当時の防犯カメラ映像も確認されたが、画質が悪く、顔貌はおろか年齢すら推測できない。
捜査員たちの顔に疲労が滲みはじめた。解決にさえ向かっていれば、体力的に辛くても顔色は潑剌としているものだが、署内に詰める彼らの顔は冴えない。徒労感をやり過ごすことには慣れているはずだが、重大事件への意気込みがあった分、空振りへの落胆も少なくなかった。土門からの連絡がないのをいいことに、都丸も遺体が発見された現場周辺の聞き取りに加わったが、成果と呼べるものは挙げられていない。
その日の午前中、強行犯捜査係の陰鬱な空気を切り裂くように、都丸の携帯電話が鳴った。土門の番号である。
「お待たせしました。その後、いかがですか」
「特に進展はありません」
苦々しい都丸の応答に、電話の向こうの相手は「そうですか」と平坦な声で応じた。
「取り急ぎ、鑑定結果をお伝えします。DNA鑑定の結果、遺体の血液型がB型のなかでもBO型であることが判明しました。また緻密質の観察結果から、年齢は二十代から三十代と推察されます」
「……は?」
まるで自明であるかのように、土門は新事実をすらすらと口にする。
「報告書は追って提出します。まずは進捗の共有まで」
「え、あの……科捜研が送ったのと同じ検体ですよね」
「もちろんです。念のため、着荷記録も残しています」
都丸は唾を飲んだ。遺体発見からおよそひと月。科捜研では突き止められなかった事実が、土門に依頼して一週間で明かされた。にわかには信じがたい。だが三浦の言う通り、この男の腕はどうやら本物らしい。
「疑わしければ、再鑑定しても結構ですが。追加料金はかかりますよ」
土門は沈黙を疑念と受け取ったらしい。都丸は慌てて「とんでもない」と言い、資料を急ぎメール送付するよう求めた。
通話を終えてしばらくしてから、心臓が高鳴っていることに気付いた。詳細な血液型と、おおよその年齢だけでも収穫だ。捜査員がほうぼう駆け回ってもつかめなかった事実を、土門はいとも簡単に示してみせた。科捜研が怠けていたのではない。あの男の技術が異常なのだ。
鑑定資料がメールで届くと、都丸は係の捜査員を会議室に集めた。そこには三浦係長の姿もある。鑑定資料を回覧し、明らかになった新事実を告げると一同がざわめいた。久しぶりの新情報に、捜査員たちは顔を上気させる。
「次は?」
一人、冷静なのは三浦係長だった。都丸は背筋を伸ばす。次の手を考えていない、とは口が裂けても言えない。
「先方と協議中です」
「早くしろ。遺体をもう少しほじくるのか、それとも証拠品の鑑定か。土門さんは毎度依頼を受けるわけじゃねえ。せっかく受任させたんだ、やれるところまでやれ。お前がコントロールするんだ。この情報、無駄にするなよ」
三浦の一喝に捜査員たちの緊張が高まる。先ほどまで憂鬱さに覆われていた空気が、劇的に変化していく。引き金となったのは土門がもたらした新情報だ。
都丸は密かに奥歯を嚙んだ。
こういう場面に立ち会うのは初めてではない。鑑識からの情報が捜査員の士気を左右する光景は幾度も見てきた。科学鑑定はたびたび捜査の突破口になると知っていたのに。それなのに都丸は土門との関係構築を軽んじた。
三浦には初めからわかっていたのだ。この事件は鑑定が肝になる。だから確かな技術を持つ土門に依頼し、その連絡役を自分に託した。厄介払いではない。都丸の熱意を信じて任命したのだ。
――俺はバカか。
これはただの雑用ではない。事件解決にかかわる大役だ。
会議室を出てすぐ、都丸は土門の携帯番号にかけた。
「土門さん」
「……何でしょう」
勢い込んだ都丸の声にも動じず、冷静な言葉が返ってくる。
「復顔がどうとか仰ってましたね」
「ああ。遺体の復顔ができれば有力な手掛かりになるでしょうね。しかし軟部組織のデータはありませんから、私にはどうしようも」
「科警研ならあるんですよね」
都丸は相手の語りを遮った。自然と声が大きくなる。
「私が科警研との渡りをつけます。データがあれば、復顔に取り組んでもらえますか」
鼻息荒く返答を待つ都丸に、土門はしばしの沈黙を挟んで答える。
「法科学第一部の尾藤主任が詳しいはずです。問い合わせてください」
事実上の了解だった。科警研のデータさえあれば復顔を引き受ける。土門がやる以上、きっと無駄にはならない。尾藤の名を手帳に書き込んだ都丸は「わかりました」と応じ、通話を切った。すかさず次の行動に移る。
科警研の連絡先を調べ出すのに、そう時間はかからなかった。
目の前の尾藤宏香は足を組み、テーブルに右肘を突いていた。瞼を閉じ、右手でこめかみの辺りを揉んでいる。気だるそうな態度から歓迎の意図は感じられない。
四十歳前後と思しき尾藤は、一見して企業の管理職といった風情である。黒のブラウスやベージュのパンツは皺一つなく、シンプルだが安物ではないとわかる。ショートの髪をしきりに耳にかけていた。
「……それで、土門先生とノコノコ来たってこと」
先生、という言葉からは精一杯の悪意を感じる。
「なんで当日になって言うわけ?」
「鑑定人を連れて行くことはお伝えしていました」
「鑑定って言えば、普通は科捜研でしょ。部外者だと思わない。ここに入るのだって素通りじゃないんだから」
つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅からタクシーで三分の位置にある、科学警察研究所。都丸はその一室にいた。隣には土門誠。対面には主任研究官の尾藤と、部下である男性研究官が座っている。
確かに、尾藤の言い分は正しい。鑑定人の名前を伝えなかったのは都丸の落ち度だ。だが、それは意図してのことだった。土門から「私の名を出すと会わないかもしれない」と言われていたため、あえて氏名を伝えなかったのだ。
「秘密保持契約は締結しています。それに土門さんは元科捜研です」
「元、ね。今は部外者」
不毛さに飽きたのか、尾藤は自ら「まあいいや」と議論を打ち切った。
「用件はだいたいわかった。身元不明の白骨遺体から、生前の通りに復顔しろ、と。せめて候補とかいないの。スーパーインポーズ法なら、もっと精度が上がるんだけど」
「何です、それ」
尾藤が土門のほうに顎をしゃくる。そっちに訊け、ということらしい。
「白骨遺体の頭蓋骨と、対象者の生前の写真とを比較する方法です。一から復顔するより、異同の判定を下すほうが確実ですから」
土門は淡々と説明する。不機嫌な尾藤を前にしても、一切動揺を見せない。
「防犯カメラの映像があるじゃないですか。犯人の一人かどうかはわかるのでは?」
「マスクとニット帽の映像では、顔貌がわかりません」
都丸の安易な提案は、即座に却下された。自然と顔が渋くなる。
「……現時点で、候補になり得る人物はいません」
「でしょうね。だから復顔するんだもんねえ」
尾藤は粘っこく、語尾を伸ばした。都丸の瞼が痙攣をはじめる。
「とにかく、軟部組織の計測データをください。あとはこちらでやります」
「お断りします」
即答だった。高らかに言い放った余韻が室内に漂っている。都丸が反論しようとすると、それより早く、黙っていた男性研究官が割り込んできた。
「復顔は我々が担当します」
科警研に復顔を依頼した覚えはない。求めたのは土門へのデータ提供のはずだが、話が予期せぬ方向に転がっている。啞然とする都丸を差し置き、男性研究官は眼鏡のブリッジを押し上げて語りだす。
「科警研では、最新の3Dデジタル復顔アプリケーションを開発しています。研究官はベルギーやオーストラリアの研究機関に赴任し、数理解析技術を習得してきました。科捜研を離れて久しい土門先生よりも、我々に一日の長があると思料します」
持って回ったような言い方に、都丸の背筋がむずがゆくなる。要は、土門よりも自分たちのほうがうまくやれると言いたいらしい。
「依頼すれば受けるということですか」
「当たり前でしょう。だいたい、こういう話はまず科警研に持ってくるべきで、順番がおかしいの。いきなり民間に持っていくなんてあり得ない」
尾藤の口ぶりは刺々しい。
捜査員の立場からすれば、復顔さえ行ってくれるならどちらでも構わない。科警研が最新技術を持っているというのも噓ではないだろう。それでも、都丸は土門への期待を捨て去ることができなかった。
「できる限り早く、結果を出してほしいんです。科警研にその余裕がありますか」
「緊急性が高いと判断すれば、優先順位は上げる」
「しかし……」
「しつこい。民間は民間らしく民事をやってればいい。刑事に首突っ込まないで」
尾藤は腕を組み、一段と高い声を上げた。都丸というより土門への発言である。
都丸は激しく引き攣る瞼を、指で押さえた。もともと気の長い性質ではない。怒鳴りだしたい衝動を堪えて、反論の術を考える。しかし怒りを鎮めている間に、土門が「いいんじゃないですか」と言い出した。
「科警研でやっていただくほうが合理的ですから。計測データを所外に持ち出すのも容易ではないでしょうし。復顔は尾藤主任にお任せします。私より正確にできるなら、の話ですが」
最後の一言に、尾藤と男性研究官の表情がこわばる。土門にしては珍しく、感情が透けて見える発言だった。明らかに挑発している。
「何それ。鼻につく言い方」
「事実を言っているだけです。そちらはじっくり復顔されたら良い。私は他の道筋から着手します。鑑定すべき試料はいくらでもありますから」
土門は口の端をわずかに歪めた。微妙な変化だが、確かに笑っている。対照的に、尾藤は眉間に深い皺を刻んでいた。鋭い目つきで都丸を睨む。
「そっちから、すぐに正式に依頼出して。所内の話はつけておくから。事件の資料も一式送って。他にできることがないか検討する。急いでやればいいんでしょう」
「そうしていただけると」
結局、反論するより先に科警研での復顔が決まってしまった。またも土門の独断が先行したが、今さら引き返せる空気でもない。何より、科警研が速やかに結果を出してくれるならそれはそれで助かる。
連れ立って科警研を後にした都丸と土門は、駅まで歩くことにした。徒歩でも十五分ほどで駅に着く。公園の緑を左手に見ながら、人気のない郊外の歩道を並んで進む。吹く風の冷たさは秋の終わりを告げていた。
「尾藤主任とは古い知り合いで?」
「ええ、それなりに」
少しでも距離を縮めようと話しかけたが、土門はあくまで簡潔に答える。深入りを避けたがるような気配を感じ、話題を変えた。
「他の試料も鑑定してもらえるんですか」
「乗りかかった船ですから、付き合いますよ。もちろん料金はいただきますが」
土門の横顔を窺う。先ほどの微笑はとっくに消え、能面のような無表情に戻っていた。感情はなく口だけが動いている。
「遺体の人物はなぜ、盗んだ宝飾品もろとも海に沈んだか。ここが鍵です」
「憶測ですが、自殺の可能性は高いと考えています」
都丸が言った。自殺説は、捜査員たちの間で最も有力と見られている。遺体が強盗殺人犯の一人だとすれば、罪の意識に苛まれ、盗品を道連れに自殺したというシナリオは一応筋が通っている。ただし違和感が拭いきれないのも事実だった。
「他の可能性もなくはないですね。たとえば、車だけを沈めて脱出するつもりが失敗したのかもしれない。誤発進で海へと落ちてしまったのかもしれない。あるいは……何者かによって殺されたのかもしれない」
捜査員たちもそれらの可能性を考えていないわけではない。いずれにせよ現状では憶測に過ぎない。遺体の人物を特定しない限り、生前の行動を追うのは困難だった。
「車と防犯カメラ。この二点から攻めましょう」
土門の横顔に変化はない。ただしその目の色は、依頼前に比べるとわずかに輝いて見えた。
翌週、都丸はセダンのハンドルを握っていた。
横目で助手席を窺うと、土門は太ももの上にノートパソコンを広げて作業をしている。乗り物酔いしやすい都丸には到底できない芸当だった。画面を覗くと、細かい英数字が羅列している。理解することを放棄して、運転に集中する。
赤信号で停止すると、珍しく「いいですか」と土門のほうから話しかけてきた。
「レンタカー会社の記録は、散逸して入手困難ですよね」
「ええ」
「映像も残っていませんか」
レンタカーの営業所では、返却スペースや洗車場、受付などに防犯カメラが設置されていることが多い。しかし都丸は首を横に振った。
「そちらの線はまったく。倒産したのが七年も前ですから」
捜査員はレンタカー会社の元社員たちも訪問したが、当時の資料の所在は不明だった。倒産前後に廃棄された可能性が高く、手に入れる手段は実質ない。
「やはりこの映像しかありませんか」
ノートパソコンのディスプレイに、宝飾店の防犯カメラ映像が映し出される。一応暗視カメラではあるが、画質がひどい。十二年前でもすでに旧式の機器を使っていたと思われる。三名の犯人たちは映っているものの、かろうじて体型が判別できる程度だ。音声も、家電の近くに置かれていたのか始終ノイズが入っている。
信号が青になり、車列が流れだした。都丸はアクセルを踏む。
「さっきから何をやっているんです」
「映像を鮮明化できないかと」
「そんなことができるんですか」
「場合によっては」
話しながら、指先は忙しなくキーボードの上を踊っている。どうやって、と訊こうとして都丸はやめた。教えてもらったところで見当もつかない。
「科警研のほうはどうなりました」
訪問後、科警研には面倒な手続きを踏んで依頼を出した。尾藤主任が担当しているのは間違いないが、続報は来ていない。「苦戦しているんじゃないですか」と言った都丸に、土門は「いや」と応じた。
「形質人類学では指折りの実力者です。何らかの結果は出してくるでしょう」
意外な反応だった。科警研での面談ではとても仲がいいように見えなかったが、実力は認めているということか。
じき、目的地である神奈川県内の警察施設に到着した。相模湾から引き揚げられた車はこの敷地内に保管されている。屋外には廃車がずらりと並び、さながらスクラップ工場の様相だった。都丸は土門を連れ、職員の案内で車の間を縫うように進む。
「これですね」
職員が示したのは四人乗りの軽トールワゴンだった。全体が錆びつき、フジツボが張り付いている。ガラス窓は一部割れていた。引き揚げ時は泥や海藻にまみれていたようだが、すでに洗い流されたせいか、思いのほか綺麗であった。塗装はグレーだ。車種は事件当時に最も販売台数が多く、ごくありふれたものだった。
さっそく、土門は食い入るようにボンネットの辺りを観察している。そうかと思うと、パソコンを入れているブリーフケースからデジタルカメラを取り出した。
「写真を撮っても?」
許可すると、すぐにシャッターを押しはじめた。写真なら鑑識も撮影しているが、注目する点が違うのだろう。しばらく土門に任せることにした。
運転席も泥やゴミは洗い流されていた。シートベルトは外れ、ドアキーもロックされていない。
「遺体の男は車内から逃げ出せたのに、そうはしなかった。つまり、脱出の意思がなかったということでしょうか」
退屈を持て余した都丸が尋ねると、土門は内装を撮影しながら「わかりません」と答えた。
「沈んでいく車のドアは、水圧でほとんど開かないですから。焦っていればなおさらです。逃げようとしたけど開かなかったのかもしれない。ドアの状況だけでは何とも言えません」
「しかし、もう少しあがいた形跡があってもいいのでは?」
都丸は食い下がる。逃げるつもりだったにしては、内装に叩いたりひっかいたりした跡がない。
「痕跡が海水で腐食してしまったのかもしれない。仮に逃げられなかったとしても、理由は他にも考えられます。怪我をしていた。縛られていた。脅されていた。当人の意思だけが要因ではありません」
土門はシャッターを切りながら冷静に応じた。内装の撮影が済むと、今度はバックドアを開けて狭い荷室を点検しはじめた。ブリーフケースから出した資料と見比べながら、再びカメラに収めていく。資料には発見直後、宝飾品が入った状態の写真が載っている。
「犯人の一人が自殺したとして、他の二人はそれを許したんですかね。仲間が死ぬのはともかく、盗品が海に沈んでいくのを傍観していたんでしょうか」
独り言のように、土門がつぶやいた。
「どうにかして出し抜いたんでしょう」
「出し抜く余裕があるなら自殺などせず、自首すればいいと思いませんか」
「発作的に飛び込んだのかもしれない」
「あれだけ周到に準備して、強盗殺人を犯した人間が?」
――落ち着け。
そう自分に言い聞かせるが、瞼の痙攣は収まらない。土門が自殺説に疑いを抱いているのは明らかだ。都丸にも確信はないが、警察が本命とみているシナリオを否定されるのは気分がいいものではなかった。
「他に考えがあるなら言ってください」
「それはまだ、何とも」
都丸のほうは一瞥もせず、土門はバックドアを閉めて塗装の観察に没頭する。
独特のマイペースぶりにはやや慣れたが、神経を逆撫でされる回数が減っただけで、苛立ちが完全に消えたわけではない。それでも今の大田署強行犯捜査係にとって土門は最大の切り札だった。うまくやるしかない。
しばらく塗装を凝視していた土門が、「おや」と唐突に声を上げた。
「見てください」
近づいてきた都丸に、土門は右ヘッドライトのすぐ横を指さした。かすかに傷がつき、白の塗料が付着している。何の変哲もない擦り傷だ。車体には他にも多くの傷がついているが、塗料が残っているのはこの擦り傷だけのようである。
「海底でついた傷ですかね」
「いえ、塗料が付着しているのでおそらく違うでしょう。腐食に耐えられたのは幸運でした。これで手掛かりが増える」
誤差の範囲かもしれないが、土門の横顔がほのかに緩んだ気がした。
「そうだとして、これに何の意味が?」
土門は顔を上げ、正面から都丸を見た。なぜわからない、とでも言いたげだ。それでも困惑する都丸に「いいですか」と含めるように言う。さながら、物分かりの悪い生徒に教える教師である。
「この塗料の正体を知ることは、海へ沈む前の動きを知るうえで非常に重要です。ガードレールや外壁塗装なら、そこへ立ち寄ったことがわかる。自動車の塗膜片なら、その車と衝突事故を起こしたことがわかる」
要は、この擦り傷が何によってもたらされたか、が重要らしい。
「科捜研では、塗料の分析は日常的に行われています。たとえばひき逃げ事件では車種の特定を行います。警察には数万種類の塗膜標本があって、残された塗膜片をFT‐IR分析にかけ、標本と照合させることで車種を割り出すのです」
「傷が小さすぎます。それに、十年以上前に海へ沈んだ車ですよ。そんなに長い時間沈んでいても、成分が残っているものですか」
「やってみないとわかりません。分析機器メーカーの企業努力はバカにできませんよ。もしFT‐IRで駄目ならSEM‐EDSもある」
口にする単語の意味は相変わらずわからないが、とにかくメモしておく。
土門の淡々とした言葉の裏には、燃えたぎる執念を感じる。並の捜査員よりもはるかにしつこく、粘り強い。そのしつこさが鑑定の原動力になっているのだろう。
「……最後の鑑定人、ですよね」
先日、係の先輩から聞いた土門の通称である。科捜研にいた頃の土門誠は、科学鑑定の最後の砦だった。その技能は全国に知れ渡り、都内に限らず鑑定困難な試料が土門のもとへと送られてきたという。
「科捜研には戻らないんですか。土門さんなら、いつでも戻れますよ」
「無理です。私は科捜研の研究員としては失格です」
硬い声音に、意志の強さが滲んでいた。
「やっていることは科捜研と同じなのに」
「そう見えるなら、あなたにはそうなんでしょう。けれど私にとっては違う」
しゃがみこんだ土門は、左フロントタイヤの観察をはじめた。そんなところまで見るのか。呆れながら、都丸は手元を覗き込む。いつの間にか、土門はゴム手袋をつけた右手にピンセットを握っていた。先端部をタイヤの溝にねじ込んで、挟まった砂利をビニールパックに集めている。
そんなものを回収してどうするのか。質問するより先に、懐の携帯電話が震えた。着信だ。二コール目の途中で出る。相手は尾藤だった。
「尾藤主任。ちょうど今、土門さんと……」
「復顔、できたけど」
勝ち誇った声音が耳朶を打つ。絶句した都丸は土門に視線で合図を送ったが、我関せずといった風情で作業を続けるだけだった。
「明日にはこいつを全国で公開する」
同日夜、会議の席上で三浦係長が吠えた。その手には、尾藤主任が復顔した白骨遺体の顔貌が握られている。どんぐり眼に縦長の顔、突き出た頰骨が特徴的だ。つかみどころのなかった遺体の人物に、命が吹きこまれた。
土門の見立ては間違っていなかった。確かに、尾藤宏香は結果を出した。
会議室に詰めかけた捜査員たちの顔は上気している。これまでで、最も遺体の身元に近い情報だった。これで聞き込みの精度は飛躍的に向上する。
「課長を通じて、内輪の話はほぼ決着している。あとは見つけるだけだ。おい、都丸。まだ終わりじゃねえだろ。追加の情報はいつ出る」
そう言われると思っていた。手帳のメモを確認しながら答える。
「科警研に、車に残された塗料の分析を依頼中。土門鑑定所では防犯カメラの映像を鮮明にする処理と、車の遺留物の分析を実施しています。一週間後を目処に進捗を確認します」
最初に車の擦り傷に注目したのは土門だが、その土門自身が「私より科警研のほうが適任です」と言ったのだ。手元に塗膜標本がない、というのがその理由であった。
――こちらは映像解析と、これの照会をしますから。
あの日の帰りの車中、助手席の土門は鞄から砂利の入ったビニールパックを取り出してそう言った。タイヤの溝から採取したものだが、都丸にはただの小石にしか見えなかった。
「確実に近づいているぞ。あと数歩だ」
三浦が締めくくり、会議は解散となった。踵を返そうとした都丸はまたも名前を呼ばれる。飛んで行った都丸に、三浦は笑いかけた。
「よく科警研まで引っ張り出したな。上出来だ」
早口で「ありがとうございます」と言った都丸の背を叩き、三浦は去っていった。
胸中には晴れがましさと同時に、後ろめたさがわだかまっていた。科警研を動かしたのは、都丸というより土門だ。都丸はただ土門と一緒に科警研へ行き、話すきっかけを作ったに過ぎない。自分の手柄と呼ぶには違和感があった。
土門は最初からこうなることを予期していたのだろうか。科警研に計測データがあることをほのめかしたのも、尾藤主任との面談で見せた挑発的な薄笑いも、すべては科警研に復顔をやらせるためだったのか。尾藤が実力者であることは土門も認めていた。だからこそ、自分より彼女が手掛けるほうがよいと判断したのか。
だとすれば、捜査員も科警研も、土門の手のひらの上で転がされているに過ぎない。
都丸は空想を打ち消した。
土門は有能な鑑定人だが、そこまで予見できるはずがない。考えすぎだ。だいたい、彼の口から尾藤の名前が出てきたのもたまたまだ。白骨遺体から偶然、復顔の話になり、そこから計測データの話になって……。
「あ」
間抜けな声が出た。そもそも、復顔について言い出したのは土門だった。
――復顔は、もうされましたか。
計測データの話をしたのも、尾藤の名前を出したのも土門だ。背筋が冷たくなる。どこまで計算で、どこまで偶然なのか。都丸は考えるのをやめた。
翌日の夜更け、相模湾沿岸での聞き込み捜査から署へ戻ったところで携帯電話が震えた。ディスプレイを見る前から、土門か尾藤のどちらかだと直感した。疲労と空腹で萎えかけていた意志を奮い立たせる。
「はい、都丸」
「まだ署にいますか」
一日ぶりに聞く土門の声には、まったくぶれがない。
「例のレンタカーが走行したと思しき地点がわかりました」
その一言で覚醒した。デスクに積み上げられた書類をかき分け、パソコンを起動する。土門からのメールには画像ファイルが添付されていた。東京西部の地図である。全域が青と赤のグラデーションで塗り分けられ、八王子市内東部が真っ赤になっている。
「日本全国土砂データベースはご存じですか」
聞いた覚えもない。都丸は素直に「いいえ」と応じ、土門の説明に耳を傾けた。
日本全国土砂データベース(JRS‐DB)は、大型放射光施設を活用し、七年をかけて作成された重元素および重鉱物の分布マップである。ウェブ上で公開されており、犯罪捜査等のために誰でも利用できる。
「……つまり、日本中の石や砂の成分をまとめたデータ集、って感じですか」
「そんなところです」
土門の返事はどこか釈然としないが、間違ってはいないらしい。
「タイヤの溝に挟まっていた砂利は大半が海底由来と思しきものでしたが、ごく一部、奥に残っていた砂利や砂礫は明らかに構造が違っていたのです。タングステンなどの元素、および白雲母などの重鉱物から、サンプリングされた砂利がどの辺りにあったものか、おおよその推定ができました。それが添付ファイルに記してある、特に赤い地点。八王子周辺です」
事件現場から遺体が発見された相模湾沿岸までの最短ルート上に、八王子東部はない。遺体が犯人だとすれば、何らかの目的で立ち寄ったか、事件前そこにいたか。復顔に並ぶ新情報である。都丸は改めて携帯電話に食らいついた。
「これ、間違いないんですね」
「関東近郊ではこの地点が最も可能性が高いです。滞在していたのか、通過しただけかはわかりませんが。念のため他の候補地も送ります」
「すぐにお願いします」
都丸の剣幕に驚いた捜査員たちが近づいてくる。土門からのファイルを印刷した都丸は、残っている面々を集めて即席の会議を開いた。眠気は感じない。
興奮の渦の中心で、都丸は血の沸騰する音を聞いていた。
署の柔道場で仮眠を取った都丸は、翌朝から他の捜査員たちと現地に出向いた。三浦係長を通じて連絡した南大沢署に立ち寄り、八王子市内東部の大まかな土地勘を頭に入れたうえで聞き込みを開始する。
情報は揃ってきた。十二年前時点で、二十代から三十代の男性。血液型はBO。体型は中肉中背。顔貌も推定されている。あとは発見するだけだ。
三日間は空振りが続いた。都丸は着替えのためだけに帰宅し、残りの時間をすべて捜査に捧げた。事件直後どころか十二年経った今、急ぐ理由はないのかもしれない。それでも都丸をはじめ、捜査員たちは不休の捜査を止めようとしなかった。
タイヤに残された砂利の解析結果がもたらされてから三日後の早朝、寝室代わりとなった柔道場で眠っていた都丸は、携帯のコール音で目覚めた。表示された尾藤の名が目に入り飛び起きる。
「尾藤主任ですかっ」
「おはよう。擦り傷に残った塗料の件、自動車塗膜だったみたい」
寝ぼけた頭で都丸は考える。塗料の分析は科警研で受理されたが、担当は尾藤ではなかったはずだ。
「……担当外なのに、連絡くださったんですか」
「偶然聞いたから、連絡してあげてんじゃない。車種も特定できたって。後で担当者から連絡行くけど、遅くなるから先に車種だけ教えておこうか」
跳ね起きた都丸は、柔道場の床に手帳を広げる。尾藤が読み上げる車種を書き取り、短く礼を言って通話を切った。
また新情報だ。十二年前、このレンタカーは自動車同士の接触事故を起こした可能性がある。接触した車自体はすでに売却、あるいは廃棄されている可能性が高い。だが、遺体の人物の足取りを推定するうえでは重要な情報だった。
窓から差す強い朝日を浴びながら、都丸は強行犯捜査係のフロアへと急いだ。
――どうなってんだよ、この人ら。
最初の土門への依頼からひと月と経っていない。この短期間で土門と科警研は競うように鑑定し、結果、飛躍的に捜査は進んだ。ただ有能というだけではない。双方、科学鑑定に懸けるプライドがなければここまでの急展開はなかったはずだ。
鑑定人たちはプライドを見せた。次は捜査員の番だ。
捜査には、波がある。
どうあがいても事実につながる手掛かりは見つからず、真相に続くと思っていた道が行き止まりだとわかる。士気は下がり、捜査員の顔からは生気が失われる。長い停滞にはまり込んだかと思えば、噓のように事態が進む時もある。波が来れば目の前の障害物が洗い流され、視界が晴れていく。
そしてまさに今、この捜査における最大の波が来ていた。
「あとは捕まえるだけだ。ここまで来たら、何としても見つけるぞ」
大田警察署の一室で、三浦係長が地鳴りのような声で怒鳴った。捜査員たちは一斉に「はい」と呼応する。事態はとうに大田署の管轄を越えていた。警視庁本庁、さらには遺体発見の対応をした神奈川県警も巻き込んでいる。だが最前線に立つのは、依然、都丸たち大田署の捜査員だ。
「古い事件だって言い訳はもう通用しねえ。これだけ捜査の手掛かりがあって、見つかりませんではプライドが許さん。お前らもそうだろ」
怒号のような声が返ってくる。解散と同時に、捜査員たちが散っていった。そのなかには都丸もいる。
尾藤主任からの連絡を受けたのが昨日。復顔した人物の目撃証言も集まりつつあるが、いずれも裏は取れておらず、信憑性に欠ける。だが、核心に近づいている予感はあった。進むべき方向は間違っていない。
昼下がり、都丸は住宅地での聞き込みから、間借り中の南大沢署へいったん戻ってきた。コンビニ弁当入りのビニール袋を提げた都丸は、足を踏み入れる前から、会議室の様子がおかしいことに気付いた。大田署の捜査員たちが慌ただしく連絡を取り、外に出ている面々を呼び出している。長机の上には書類が広げられていた。
「都丸さん。ちょっと!」
後輩捜査員は、紅潮した顔で一枚の書類をつまみ上げた。
「とうとう出たんですよ」
書類には被疑者写真記録が掲載されている。逮捕時に必ず撮影するものだ。ふてくされたような表情で正面を向いている顔は、尾藤が復顔した顔貌とよく似ていた。
「おい、これ」
後輩は黙って頷く。心拍数が高まる。都丸は弁当も忘れて、書類に目を通した。
写真の男の名は、矢野巧。事件当時の年齢は二十七歳。
山梨県内の中学校を卒業後、十七歳の頃に傷害で逮捕され保護観察処分となっている。その後一時的に地元建設会社に就職したが、二十歳で行方をくらました。以後は都内で居所を転々としながら、パチンコ店や雀荘に入り浸っていたという。二十五歳で建設現場の資材を盗んだことが発覚して逮捕、執行猶予付きで懲役二年半の判決が下っている。強盗殺人事件が起こったのは、その執行猶予期間中だった。
――こいつだ。
頭の芯が痺れる。直感が、遺体はこの男だと告げていた。
「執行猶予中の居住地として届け出ている住所は、八王子です。担当だった保護司いわく、事件発生の時期と前後して矢野は面談に来なくなったとのことですが、勝手に面談をやめてしまう者は多いので、さほど深く考えてはいなかった、と」
都丸が血走った目で書類を読んでいる間に、三浦係長が到着した。
「おい、いよいよだぞ」
すぐさま緊急会議が開かれる。二名は山梨県内の実家へと急行し、残る捜査員は当時の矢野の人間関係を洗うことになった。執行猶予中の住所は八王子市内のアパートで、当時の世帯主は別の女性であることから、矢野はその女性と同棲していたとみられる。
再び署外へ飛び出そうとした都丸のもとに着信があった。
「今、よろしいですか」
落ち着いた土門の声音が鼓膜に届く。土門にそう言われれば、「どうぞ」と応じないわけにはいかない。
「防犯カメラの解析ですが、画像の鮮明化は不可能でした」
「土門さんにもできないことがあるんですね」
嫌味ではなく、本心からの感想だった。
「当然です。ただ、音声は一部ノイズを排除できました。メールで送ります」
「すぐには開けないんですが。何か聞こえましたか」
話すべき箇所を逡巡しているのか、土門は少しだけ沈黙した。やがて、咳払いの後に土門は言った。
「……映像の終盤、犯人の一人が『もうやめよう』と言ったのが聞こえます」
強盗の最中に中断を勧める犯人など、普通ではない。その人物は、犯行に乗り気でなかったのだろうか。
映像に映った三人のうち、体型的に中肉中背の男が矢野であることはほぼ疑いない。矢野はもともと犯行に消極的で、強盗中も仲間に中断を訴えていた。そして犯行後、自責の念に苛まれ、盗品を入れたままレンタカーで海へと沈んだ。そう考えれば辻褄は合う。
「言ったのは中肉中背の男ですね」
期待を込めた問いかけに、土門は「いいえ」と返した。
「マスクの動きから、最も背の高い犯人と思われます。もう一人の背が低いほうも同調しているようです。中肉中背の男は、一貫して二人の訴えを無視していますね」
肩透かしを食った気分である。土門の解析が正しいなら、矢野が他の二人を主導して犯行に及んだ可能性が高い。そうなると、捜査員たちが有力と見ていた自殺説には疑問符が付く。仲間の反対を押し切ってまで犯行に及んだ人物が、罪の意識に苛まれて自殺するのは不自然だった。ならば、矢野はなぜ死んだのか?
「あとはお任せします」
土門の言葉に違和感を覚えた都丸は「えっ」と聞き返した。
「鑑定人に、被疑者の逮捕はできません。あとは皆さんにお任せします」
熱い塊が胸にこみ上げる。どんなに優秀な鑑定人がいても、犯人確保の最後のピースをはめるのは捜査員だ。科捜研を辞めたとはいえ、きっと土門の心の一部はまだ警視庁に残されている。
都丸は大きく息を吸いこみ、ごまかしのない声音で言った。
「任せてください」
八王子のアパートを借りていた中山という女性は、江戸川区に転居していた。四十歳になった彼女は現在、倉庫会社の社員として働いている。
中山は捜査員の聞き取りに対して、事件当時、確かに矢野と同棲しており「ある日、いきなりどこかへ消えた」と証言した。捜査には協力的な態度であり、犯行にかかわっていた可能性は低いとみられる。
当時の交友関係を尋ねたところ、共犯者の候補と思しき人物が数名浮かび上がった。とりわけ捜査員たちの関心を引いたのは、矢野と頻繁に行動をともにしていたという男である。
渡部紀明。事件当時、二十五歳。
高校卒業まで横浜市内で過ごし、大学進学を機に八王子へ転居。そこでディスカウントストアのアルバイトをはじめ、職場の先輩たちと遊ぶようになった。ある夜、女性の先輩が職場の飲み会に見知らぬ男を連れてきた。男は先輩の恋人で、渡部はすぐに彼と意気投合。その後は先輩を交えて三人で遊ぶようになった。
その男こそが矢野であり、職場の先輩というのが中山だった。
非行や不登校の過去がない渡部は、矢野のアウトローな部分に魅力を感じ、徐々にそれまでの軌道を外れていく。大学は中退し、アルバイトや短期派遣の仕事で食べていた。矢野が呼べば何時だろうが飛んできた、というのが中山の証言だった。執行猶予期間中も矢野とはしょっちゅうつるんでいたという。矢野が姿を消してからは中山と渡部の交流も途絶え、今どこで何をしているかは不明。
この報告を受けた捜査員の大半が、渡部紀明に狙いをつけることで合意した。
現住所はすぐに判明した。十年前から横浜市内にある彼の実家に住んでいるという。神奈川県警に断りを入れ、翌早朝、都丸を含む四名の捜査員が向かうことになった。
渡部の実家は、郊外に建つ一軒家であった。音もなく停止した警察車両から四人の捜査員が降り立つ。日が上りきっていない時間帯、彼らの脂ぎった顔が朝日を浴びていた。都丸ともう一名が正面から訪問し、残る二名が逃走防止のため勝手口に回る。
インターホンのボタンを押すと、ややあって「はい」と女性の声が返ってきた。
「警察です。紀明さんはご在宅ですか」
都丸が告げると、数秒後には玄関扉が開いた。顔を覗かせたのは還暦前後と思しき女性である。化粧気はなく、服装はスウェットの上下だった。渡部の母か。門を抜けた都丸たちはすかさずドアハンドルに手をかける。
「あ、ええっと、紀明の母ですが……どういうご用件で……」
怯えきっている女性の背後に、男が立っていた。見た目は三十代で身長は一八〇を少し超える程度。出勤の支度中だったのか、ワイシャツにスラックスという出で立ちであった。男は棒立ちになって捜査員たちを見ている。
「紀明さんですか」
都丸は母親の肩越しに直接声をかけた。
「はあ、そうですが」
身体がかっと熱くなる。土門から送られた、防犯カメラの音声と同じ声だった。もうやめよう、と弱気な発言をしたあの声。相方の捜査員と視線を交わす。彼も同じ感想を持ったようだった。
「早朝にすみません。警察です」
曖昧だった渡部の顔から血の気が引いていく。目は見開かれ、半開きになった唇の間から、ひゅう、と隙間風のような吐息が漏れた。警察が来たという事実から、彼はすべてを察していた。
「お話を伺いたいので、警察署までお越しいただけますか」
「……どういうこと?」
母親は視線を泳がせ、狼狽している。渡部の顔色は蒼白のままだったが、すでに覚悟を決めたのか、しっかりした口調で「ごめん」と言った。
「これから、ちゃんと全部話すから」
「ねえ、何か知ってるの?」
「こちらへ」
渡部はすがりつく母親の肩を無言で押さえ、都丸の言葉に深く頷いた。革靴を履いた渡部を、都丸ともう一人の捜査員で両側から挟んで歩く。戸口では母親がその様子を呆然と見送っていた。
勝手口で待機していた二人と合流し、警察車両に乗り込む。渡部は抵抗もせず素直に後部座席に乗り込んだ。都丸はその左側に座る。
「覚悟はしていました」
動き出した車両のなかで、渡部が誰にともなくつぶやいた。
「矢野さんの似顔絵、見ました。いずれ私のところにも来ると思っていました」
「話は警察署で聞きますから」
「……犯人の一人です」
うつむいた渡部は、虚ろな視線を手元に落としている。運転手を除く、三人の捜査員が目配せをした。確かに三人とも耳にした。
「私が、宝飾店を襲撃した犯人です」
駄目押しの自供だった。運転手が長い息を吐く。これまで積み上げてきたことが、ようやく報われた。まだ捜査は終わったわけではない。だが、ある種の安堵はあった。彼らの仕事はこの瞬間、一つの通過点を越えた。
都丸もまた安堵していた。これで土門との約束を守ることができた。
……十二年。
長かったですよ。でも、振り返ってみれば一瞬だったような気もします。
それは、色々ありましたよ。就職もしたし、転職だってしました。事件から一年ほどは常に怯えていましたが、だんだんと意識から薄れていくんです。普段はもう、綺麗さっぱり忘れているんですよ。自分があんな恐ろしいことをしたなんて、信じられない。悪い夢だったかのように。
でもね、風呂に入っている間とか、仕事の帰り道、ふとした時に思い出すんです。あの日の矢野さんの血走った目。殺される直前の夫婦の顔。海に沈んでいく車。そういうものがフラッシュバックすると、どうにかなりそうになる。
……きっかけは学生時代のアルバイトでした。一人暮らしをはじめてすぐ、情報誌で楽そうなバイト先を探しました。そのディスカウントストアを選んだのも偶然です。
二十歳の夏に、バイト先の皆でバーベキューしたんですよね。その時、何人かは彼氏とか彼女も同伴で。その時、矢野さんと初めて会いました。
最初見た時、いかついな、と思いました。両腕にタトゥーがびっしり入ってたんですよ。怖いけど、肉焼きながら恐る恐る声かけたんです。そうしたら、思ったより普通だったんですよね。冗談も言うし。酒も入っていたし、そのうち普通に話せるようになって。最後のほうは肩組んで乾杯してましたね。
「渡部くん、面白いなあ。今度また遊ぼうよ」
別れ際にそう言われて、嬉しかった。自分は別世界にいるような人とも、こうしてコミュニケーションが取れる。そういう人にも認めてもらえるって、勘違いしたんです。
でもそれは、矢野さんの手口でした。最初に怖い人だと思わせたうえで、優しく接する。ギャップですね。人付き合いに慣れていない若者はそれだけで嬉しくなるんです。
それからちょくちょく、遊ぶようになりました。矢野さんは煙草吸ったり酒飲んだりする仕草がいちいち決まって見えるんですよね。整った顔じゃないけど、無骨っていうんですかね。いかにも男って感じで……バカですよね。十代で逮捕されたことも早めに教えてもらいました。仲間を守るために傷害事件を起こしたとか。実際はどうか知らないですけど、当時は信じてました。
そのうち他にもう一人、森井って取り巻きができました。どこで知り合ったのかわからないけど、森井も別の大学の学生でした。とにかく、矢野さん、私、森井の三人でつるんでいたんです。
あの人は時間とか関係なく呼び出すんですよ。速攻で平和島に来い、とか。大学の授業って言うと「もういいよ、死ね」で電話を切られる。そういう時は、自主休講にして急いで電車に飛び乗りました。言われた通りにすると、矢野さんがにこっと笑うんですよね。「よく来たな」って。その笑顔が見たくて、矢野さんの要求に応え続けました。
四十時間ぶっ続けで麻雀に付き合うとか、前触れなく北海道に旅行に行くとか。大学の授業なんか、まともに受けられるわけないですよね。一時はメンタルをやられて不眠症の薬を出してもらっていました。
大学三年の時に留年が決まって、親と大喧嘩しました。その時、実家に戻れって言われたんですね。そもそも横浜だから八王子にも通えるんですよ。でもそれだけは嫌だった。矢野さんと遊べなくなるから。
「だったらもういいよ、大学辞めて働くわ」
……そう言っちゃったんですよね。
ディスカウントストアでのアルバイトは続けていて、月十五万くらいあったんで何とかなりました。不思議なもので、矢野さん、後輩に金をせびることだけはしなかったんですよね。そこはプライドがあったみたいで。そのプライドのせいで、あんな事件起こしたんですけど。
大学中退から三年くらいして、矢野さんが逮捕されたんです。建設現場から資材を盗んで。電気ケーブルとか足場材とか、売ればそれなりの金になるんですって。単独犯だったそうです。タトゥーは凄いし、性格も悪いからどの職場でも疎まれちゃって。で、金がないからやった。それだけの理由でした。逮捕されたのは二度目で、規模もしょぼかったから執行猶予がつきました……そうそう。成人前の逮捕歴は考慮されないんですってね。
矢野さんが拘置所を出てきてからはまた一緒につるんでいました。もう、他にやることもなかったんですよね。森井も似たようなものでしたよ。大学は卒業したけど、フリーターやってて。
……え?
いや、何ででしょうね。私も森井も、どうしてか見捨てられなかったんですよね。わかりますよ。客観的に考えて、そんな屑と付き合う必要ないですよね。ただ、あの人の面倒を見ることが生きがいになってました。いわば矢野さんのために大学中退して、就職も諦めたようなものですから。そこで離れたら、今までの数年間は無駄だってことになるでしょう。認めたくなかったんですよね。
……覚えています。二十五歳の九月二十二日です。
何日か前に、私と森井が深夜のファミレスに呼び出されて、矢野さんに言われたんです。
「新宿の外れに、ヨボヨボの夫婦がやってる宝石屋がある。そこを襲って金を稼ぐ」
正直、本気だと思っていませんでした。でも、私が「噓でしょ?」って言うと矢野さんがブチ切れたんです。それで真剣なんだとわかりました。私も森井も止めましたけど、矢野さんは熱弁してました。
「逆転だよ。でかい金つかんで、一発逆転すんだよ。それしかねえよ」
矢野さんは折れなかった。どんなに説得しても聞く耳を持たなかった。
そのうち森井が「うまくいくなら、いいですけど」と言い出したんです。私も乗せられて、「失敗しない保証があるならやります」って言っちゃったんですね。矢野さんはもうそれで、私たちがやる気になったと勘違いして、得意そうに計画を話しだしたんです。施錠を破壊して店内に押し入り、警備員が駆け付ける前に逃げる。二階に寝起きしている店主夫婦が起きてきたら、刃物で脅す。計画と言ってもそれだけのことですよ。
「やらないなら、俺は死ぬ」
そんなことまで言いだして、呆れました。でも矢野さんなら本当に死んじゃうかもな、と思ったんです。あの人、妙に本気なんですよ。口先だけで言ってればいいのに、噓がつけないっていうか。まっすぐな愚か者、という感じですね。
結局、私と森井は矢野さんの強盗計画に協力しました。
本番は驚くほど予想通りに事が運びました。施錠は素人でも何とか破壊できたし、警報は鳴ったけど誰も来ませんでした。深夜の裏通りで、周辺には人気もなかったですから。
警報が鳴った時点では俺も森井も止めようとしたんです。でも矢野さんは言うこと聞かなくて。そのうち、一緒になってウィンドウを叩き割っているうちに興奮してきました。親指の爪くらいあるダイヤモンドを無造作につかんで、汚いバッグに入れていくのは爽快でした。
そろそろ逃げようか、というタイミングで、二階から夫婦が下りてきました。五、六十歳くらいの夫婦でした。旦那のほうは物凄い形相で、木刀持ってましたね。矢野さんが包丁見せたんですけど全然怯まずに殴りかかってきて。
気づいたら、夫婦揃って血まみれで倒れていました。
矢野さんは震えてましたよ。殺意はなかったと思います。でも怖かったんでしょうね。殴られるくらいなら刺してやれ、って。ほら、言ったでしょう。いつだって妙に本気なんですよ、あの人。
とにかく逃げるしかないから、森井と一緒に矢野さん引っ張って、外に停めたレンタカーに乗せました。ハンドルは私が握って、二人は後部座席にいました。下道を走って、八王子まで逃げたんです。警察が追ってこなかったのは奇跡でした。
ただ……その途中で、事故に遭ったんです。
事故と言っても軽いですよ。狭い道を走っていたら対面の車が来て、少しだけ擦ってしまったんです。そのままやり過ごそうと思ったら、突然、矢野さんが車から飛び出したんです。
「ふざけんなてめえ! 殺すぞ!」
相手の車にそう叫んだんです。信じられますか。一時間前に強盗殺人を犯して、逃げている最中ですよ。人を殺して興奮していたのか……相手が無視してくれたのは不幸中の幸いでした。森井が必死に連れ戻したんですけど、矢野さんはずっとキレてましたね。
そこで思ったんですよね。このままだと絶対にバレる、って。
すーっ、と何かが醒めていったんです。代わりに、それまでの数年ずっと忘れていた感情を取り戻したみたいでした。悪夢から目覚めたというか。あれ、俺、何やってんだろう。強盗して、人殺しに加担して。現実じゃないみたいでした。
バックミラーに暴れている矢野さんが映っていました。この人だ。この人のせいで、俺の人生はめちゃくちゃになる。やっとそのことに気付いたんです。五年かかりましたね。
とりあえず私のアパートに行って、血まみれの矢野さんにシャワー浴びてもらいました。その間、森井と話したんです。
「お前、このまま矢野さんに付き合うの?」
そう訊くと、森井も黙りました。同じようなこと考えていたんでしょうね。何も言わずにうつむいてると思ったら、いきなりボロボロ泣き出したんです。
「もう嫌だ。こんなこと、したくなかった。捕まりたくない」
それが森井の本心でした。そして私も同じだった。
「全部チャラにしよう」
森井の目の色が変わるのがわかりました。あいつは誰か、ついていける人がいればそれでいい。矢野さんでも、私でもよかったわけです。
シャワーから上がった矢野さんにビールを勧めました。まずは祝杯を挙げよう、と誘うと、ようやく落ち着いた矢野さんはあっさり飲んでくれました……そうです。ビールには睡眠導入剤を混ぜていました。不眠症の頃に処方されていた薬を残していたんで。疲れもあったのか、矢野さんはすぐに眠ってしまいました。
降りたばかりの車に再び矢野さんを乗せて、海へと走りました。森井は協力的でしたよ。この状況がチャラになるなら、何だってしてくれそうでした。
相模湾沿いの廃港跡で停めました。眠りこけた矢野さんと盗んだ品物を全部残して、私と森井は車を降りました。宝石だけでも持っていきたかったけど、そこから足がついたらつまらないんで諦めました。
車をアイドリングしたまま、海に落ちる寸前で降りたんです。オートマ車だったんで。クリープで勝手に進んで、数秒後には海に落ちました。しばらく海面に浮かんでいたんですけど、何分か待っていると沈んでいきましたよ。
あっけなかったですね。断末魔も聞いていないし。本当に夢を見ているみたいでした。私と森井は、連絡は取り合わないと約束して別れました。
すぐに実家に帰りました。家族に土下座して、やり直させてほしいと頼みました。親は許してくれました。やっと目が覚めたか、という感じでしたね。色々ごたごたしましたけど、父親のツテで都内の会社に入れてもらってから十年、真面目に働いてきました。本来、私はそっち側の人間だったんですよね。
……それはもちろん、忘れられないですよ。森井も同じなんじゃないですかね。言ったでしょう。思い出すと気が狂いそうになるんです。ただ、思い出すのは強盗した瞬間とか、矢野さんが夫婦を刺し殺す場面とか、逃げる途中に車と擦った時のことですね。海でのことはほとんど思い出さないです。
私には、矢野さんを殺した手応えがないんです。
矢野さんの乗った車が海に沈んでいく光景を見て、過去が清算された気分になりました。これでもう、人生を狂わされることもない……そうですね。すっきりしていました。今後は迷惑をかけられることもない。矢野さんのいない人生がはじまる。
だから……車ごと沈めたのも、仕方なかったんです。
さんざん身勝手に生きてきて、最後の最後に仲間だった私に裏切られた。でもそれって、自業自得ですよね。
矢野さんが屑なのが悪いんですから。
二度と来ないだろうと思っていた建物が、目の前にそびえている。
都丸は〈土門鑑定所〉と刻まれたプレートを睨んだ。前回ここに来た際は不愉快な思いしかしなかった。だが今回は違う。右手には資料の詰まった鞄ではなく、菓子折りの入った紙袋が握られている。
インターホンを押すと、今回も高倉が応対に出てきた。
――あのハーブ水が出てきませんように。
応接間のソファで待っている間、そう願った。だが都丸の祈りは通じない。
「今日は新作ですよ」
高倉は嬉々として、水の注がれたグラスをテーブルに置いた。遠慮しようにも、彼女は期待のこもった視線で見ている。仕方なく右手でつかみ、口を付ける。形容しがたい苦みが舌の上に広がった。ブレンドしたハーブを浸したという水からは、青臭い香りが立ち上っている。
「どうですか」
傍らに立った高倉が都丸の顔を覗き込んだ。
「……牛乳とかで割ってくれると、もっとおいしいと思います」
なるほど、と高倉は小声でつぶやいた。
「あの。どうしてハーブ水なんですか」
相手を困らせようという悪意があるか、よほどの味覚音痴でない限り、こんなにまずい飲み物を客に出そうという発想には至らないはずだ。
真顔になった高倉は、「趣味です」と答えた。
「趣味」
どこまで詮索していいものか悩む都丸に、高倉は笑いかけた。
「やっぱり教えてあげます。データも溜まってきたし」
高倉は対面の席に座った。困惑する都丸に、微笑した高倉は「噓を見破る訓練なんです」と言った。
「私、もともと人の噓に興味があって。学生時代にもポリグラフ検査の研究をしていたんです。不確かな記憶や、偽物の記憶を見破るための検査ですね。そういうことばっかり考えているうちに、自力で噓を見破れないかと思って。変だと思います?」
「あ……いえ」
「今、また噓つきましたね」
都丸は曖昧に頷いた。どう答えても本心を言い当てられそうな気がしてくる。
「噓を見破る訓練のためには、噓をつく時の特徴を知らないといけない。だから人が噓をつく状況を、あえてつくることにしたんです」
高倉の思想はともかく、意図はおぼろげに理解できた。
「つまり、まずいものをおいしいと言わせて、その時の反応を見ているということですか」
「秘密ですよ。他の人には言わないでくださいね」
ええ、と答えながら苦笑が漏れた。言ったところで信じてもらえないだろう。
奥のドアからノートパソコンを抱えて現れた土門は、表情のない顔つきで向かいのソファに腰を下ろした。都丸の手元を一瞥する。
「高倉さん。そろそろ、この習慣はやめたらどうです。皆さん困っているようだ」
「そうですか?」
自分のデスクに戻っていく高倉を視界の端で見送りつつ、都丸は紙袋を差し出した。
「改めてお世話になりました。これ、つまらないものですが」
土門は眉をひそめた。受け取ろうとしない。
「報酬ならいただいています。必要ありません」
「まあ、そう言わず」
菓子折りは三浦係長からの命令である。
「甘いものは苦手で」
都丸が気を揉むのを知ってか知らずか、土門はあっさり言い放つ。そう言われると無理に渡しづらい。とりあえず紙袋は机上に置いた。
「……それで、本題なんですが」
都丸は渡部紀明から聴取した内容を手短に語った。警察職員ではない土門に、捜査経緯をいちいち報告する義務はない。だが、そうしないと都丸の気が済まなかった。この事件は土門が鑑定しなければ解決しなかった。真の立役者が、犯人の動機すら知らないというのはあんまりだ。
渡部の供述で、もう一人の共犯者も明らかになった。森井は証言の翌日には身柄を確保され、十二年の時を経て強盗殺人犯たちは捕まった。
「どう思いますか」
語り終えた都丸は、上目遣いに土門の反応を窺う。
「何がです」
「渡部の反応ですよ」
都丸は一度だけ渡部の取り調べを担当した。自ら事件の経緯や当時の人間関係について話してくれたため、手間はかからなかった。だが取り調べの間、言いようのない不快感が肌に絡みついていた。
渡部は終始、過去の事件を他人事のように語った。仮にも押し込み強盗の従犯であり、矢野を殺した主犯である。しかし彼は犯した罪の重さを認識していない。運が悪かった。自分は被害者である。そんな意識が、言動の端々から見て取れた。
軽薄な口調にもそれは表れている。まるで友人にでも話すような気安さで、渡部はぽんぽんと過去を明かした。架空の物語でも話しているように。実際、彼にとっては現実感などないに等しいのだろう。
渡部が己の罪の重さに気付く日は、最後まで来ないかもしれない。それでも都丸は退かない。たとえ誰一人反省せずとも、罪を犯した人間に手錠をかけることを諦めない。その意欲が萎えるのは、捜査員として死ぬ時だけだ。
質問を咀嚼するように黙り込んでいた土門が、口を開いた。
「……被疑者の動機に、正しいも間違っているもありません。あるのは、罪を犯したという事実だけです」
科学鑑定を生業とする、彼らしい感想だった。それ以上語るつもりはないらしく、土門は膝の上にノートパソコンを広げて作業をはじめた。
「ここに来たのは、その話をするためですか」
「それと、捜査協力の御礼です」
都丸は改めて紙袋を差し出す。土門は一瞬だけ視線を上げ、ため息を吐いた。
「中身は何ですか」
「栗饅頭。うまいですよ」
土門の瞳がかすかに開く。興味を示しているようだ。だんだんと、微妙な表情の変化がわかるようになってきた。
「それなら、科警研に持参するといい。きっと喜ばれますよ」
「誰が喜ぶんです」
「尾藤主任です。栗は好物なはずですから」
土門と尾藤がどういう関係か知らないが、科捜研時代からそれなりに交流はあったのだろう。相手の好物まで知っているのだから。
「よく、そこまでご存じですね」
「彼女は元妻ですから」
無意識のうちに「えっ」と口にしていた。いかにも他人に頓着しなそうな土門が結婚していたことがそもそも驚きであり、相手があの尾藤だということがさらに驚きであった。振り向けば、高倉も口を開けている。呆然としているところを見ると、彼女も知らなかったらしい。
「結婚していたんですか、土門さんが。へえ」
「昔の話です」
「そうでしたか……それにしても、全然気が付きませんでした」
土門は作業の手を止め、動揺を隠せない都丸を正面から見据えた。
「時には生きている人間より、遺体のほうが雄弁に語ってくれることもあります」
「それは……どういう……」
作業に戻った土門はもう答えない。都丸は懸命にその表情から内心を読み取ろうとしたが、土門の面持ちは無風の湖のように静かだった。
(『最後の鑑定人』は4つの中編を収録した連作集です。ほか3編は本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:最後の鑑定人
著 者:岩井 圭也
発売日:2025年06月17日
嘘をつくのは、いつだって人間です――孤高の鑑定人・土門誠の事件簿!
かつて科捜研のエースとして「彼に鑑定できない証拠物なら、他の誰にも鑑定できない」と言わしめ、「最後の鑑定人」として名を轟かせた土門誠。しかしとある事件をきっかけに、科捜研を辞職。新たに民間鑑定所を立ち上げた土門のもとに次々と不可解な事件が持ち込まれる。いつも同じ服、要件しか話さないという一風変わった合理主義者でありながら、その類まれなる能力で、難事件を次々と解決に導いていく――「科学は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつだって人間です」。孤高の天才鑑定人・土門誠の華麗なる事件簿。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000809/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら