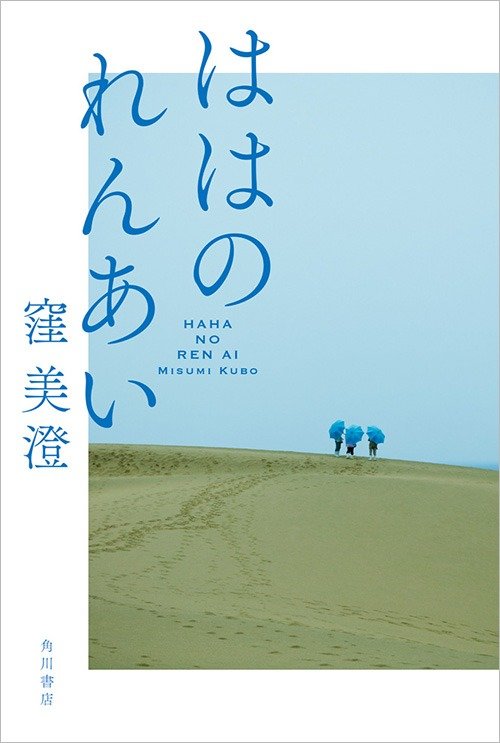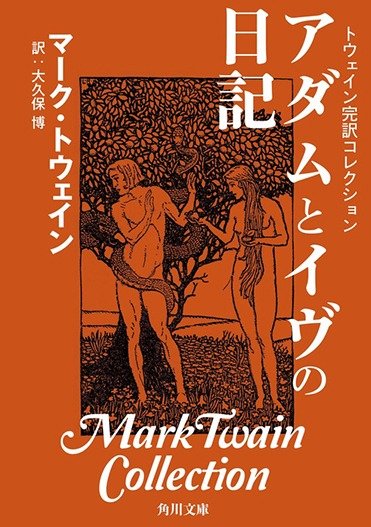窪 美澄「ははのれんあい」

三人の子どもたちのなかで、智晴だけが両親が離婚した本当の理由を知っている。『ははのれんあい』窪美澄
『ふがいない僕は空を見た』『晴天の迷いクジラ』『トリニティ』など、これまで多くの話題作を刊行してきた窪美澄さん。最新作は、シングルマザーの母と、その母と双子の弟たちを支える「僕」のふたりを通して描く家族の物語です。こんな息苦しい時代に、一筋の光を灯してくれるような家族の一代記。その一部を公開いたします。
>>第1回へ
第二部
第一章 ちはる、ははになる
十五歳になった智晴の朝は寛人と結人を起こすことから始まる。
「おい、寛人、結人、起きな」
二段ベッドに寝ている二人の布団をひっぺがす。寒いだの、眠いだの、二人は言いたいことを言うが、「めし、食っちゃうぞ」と智晴が声をかければ、二人はぶつぶつ言いながらも着替えを始める。
今日は結人も学校に行くのか、そのことにほっとして階段を二段飛ばしで降りる。キッチンに向かい、フライパンの中にある三つのハムエッグをそれぞれの皿に盛る。オーブントースターの中で焼き上がった二枚のパンを取り出し、さらに二枚のパンを入れる。もう一回パンを焼かないと自分の分はない。冷蔵庫の中には母が作っていったポテトサラダがあったから、それを三等分にして三枚の皿に載せた。
「おまえ、歯磨いてないだろう」
「磨いたよ!」
寛人が歯をいーっとして智晴に見せる。
「嘘つけ!」
智晴の言葉には耳を貸すことなく、寛人がパンに齧りつく。
「ジャージがない! ジャージがない!」と結人が叫んでいる。結人はいつもこれだ。
「ああっ、もう!」と言いながら、智晴は洗面所に向かい、洗濯かごの中から洗っていない結人のジャージをつまみ出し、キッチンに入ってきた結人に向かって投げた。
「臭い! 洗ってない!」
結人が泣きそうな顔で言う。
「おまえが夜中に出すのが悪い。今日はそれを持ってけ」
え─と言う結人の声を無視して、智晴もパンに齧りついた。
いつか母が、
「男の子が三人いるのは、大型犬が三匹いるのと同じ。いつもごはんのことばっかり考えてる」とこぼしていたことがあったが、智晴にとっては寛人と結人だけで手に余る。もし将来、自分が結婚することがあったら、子どもは絶対に一人でいい、と思いながら、智晴はハムエッグとポテトサラダを一緒に口に入れた。
管理職として働く母の朝は早い。弟たちに朝食を食べさせて学校に送り出すのは、智晴の役目だった。
智晴はこのあたりでは中くらいの頭の出来の子どもが行く高校に通っていた。保育園、小学校、中学校と一緒だった彩菜と敦史も同じ学校に進んだ。大地はこのあたりでいちばん頭のいい子どもが行く進学校に進んだ。
自転車に乗って学校に行くと、いつのまにか彩菜が後ろからついてくる。振り返るとにこにこしているが、絶対に横に並ぶことはない。それを見て追い越していくのが敦史だ。ひゅーひゅーと、奇妙な声をかけながら二人を追い越していく。
彩菜と敦史とは別々のクラスになった。新学期が始まって二カ月が過ぎていたが、智晴にはまだ親しい友人はいなかった。智晴の住む町には工場が多かったから、外国人の生徒も数人いる。小学校のときからそうだった。智晴のクラスにも、ブラジル、フィリピン、アルゼンチンの生徒がいた。智晴は小学校のときから、日本ではない国の子どもとでも、分け隔て無く遊び、学んできた。先生にも母にもそう言われて育ったからだ。
シリラットという女の子とは高校で初めて同じクラスになった。顔と名前は小学校のときから知っていたが、同じクラスになったのは初めてだった。
シリラットは教室に入る智晴を見ると、満面の笑みを浮かべた。いつもそうだった。智晴はそうされると、どうしていいかわからず、いつも曖昧な笑みを返した。シリラットは父が再婚した相手の子どもだった。それが智晴の心を複雑にしていた。よりによって、と思ったこともある。彼女と同じクラスになったことを、智晴はいつまでも母に話せないでいた。
それでも智晴は学校そのものが嫌いではなかった。授業は正直なところ、楽しくはない。英語と世界史にだけは少し興味があったが、とりたてて成績がいいというわけでもない。
高校に入ってクラブ活動が強制参加でなくなったのは、智晴にとって有り難いことでもあった。
放課後になると、図書室に行き、料理本を探す。めぼしい料理を見つけると、そのページをコピーし、それを手にしてスーパーに寄った。安くて、簡単にできて、ボリュームがあるものを食べさせたい。二人の弟にとって、智晴はいまや第二の母だった。
夕方、智晴が朝食の食器を片付け、夕飯の煮物をこしらえていると、外で車が停まる音がした。
「ただいまー」
母が疲れた顔で家に入ってくる。肩にかけた鞄からは、黒いクリップでとめた紙の束があふれそうになっていた。母が会社で何をしているのか、具体的に智晴は何ひとつ知らないが、なんだか大変そうな仕事をしている、ということはわかる。家にはできるだけ早く帰ってはくるが、居間のテーブルで深夜まで仕事をしている。
母は申し訳程度にキッチンのシンクで手を洗うと、
「なんだかとってもいいにおい」と言いながら、智晴のおしりをぺちっと叩いた。
「やめろ」と体をよじらせながら、智晴は小皿に煮物を少し載せ、母に渡した。母は行儀悪くそれを指でつまんで口に入れた。
「あーおいし。あんた、料理うまくなったね」
そう言いながら、もう一度、智晴のおしりを叩いた。母は冷蔵庫のドアを開け、缶ビールを取り出す。ぷしゅっ、と音を立てて缶を開けると、ごくり、と飲んだ。
「はあああ、生き返るわー」
そう言いながら、首を回して、関節を鳴らした。ビールといってもそれは、いつもスーパーで買い求めている安い発泡酒だった。
母がこんなふうに酒を飲むようになったのは、離婚後のことで、初めてその姿を見たとき智晴は驚いたが、母の働きぶりを見ていると、お酒でも飲まないとやっていられないんだろう、と思うようになった。
「寛人は?」
「バスケ部の部活!」
「結人、今日は学校に行ったの?」
「行ったよ。今日は美術があるからさ」
「あ、そうか」
弟の結人が時々、学校に行きたくない、と言い始めたのは、中学に入った頃からで、不登校とはいわないまでも、学校は行ったり休んだりしていた。いじめに遭っているようでも、何か悩みを抱えているようでもない。けれど、原因は両親の離婚にあるのでは、と智晴は思っていた。
両親の関係は、智晴が中学に入学した頃から決定的に悪化した。
理由は父に別の女の人がいたからだ。三年の間もめにもめて、結局、離婚し、智晴と寛人、結人の三人は、母と元々住んでいた家でそのまま生活を送るようになった。
幼い頃の智晴から見た母は、いつも穏やかで優しく笑っている母親だったが、父ともめている間に、次第に笑わなくなっていった。笑う余裕もなかったのだろう。
離婚後、智晴と寛人と結人の暮らしを支えるために、母は猛然と働くようになった。その頃には、時々笑顔を見せるようにもなっていたが、それはどこかぎくしゃくとした笑顔だった。
朝は子どもたちより早く家を出て、帰宅すると立ったまま缶ビールを飲み、家で深夜まで働く。そういう母を非難する気持ちは智晴にはなかったが、母の変貌を目の当たりにして、智晴の頭のなかに浮かんだのは、蝶の羽化だった。
芋虫が蛹になり、やがて蝶になる。今の母をたとえるなら、蛹だ。智晴が幼い頃、母はふわふわの芋虫みたいにやわらかかった。今の母はなんだか硬い。まるで木の枝と同化しているみたいに。もう少し肩の力を抜いたら、などと、気のきいた言葉は智晴には言えなかった。せめて家事を引き受けることが、母への応援になり、支えになればいい、と智晴は思っていた。
本当は会社で残業があるはずなのに、子どもたちが帰ってくる時間には、母は必ず家に帰ってくる。もしかしたら、それは、会社員である母にとって、とても大変なことなんじゃないか。そして、何より、学校に行ったり行かなかったりしている結人のことが心配なのだろう。
高校に入ったとき、敦史に、
「おまえんとこ、母子家庭だろ」と何気なく言われたことがあった。とっさに言い返せなくて、黙ってしまったが、そうか、うちは母子家庭なんだよな、と改めて思った。その言葉は、小さな棘のようにいつも智晴の胸にあった。
そうだ、うちは母の稼ぎで食べさせてもらっている。けれど、それの何が悪いんだ。悪いのは母と僕たちを捨てた父だ。父のことを思うと、智晴の胸の内側に冷たい墨のようなものがさっと流れた。
自転車で三分のところにある祖父の茂雄の家に行くのも智晴の役割だった。高齢の一人暮らしとはいえ、自分でなんでもできる茂雄だったが、耳が遠く、最近はしばしば物忘れもする。
午後八時前には寝てしまうので、しっかりと布団に入ったことを見届け、電気の消し忘れがないかを確かめ、戸締まりをし、預かっている合い鍵で玄関ドアを閉めて帰る。
その日、夕飯を終えた智晴が茂雄の家を訪れると、居間のテレビが大音量で点いたままになっていた。茂雄はテレビの前のテーブルでつっぷして眠りこけている。
「じいちゃん、じいちゃん。こんなところで寝たらだめだよ」と智晴が声をかけると、
「邦子か」と大きな声で叫ぶように答えた。
「違うよ、智晴だよ」
「ああ、智晴か。智久はどこに行った」
茂雄は寝ぼけている。智晴は心のなかで〈女の家に行ったよ〉と返事をした。
三人の子どもたちのなかで、智晴だけが両親が離婚した本当の理由を知っている。父が浮気をして、女の人との間に子どもができたこと。その相手は日本の人ではなくて、元々子どもがいたのだけれど、父と一緒に住むようになって、前夫との子どもをこの町に呼び寄せた。
その子が智晴のクラスにいるシリラットだ。それを知ったとき、いったい、どうなってんだよ、と思った。父が浮気をした人の子どもと同じ学校で勉強しなくちゃならない子どもがどれくらいいるのかわからないが、いつまで経ってもシリラットと仲良くなれる気はしなかった。
茂雄を布団に寝かせ、戸締まりをして家を出た。父の浮気も、離婚も、浮気相手の子どもと同じ学校に通わなくちゃいけないことも、正直、智晴にはとってもつらい、とか、泣きたくなるほど悲しい、というわけではない。そういう感情を抱く前に、まだ現実としてうまく飲み込めてはいなかった。
自転車を力一杯漕ぎ始める。田圃の中の一本道を走る。心のなかで「どうなってんだよ」と絶叫しながら。
智晴にとって憂鬱な日曜日がやって来た。両親が離婚したときの取り決めで(子どもたちはまったく蚊帳の外だった)、月に一度、父は子どもたちと会うことになっている。寛人は部活の練習試合があって行けないという。智晴もなんだかんだと理由をつけて行くのをやめたかったが、部活をしていないので断りにくい。嫌々ながらでも、父と会うようにしているのは、結人が父親に会うことを心待ちにしているからだ。
父と離れて暮らすと決まったとき、智晴と寛人は仕方がないか、というあきらめの気持ちを抱いたが、結人は、お父さんと暮らしたいと言って母を困らせた。父は母に、結人だけでも自分と一緒に暮らさせてもらえないかと提案したようだが、母は頑として首を縦に振らなかった。子どもたちがばらばらに暮らすことには、智晴も反対だった。結人が一人で父に会い、お父さんと暮らしたい、と言い出すこと、それは母だけでなく、智晴にとっても絶対に避けたいことだった。
智晴と結人を後部座席に乗せた父の車は、町を抜けて、どんどん山奥に入っていく。近頃はいつもそうだった。山奥の渓流に連れていかれ、釣りをする。釣りそのものに興味がない智晴は、釣り竿を無理矢理持たされ、早く夕方にならないかな、と思っていたが、結人のはしゃぎっぷりは半端ではなかった。
自分になついている結人が可愛いのか、父はあれこれと世話を焼き、釣りの指導をしている。
弟の無邪気な笑い声を聞くのは、智晴にとってもうれしいことではあったが、父親然と振る舞う後ろ姿を見ていると、
「母さんと僕たちを捨てたくせに」という思いがわき起こってくる。
智晴は早々と釣りをやめて、渓流のそばに立つ木の根元に敷いたビニールシートに横たわり、目をつぶった。
「兄ちゃん! やった! 釣れた! 山女魚!」
目を開けると、釣り糸の先に魚をぶらさげて、結人がこちらに駆けてくる。家の中では見たことがないような結人の笑顔を見ると、智晴の胸はせつなさできしんだ。
智晴は、父が一緒に暮らしている女の人の顔を一度だけ見たことがある。高校に入ってすぐ、いつものスーパーではなく、たまたま入った駅前の大型スーパーでカレーライスの材料を選んでいたときのことだった。
父は、智晴たちの家とは駅を挟んで反対側の町にある団地で暮らしていると、母から聞いていた。父の相手が日本の人ではないということも。
相手の人について、母は何も言わなかったし、智晴もとりたてて何かを感じたことはなかった。しかし、それがどんな国の人であれ、自分の父親が見知らぬ女の人とスーパーのカートを押しているところを見るのは、気持ちがいいものではなかった。
じゃがいもを選びながら、智晴は自分の手がかすかに震えていることに気づいた。父たちに見つからないように、こそこそと隠れるようにしている自分は、なんだかみじめだ、と思った。
両親の離婚について、智晴は感情をあらわにしたことはなかった。子どもたちのなかでいちばん大きな声で泣いたのは寛人だったが、泣いたのはそれ一度きりで、そのあとは案外けろっとしていた。結人は寛人のように泣きはしなかったが、だからといってショックを受けていないわけではない。
結人は、学校をしばしば休むようになっていた。それが結人なりの、両親の離婚に対する感情の表し方なのかもしれなかった。だから、母も智晴も、結人が学校に行かないことについて、とりたてて騒いだりしなかった。母は、学校の先生と面談をしたようだが、それだけで、結人が毎日学校に行くようになる、というわけでもなかった。もし結人が両親の離婚で心の傷のようなものを負ったのなら、いつかその傷が癒えたとき、学校に行くだろう、と智晴は考えていた。
本当のことを言えば、智晴だって、寛人のように泣き叫んだり、結人のように部屋に閉じこもったりしたかった。けれど、自分がそうしたら、この家は立ち行かなくなってしまうのではないか。それが、智晴の一番の心配ごとだった。
自分たちの家から父の荷物が運び出されているとき、智晴たちは母が運転する車に乗って、隣町のファミレスに行った。この町では車がないと不便だから、母は離婚を決めたときから、教習所に通い、三カ月も経たないうちに免許を取った。
その日、寛人と結人は後部座席に座り、智晴は助手席に座った。免許を取り立ての頃は、乗っているだけでひやひやした母の運転も、いつのまにかうまくなっていた。時々、運転している母の顔を智晴は見た。悲しそうでも、泣きそうなわけでもない。何を考え、何を感じているのかはわからないが、どこかせいせいとした顔をしていた。それは智晴が初めて見る母の顔だった。
「なんでも好きなもん食べなよ」
そう言って母はぺたぺたするファミレスのメニューを開いた。あれもこれも、とはしゃいでいるのは寛人だけで、正直なところ、智晴は食欲がなかったし、結人も強張った顔をしている。何も選ばない二人に業を煮やしたのか、母はウエイトレスを呼んで、メニューを適当に指差した。
いくら男の子三人でもこんなに食べられないだろう、という数の料理がテーブルの上に並んだ。空腹に負けて、智晴も寛人も、フォークを手にした。結人も食べ始めたら食欲が出てきたのか、唐揚げを口いっぱいに頬張っている。
「なんにも心配いらないんだから」
まるで大型犬のように勢いよく皿を空にしていく子どもたちに向かって母が宣言するように言った。
「あの家があるんだし」
邦子が残してくれた家は、母と子どもたちのものになった。
「行きたかったら大学にも行かせる」
母は何も食べていなかった。コーヒーだけを飲んでいる。
「なんにも心配いらないんだから」
砂糖もミルクも入っていないコーヒーを口にして、またさっきと同じことを母は言った。
「大丈夫だから」
それは、母が自分に言い聞かせているんじゃないか、と智晴は思った。
(このつづきは本書でお楽しみください)
▼窪美澄『ははのれんあい』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321612000240/