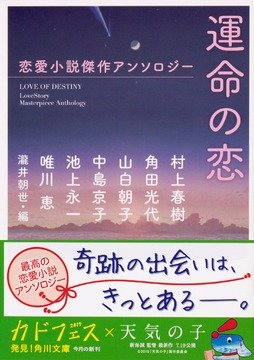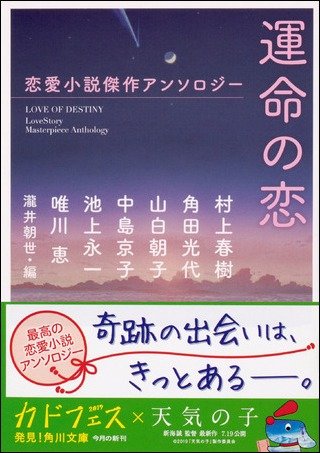一途なアラサー女子の〈全力疾走〉片思いラブストーリー!
岸井ゆきのさん・成田凌さん主演、映画『愛がなんだ』が4/19(金)に公開となります。
公開日まで5日間、カドブンでは角田光代さんによる原作小説の試し読みを行います。
____________________
「あいのひかり公園」で、愛とはほど遠いメンツにかこまれ、
愛について考えてみる
ずっと先に高層ビル群の明かりが見える。橙や黄や、白や赤のちいさな明かりが、点滅したりしなかったりしている。それらを映して、夜空は薄い紫色だ。私の頭のちょうどてっぺんに、まんまるより少し欠けた月がある。白い、ちいさな、いびつな月。
ついさっき、五時間ほど前も、マモちゃんちに向かう電車の窓から、私はこの高層ビル群を眺めていた。低い位置に流れる星雲みたいだと思いながら。なんてうつくしいんだろうと感動までしながら。
風邪ひいて寝てんだ、とマモちゃんから電話がかかってきたのは八時すぎだった。今日あたり電話がくるにちがいないとふんでいた私は、会社で残業するふりをしていた。今日なんにも食ってないんだ。耳に押しあてた携帯電話から聞こえるマモちゃんの声は鼻声で、妙に色っぽく感じられてぞくぞくした。
今すぐそこに駆けつけて、風邪に効く料理をこしらえてあげるよ、と、のどまで出かかった言葉をのみこみ、「なんにも食べてないの? やばいじゃん」私は言って、なんでもないことのように笑った。求められてもいないことをみずから提言するのはよくない。押しつけがましい。ときに相手をびびらせる。
山田さん、もし、もしだよ? 今会社とかにいて、今から帰るところだったりしたら、なんか買って届けてくれないかな。まじで熱でふらふらして、コンビニもいけないんだよな。マモちゃんは言った。「げえ、私まじで会社にいるよ、帰るところだよ、しょうがないなあ、じゃあたのまれてやっか」言いながら、片手で机の上をかんたんにかたづけて、フロアを出てロッカーから鞄を出し、「ほんじゃあ、あとかたづけしたらそっち向かうね」そう言って電話を切るときには、小走りに駅に向かっていた。
けれど今、ずっと先で点灯している高層ビル群の明かりは、もはや星雲なんかには見えない。埃をかぶったショーウィンドウに飾られた、安っぽい、くだらない、にせものくさい豆電球みたいだ。
高層ビルが見えてきたということは、もう代々木に近いんだろうか。というより先に、地理がわからないからとりあえず新宿を目指しているが、それでただしいんだろうか。今が午前一時二十二分、新宿を通過して自分の家にたどりつくのは、いったい何時になるのだろう。神の子イエスさまに一目会うために、星の光を追って歩いた博士たちって、こんな気分だったんだろうか。五歳のころのことをふいに思い出し、もうろうとしてそんなことを考える。幼稚園の年長組のとき、クリスマスのページェントで私はその博士2を演じた。乳香を持って歩く博士の役だ。「見よ、ベツレヘムの星があそこに瞬いている。あの下に、我々の王となられるかたがいらっしゃるのだ」と、客席高くぶらさがる金紙の星を指して、言うのだ。
ふくらはぎは早くも痛みはじめていて、のどが渇いた。それに、この暑さ。九月もなかばだというのに、いつまでこの残暑は続くのか。額は汗でぬらぬらしている。冷たいビールを思いきり飲みたい。冷たいペプシでもいい。冷たいシャワーでもいい。冷房のきいた車両でもいい。
今歩いてきた三十分の道のりを引き返して、マモちゃんのアパートに戻り、走ったけど終電に間に合わなかった、しかも財布を見たらタクシーに乗るお金がなかった、と正直に言おうか。眠らせてくれとは言わない、始発電車が出るまで部屋のどこかに置いてくれとたのもうか。
幾度もそう思うが、しかしそのたび自分でそれを強くうち消す。きっと噓だと思われる。泊まりたいために噓を言っていると思われる。それできっと、嫌われる。
嫌われるくらいだったら、あと三時間でも五時間でも、朝がきて昼になっても、足の痛みとのどの渇きを抱え東京砂漠で行き倒れても、戻らず自分のアパートを目指したほうが何百倍もいい。
こんな時間に街道沿いを歩いている人なんかだれもいない。車はとぎれることなく、白や黄色のライトを流して私のわきをすり抜けていく。少し先にコンビニエンスストアがある。看板がアスファルトをほんのり白く染めている。歩きながら、さっき見たばかりの財布の中身をもう一度確認する。三百二十七円。飲みものくらいなら買える。ペプシといわず、発泡酒くらいなら。
ファミリーマートの店内は、涼しくて、通りにひとけはまったくないのにそこそこ混んでいて、ほっとした。キャミソール姿の女の子と、秋物のニットを着た女の子が、雑誌コーナーで立ち読みをしている。スーツを着た若い男が弁当をひとつひとつ手にとって吟味している。カップルが、売れ残って安くなった花火をきゃあきゃあ言いながら選んでいる。
好きな人のアパートを追い出されて、電車で一時間近くかかる道のりを歩いて帰ろうとしている私も、彼らがそうであるのと同様、ここにいることが当然であるかのように思えてくる。存在がひどくまっとうであるかのような。何もまちがっていないような。
五百ミリリットルの発泡酒を一本買う。ありがとうございました、とレジ係の、金髪眉ピアスのおにいさんに言われて、不覚にも泣き出しそうになる。なんだかその言葉が、自分だけに向けられた特別な言葉であるような気がして。
店を出てすぐプルトップを開ける。きんと冷えた苦い液体がのどをすべりおちていく。首を傾けてごくごく飲むと月はまだ頭の上にある。
三分の一ほどを一気に飲んで、ふたたび歩きはじめる。地図看板に気づいて近づくと、もうずいぶん歩いた気がするのに、マモちゃんのアパートからそれほど離れてはいない。町名すらかわっていない。絶望的な気分になるが、自分の歩いている道が環状七号線だと知る。環七って高円寺にも走っていなかったか。ということは、このまま歩けば新宿を経由せずとも高円寺につくのか。しかし、いったいあとどのくらい歩けば、高円寺にたどりつくのか。
地図のなかに、高井戸、という文字を見つけ、私は携帯電話を取り出す。アドレスから坂本葉子を捜し出し、通話ボタンを押す。
葉子はまだ起きていたらしく、二度目の呼び出し音で電話に出た。自分のアパートから遠く離れた町にいて、財布には百円と少ししかないことを簡潔に伝える。
「それで、ねえ、町の地図を見たらね、どうやらここから高井戸は近いらしいんだけど、葉子ちゃんちにいってもいいかなあ」
地図に顔を近づけて、現在地と高井戸までの距離をはかりながら私は言う。人差し指ぶん、二十分も歩けばつくのではないか。
「何やってんの、あんたは?」葉子は独特の甲高い声で言い、私のいる場所を訊いて、てきぱきと指示をする。「そこからなら二千円しないと思うからタクシーに乗りなさい。私が払うから。甲州街道じゃなくて井の頭通りに出てください、と言うのよ、高井戸団地で左折してください、と言うのよ、レンタカー屋の前で私待ってるから、早くきなさい、わかった?」
井の頭通りに出てください。高井戸団地で左折してください。口のなかでくりかえしながら、残りの発泡酒をちびちびと飲み、流れる車のなかに空車ランプを捜す。