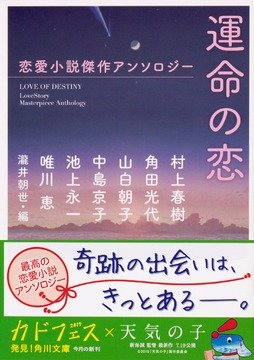角田光代『今日も一日きみを見てた』
極上の一章


【「極上の一章」とは?】
「この一章を読んでもらえれば、買わせる自信あり!」という一章を担当編集者がセレクト。その作品への熱い思いも込めてお薦めさせて頂きます。まずはこの「一章」から、ご一読下さい。

トトのことになると、角田さんは極端に心配性になって、オロオロしてばかりいる。でも愛するものができるって、そういうことだよなぁ。一匹の猫との出逢いで、世界はこんなにもガラリと様相を変える、その瑞々しさ。うちに来てくれてありがとう――ただひたすら愛と感謝に貫かれたその気持ちに、読んだ誰もが心うたれること間違いなし! かわいい写真にもとろけてください。
猫がきた理由
我が家の猫であるトトが、漫画家の西原理恵子さんの家からやってきたことは、すでに書いた。まったくの初対面である飲みの場で、猫をあげようか? と突然西原さんが言ったのである。私は「ほしいです」と即答し、帰ってから家の人に猫を飼ってもかまわないかと訊いた。子どものころからずっと猫を飼っていた家の人は、私以上によろこんだ。
その一件から一年半後、西原さんのおうちの猫は子どもを産み、そうして本当に猫が我が家にやってきたわけである。
猫はどこからやってきたのかとよく訊かれるので、そのように答えているのだが、たまに、「どうして西原さんは初対面なのに、猫をあげようかなどと言ったのだろう?」と疑問を口にする人がいる。
たしかに、言われてみればそうなのだ。
二十年来の一ファンとして、西原理恵子さんという人は、描かれる漫画のとおりなんだか突拍子もない人なのだろうと思いこんでいる。突拍子もない人だから、初対面の人にも猫をあげましょうかという突拍子もない提案をしてくれたのだろうと、はじめてお目に掛かったときに私はすんなり納得してしまった。でも、本当にそうなんだろうか。
よくよく考えれば、猫をあげる、ってすごいことだ。はじめて会った私という人間を、西原さんはまったく知らないはずだ。だからもしかしたら、愛想よくしていても裏ではものすごく残忍な人間で、猫をいじめる可能性だってある。飼い主失格な暮らしぶりをしているかもしれない。はたまた愛情が強すぎて、猫が食べてはいけないものを延々あげ続けるようなことをするかもしれない。
そういうことを避けるために、今の猫の里親制度はとても厳しくなっていると聞いたことがある。譲り手と面談がある、家庭訪問がある、誓約書が必要、等々。はたまた、先住猫や先住犬がいると失格だったり、同居家族がいないと失格(飼い主がもしものときに面倒をみられない、という理由)だったり、今はそうでなくとも、将来的にペット不可の集合住宅に引っ越さねばならない可能性がある場合もだめだったりする。そんな話も聞いたことがある。
もちろん私は、自分が動物をないがしろにするような人間ではないことは重々承知だが、それでも、やっぱり猫がくるまでは不安だった。ちゃんと世話ができるか。猫に嫌われないか。飼ってから、猫が苦手だと気づいたりしないか。自分でも不安だったのだから、知らない人間に猫をあげる西原さんは、もっともっと不安だったろう。
トト以外の兄姉猫は、猫歴のある人たちのおうちに引き取られていった。ずっと猫を飼ってきていて、今も飼っている、いってみれば猫に心得のある人たちだ。
家の人が猫歴があるといっても、私自身はまったくのはじめて。よく考えてみれば、そんな猫初心者、なおのこと不安だっただろう。
ともあれ猫はやってきて、私は嫌われることもなく、苦手なこともなく、猫のいる暮らしになじんでいった。このようにともに暮らしてみると、トトが、猫のように思えなくなってくる。猫の姿を借りた、何かべつのものに思えるのである。ずっと前から知っていた、会うことも決まっていた、とくべつな何か。きっとトトが、猫でなくても、犬でも、鳥でも、人でも、もしかしたら木でも、私はトトだとすぐにわかって、今と同じく好きになってしまうだろうと考えることもある。何かしんどいことがあったとき、ストレスやプレッシャーにじわじわと攻撃されているとき、ごはんを食べていないふりを執拗に続けるトトと向かい合い、トト、うちにきてくれて本当にありがとうね、とよく話しかけている。他人から見たら、ちょっと不気味な猫馬鹿だろう。
トトがうちにやってきてから三年後、西原さんにまた会えることになった。大勢参加した花見の席で、飲みながらトトやトトの両親の話などを西原さんとしているうち、なぜ西原さんが初対面の私に猫をくれると言ったのか、私は唐突に悟った。ずっと長く忘れていたことを、思い出したのである。
西原さんと、はじめて会えることになったその当時、私はひどくすさんだ心持ちでいた。いろいろうまくいかないことが重なって、さらに、許すことも忘れることも、どうしてもできないものが心にへばりついたままで、人なんか信じてたまるか、というような、どうせ世のなかなんてそうしたもんだろう、というような、すねたようなぐれたような状態だった。でも、人というのは不思議なもので、いくらすねていようとも、ぐれていようとも、すさんでいようとも、怒りや憎しみでがんじがらめになっていたとしても、ふつうに日々を送ることができる。私の場合はごはんを作って食べて、小説をひたすらに書き、友だちや家の人と飲み、笑い、眠ることができていた。病は気から、というけれど、心はそんなふうでも、私は健康だった。すねたようなぐれたような心持ちというのは、ずーっと心の奥にある一方で、でも、私の仕事や生活を邪魔することはしないのだった。逆に考えれば、邪魔しないからこそ、消えることなく心にへばりついていたのかもしれない。
あまりにもふつうに(しかも、ときにはたのしく)暮らしているものだから、私ですら、自分の心に巣くった暗い部分を自覚しなくなった。麻痺した、といっていいのかもしれない。それがあることが、当たり前になっていた。
ましてこの日は、ずっとファンだったところの漫画家のかたに会えるということで、緊張もしていたけれど、私はよろこびに満ちて浮かれてもいた。
それでも西原さんは、見抜いたのだ。自分ですら意識しなくなった、私の、すねてぐれて怒りでがんじがらめになって、ひどい不信に陥っている部分に、気づいたのだと思う。それで、猫、だったのではないか。
花見の席で、私はそんなことを唐突に悟り、西原さんに訊いた。あのとき私に猫をあげようかと言ったのは、酔った勢いなんかではなくて、私を見ていて、まずい、と思ったからですか、と。西原さんは笑っていた。笑って、そうよ、と言った。そうよ、あなた、やばかったもの、とっても。
あのとき私は、自分の乗ったボートの底に、ちいさな穴が開いているのに気づかずに、ごくふつうに小説を書き、ごくふつうに友だちと笑い、ごくふつうに食事を作っていたのではないか。ちいさな穴からゆっくりと水はあふれ、ボートは沈みゆくのに私は気づかない。もちろん沈めているのは他者でも世のなかでもない、私だ。不信や怒りを重りのように溜めこんだ私自身である。それを一瞬で悟った西原さんは、おそらく反射的に、救命具を投げたのではないか。はじめて会ったあなたがどんな人だかよく知らない、でもとりあえずそのボートから出ておいで、逃げ出しておいで。そんなふうに。
もちろんこのとき、トトのおとうさん猫とおかあさん猫は、何匹の子どもを産むかわからなかった。七番目に生まれた子がいたら、その子をあげる、という約束だったけれど、果たして七匹目が生まれてくるか、わからなかった。西原さんにもわからなかったろう。それでもとりあえず、投げてくれたのだ、救命具となる言葉を。
ちゃんと生まれた七番目のちいさな生きものを、四年前、私は私を救う何かだとは夢にも思わずに、家に連れて帰ってきた。その生きものは、いっさい鳴かずにトイレで用を足して、まるで決まっていたみたいに私の手の甲にちいさな頭をもたせかけて眠った。私はそれに自分が助けられているなどと思いつくこともなく、トイレの掃除をし、病院に連れていき、駆けずりまわって遊び相手をし、薬を飲ませ、いっしょに眠り、この子がいなくなったらどうしようと家の人と話しては涙ぐんでいる。助けられているなんて、思ったこともなかった。
その花見のあとのこと。悪夢を見て、汗だくで目覚めた。目の前に、人とおんなじ恰好で長く寝そべって布団に寝ているトトがいた。あまりの人っぽさに、思わず笑いが出た。ああ、夢だと気づいた。現実に帰ってこられたと思った。そして私は確信した。たしかに私はこの生きものに助けられた。いや、今も助けられている。癒やし、という言葉とはまったく異なる。なまあたたかいかわいらしいものに、心が安らぎ、リラックスする、というのとはまるきり違う。あのとき抱いていた、すさんだ心持ちというものが、トトの出現によってすべて払拭され、気持ちの真っ白な人間になった、というのとも違う。私は相変わらずすねているし、怒りや不信が無になったとは言えないが、けれど、それらから逃げる場所を得たとは思う。
自分以外の、言葉を持たない自分より非力な生きものの、いのちの心配をし排泄の世話をし、薬を作り体重を量り、自分ではちっともたのしくない遊びの相手を延々とすることで、逃げられたように思うのである。トトが、犬でも鳥でも好きだったろう、と思うのはそんなときだ。私が自分を助けるには、自分以外の何ものかが必要だったのだ。私をごくごくシンプル、かつ具体的な意味合いで必要としてくれる何ものかが。
家の人にとっては、トトはまったく違った存在だろう。私とトトがそうであるように、家の人とトトには、その二者だけの関係があり運命がある。そんなふうなことも、考えるようになった。
朝息苦しくて目覚めると、トトが私の胸にのっている。つややかな鼻が目の前にある。なんでのってるの、重いよ……と文句を言いつつ、やっぱり心のどこかで思っている。うちにきてくれてありがとう。私に会ってくれて、ありがとう。
(この続きは本編でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。