西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』
極上の一章


【「極上の一章」とは?】
「この一章を読んでもらえれば、買わせる自信あり!」という一章を担当編集者がセレクト。その作品への熱い思いも込めてお薦めさせて頂きます。まずはこの「一章」から、ご一読下さい。
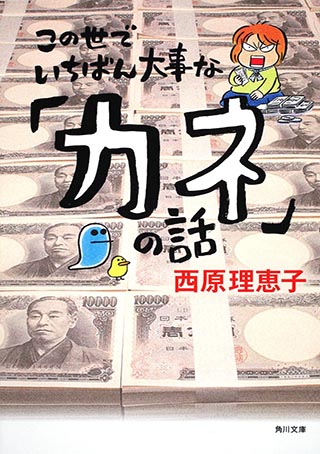
貧しさはやがて濁流になってすべてを呑み込み、人が人でなくなっていく――西原さんは子どもの頃、その現実を目の当たりにして、身体にたたき込んだ。新刊『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』で女子の経済力の大切さを説く背景には、そういう壮絶な体験の裏打ちがある。西原さんの言葉がどうしてこうも胸に突き刺さるのか、本書を読むとその理由がさらによく分かります!
何にもなくても、認められたかった。
何にもなくても、好きになってほしかった。
大人になるって、どういうことなんだろうね。
そのころのわたしに聞いたら、たぶん、「何かが終わっていくこと」って答えるかもしれない。ひとつ、年齢が上がるたびに、カウントダウンがはじまる感じ。
田舎の不良って「なる」のもはやければ、回転もはやい。女の子がぼろぼろになるのもはやいんだよ。たとえばね。
地元に残った女の子は、だいたい十八くらいで結婚する。旦那はヤンキーあがりでたいていは日給の仕事して、1DKくらいのアパートで子どもが増えて、旦那の収入では生活はいつもギリギリ。子どもは手がかかるし、生活はどんどん苦しくなるしで、あ~ら、不思議。いつの間にか、あの「いつも怒ってて、太ってて、へんなパーマかけてるお母さん」の一丁あがり。気がつくと、子どものころ、殴られるのが嫌で逃げ出してきたはずの家と、そっくりな家を自分でまたつくってる。
「こんなはずじゃなかった」って怒ってばっかりいるお母さんたちは、地元に残った女の子たちがやがてそうなる「将来の自分の姿」だった。
そういうお母さんやお姉さんたちの姿を見ていれば、女の子たちは当然不安になる。自分もやっぱり、いつか、ああなるんだろうか。
そりゃあ、お母さんたちだって必死でがんばっているんだろうけど、それはどこにも行けない、諦めやグチとセットになってる人生に見えた。
「あんたのために、お母さん、離婚しないで我慢してるんやで」
子どもにしたら、そんなことを言われてもせつないだけだし、「ずるい」って思う。自分だけ被害者ヅラすんな。子どもにしたら、あんただって十分、加害者じゃ……。
だけど、そんなこと言えるものじゃない。どんな親でも、やっぱり親は親なんだよね。親のことはみんな、心底から嫌いにはなれない。
子どもが親を「嫌い」っていうとしたら、それはよっぽどのことがあったんだと思う。怒ってばっかりの親に反発はしていても、心の底では好きで、でも顔をあわせれば殴られるんだから、子どもたちは、いつも、せつなかった。
だけど、「自分は親と同じような人生だけはイヤだ」って思っても、どうすればいいのかわからない。
若さと容姿を切り札にして水商売なんかをやって、ブランドもので着飾っていた女の子たちだって、三十、四十にもなれば、もうどこも雇ってはくれない。当時、田舎で女の人が働ける場所は本当に限られていたから、借金でどうにもならなくなればどんどん落ちていくしかなくて、そうして、いつの間にか姿を消してしまう。
思春期のわたしに見えてきたのは、「将来」なんかじゃなくって、そういう「行き止まり」だった。
「行き止まり」なんてひどい言い方だけど、若くて、バカで、空回りばっかりのわたしたちには、それはもう、「行き止まり」としか思えなかった。そして、その行き止まりに、そのうち自分たちもずるずると引きずりこまれていく……。
へらへら笑っていても、心の中は不安で、不安でしょうがないから、自己評価の低い女の子はヤリマンになっちゃうの。
いい子なんだよ。でも自己評価が低くていい子だと、「自分には何のとりえもない」「人から愛される要素なんて、わたしにはない」って、そう思い込んでいるから、男の子にちょっとでも優しくされると、優しくされたことが嬉しくて「こんなわたしに、そこまで言ってくれるんなら」って、誘いを断れない。それで誰とでもすぐ寝る子になっちゃう。
はっちゃけるしかない男の子たちと、不安でしょうがない女の子たち。
たまり場になってるアパートのせまい部屋では、とんでもないことが起こっていた。
男の子も女の子もシンナーでラリって、乱交しちゃう。わけがわかんなくなったその勢いで、セックスしちゃう。
不良のお兄さん、お姉さんたちが、誰が誰かもわかんない状態で、こんがらがったり、からまったりしていて、あれだけはもう、わたしには耐えられなかった。そういう日は、たまり場から一目散に逃げ出すしかなかった。
「貧しさ」っていうのは、たとえば、こういうことでもあるんだと思う。
人は将来に希望が見えなくなると、自分のことをちゃんと大事にしてあげることさえできなくなってしまう。やぶれかぶれで刹那的な楽しさを追い求めるうち、モラルをなくしてしまう。
女の子のあいだでは、中絶費用のカンパが回ってくるなんてことが珍しくもなかった。町には保険証がなくてもたった四万円で中絶する医者がいて、女の子どうしで千円ずつ出し合ったりしていた。
こういうとき、相手の男は絶対に逃げるんだよ。当然のように知らん顔を決め込んでいる。
こわかった。このままでいたら自分はどうなるんだろうって。
女の子は、あっという間にボロボロになっていくし、お母さんたちは、みんな、怒ってばっかりで、このままこの町にいたところで、先が見えてる。
わたしはいつかこの町を出るんだろうか。出られるんだろうか。
勉強もろくにできない自分が、自分の力でこの町を出ることは考えられなかった。だけどまわりを見ても、ダメな先輩や大人の見本市で、「希望」がなかった。
真夜中のドーナッツ
貧乏は病気だ。それも、どうあがいても治らない、不治の病だ。
それは、たとえばあの窓ガラスが割れたまま、ほったらかされていた家みたいなもの。あれも何かひとつの原因でそうなったわけじゃない。何年も何年もかけて、ああなって、いつからそうなったのかも、もはや、わからない。
そうして長い歳月をかけて積み重なったものがいったん決壊をはじめたら、人は、押し寄せる流れに抵抗することもできない。ただずるずるとのみこまれていくだけ。
貧乏っていうのは、そうやって土砂崩れみたいに、何もかもをのみこんで押し流してしまう。そういうこわさを、わたしは、あのころに見て、知った。
だけど、あのころのわたしは、やっぱり、どこまでいってもまだ十代の子どもだったんだと思う。両親がお金のことでさんざん言い争っているのを見ていたはずなのに、自分の家のことを、まあまあ「お金持ち」だって思っていた。
地元の友だちがあまりにも過酷な状況だったので、うちはまだマシ。まあまあ、うちは山の手かしらって。
浦戸から引っ越して最初に住んだ家は、せまい借家だった。
トタンをはりつけただけのような平屋で、トイレとお風呂ははなれ。あとからとってつけた台所に部屋が三つ。そこに、お母さんと新しいお父さん、そのお父さんの寝たきりのお父さんに、そして、お兄ちゃんとわたし。
家の中は、とにかくいつも散らかっていた。お母さんは働いて、家事もぜんぶやって、寝たきりのおじいちゃんの下の世話までやってたんだから、片付かないのはあたりまえ。床は歩くとニチニチして粘っこいし、酢みたいなすっぱい匂いがする家。でも、そんな家でも、友だちにはものすごくうらやましがられたんだよ。
その次に住んだ家は、父親が一念発起して建てた一軒家。会社を興したお父さんが、いちばん羽振りがよかったのも、このころ。
「理恵ちゃんちが本当にうらやましかった」
子どものころの思い出を友だちと話してると、いまだにそう言われる。
「車で送り迎えされるし、家族で温泉旅行にも行ってたし、だいたい親に殴られることもないし、理恵ちゃんちは本当によかったよね」って。
たしかに、父親はアメ車のでっかいのに乗っていたし、家では、朝からステーキやメロンが出てくることもあった。
彼氏の風呂なしのアパートに転がりこんでいた友だちが遊びにくると、親には内緒でお風呂に入れてあげて、自分の服を貸してあげたりもしたからね。
学校の同級生はみんなお金持ちで、財布にはふつうに万札が入っている子ばっかりだったけど、わたしのお財布に入っているのは、せいぜい二、三千円。毎日お昼代に五百円もらって、学食で三百五十円の定食を食べて残る百五十円をコツコツ貯めて貯金していた。本物のお金持ちの同級生たちはたぶんそんな貯金なんてしてなかったと思う。わたしは、それでも地元の友だちからしたら、十分に「お金持ち」っていう感じだった。
それに家の中だって、嵐の日ばっかりじゃなかった。
今でも覚えてる。お父さんが夜中によく料理をつくっていた姿を。
戦争で、食べたいものもろくに食べられなかった経験をしている父親は、食べたいものがあると、夜中だろうが何だろうが、もう我慢ができないの。いてもたってもいられなくなって、いきなり、自分でつくりだしちゃう。
いちばん得意だったのは、ドーナッツ。お酒はまったく飲まなかった父親は甘いものが大好き。昔、パン工場をやっていたこともあるので、自分でつくるのもすごく上手。ちゃんとメリケン粉にイースト菌を入れて発酵させた生地を、型で抜いて、油であげる。
「あー。みぃつけた!」
「おお。うまいぞ。理恵子も食べるか?」
いい匂いで、眠っていたわたしも目が覚めちゃって、一緒に食べる。
よくつくっていたのが雑炊。冷蔵庫にある白菜とかニンジンなんかを適当に入れて、ぐつぐつ煮るだけ。味の決め手は「ほんだし」。カツオ風味のあれを「これでもか!」って入れたのが、お父さんの雑炊だった。
わたしにとって、たまにしか帰ってこないお父さんがつくる料理は「外食」で、お母さんがいつも食卓に並べるおさしみやお煮しめとはちがう、特別でよそいきの味がしたもんよ。いつ何をつくるのか、予想もつかない。でも何をつくっても、本当に、おいしかった。
いつも、こういうお父さんならいいのに。
妙にしんとした夜中の台所。
ほろほろと口の中でとけていった甘い味。
じゃりじゃりする砂糖をまぶした、お父さんのドーナッツ。
わたしは、きっと自分のことを「愛されているしあわせな子ども」だと、いつまでも思っていたかったんだと思う。
お父さんが、行ってしまった日
終わりは突然やってきた。
お父さんが首を吊って、死んだ。
その日は、わたしが東京の美大を受験するはずの日だった。このことはあとでまとめて話すけど、わたしは高校三年生のとき、学校を退学になっていた。それで一年かけて大検をとって、夢にチャレンジするはずの日に、お父さんが死んだ。
受験なんかできるはずがない。
電話で呼び戻されたわたしが高知の家にとって返すと、喪服を着たお母さんがいた。顔は殴られて、ぼこぼこに腫れて、頭も髪の毛も血だらけだった。
お母さんは、独身のころに働いて貯めたお金でローンを組んで、家を三軒ばかり持っていた。「持ち家が三軒」というと何かすごいみたいだけど、田舎だから土地なんかいくらでもあって、五十坪もあってもたった五十万円とか、破格の安さなんだよ。でもお母さんにしたら、それは大切な虎の子。
この土地さえあれば、万が一何かあっても、どうにか生計を立てていける。わたしのお母さんはそういう経済観念だってちゃんとあった人だった。
なのに、男でつまずいちゃった。女の人生にはよくあることだと思うけど、バクチに狂う旦那のために、大切な土地と貯金をどんどん切り崩さなくてはならなかったのが、わたしのお母さんの結婚生活だった。
お父さんが会社を興したカネも、もともと、お母さんが貯めた貯金だった。
お父さんがバクチにつぎこんだカネも、もともと、お母さんの貯金だった。
それなのに、お父さんは羽振りがいいフリをして、見栄をはった。家を建てて、アメ車を乗り回し、娘のわたしは私立の学校に行かせる。そういうすべてが、お父さんの見栄の産物だった。
それでもバクチさえやらなかったら、結果はちがったのかもしれない。会社で儲けたお金も湯水のようにバクチに使ってしまって、そのせいでいよいよ、家にお金が入ってこなくなっても、まだ見栄の生活をつづけた。
現実の収入に見合わない、ムリをした生活。バクチの借金がそれに追い討ちをかける。それを挽回しようと、お父さんはさらにバクチにのめりこんでいった。
バクチをしている最中に、高揚感のあまり意識がふっと飛ぶことを「ブラックアウト」という。このころのお父さんは、家に帰ってきても、わけわかんないことをわめいては、突然バタンと眠ってしまったりした。ブラックアウト。バクチの黒い大きな闇が、やぶれかぶれのお父さんをのみこもうとしていた。
とうとう崖っぷちまで追い詰められたお父さんは、最後にバクチで自分の人生をひっくり返そうとした。たかがバクチに、自分の人生を丸ごと賭けてしまった。
お父さんがわたしの貯金に手を出したときのことは忘れられない。バイト代やお年玉、そして学食のお釣りをコツコツ貯めた、たった十二万円の金額の貯金通帳をひったくるようにして持っていった。お父さんはそれを入れてぜんぶで四十万円を持って、隣町にある競艇場に行くという。
「これが人生最期の大勝負じゃ。これで負けたら、俺は死ぬ」
わたしは思った。そんな勝負に、勝つわけがないだろう。この人はもう、死んだほうがいい……。
お父さんが死んだあの日も、お父さんはお母さんを車に乗せて、坂道や崖道をずーっと走らせながら「あの土地を売れ。この俺に死ねと言うのか」って言いつづけたんだって。ハンドルを切れば、ふたりとも死ぬ。俺はそれだけの覚悟でいるんだぞってことを、お母さんにほのめかせながらのドライブ。
だけど、そういう状況でも、お母さんは頑として首を縦にふらなかった。三軒あった家は、もう最後の一軒しか残っていない。「あれは子どもたちにあげるための土地と家だから。あれだけは絶対に売れない」と答えるお母さんを、お父さんはバンバン、バンバン殴った。
お葬式の日。
だから、お母さんは血だらけだった。そして、弔問に来た人たちは、誰もお父さんの死をかなしんではいなかった。
麻雀の借用書を片手に「五千円返せ」と言ってくる人。「生前、もらう約束をしていたので」と、お父さんのゴルフクラブのセットを持って帰る人。どさくさにまぎれて、もらえるものはもらっておこうっていう根性の人がどっさり、来ていた。
わたしは、お父さんは社長だって思っていた。でもちがったみたい。
「社長」「社長」ってペコペコすりよってきていたのは、どうしようもない、乞食みたいな人たちで、お父さんは社長は社長でも、乞食の社長だった。
最後の最後まで羽振りのいいフリをして、見栄をはっていたお父さんの残していったなけなしのものが、身ぐるみをはがされるように持っていかれようとしている。
お母さんは、そんなお父さんに殴られて腫れ上がったままの顔で、そういう人たちに「すみません、すみません」って頭を下げている。
そのときになって、わたしは、初めて本当に知った。うちには、本当は「カネ」がなかったんだって。
知らなかった。知ろうともしなかったことが、本当に、恥ずかしかった。
幼いころ、言い争うお父さんとお母さんのあいだにはさまれて、目をつぶったまま、いつも嵐が通り過ぎるのを待っていた。そのころから、わたしはちっとも変わっていなかったんだと思う。
それどころか、あのころはいつも怒っているお母さんのことが、うとましくて反発ばかりしていた。沈没寸前のわが家を何とかもたせようと、仕事も家事もぜんぶひとりで引き受けて奮闘しているお母さんに感謝するどころか、「子どもたちを思えばこそ、自分はこんなに苦労してる」という空気をみなぎらせているお母さんから、逃げ出したくってしょうがなかった。
それで、本当は見えていたはずのことも、見えないフリをしていた。
どうせ何かを手伝ったってほめてくれるわけじゃなし。「何であんたは、こうなの!」って文句を言われるだけ、ソン。そうして理屈だけはいっぱしの、お皿の一枚も洗わない娘になって、見たくないことには都合よく背中を向けて、自分は「社長の娘」で「しあわせ」みたいな顔をしていた。それが、わたし。
わかってるつもりで、本当は何ひとつ、わかっちゃいなかった。
子ども時代の終わりに
そのまま行ったら破滅するに決まっている道を、人は突き進んでしまうことがある。シンナーでラリって死んじゃった先輩も、借金で首が回らなくなって家族ごと町からいなくなった友だちも、「こんなはずじゃなかった」という道を突き進んで、消えていった。
「バカだ」「何で引き返せないんだ」、そういう人のことを、まるで対岸の火事のように思っている人たちは、きっとそう言うかもしれない。
でもね。世の中には正しいからっていったって、「だから何だ」っていうことがあるのよ。正論が、通用しない場所もある。
そういう場所で、何とか生き抜こうとしたら、たとえまちがってたって、その人にとっては「そう生きるしかなかった」っていうことが、あるんじゃないか。
だって、わたしは、お父さんを見ていて思った。
人が暗い落とし穴に落ちるきっかけは、たぶん、ひとつではない。たったいっこの小さな事件で、一家が離散するような、あんなかなしいことが起きるわけがない。
お父さんも、やっぱり心の風邪をこじらせた人だったのかもしれない。
よくない、悪い風をたくさん、たくさん浴びて、そう生きるしかない道を突き進んでしまった。だから誰にも止められなかった。逃げて、逃げて、でも最後にはとうとう逃げ切れなくって、最後にはそれで死んでしまった。
お金がないことに追い詰められると、人は人でなくなっていく。その人本来の自分ではいられなくなって、誰でもなく、自分で自分を崖っぷちまで追い詰めて、最後には命さえ落としてしまうことがある。
貧しさが、そうやってすべてをのみこんでしまうことがある。
「理恵子の話は面白いなあ。お母さん、この子はよその子とはちょっとちがうぞ」
幼いわたしを自分の膝の上にのっけては、たわいないおしゃべりを聞いてくれた人は、もういない。
何もかもをいっぺんになくして、わたしは、そこから自分の足で歩き出すしかなかった。
(この続きは本編でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。























