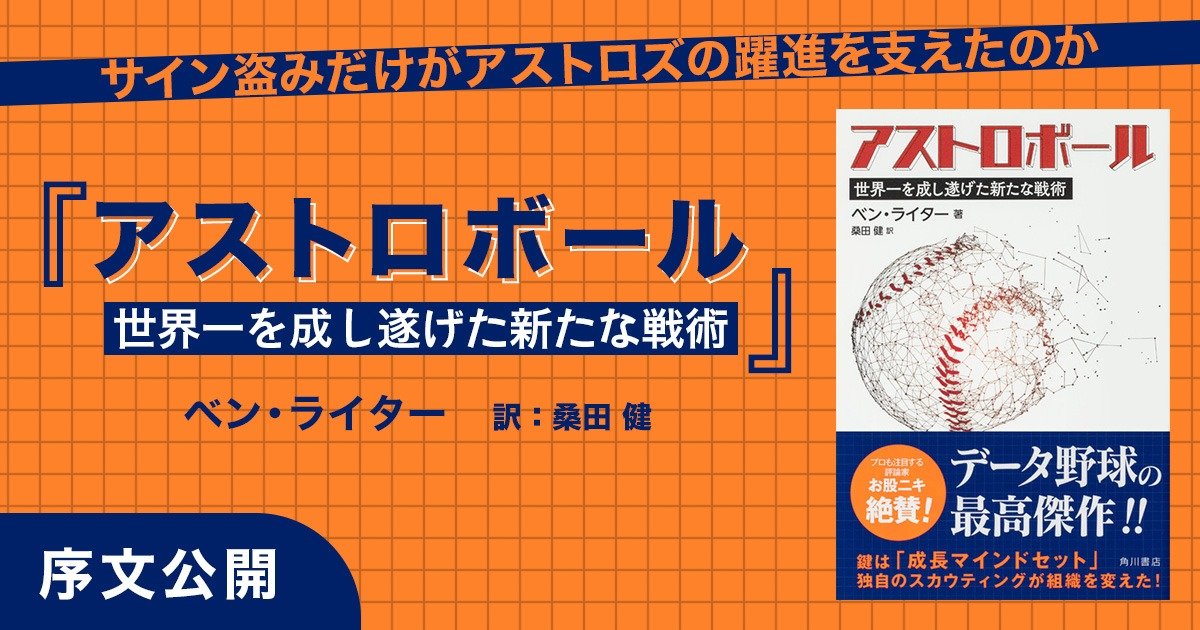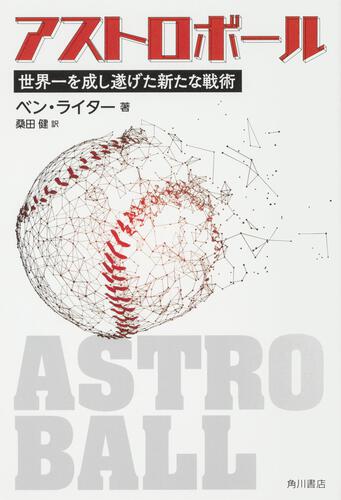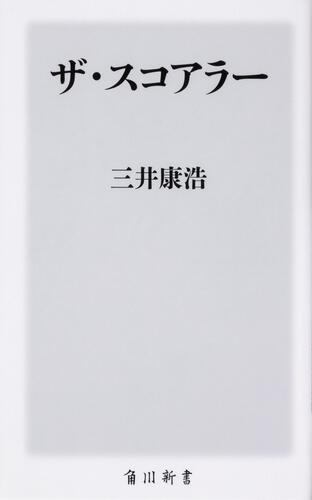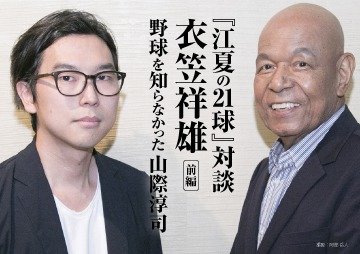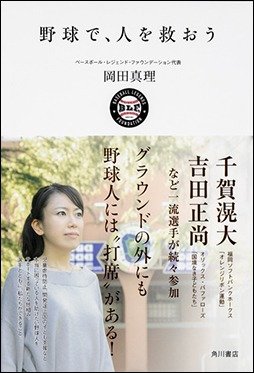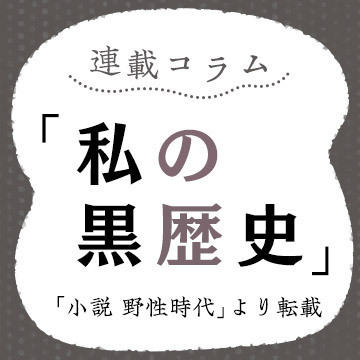2017年にメジャーリーグでワールドチャンピオンの座に輝いたアストロズ。元は3年連続で100敗以上を喫するなどメジャー屈指の弱小球団だったアストロズがいかにして世界一に輝いたか、そのチーム作りの軌跡を追ったドキュメンタリー書籍が『アストロボール』です。そのアストロズは、2017年に電子機器を使ったサイン盗みを行っていたことが発覚し、球史に残る一大スキャンダルを巻き起こしています。「不正行為があったと知ってから読むと、本書の内容の一部の信憑性に疑問が出てくることは否めない」(訳者あとがきより)ですが、それでも「ほかのチームにはない視点でのスカウティングとドラフトへの取り組み、成長マインドセットという概念、チームの和の醸成など、不正なサイン盗みとは関係のないプロセスには学ぶべき点が多い」(同訳者あとがきより)と考え、出版する運びとなりました。
本書を「データ野球の最新版にして最高傑作」と推して日本語版への序文をいただいたのは、プロも注目する野球評論家のお股ニキ @omatacom 氏。
本書の内容をよりよく知っていただくべく、お股ニキ氏による日本語版序文を特別公開します。
◆ ◆ ◆
日本語版への序文 データと直感の融合が生んだ大逆転劇
本書には野球のすべてが詰まっている。『マネー・ボール』『ビッグデータベースボール』に次ぐ、アメリカデータ野球の最新版にして最高傑作が本作『アストロボール』である。
アメリカで最も一般的なスポーツ週刊誌、スポーツ・イラストレイテッド(SI)は 2014 年 6 月 30 日号の表紙に「2017 年のワールドシリーズ覇者」というタイトルをつけて、ヒューストン・アストロズのジョージ・スプリンガー外野手を起用した。アストロズは当時 2011 年から 3 年連続で 100 敗以上を喫していた、ここ半世紀で最低のチームである。視聴率 0 %を記録したこともある、誰も試合を見ていなかった最低のチームを取り上げた大胆な予測には、多くの抗議の声があったそうだ。
だが、その 3 年後。見事予測は的中した。最低のチームを頂点にまで再建する中心となったのが、2011 年にGMに就任したジェフ・ルーノウである。メキシコシティで生まれた、アメリカ人の両親を持つルーノウには野球のプロ経験はない。経済学と化学工学の二つの学士号とMBAを取得しているルーノウは、マッキンゼーのコンサルタントになる前はゴアテックスを製造販売する会社でエンジニアとして、兵士たちを核兵器や生物兵器、化学兵器から保護する特殊スーツのデザインをしていた。インターネットビジネスでオーダーメイドの服を提供する事業の立ち上げにも携わっていた。
アストロズのGMに就任する前、ルーノウはセントルイス・カージナルスにいた。米国で最も熱狂的で野球通のファンを持つ真のベースボールタウンを本拠地とするカージナルスは、最も模範的な球団運営をする古豪の一つである。完全ウェーバー制のドラフト制度やFA補強によるドラフト権の譲渡、贅沢税など、強豪チームや年俸の高いチームが勝ち続けるのが難しいメジャーリーグで、安定して結果を出し続けるのには理由があった。ファームシステムの充実とそのためのドラフトである。年俸調停権やFA権を取得するまでは実力に比して非常に安い価格で選手を保有できる現在の大リーグの仕組みにおいては、ドラフトによる若手選手の獲得は何よりも重要である。
カージナルスの筆頭オーナーの1人であるビル・デウィット・ジュニアは、『マネー・ボール』時代が始まると、野球とビジネスを、ドラフトで融合できないかと考えた。彼がルーノウに白羽の矢を立てたのは、野球界とは無縁でありながらも、野球ゲームの一つである「ファンタジー・ベースボール」で無敵の強さを誇っていたからだった。
ルーノウはスカウト部長として、データ主導のアプローチで手腕を発揮した。カージナルスのドラフトは、のちの調査で上位 1 %にも含まれるほどの成果をあげた。データ主導のアプローチに、スカウトらによる経験や「直感」を組み合わせるようなシステムをつかみかけていたという。
「最低のチーム」だったヒューストン・アストロズを 2011 年に買収してオーナーとなったジム・クレインは、データ・ドリブンによる運送業により財を成した人物である。買収したチームを強化するために、データ主導によるアプローチと長期的な計画を持つルーノウをGMとして迎え、チームの抜本的な改革と強化に着手した。カージナルスではスカウト部長として、新人の獲得だけに留まっていたが、チーム全体の強化、戦略にまで関わりたいと考えていたルーノウには、またとない機会だった。
ルーノウは長期的な計画を用意していた。少なくとも、表面上チームを強化しているかのようなポーズを見せるためにベテランのFA選手に大金を支払うような、中途半端な補強は一切しなかった。最初の 2 年は、結果が出ず、それどころか資金も出し惜しみわざと負けにいっているかのように思われた。世間の目にはそのように映っていた中で、最低のチームはファームを含めたメンバーをドラフトとトレードで入れ替えていった。ホセ・アルトゥーベ、カルロス・コレア、SI誌の表紙を飾ったジョージ・スプリンガー、アレックス・ブレグマンらはルーノウが獲得したチームの「コア」である。
データ主導のルーノウのアプローチを支えたのが、シグ・マイデルである。デンマーク人の父親を持つシグは、メジャーリーグの試合をシミュレートするボードゲーム『オールスター・ベースボール』の回転盤を回すのが大好きな子どもだった。
カジノのブラックジャックのディーラーとしてのバイト経験も持つシグはNASAでロケット工学の専門家になる。数学的素養を持つ分析官であるシグはロケットを軌道から外さずに飛ばすにはどうすればいいかという工学的な問題よりは、数学と科学が人間とどのように交わっているか、人間が生まれ持った限界を理解して克服するのにどのように役立てるか、という領域に魅力を感じていた。『マネー・ボール』を読んで、非効率な選手評価の部分を、シグと同じような素養を持つアスレチックスのフロントがデータの力によって強化して、球界の土台を作り直していく様子を見て、自身にも球界に居場所があるのではないかと考えるようになった。そして、ウインターリーグでアピールをした結果、ルーノウに採用されることとなった。
「人間が気づくことは、人間が数値化できる」「数値化できれば、そこから学ぶことができる」
NASAのロケット工学の分析官やマッキンゼーのコンサルタントといったプロフェッショナルたちは、徹底したデータ主導のアプローチでチームを再建していった。人間の判断には限界があり、試行数を重ねると長期的には確率の通り収束するデータの方が信頼性は高い。しかも、ただの「データ」ではない。基本的なセイバーメトリクス指標やプレイのトラッキングデータだけではなく、スカウトの直感までをもアルゴリズムに取り込んでいったのだという。ドラフトにおいてスカウトに「直感シール」の使用を認めていたのもそのためだろう。地域のレベルを反映した数字やスカウトの経験や直感、選手の怪我の耐性や「成長マインドセット」など、目に見えないものまでも数値化していった。
「データを使っているからといってすべてを知っていると傲慢にはならなかったこと」も重要であった。球速が 140 キロ強の派手さとは無縁の技巧派左腕、ダラス・カイケルがサイ・ヤング賞投手にまで成長することや、守備や走塁では平凡な 20 代後半に差し掛かる外野手、J・D・マルティネスが、オフにプロ経験のないヒッティングコーチの下で抜本的なスイングの改造に着手し、それまでとは違った打者に変貌を遂げていたことなどは、数値だけでは予測ができなかった。カイケルはせいぜいローテーションの 4 ~ 5 番手を埋める存在かトレード要員と考え、マルティネスにはチャンスを与えることができずに戦力外としたが、両者ともに後に大活躍。マルティネスは 2018 年にはレッドソックスの一員として、アストロズの 2 年連続ワールドシリーズ進出の夢の前に立ちはだかった。回帰分析に伴う問題の一つはカイケル、マルティネスのような「外れ値」特定が難しい点だが、彼らはそうした失敗からも学び、活かしていった。
加えてデータによるプレイの進化や成長が可能だとしても、最後にプレイし決断するのはプレイヤー本人である。選手本人がより成長し、優れたプレイをしていきたいという気持ち「成長マインドセット」を持っているか否かも重要な要素となる。コアであるアルトゥーベやコレア、ブレグマンやスプリンガーはそれを持っていた。カイケルやJ・D・マルティネスもである。
本書における最大の学びはここにある。『ビッグデータベースボール』が出版されたように「データ」の重要性が叫ばれるこの時代に、彼らは「データ」の弊害、「データ」に頼りすぎると平凡なチームが出来上がることを理解していた。
ルーノウが持つ強みの一つは、アストロズの立て直しにつながったのが、データ主導のアプローチだったにもかかわらず、彼は自分の知らないこと――データが説明できないことに秘められているかもしれない価値――を無視するのは愚か者だけだと認識していた点だ。「数値化できないからといって、存在しないという意味にはならない」とルーノウは言う。
小柄なアルトゥーベに対して同じようなミスは犯さなかった。身長 1 メートル 68 センチの「小さな巨人」アルトゥーベはどんなボールでも打つことができる。ドラフト 1 位で指名することができたアレックス・ブレグマンは、実力だけでなくリーダーとして、チームを引っ張っていったし、英語圏とスペイン語圏で分かれがちなメジャーリーグのロッカールームをまとめる役割も担っていった。小柄な選手はセレクションで不利な扱いを受けやすいことから、身体的に見るからに優れている選手よりも、土壇場でもリスクを恐れずにプレイすることができるといった仮説も立てていた。ブレグマンは 2017 年アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ(ALCS)の対ニューヨーク・ヤンキース戦の最終第7戦で、しくじれば大変なことになる成功確率 25 %ほどのホームへのスローイングを決めてみせた。
本書でのキーワードの一つとなる「直感」。
デトロイト・タイガースのエース、メジャーのエースとして君臨するジャスティン・ヴァーランダーの獲得にも「直感」が重要なキーワードとなる。全球団へのトレード拒否権を持つヴァーランダーは最終的には恋人であるケイト・アプトンの言葉に従い、「直感」でアストロズへの移籍を決意した。30 代半ばの投手への高額年俸の負担と期待の若手の放出は経済的な合理性だけでは不合理にも見えたが、ヴァーランダーが持つ「成長マインドセット」により、スライダーを改善していたこと、また巨大ハリケーンの被害を受けたヒューストンの街を救うためにもヴァーランダーのようなスターの獲得は不可欠だった。
他にも、メジャーリーグの選手経験を持つ上で、フロントの仕事も経験して理解しており、心理学の学位も持つ若き指揮官、A・J・ヒンチ監督の採用にもヒントが詰まっている。彼はデータによる適切なスターティングメンバーをフロントに提示されたとしても、それに無条件に従うのが監督の役割ではないことを理解していた。現場で選手の体調や調子、精神的な状況をもすべて把握しうる監督はそれらを考慮して、確率を無視して直感に従ったほうがいいと判断しうる知識全般を有している。フロントも監督の決定を助けるあらゆるデータを提供するが、最終的な判断をコンピューターが下すことがあってはならないと理解していた。フロント、選手、監督、コーチが各自の役割を理解し全うしたことが、弱小球団の大逆転劇という大きなストーリーにつながった。
ただし、アストロズがこうした成果を出す過程で、球史に残る汚点を作ったことに触れないわけにはいかない。2020 年 1 月 13 日、MLBのコミッショナーは調査結果を発表し、アストロズが 2017 年のシーズンを通して、および 2018 年のシーズンの途中まで、電子機器を使用して試合中に相手チームの捕手のサインを盗んでいたと断定した。グラウンドの中でのみ行われるのであれば相手選手の癖やサインを盗むことには罰則はなく、モラルとルールの狭間にある技術の一つといえる。セカンドランナーがキャッチャーのサインを盗んで伝達するのは日本の高校野球でも議論となったが、こうした行為はプロアマ問わず全世界で現実として行われている。送りバントでセカンドにランナーを置きたがるのは、そうした側面もある。だが、試合中の電子機器を使用したサイン盗みは 2017 年のシーズンには明確に禁止されていた不正行為である。
アストロズには 500 万ドルの罰金と、2020 年と 2021 年のドラフト 1 巡目と 2 巡目の指名権の剥奪が、GMのルーノウと監督のA・J・ヒンチには 1 年間の職務停止処分が科された。決定を受けてアストロズのオーナーのジム・クレインは、ルーノウとヒンチを解任した。1 月 17 日の時点ではルーノウとヒンチが直接関与したという証拠は出ておらず、当人たちは関与を否定しているが、ルーノウ主導によるチーム作りは幕を閉じることになった。
サイン盗みを主導した一人として名前が挙がっているのは、カルロス・ベルトランである。ベルトランは 2020 年からはメッツで監督として指揮をとる予定だったが、まったくの白紙になってしまった。本書ではベルトランが相手投手の癖をビデオによって見抜く技術を選手たちへ伝授していった様子が描かれている。
昔から日本でもユニフォームのシワやグラブの動き、表情、首より上の動きなどで、球種や牽制かホームへの投球かを見抜ける選手は数多くいる。アンドリュー・ジョーンズが楽天に来た際にも、田中将大の投球をブルペンで 5 球見ただけで変化球かストレートかを見抜いたという逸話がある。特にラテンアメリカ出身の打者にはこうしたセンスが備わっている印象を受ける。ダルビッシュ有が 2017 年のワールドシリーズで攻略された際にも、ストレートとスライダーでセットポジションでのグラブの動きが違ったことが指摘されている。ダルビッシュには日本時代からストレートを投げる前の癖があった。
当たり前だが事前に球種を見抜けることの効果は絶大なものがある。その結果、モラルが崩壊してそもそもサインを盗んで伝えればいいという発想にエスカレートし、フロント主導の電子機器の使用や伝達につながってしまったとしたら、きわめて残念と言わざるを得ない。
こうしたモラルの低下はロベルト・オスーナの獲得にも象徴される。DV疑惑による出場停止期間中だったオスーナの獲得には賛否があったが、実力は疑いがない。ただし、2019 年のワールドシリーズ前に、トーブマンGM補佐がオスーナの獲得を肯定するような発言を多くの女性レポーターが集まる場で行ったことで、結局解任されることとなった。「データを使っているからといってすべてを知っていると傲慢にはならなかった」はずのアストロズで、少なくない人間に傲慢さが芽生えていたことが、様々な問題の温床となったのだろう。
しかし、本書に描かれている、フロント、監督、選手という複雑なパズルを組み合わせて、アストロズがチームを強化していく様子は大変に参考になる。先に述べたベルトランはスイッチヒッターとしてプレーオフでホームランを量産してきたスーパースターという実績を持つだけでなく、プエルトリコ出身で文化・言語の壁に直面したルーキー時代の困難の記憶を併せ持っていた。そうした経験によって、ベルトランはロッカールームをまとめる役割を果たしていた。チームワークや若手へのアドバイスといった貢献は数値化が難しいものであるが、こうしたこれまで数値化されてこなかった直感的な部分を軸とした独自のスカウティングこそ、本書から学ぶべきビッグデータ時代の人事である。アストロズの躍進は決してサイン盗みだけによるものではない。それはそれ、これはこれとして、チームの功罪は区別して考える必要があるだろう。
シグ・マイデルやルーノウが野球の仕事につけたのも、データ重視の時代に彼らのような人材が求められた運もあった。
データ、統計に誰でもアクセスできる時代、合理的判断には誰もがたどり着ける時代だからだからこそ、人間の直感は重要であり続けるはずだ。
2020 年 1 月 お股ニキ(野球評論家)
▼ベン・ライター/訳:桑田健『アストロボール 世界一を成し遂げた新たな戦術』詳細(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000143/