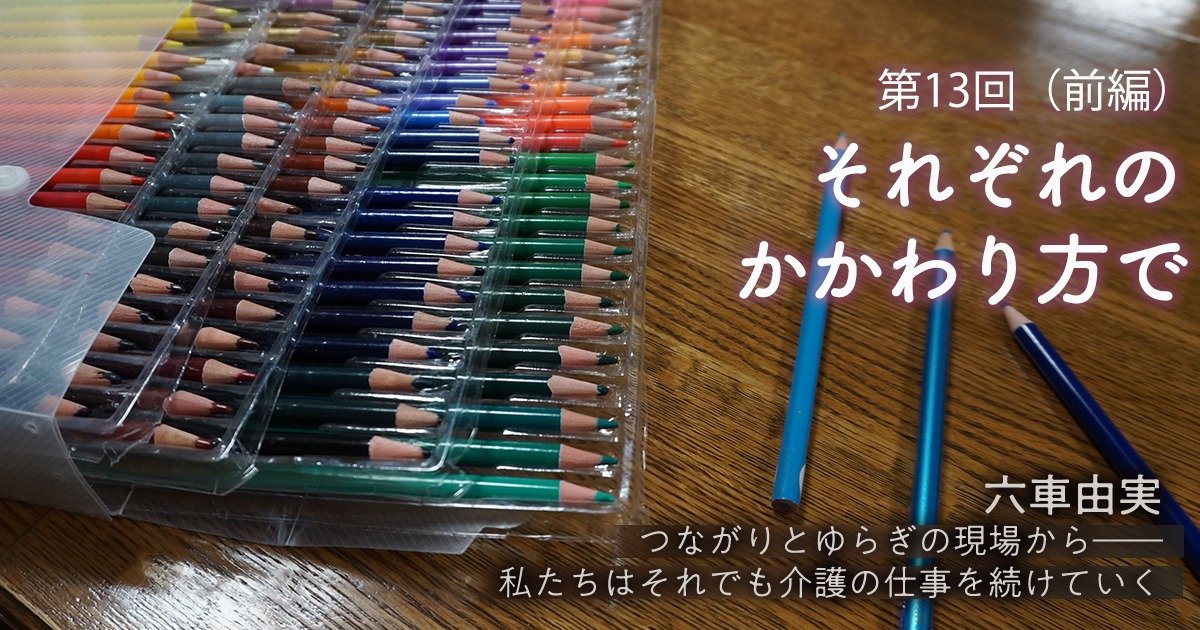
六車由実の、介護の未来13 それぞれのかかわり方で(前編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
星に願いを
6月中旬、七夕祭に向けて、スタッフたちは利用者さんたちと準備を始めていた。まずは、折り紙で天の川や笹の葉、星等の色とりどりの七夕飾りを作り、デイルームの天井を飾った。スタッフのカイさんは、トウコさんが折り紙で作った八角形の箱を上手に使って、吹き流しを作って飾ってくれた。箱以外の使い道を考えつかなかった私は、「なるほど! 飾りにもなるんだ」と、そのアイディアに感動し、箱をたくさん持ってきてくれるトウコさんも、「わー嬉しい! きれいに飾ってくれてありがとう」と喜んでいた。
デイルームの天井が七夕飾りで彩られたら、今度は、利用者さんたちやスタッフに、それぞれ願い事を短冊に書いてもらう。これも毎年の恒例行事だ。
私も真っ先に、二つの短冊に願い事を書いた。一つは、「マロンと母が、怪我も病気もなく、1年間元気にすごせますように」。この1年程の間にマロンは両足を怪我し、母も肩や足の痛みがひどくなって、ずいぶんと心配したので、まずはこのお願い。そして、もう一つは、「今年こそはみんなで忘年会が開けますように」。一昨年の年末にすまいるほーむを会場に移転後初めて開いた会社の忘年会は、社員とともにお手伝いをしてくれている地域の人たちや母も参加して、ワイワイ盛り上がる楽しい会だった。けれどそれ以来、感染予防のために、みんなでお酒を飲みながら楽しく過ごす機会は全くなくなってしまった。何の心配もなく、年の瀬にみんなでお酒を飲んで騒ぐ。そんな普通の時間が戻ってきてほしい、と心から願うのである。
さて、利用者さんたちは、短冊に何と書いたのか。
みよさんは、「父、母が元気でおりますように」と書いていた。みよさんは、最近、両親が生きていた頃の記憶や、夫や義母と一緒に住んでいた頃の記憶の中にいることが時々ある。そんな時は、実家や結婚当初に住んでいた家へ帰ろうとして、荷物をまとめてマンションを出て夜道を彷徨い歩くことなども増えてきた。その度に本人の携帯から私や娘さんへ「道に迷った」と電話があるので、何とか事なきを得ているが、短冊を書いている時も両親は生きており、みよさんは心からその健康を祈っているのだった。
美砂保さんは、コロナ禍でなかなか会えない東京や横浜に住む子供や孫たちの健康と幸せを願う言葉を丁寧に綴った後、小さな文字で少し遠慮がちにこんな一文を加えていた。「すまいるの生活は嬉しいよ いつまでも続きますように」。認知症の症状が徐々に進んできて混乱したり、傷ついたり、落ち込んだりすることの多くなった美砂保さんにとって、今、唯一喜びや幸せを感じられる場所が、仲間たちと安心して過ごせるすまいるほーむだという。「すまいるほーむの生活がいつまでも続きますように」というのは、そんな美砂保さんにとっての切実な願いなのだろう。
5月から利用を始めて、毎回折り紙で作った箱を持ってきてくれるトウコさんは、2枚の短冊に願い事を書いた。「100歳まで元気ですまいるほーむに通えますように」。そして、息子さんとお嫁さんの名前を記して、「いつまでもお世話になります」と。
以前通っていた大規模のデイサービスで、箱や人形等手作りの作品を他の利用者さんたちへプレゼントしたことを職員から叱責されて、深く傷つき、自信を失っていたトウコさんが、今は、100歳まで生きたい、すまいるほーむに通いたい、と前向きな気持ちになってくれていることが私はとても嬉しかった。それに、息子さん夫婦に世話になることについても、「お世話になります」と受け入れている。「いろいろあったけど、私は今が一番幸せなの」という言葉を最近頻繁に口にするトウコさんの思いが溢れている短冊だ。
アンビバレントな願望
利用者さんたちの短冊は、家族の健康や幸せを願ったり、自分の前向きな思いや希望が記されていたりするものが多いが、その一方で、人生に絶望する気持ちを吐露した短冊もある。
目の不自由な六さんは、スタッフに代筆を頼み、短冊にこう書いてもらっていた。
「星屑になりたい」
社会や人生を皮肉ったり、揶揄したりする六さんの独特の表現なのだろうが、一昨年は、「元気なうちに富士山に登りたい」、去年は、「宇宙旅行に行って、月から地球を見てみたい」という大きな夢を記していたことからすると、「星屑になりたい」というのは、随分と悲観的な願いだ。ここ1年で少しずつ衰えを見せてきた体力や不調の続く健康面への不安、そしてコロナウイルスの感染の恐怖でイラついたり落ち込んだりすることの多い気分の表れなのかもしれないとも思う。でも、一方で、六さんの短冊のもう1枚にはこんなことも書かれていた。
「これからも人生悔いなく過ごしたい。一日一日を無事に過ごす」
これは、今でも毎朝畑に通って農作業をし、作物が収穫できるとすまいるほーむに持ってきてくれる、堅実で一生懸命な六さんらしい願い事、というより生きることへの決意のように思える。ネガティブな思いとそれでもポジティブであろうとする思いとが、六さんの中で共存しているのだ。
いつも元気で、そしてどんな時でもどんな場面でも我が道を行くテンさんも、「長生きさせてください」と短冊に記しながら、次の瞬間には、「明日には逝ってるよ」と口にしている。テンさんは、普段から、「生きられるだけ生きたいよ」「300歳まで生きたい」というのと、「もう死んでもいいよ」「300歳なんて生きられるわけないじゃ、明日にも死んでるよ」というのが口癖なのだ。
毎年この時期に、短冊に書かれた願い事を眺めていると、そんな利用者さんたちの抱える複雑な心の内が垣間見えてくる。きっと高齢の利用者さんたちは、老いのプロセスの中で、「もっと生きたい」と「もう死にたい」というアンビバレントな願望の間で常に揺れ動きながら、それでも懸命に今を生きているのだろう。だから、私たちは、ポジティブな思いもネガティブな思いもどちらも受けとめながら、利用者さんたちが生きている今という時間を共にし、大切にしていきたい、と毎年改めて思うのである。
あゆみさんの「願い」
けれど、今年もそういう思いを共有した私たちにとっても、あゆみさんが短冊に書いた願い事はあまりに衝撃的だった。
「迷惑をかけずにピンピンコロリと死にたい!!」
「願い事なんてないけど……」と最初は短冊に願い事を書くことを躊躇していたが、書き始めると鉛筆で何度もなぞって太字にし、しかも、「死にたい」に感嘆符を二つも付けて強調した。あゆみさんは、願いはこれだけだから1枚でいいという。
これもアンビバレントな思いとして受けとめればいいのか。でも、私には、この短冊からは、本気で「死にたい」と願う絶望の呻き声しか聞こえてこなかった。
利用者さんたちもあゆみさんの短冊に戸惑いを見せていた。隣で、両親の健康を願う言葉を記していたみよさんは、あゆみさんの短冊を見て驚き、こう叫んだ。
「あんた、死にたいなんて書くもんじゃないよ」
ほがらかな性格のみよさんだが、この時ばかりは、あゆみさんを説得するのに必死で、語気を荒らげていた。
「私らみたいな年寄りならまだしも、あんたまだ若いんだしさ。そんな簡単に死ねるもんじゃないよ。死にたいなんて書かないでよ」
みよさんは少し涙ぐんでいるようだった。けれど、みよさんの説得も虚しく、あゆみさんは、こう言い放って、そのまま短冊をスタッフの亀ちゃんに渡して、鉛筆を片付けた。
「だって、死にたいんだもん。みんなに迷惑かけるんなら、死んだ方がましでしょ」
みよさんは、それ以上は何も言えずに、押し黙ってしまった。あゆみさんから短冊を渡された亀ちゃんは、どうしたものかと困惑していたが、とりあえず、糸を通して、他の利用者さんたちの短冊と共に七夕飾りの間に吊るしていった。あゆみさんの短冊は、目立たない隅の方に。他の利用者さんたちへの、そしてあゆみさん自身への、亀ちゃんの配慮だったと思う。
エアコンやサーキュレーターの涼風に吹かれて、たくさんの短冊や七夕飾りが、さらさらと愉しげに揺らめいたり、絡み合ったりしている。利用者さんたちは毎日天井を見上げて、その様子を眺めては、「きれいだねえ」「ホントねえ」などと和やかに話をしている。ただ、あゆみさんの「願い」だけが、天井の隅で一つ寂しげに、くるくると回っていた。
自信をなくしていくあゆみさん
実は、短冊を書くしばらく前から、私にも他のスタッフたちにも、すまいるほーむでのあゆみさんの様子が以前とは違ってきたように見えていた。
もともと絵を描くのが好きで、あゆみさんは今でも週に1回隣町の絵画教室に通っている。すまいるほーむでも、ミュシャの絵や世界の名画をモチーフに作られた細密画の塗り絵を、160色の色鉛筆を駆使して、大胆な色使いで何度も重ね塗りして仕上げていた。以前は、夢中になって作品作りに取り組んでいたのだが、この春頃からは、色鉛筆を持ってもなかなか塗ることに集中できなくなっていて、頻繁にトイレに立ったり、出窓に設置してあるフリードリンクのお茶を何度もお代りしたりなど落ち着かない様子が見られていた。
そんなあゆみさんの様子を気遣ったスタッフたちが、季節ごとに作り替えるデイルームの飾りを「一緒に作りませんか」と、他の利用者さんたちと共にあゆみさんも誘ってみるのだが、「私はいいです」と言って断られてしまうことが多くなった。そして、スタッフや他の利用者さんたちが楽しそうに作っているのを、あゆみさんは遠目に見ては、「あんなもの作って意味があるのかしら……」とぼやいている。かと思えば、隣で一生懸命に作っているみよさんに対しては、「もっとこうやった方がいい」等と口や手を出してしまう。初めは、「そうかな。そうやった方がいいかね」と素直にアドバイスを受け入れていたみよさんも、あゆみさんの介入の度が過ぎてくると、だんだんと鬱陶しくなってしまい、「私のやりたいようにやらせてよ」とあゆみさんに背を向けてしまうこともあった。そんな時、あゆみさんはトイレに何度も立ったり、お茶を何杯もお代りしたりして、また落ち着きをなくしていくのであった。
今まで熱心だった細密画の塗り絵に取り組まなくなっただけでなく、以前は、興味を持てば、折り紙や色画用紙を使って季節の飾りを作るのを手伝ってくれていたのに、それもやりたがらなくなってしまったのは、なぜなのか。あゆみさんの様子を普段からよく見てくれているスタッフたちの意見は、あゆみさんがすまいるほーむに通い始めた1年半前に比べて、認知症の症状が進行し、細かい作業ができなくなっているからではないか、そのことをあゆみさん自身もよくわかっているからではないか、ということだった。
たとえば七夕祭で、亡くなった方の思い出を語り合い、供養する時に灯す灯籠を作る時だった。あゆみさんは最初は躊躇しながらもしばらくすると作り始め、折り紙で自分の家の家紋を切り抜いて灯籠に貼ろうとした。しかし、自分の思い描いていたような家紋がなかなかできず、だんだんと苛立っていって灯籠を作るのを止めてしまった。スタッフが手伝おうとする余地もなかったという。
また、ひな祭りの時には、ちらし寿司の上に飾る錦糸卵用に薄焼き卵をあゆみさんが焼いてくれた。しかし、厚焼きになってしまったり、油が少なすぎてフライパンに焦げ付いて破れてしまったりと、上手に焼くことができず、一人で悪戦苦闘していた。やはり、スタッフが手伝おうとすることには否定的だったし、「厚くたって、破れていたって、細かく切るから大丈夫だよ」と励ましてみても、思い描いたようにできないことにひどく落ち込み、最後には憔悴しきってしまっていたという。
今までできていたことができなくなっている。そのことにあゆみさん自身が深く傷つき、自信を失っている。すまいるほーむでの活動に対して消極的になっていることも、また、短冊に「死にたい!!」という「願い」を書いてしまうことも、自信を喪失したあゆみさんが自分の人生に絶望しているからではないか、と私たちには想像できた。
あゆみさんの絶望を想像できたからといって、では私たちに何ができるのだろうか。
※次回は7月31日(土)に掲載予定




























