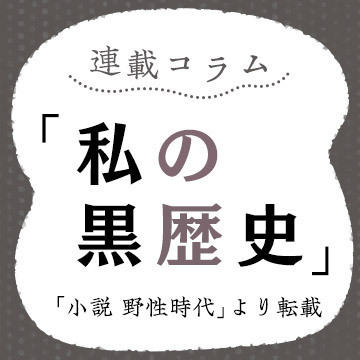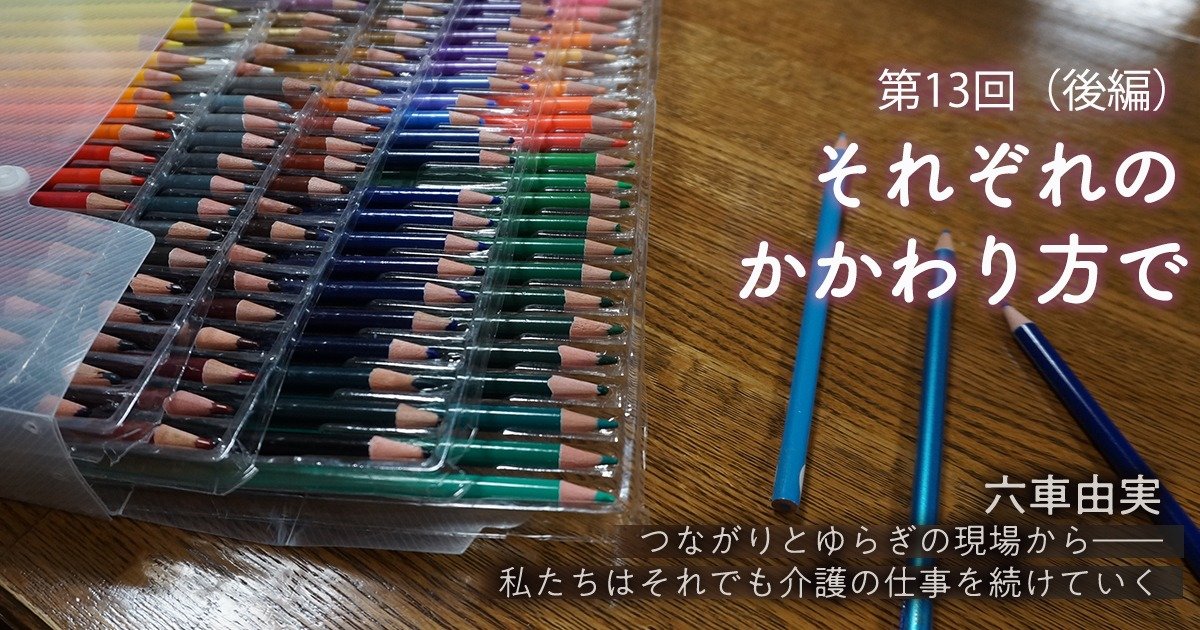
六車由実の、介護の未来13 それぞれのかかわり方で(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
>>前編はこちら
◆ ◆ ◆
関係性が結べない
すまいるほーむでは、これまで、利用者さんたちが傷ついたり、苦しんだり、自信を失ったりした時にどうしてきたか。
例えば、美砂保さんは、自宅で夫に責められて傷ついた時や物忘れがひどくなってきていることに落ち込んだ時等に、「由実さん、今日ちょっと話があるんだけど時間ある?」と言って、二人だけの時間の中で自分の抱える苦悩を語ってくれた。私は、何か解決策を提示できるわけでもなく、ただ美砂保さんの話を聞くことしかできなかったが、それでも、語り終えた美砂保さんは、「聞いてもらえてよかった」と暗く沈んでいた表情を変え、明るい笑みを浮かべていたのだった。
利用者さん同士で互いを励まし合う様子もよく見られる。以前通っていた大規模のデイサービスで受けた深い傷が癒えないトウコさんは、昼休みに隣に座っていたみよさんに、その時の思いを語っていた。みよさんは、「それは酷いね」「辛かったね」「私も悲しくなってくるよ」とまるで我が事のように目に涙を浮かべて、トウコさんの話を聞いてくれていた。トウコさんが、「100歳まで生きたい」と前向きな願いを持てたのも、自分の思いを受けとめてくれる仲間の存在が大きいのではないかと思う。
スタッフたちも、利用者さんたちの表情が曇っていたり、元気がなかったり、苛立っていたりすると、送迎車の中やお風呂の中で声をかけ、話を聞いている。また、その利用者さんを励まそうと、その方の好きな歌をみんなで歌おうと他の利用者さんたちに呼びかけて歌ったり、みんなの中に入れずに一人でぽつりと淋しそうにしている利用者さんの傍にそっと寄り添ったりしている。
すまいるほーむでは、そうやって、それぞれに合わせて、それぞれのやり方で、互いの弱さをみんなで受けとめ合ってきたのだった。だからこそ、多くの利用者さんたちやスタッフたちが、ここにいることで安心したり、心の拠り所と感じたりしているのだと思う。
けれど、あゆみさんは、困った時に助けを求めてもくれないし、自分の苦しみや辛さをスタッフや他の利用者さんに語ってもくれない。そして、私たちスタッフも、そうしたあゆみさんに積極的に声をかけたり、寄り添ったりすることができずにいた。私たちが躊躇してしまうのは、あゆみさんが、突然、予想もつかないことがきっかけとなって、感情を爆発させ、すまいるほーむを飛び出してしまうことが何度もあったからである(第7回)。
3月にも飛び出してしまうことがあった。そのきっかけは、朝から10杯以上お茶をお代りしていたあゆみさんの体調を心配したスタッフが「そんなに飲んで大丈夫?」と声をかけたことにあった。
何が引き金となってあゆみさんを激昂させてしまうかわからないという不安と緊張感は、私たちのあゆみさんへの気軽なかかわりを阻害することになってしまっている。あゆみさんへ話しかける時には、そのタイミングやあゆみさんの表情、かける言葉にかなりの気遣いを要する。すると、どうしてもかかわる機会は他の利用者さんよりも少なくなるし、あゆみさんとスタッフとの間の距離感もなかなか縮まってはいかない。
また、あゆみさんは、他の利用者さんと関係を持つことも拒んでいる。自ら話しかけることはまずないし、他の利用者さんが通りがかりに声をかけたりしても、「えっ、何なんですか?」と顔をしかめ、身を固くして縮こまってしまう。おそらく、70歳のあゆみさんにとって、80代、90代の利用者さんたちは、遠い存在であり、仲間という意識をもつことはできないのかもしれない。
たった一人、いつも隣に座っているみよさんにだけは、話しかけることができている。でも、まくし立てるように一方的に思い出話や世間話をするだけで、自分の心の内に抱える苦しみを吐露することはない。それに、認知症のみよさんが、以前働いていたホテルで仕事をしているつもりで、「タイムカード押すの忘れた」とか、「今日、泊りのお客さんいないのかな」等と口にすると、すっと距離を取り、私たちに、「隣の人、ちょっとおかしいです」と言いに来たりする。あゆみさんにとって、みよさんは話し相手ではあるが、その存在を受けとめられる信頼できる相手ではないのかもしれない。
だから、利用し始めて1年半が経つというのに、あゆみさんはどの利用者さんとも関係を深めることができないままでいるのである。その意味で、すまいるほーむにおいても孤独を感じているのではないかと思う。
抉られるトラウマ
そして、私たちがあゆみさんのことで何よりも心を痛めているのは、彼女が他の利用者さんたちとのかかわりを拒絶するばかりでなく、人格を貶めるかのような態度をとってしまうことに対してである。
例えば、脳出血により左片麻痺になったテンさんが、自分で箸を持ち、こぼしたり、口の周りを汚したりしながらも、一生懸命にご飯を食べているのを目にして、露骨に表情を歪め、みよさんに対して、「汚いね。あんなふうになりたくないよね」と囁いたことがある。
レビー小体型認知症のフクさんが、何かが見えるのか前の方に手を伸ばしたり、独り言を言ったりしていると、やはりみよさんを肘で小突いて、「あんな人と一緒にいたくないよね」等とこそこそと悪口を言い始め、挙句の果てに、フクさんが視界に入らないように、テーブル中央に設置しているアクリルボードに紙を貼って見えなくしたりするのである。
あるいは、大正生まれのスズさんが、杖をつき、スタッフに体を支えられ、足を引きずりながらなんとか歩いてトイレまで行こうとしているのを、気遣うでも応援するでもなく、ただ嫌そうに見ては、みよさんに何か囁いている。みよさんは少し困ったように、「気にしなきゃいいじゃ」と答えている。
認知症の進行した利用者さんや高齢で体が思うように動かない利用者さんたちに対する、あゆみさんのそうした言動は、今年になってとりわけ酷くなってきたように思える。それは、もしかしたら、あゆみさん自身にできないことが増えてきたことへの不安と絶望の裏返しなのかもしれないとも思う。「ああはなりたくない」「あんな人と一緒にいたくない」というその存在の否定は、自分がいずれ同じように老い、認知症が進んで、心身共に衰えていくことへの強烈な拒絶なのだろう。
けれど、そうであるかもしれないと理解はできても、私はあゆみさんの態度が、どうしても許せないことがある。許せないばかりか、恐怖さえ覚えてしまい、あゆみさんとかかわることができなくなってしまうこともある。というのも、テンさんやフクさんたちに対するあゆみさんの嫌悪のまなざしや言葉が、あたかも私自身に向けられたもののように心の奥に突き刺さり、鈍い痛みを感じてしまうことがあるからである。
なぜ、そんな痛みを覚えてしまうのか、初めは自分でもわからなかった。しかし、だんだんとその痛みが強くなり、恐怖のあまりあゆみさんの顔さえ見られなくなって、自分ではどうしたらいいのかわからなくなってしまい、私はある日の夕方、事務所へ行って、三国社長に苦しみのうちを泣きながらぶちまけていた。突然のことに驚きながらも、三国社長はじっと私の話を聞いてくれた。そうやって話を聞いてもらっているうちに、痛みや恐怖を感じる原因がわかったような気がした。
それは、あゆみさんの言動によって、私の心の奥底に封じ込められていた辛い経験が抉り出され、フラッシュバックするように体の中に戦慄が走ったからだった。
中学生の頃からだろうか。私は、新しい集団の中に入った時に、ある日突然、一部の人たちや集団全員から嫌悪や非難のまなざしを受けて、避けられるようになる、という経験をしてきた。それはすまいるほーむへ来る前まで何度か繰り返された。何が原因かは自分ではわからない。私が誰かを傷つけるようなことを言ったのかもしれないとも思うが、鈍感な私には思い当たることが浮かばなかった。理由を尋ねることも謝ることもできないまま、私は孤独の時間をやり過ごすしかなかった。ただ、私が弾かれる集団は、合宿とか研修とか、一時的に作られたものばかりだったから、一時孤独に耐えれば、解散とともに苦痛から解放されて、それで終わりだった。だから、その時に受けた心の傷が自分にとってのトラウマになっていたという自覚もなかったのである。
しかし、あゆみさんの言動を自分に対することとして感じることで、私は、突然集団から排除された幾度かの経験が、自分の人格も存在も否定されるということへの堪えがたい恐怖として、心に深く刻まれていたことに気づいたのだった。その経験があったからこそ、自分ばかりでなく、そこにいる誰かが傷つけられたり、人格や存在が否定されたり、排除されたりすることのない場所があったらいいと、私はずっと求め続けてきたではないかと思った。そして求め続けて、今、やっとここにみんなで作り上げてきたのがすまいるほーむだったのだ。
だから、多くの利用者さんたちが心の拠り所としてくれているすまいるほーむで、どんな理由があろうが、あゆみさんが他の利用者さんたちの人格を否定するような態度をとることが許せなかったのだと思う。
「それがすまいるほーむでしょ」
だが、そう気づいてみると、私は、誰も傷つかない、排除しない場所としてすまいるほーむを守ろうとする一方で、あゆみさんを排除しようとしているのではないか、と思えてきた。自分がトラウマによって恐怖を抱くためにあゆみさんとかかわれないことは、支援の専門職としても、管理者としても失格ではないか、とも思えて自分の至らなさが情けなくなった。私はますますどうしていいのかわからなくなって、また涙が溢れてきた。
それまで私の話をじっと聞いていた三国社長は、言葉を選びながら、ゆっくりとこう言った。
「いいんじゃないかな、それでも。あなたは深く傷ついてきた。それがトラウマになって、今は、あゆみさんにかかわることができない。そして、すまいるほーむのみんなを大切に思って守ろうとしている。それはそれでいいんだと思うよ。それで自分を責めることはないよ」
えっ、いいの? こんな私でも……。予想外の言葉に驚いたが、私は救われたように感じた。そして、三国社長は続けた。
「そんな今のあなたの気持ちを他のスタッフにも伝えてみたらいいよ。みんなわかってくれるし、助けてくれるよ。それがすまいるほーむでしょ」
確かに、弱さや至らなさを受けとめて、互いに補い合うのがすまいるほーむだった。
みんなの前でというわけにはいかなかったし、トラウマそのものを告白するまでの勇気はなかったけれど、私は、事務室で昼食を食べている時や送迎後のスタッフだけになった時などに、それぞれ何人かのスタッフに、私が抱えるあゆみさんへの思いと、今は積極的にあゆみさんとかかわるのが難しいということを伝えてみた。どのスタッフも、「そうなんだ。よくわかるよ」と受けとめてくれ、それぞれができる方法であゆみさんとかかわるようにしていくから大丈夫だと言ってくれた。
スタッフにそんなふうに苦しさを受けとめてもらえたことで、私は少し気が楽になったように思えた。そして、私なりにできるあゆみさんとのかかわりはどんなことがあるのかを、少しずつ考えられるようになっていった。
一つ、これはできると思いついたことがあった。それは、送迎中の会話だった。情けないことに、あゆみさんと目と目を合わせて正面から向き合って話をすることには、まだ恐怖を感じてしまう。けれど、不思議なことに、助手席に座ったあゆみさんとは、二人とも同じ方向を向いているせいか、何の恐怖心も躊躇もなく会話することができていたのである。
特に、車の中でかけている米津玄師の曲についての話題は盛り上がった。高校時代に合唱部に所属していたあゆみさんは、男性歌手の特に高音の声にとても魅了されるようで、高音から低音まで歌いこなす米津玄師の曲を聞くたびに、「米津さんって、すごいですねー! こういう人を天才って言うんでしょうね」と感心していた。そして、送迎の間のほとんどの時間を私たちは米津談議に費やすのだった。
短い送迎時間のこんなたわいもない会話が、あゆみさんとの関係を深めたり、彼女の抱える孤独や絶望を癒したりすることにつながるわけではないことはわかっている。でも、これが今私にできることであり、このわずかな時間でも、あゆみさんもそして私も、笑い合ってすごせること、それを大切にできたら、と思う。
いつかは
6月の下旬、入浴介助が終わって、私がデイルームに戻ってくると、あゆみさんを取り囲んで、利用者さんたちやスタッフが何やら大騒ぎをしている。いったい何があったのか心配になって、近くにいたスタッフのクミさんに尋ねてみると、あゆみさんが長い間かかって、カナレットの「ヴェネチア、大運河の入り口」という絵画の塗り絵を完成させたので、みんなで壁に飾ろうと促していたのだという。
見てみると、あゆみさんは、「恥ずかしいからいいです」と明らかに困惑している。けれど、それでも利用者さんたちは口々にあゆみさんの作品を褒めていた。
「ブルーとホワイトで彩られて本当に美しい作品です」
「こんな絵はあゆみさんにしか描けないよ」
「本当に素晴らしいから飾って見せて」
利用者さんたちのあゆみさんに対する心からの賛辞だった。その気持ちが届いたのか、あゆみさんも、「それじゃあ」と言って、作品を飾ることを初めて承諾してくれた。亀ちゃんは早速、青と白がより一層映えるようにと黒い画用紙の上に作品を貼りつけ、それをあゆみさんにもみんなにもよく見える壁の上方に掲げてくれた。
利用者さんたちもスタッフも、その作品を見上げて、また、「すごいねー」と感嘆の声を上げた。あゆみさんの顔には、いつになく嬉しそうな笑みが溢れていた。
利用者さんたちは、あゆみさんのことをちゃんと見守ってくれていたのだ。あゆみさんのきつい言葉や態度と裏腹の苦悩も絶望も、もしかしたらみんなわかって、受けとめてくれていたのかもしれない。
あゆみさんにとって、今は、すまいるほーむは安心できる心の拠り所ではないかもしれない。でも、ここで利用者さんたちやスタッフと共に時間をすごし、それぞれとそれぞれなりのかかわりを持っていくことで、いつか、「生きていてもいいかな」と思ってくれたらいいと心から思う。
※次回は8月21日(土)に掲載予定