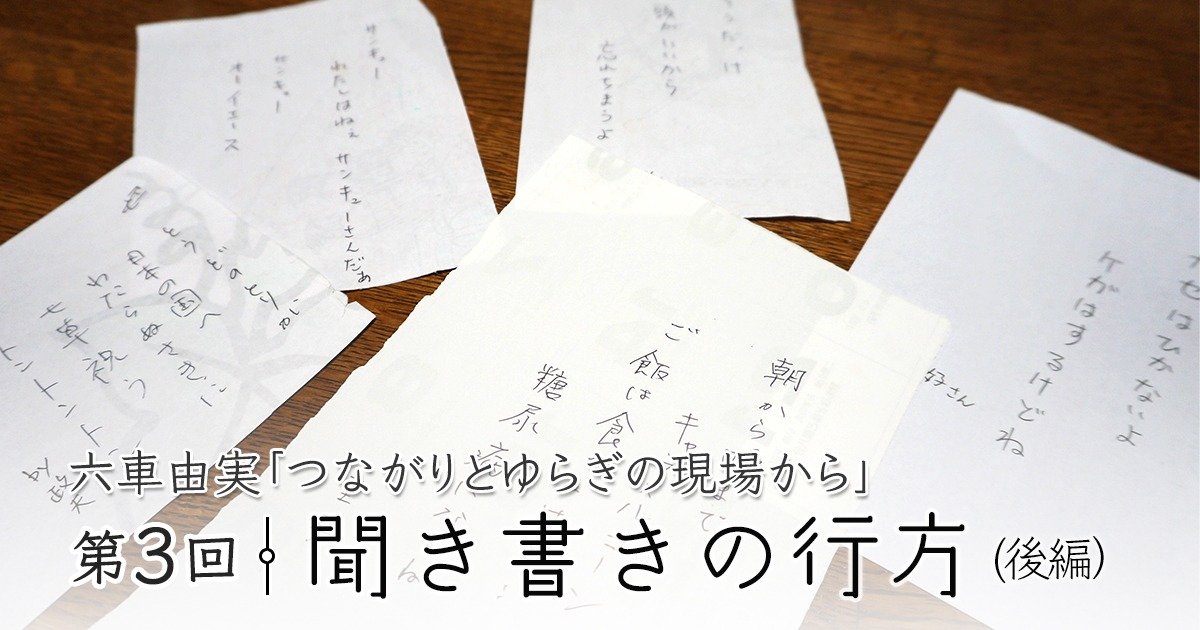
六車由実の、介護の未来03 聞き書きの行方(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
>>前編はこちら
マスクとアクリルボードによって変わった日常
私は、開かれた聞き書きによる「すまいるかるた」を、すまいるほーむという場がこれからもつながりを結ぶ場であり続けるためにもみんなで作り続けていきたいし、作り続けるだろうと漫然と考えていた。
それに、開かれた聞き書きによる「すまいるかるた」作りは、利用者さんもスタッフもみんなで協力して聞き書きから読み札作りをするので、特定のスタッフに大きな負担がかかることはないし、特別な訓練も知識も技術もいらず、誰でもすぐに始められるという特長もある。そのため、昨年末まで引き受けてきた各地での講演では、その後半に必ず、4~6人程度のグループに分かれて、「すまいるかるた」を作るワークショップを行わせてもらった。実際に、聞き書きでかるたを作るという経験をした参加者の多くは、「面白かった」「現場に帰ってすぐにできそうな気がする」という前向きな感想を寄せてくれたのだった。
今まで、拙著を読んだり、講演を聴いてくださった方からは、「意味のある活動だが、聞き書きをしたくても自分の働く現場は忙しすぎてできない」とか、「知識や経験のある六車さんにはできるかもしれないが、自分たちにはハードルが高すぎる」という否定的な意見をもらうこともあった。私はそれにどう答えたらいいのかずっと迷ってきたが、「すまいるかるた」がそうした意見に対する一つの明確な答えになるように思えた。誰でも簡単に始められて、しかも現場を変えていく力のある聞き書きの形。試行錯誤を続けてきた聞き書きの「完成型」だという自負も私にはあった。
にもかかわらず、今、私は、開かれた聞き書きができなくなっている。冒頭に紹介した六さんへの聞き書きは、仕事遍歴を整理するための年表作りを目的としたものであって、「すまいるかるた」を作ろうとしたわけではない。でも、あの時の雰囲気の中では、かるたを作ろうと思っても、作れたかどうかわからない。静枝さんへの聞き書きのような、みんなが身を乗り出して語り手の話を聞き、質問とそれに対する応答が飛び交っていた熱気が、その時にはほとんど感じられなかったのである。今までと同じように、利用者さんもスタッフもテーブルを囲んで座っていて、形としては開かれていたし、六さんの人生語りもとても興味深いものだったのに、いったいなぜ聞き書きの場の空気をみんなで共有することができなかったのだろうか。
その場の様子を思い起こして、考えられることの一つは、マスクである。コロナ禍が続いている中で、聞き手である私も、語り手である六さんも、そして周りで聞いていた利用者さんたちもスタッフもみんなマスクをつけていた。マスクをつけていると当然表情は分かりにくく、相手に感情がなかなか伝わらない。また、声も籠ってしまい聞こえにくいし、常にマスクをつけているという状態であるので、それぞれが息苦しさや不快感を多少なりとも感じているだろう。だから、みんなの心も開放的にはなかなかなれないのかもしれない。そうしたマスク着用による弊害が、聞き書きを開かれたものにしにくくしている、ということは確かだろう。
そして、もう一つ大きいのが、アクリルボードの存在だと私は考えている。コロナの脅威がいよいよ身近に感じられるようになってきた4月の中旬、飛沫感染を防ぐために、ホームセンターで大きなアクリルボードを6枚購入してきて、デイルームのテーブルの中央に設置したのである。このアクリルボードを利用者さんたちは特に嫌がることもなく、「いいアイディアだね」と許容してくれた。ただ、実際には、それによってすまいるほーむの日常にも少なからず変化があったと思う。
すまいるほーむでは、利用者さん同士がよく話をしている。近況報告をしたり、家族関係の悩みを相談し合ったり、テレビを見ながら会話がはずんだり。スタッフがその場にいなくても、前に座っている人や横に座っている人と、あるいはテーブルを囲んでの何人かで話が盛り上がっていた。ところが、アクリルボードを設置してからは、前に座っている人との会話が難しくなった。たった厚さ2mmのアクリルボードだが、それがあることで声が聞こえにくくなるのだ。
それでも、いつも他の利用者さんやスタッフを気遣ってくれる美砂保さんは、透明なアクリルボード越しのテンさんやハコさんの様子を見て、「お元気ですか?」「すてきなマスクをしていますね」等と声をかけてくれる。テンさんやハコさんはそれでなくても耳が遠いから、美砂保さんの声は全く届かず、「え?」「何言っているんだかわからない」と首をかしげる。美砂保さんは、また頑張って声を大きくして、そして、身振り手振りを加えて話しかける。それでも二人には美砂保さんの言葉は届かない。見かねたスタッフが二人の傍に行って、耳元で、美砂保さんの言葉を伝える、といった具合なのである。耳が遠くなくても、声を出す方も、その声を受ける方も、お互いに相当頑張らないと言葉が届きにくい。そんな状態なので、以前ほど、みんなの会話ははずまなくなっている。
それに加え、以前はよく見られた微笑ましい光景も今は見られない。テーブルの中央に、共有のティッシュペーパーを置いたり、花瓶に花を飾ったりしているのだが、以前だと誰かがティッシュペーパーに手を伸ばそうとしたら、その向かいに座っている利用者さんがそっと手を差し伸べてティッシュの箱をその人の方へ押してあげたりしていた。また、向かいに座った人同士が、中央に飾ってある花を「きれいだね」と愛で、花瓶を交互に手に取って、花の香りを嗅いだりしていた。こうしたさりげない触れ合いや香りの共有は、アクリルボードが設置されてからは全くできなくなってしまった。
人は体液を交換し、触れ合いながら対話をしている
このようにすまいるほーむの日常を変えてしまった感染防止のためのマスクとアクリルボードが、聞き書きの場をみんなで共有することを妨げる大きな壁となっているのではないだろうか。
そこで思い出すのが、精神科医の斎藤環さんが、今年の4月20日に公開した「コロナ・ピューリタニズムの懸念」というnoteの記事である。斎藤さんは、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で獲得されていった禁欲主義を、「コロナ・ピューリタニズム(CP)」と名付ける。そして、CPによって、「他者に触れてはならない」という他人の身体との接触を禁止する、まったく新しい倫理観がもたらされたという。なぜなら、ハグやキスを含む日常的な挨拶や対話は、感染リスクのある「体液の交換」であることが判明したためであり、だから、「体液の交換」を伴う一切の接触が禁止されたのだ、と。
「つまり、ここに至って『親密さ』は、体液の交換として再定義されたのだ。もちろん、他人と“知り合う”ことはいささかも禁止されていない。ネット上で知り合いたければ、それはいくらでもどうぞ。しかし親密な関係性は築かれないだろう。親密な関係は、その人に身体的に寄り添い、声を交換することなくしては構築が難しいからだ。そして、寄り添いも対話も、そのままエアロゾルという体液の交換にほかならないのだ」
親密な関係を築く寄り添いも対話も、「体液の交換」である、という。「体液の交換」というこの一見過激な言葉に、私は深く得心がいった。私たちが現場で行ってきた利用者さんたちとのかかわりも、そして開かれた聞き書きも、「体液の交換」というキーワードで考え直すことができるかもしれない。
斎藤さんは、フィンランドの精神科医療において1980年代に始まった「オープンダイアローグ」という対話主義の治療方法にいち早く注目して、日本に紹介し、その実践を行っている方である。「オープンダイアローグ」、すなわち「開かれた対話」を、患者本人と家族、医師や看護師等の専門職とが平等な立場で何度も繰り返すことによって、関係性が修復され、精神疾患の症状は改善されていく、という。
対等な立場で、話題を限定せずに何でも語り合える雰囲気で対話を進めることや、何度でも対話を繰り返すことによって関係性が変化していくこと等の特徴は、すまいるほーむで重ねてきた開かれた聞き書きと類似点が多く見られる。勉強不足で、オープンダイアローグと聞き書きとを関連付けて説明することはまだできないが、私はオープンダイアローグを知ってから、勝手にシンパシーを感じている。
そのオープンダイアローグの実践者であり、人間関係の構築や修復における対話の重要性を指摘してきた斎藤さんが、対話は「体液の交換」によって成り立っている、という。おそらく、「体液の交換」とは、コロナ禍がなかったら意識されなかった自明の構成要素だったのではないだろうか。
すまいるほーむでの聞き書きで言えば、私はこれまで、言葉のやりとりと、身振り手振りや表情などの身体表現には注目してきた。けれど、斎藤さんのいう、対話とはすなわち「体液の交換」によって成り立っているということを参考にすれば、聞き書きも、言葉や身体表現を聴覚、視覚を使ってやりとりするだけでなく、触覚、嗅覚、味覚も含めた全身の感覚を使って交換し合うことだったと言えるのではないだろうか。とりわけ、みんなでその場を共有して、一人の語りに耳を傾ける開かれた聞き書きは、それぞれが全身の感覚をフル活用したところで初めて成り立っていたのだと思う。
ところが、感染防止を目的としたマスクの着用とアクリルボードの設置によって、全身の感覚を使ったやりとりが阻害されてしまった。これから先、まだしばらくはコロナの脅威は続くだろう。だとすれば、すまいるほーむでの聞き書きはいったいどうなるのだろうか。開かれた聞き書きによる「すまいるかるた」作りは、もうできないのだろうか。できないとすれば、みんなが希望や力を得てきたつながりは、この場でどうやって結んでいったらいいのだろうか。私には、すまいるほーむのこの先の展望が見えなくなってしまった。
それでも面白いことをやり続ける
私は向かうべき方向性を見失ってオロオロするばかりだったのだが、そんな中でも、スタッフたちは面白そうなことを自分たちでいろいろと見つけて始めていた。
3月頃からだったか、亀ちゃんとまっちゃんが、コピーの裏紙を切って作ったメモ用紙に、時々何かを書き込んで、それをクリアファイルに入れていた。見てみると、そこには、利用者さんたちが発した言葉や、利用者さん同士の会話が記録されていた。
例えば、大正12年生まれのハコさんが立ち上がる時にいつも口にする掛け声である「よいとどっこい、きたこらさ」とか、誰かが、クシュンとくしゃみをした時にタケコさんがよく呟く「一褒められ、二憎まれ、三惚れられて、四風邪をひく」とか。六さんによるオムレツの上手な作り方の教えの「ダンスを踊るように、体全体を動かすんだよ」とか、まささんとみよさんのおじゃみ(お手玉のこと)をめぐる会話として、まささんが、「お茶の実を入れたから、『お茶の目』からおじゃみになった」と言ったのに対して、みよさんが「うちでは海の浜で石を拾ってきて入れたよ」と言ったということとか。
その内容はバラエティに富んでいる。利用者さんと普段かかわる中で、面白いとか、すごいと思った言葉をとにかくメモして集めているようだった。もう既に77枚も集まっている。聞けば、こうやって集めた言葉を一日一言ずつ書いて日めくりカレンダーを作ろうかと思っているとのこと。記された一言一言から、それを発した利用者さんの人となりとともに、その人へのスタッフの愛情も感じられて、きっと素敵な日めくりカレンダーになるに違いない。365枚集まってカレンダーが出来上がるまでには、もうここにいない人もいるかもしれない。そうであっても、毎日一枚ずつめくって言葉に出会うことで、その仲間に思いを馳せるきっかけになるだろう。
そして、最近は、亀ちゃんが中心となって、「すまいる劇団」による劇「白雪姫」のシナリオをみんなでワイワイと考えている。「すまいる劇団」は利用者さんたちもスタッフも全員が参加する劇団で、毎年一回、敬老会に向けて起ち上げられる。昨年から、高校で演劇部に所属していたという亀ちゃんに台本制作を任せており、昨年は、「かぐや姫」をみんなで練習し、地域の老人会の方たちを招待して披露した。今年は、コロナの影響で老人会との交流はできなくなってしまったので、10月に文化祭と称して、内輪で披露しようと考えている。
先日、亀ちゃんが、「白雪姫」のシナリオの下案を作ってきてくれた。そこには、白雪姫役のハコさんが「よいとどっこい、きたこらさ」と言って息を吹き返すとか、「さすらいの料理人」の六さんが船に乗って片浜海岸に登場して、りんごをおいしく調理するとか、今までの聞き書きが参考にされていたり、自分たちで面白いとメモした言葉がふんだんに盛り込まれている。亀ちゃんは、耳の遠いハコさんの隣に座って、このシナリオを大きな声で読み上げて、みんなに意見を聞いていた。マスクとアクリルボードがあるけれど、亀ちゃんの大きな声はよく通り、みんな頷いたり、笑ったりしながら聞いている。
すると、総監督となった六さんが駄目だしを入れる。
「白雪姫が倒れて、王子様が登場するまでに、白雪姫を介護する人が出てきた方がいいんじゃない?」
「介護する人? 7人の小人が心配するんじゃ駄目なの?」
「小人じゃなくて、介護する人。白雪姫を寝かせたり、背中をさすったりする人さ」
「そうか、誰がいいかな」
「優しいから美砂保さんがいいんじゃないの」
「私でいいの? じゃあ、『大丈夫?』って駆け寄って、手をさすったり、背中をさすったりします」
「美砂保さんが適任だよ。じゃあ、美砂保さんは看護師さんとして登場することにしよう」
今までの聞き書きや普段の会話で、既にお互いのことをよく知っている仲間だからこそ、この役はこうだからこの人がいい、とみんなから意見が出され、決まっていく。更に、決まった配役から、その人の経験や思い出に合わせて、シナリオも修正されていく。何だかみんな楽しそう。聞いている私も、ワクワクしてくる。これからシナリオの書き直しをして、みんなで議論するのを何度か繰り返し、そして小道具作りとセリフ合わせが進められていく予定である。いったいどんな劇になるのだろう。
コロナ禍での聞き書きの行方や、すまいるほーむのこの先の在り方を案じて、私が呆然と立ち尽くしている間に、これまで耕されてきたすまいるほーむの土壌に新しい芽がいくつも生えてきていた。それらの芽がどんなふうに成長するかわからないし、それがここでどんな意味を持つかもわからない。それによって、マスクとアクリルボードで阻まれた「体液の交換」が回復されるかどうかもわからない。
けれど、一つだけ言えるのは、意味があるかどうかではなく、みんなが面白いと思えることを今はとにかくやるしかない、ということだ。それを続けていくことで、きっと次の何かが見えてくる。そもそも聞き書きも最初から何か意味を見出してやっていたのではない。面白いという気持ちと好奇心に掻き立てられて進めてきたのだ。だから、今は、それを信じて、私もそれらを楽しみたいし、形にこだわらずに、面白いという気持ちに任せて、聞き書きもまたしていきたい。そうしていくうちに、また新しいすまいるほーむがきっと生まれていく。
※次回は10月24日(土)に掲載予定

























