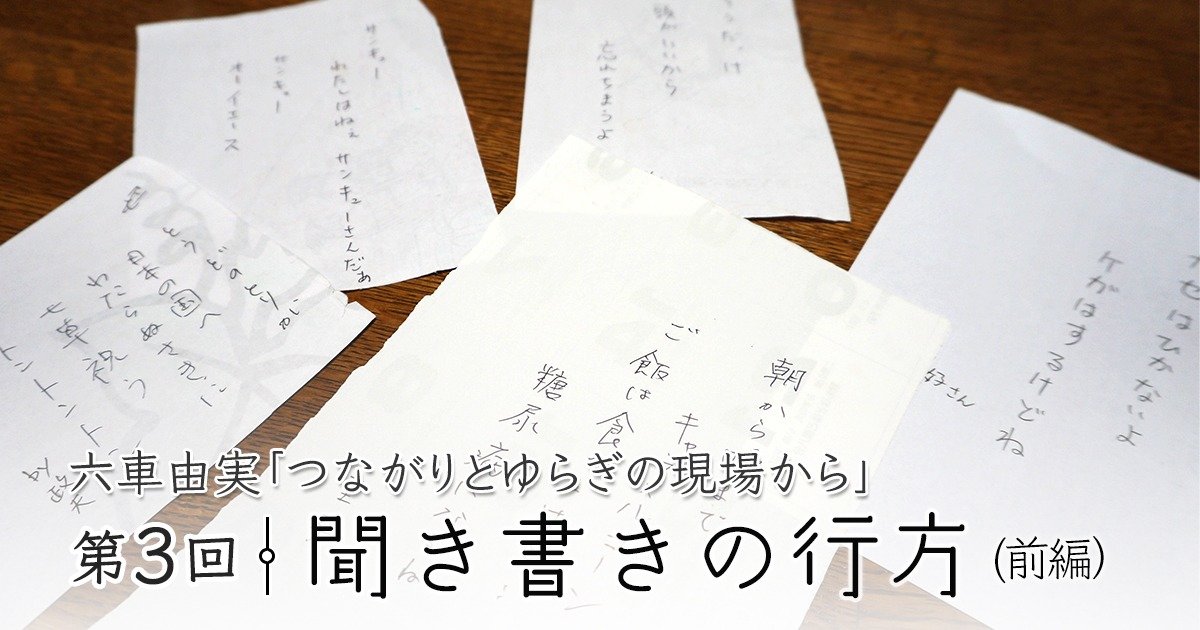
六車由実の、介護の未来03 聞き書きの行方(前編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
久々の聞き書き
7月下旬のある日、私は久しぶりに聞き書きをした。コロナ禍の緊張と不安の日々は続いていたが、そういう状況にみんなも慣れてきたこともあって、すまいるほーむに平穏な日常が戻りつつあり、私自身も心と時間に少しだけゆとりができたのであった。そこで、午後のレクリエーションの時間を使って、以前からずっと気になっていた六さんの仕事について聞き書きをすることにした。調理の仕事をしていたという六さんと話をしていると、沼津の老舗レストランで働いていたと思えば、ある時は、東京のデパートで食材の仕入れの仕事をしていたというし、また洋上でコックをしていて、世界中を旅していたという話にもなる。いったいいくつの仕事にどの順番で就いていたのか、聞いているこちらは混乱してしまう。これは、一度、時系列的に聞いて、整理してみないとだめだな、と思っていたのである。
「六さんはいろいろな仕事をしていたみたいですが、あまりに多くて、私、よくわからなくなってきたので、今日は、六さんがどんな仕事をしてきたのか、年表を作ってみたいと思っています。六さん、一番初めにした仕事は何ですか」
「うちの農業の仕事を手伝いながら、土建業もやったりしたよ」
「それは何歳くらいの時?」
「学校を出てから二十歳までだね。農閑期には映画の俳優もやったよ。御殿場で、東宝の『最後の脱走』っていう映画の撮影があって。谷口千吉が監督で、鶴田浩二と原節子が主役の映画で、終戦後に満州で中国の八路軍に追われる話なの。私はエキストラで参加したんだけど、原節子の子供役にされたんだよ」
「え、六さん、映画に出たの? しかも、原節子の子供役で? すごいね、どうだった、原節子は? きれいだった?」
「原節子に手を握られたよ。まあきれいだったね」
調理人の仕事の話を聞こうと思ったら、最初から驚きの展開。映画に、しかも原節子の子供役で出演していただなんて、初めて聞いたことだった。聞き書きはこうした予期せぬ展開があるから面白い。
六さんは、『最後の脱走』に出たのをきっかけに、俳優になろうと思ったそうだが、父親に大反対されて断念したという。その後、20代で三島にある総合病院で給食を調理する仕事に就き、入って1年で院内感染による赤痢に罹り、1か月隔離された。そのことで院長と喧嘩になり、病院を辞め、沼津の老舗レストランの調理師になった。そこで出会った洋食の料理部長がかつて宮内庁の調理人として働いていた経歴のある人で、調理の技術だけでなく、身なりや礼儀、教養まで厳しく指導され、その人の下で働いたことで調理人として成長できた、と六さんは言う。
30歳を過ぎた頃に、人事に反発して老舗レストランを辞め、東名高速道路のドライブインのレストランの調理人に転職。チーフを任され、人集めに奔走したそうだ。六さん曰く、
「このあたりのチンピラ小僧を集めてきて使ったんだよ。血の気が多くて、すぐに喧嘩するから、その仲裁も大変だった。でも、そういう人は、まじめになるとちゃんと仕事をするようになるんだ。厳しく叱ったし、自分の奢りで何度も飲みに連れて行って、励ましたり、悩み相談にのったりした。飴と鞭だね。みんなよく頑張って、他の職場でチーフになった人も多いよ」
面倒見がよくて、いつも周囲に気遣いをしてくれる六さんらしいエピソードだ。こうした人材育成方法も、六さんを老舗レストランで指導した元宮内庁調理人の影響だったそうだ。更に、六さんは自己研鑽にも熱心だった。料理の研究のために、銀座のフランス料理店のマキシム・ド・パリ等、高級レストランの食べ歩きをしたという。
「銀座のマキシムにも何回も行ったよ。ものになりそうな若い子を連れて行ったこともある。もちろん、全部私がお金を払ってさ。人並のことをしていたら、人の上には立てないよ。自分はそれ以上に勉強しないといけない。料理の工程は全てフランス語を使うから、フランス語も独学で勉強したさ」
お金も時間も努力も惜しまず、洋食の調理の仕事と勉強に打ち込み、後輩の指導にもあたってきた六さんだが、ドライブインのレストランは2年くらいで辞めたという。どうして辞めたのかはここでは聞けなかったが、一つの職場に執着しない、六さんのこの潔さが私には心地よく感じられた。そして、貿易船のコック長となって洋上へ。そこで、タイムアウト。3時のおやつの時間になり、残念ながら聞き書きはストップせざるを得なかった。
約50分の間に聞いた10代半ばから30代半ばまでの20年の出来事についての語りは、予想以上に紆余曲折があり、聞いている私もまるで六さんと一緒にジェットコースターに乗っているかのように上下左右に揺られ、ドキドキしながら、猛スピードで過ぎていった。既に、農業、土建業、俳優、そして、病院、老舗レストラン、ドライブインレストランの調理人、貿易船のコック長と、7つの仕事を渡り歩いた六さんが、それから60代までの約30年間、いったいどれだけの職場で働いてきたのか、私の好奇心はますます刺激され、胸は高鳴った。
開かれた聞き書き
久々の聞き書き体験は刺激的で、私はとても興奮した。思いもよらないような経験をしてきた利用者さんたちの人生語りを聞くのはやっぱり面白い、と率直に感動していた。
けれど、終わってみると、これまでの聞き書きと何かが違う、という残念な思いも少なからず残った。いったい何が違うのか。それは、今回の聞き書きが、六さんと私との一対一のやりとりに終始していたように思えたことだった。確かに、デイルームのテーブルを囲んで座っていた他の利用者さんたちも、私の六さんへの聞き書きを聞いていた。でも、そこにみんなが積極的に参加している、という感じではなかったのである。すまいるほーむでここ数年行ってきた聞き書きの定番は、みんなで一人の利用者さんへの聞き書きをして、その方の思い出をみんなで共有する、という形だった。同じようにみんなが集まるデイルームで六さんへの聞き書きをしたのにもかかわらず、今回はどうして聞き書きがみんなに開かれていかなかったのだろう。
私がすまいるほーむで働き始めたのは平成24年の10月。『驚きの介護民俗学』を読んだ三国社長が、是非、すまいるほーむでも聞き書きを通して、利用者さんたちと一人の人間として向き合う場を作ってほしい、と誘ってくれたのがきっかけだった。ところが、すまいるほーむで聞き書きを始めるのは思いのほか難しかった。介護職として送迎から排泄、入浴、食事介助等、現場のあらゆる仕事に携わりながら、管理者、生活相談員としての業務や事務処理をこなしていくことで精一杯で、利用者さんにゆっくりと聞き書きをする時間をとることはできなかったのである。それに、それまでの大規模の施設と違って、聞き書きのために私が別室に籠れるような人員的余裕もない。
そこで苦肉の策として始めたのが、みんなが集うデイルームで、一人の利用者さんに聞き書きをするということだった。とりあえず、私は、昼食後のみんながまったりと寛いでいる時間に、利用者さんの横に座り、聞き書きを始めてみた。すると、テーブルをはさんで前に座っていた利用者さんが興味をもってくれて、相槌をうったり、質問をしたりと、聞き書きの中に参加してくれるようになったのである。スタッフの私だけでなく、同世代の利用者さんが加わり、質問したり、共感したりすることで、語り手も饒舌になる。聞き書きは少しずつ盛り上がってきて、そのうちに、他の利用者さんもそこに加わってくれたり、スタッフたちも利用者さんたちの間に入って、フォローしてくれたりするようになった。聞き書きは、いつの間にか、私と対象の利用者さんとの一対一の形から、デイルームにいるみんなを巻き込んだ開かれた形に展開していったのだった。
そんな中で新たに始めたのが、みんなで聞き書きをして、「すまいるかるた」を作る、という試みだった。すまいるほーむが開所して15周年を迎えることになった平成27年の秋に、それを記念して何か作ろうかという話を利用者さんたちにしたところ、『介護民俗学という希望』(新潮文庫)で恋バナを語ってくれたをゑみ子さんが、「かるたがいい!」と提案してくれたのである。
それまでも、みんなで聞き書きをして、何人かの利用者さんの思い出の味の再現をしたり、また、聞き書きしたエピソードをマスに書いて並べて、人生すごろくを作って、レクリエーションの時に遊んだりしていた。だが、「すまいるかるた」作りが今までと違う展開を見せたのは、聞き書きをみんなで行い、更にその場でみんなで協力してかるたの読み札を作ってしまう、聞き書きからその作品化までのプロセスをすべて共有するということだった。
「すまいるかるた」という聞き書きの形
「すまいるかるた」作りは、午後2時から3時までのレクリエーションの時間を使って行うようになった。デイルームのテーブルを囲んで座っている利用者さんと共に、スタッフたちもその間に腰掛けてみんなで参加する。スタッフたちは、聞き書きのやり取りについていくのが難しい耳の遠い利用者さんには磁気ボードに要旨を書いて伝えたり、認知症の症状が進んで、その場の状況把握が難しい利用者さんの横で実況中継するなどのフォローをしてくれ、みんなで参加する雰囲気が作られていった。
たとえば、沼津の片浜海岸のすぐそばで生まれ育った静枝さんのかるたは、こんな感じで作られた。
「静枝さんは、この間、片浜海岸でよく魚が獲れたと言ってたよね」
「獲れましたよ。大きな魚に追われてね、はっちゃがるの」
「はっちゃがる?」
「はっちゃがるの。岸にね、波と一緒にさーっと上がってくるの。イワシとかアジとか」
「獲れたんだね」
「そう。そうするとね、浜にいる衆が呼ぶの。浜で『おーい、おーい。魚が獲れるからバケツ持ってこい』って」
静枝さんは、向いに座っているとよさんに向かって、大きく身振り手振りを加えながら、魚が浜に「はっちゃがる」様子を語ってくれる。新潟生まれで、そんな海の暮らしについては知らないとよさんは、頭にたくさんのクエスチョンを浮かべながら、目をまん丸くして聞いている。更に、他の利用者さんやスタッフも加わって、聞き書きは進んでいった。
「獲れたイワシはどうやって食べるの?」
「生で開いてさ、すり身にしてもさ。煮てもさ。目刺しにしてもさ。食べるだけ食べたよ。だけどいっぱいだから食べきれないじゃ。だから、田んぼに刺すの」
「田んぼに刺すの? なんで?」
「肥やしになるじゃない」
「えー、すごい!」
「稲を植えてあるでしょ、その根元に刺すの。そうすると肥やしになるの」
「そのまま? 生で? 干したものを? 硬いの?」
「硬くなきゃ刺せない」
「そりゃそうだ(笑)」
食べるためにイワシを獲りに行ったのだと思ったら、実は田んぼに刺して肥料にしていたという。この予想外の展開に、みんな驚きの声を挙げる。もちろん、私も大興奮。北海道で大量に獲れたニシンから油を搾ってニシン粕にし、それが各地で肥料として高値で売れたことは知っていたが、イワシを丸のまま干して田んぼに刺すなどというのは初めて聞く話だった。
そんな熱気の中で、耳が遠いため、スタッフが磁気ボードに文字を書き要旨を伝えていたゑみ子さんも聞き書きの中に入ってきたが、その質問はその場の空気とは時間差があり、「静枝さんは、兄弟は何人いるの?」というものだった。その質問で、みんなが盛り上がっていたイワシを田んぼに刺す話題は中断されてしまったが、それを咎めたり、嫌がったりする人はなく、静枝さんもゑみ子さんに向かって指で「7(人)」を示し、にっこりと笑った。
すまいるほーむでの聞き書きには、何の決まりもない。みんなが聞きたいことを質問し、語り手は答えたいように答える。人を攻撃したり、侮辱したり、傷つけたりしなければ、それでいいと私は思っているし、みんなもそれをよしとしてくれている。だから、聞き書きは、行きつ戻りつするし、急に別な話題へとポーンと飛んでしまうこともある。でもその自由さがあるから面白いし、予期せぬ方向へ展開した先に今まで聞いたことのない宝石のような記憶が語られたりすることも多いのである。
そうやって聞き書きを楽しんでいると、レクリエーションの1時間のうちの40分くらいはあっという間に過ぎてしまう。そこで、いったん聞き書きを終え、残りの20分くらいをかけて、今度は、みんなで読み札づくりに取りかかる。
「いろいろ聞いてどれもすごく面白かったんだけど、やっぱり今回はイワシのことをかるたにしたいな、いい?」
「うん、うん」
「えー、大きな魚に追われ……」
「追われたイワシがはっちゃがり」
「大きな魚に追われたイワシがはっちゃがり、バケツを持って海に跳んでった静枝さん」
(笑)。
「面白いね。何だか目に浮かぶようだね」
「それを、カワラ(海岸のこと)に干して」
「乾いたら田んぼの肥やしにする」
「田んぼに刺すんだよね」
「刺す手間のない家は、粉にして撒く」
「ああ、その方が簡単だよね」
「簡単だけどね、頭から刺した方が効くだよね」
「刺した方が効き目がいいんだ。面白いね。それも入れよう」
私が考えた言葉をつぶやくと、そこに、語り手である静枝さんや、他の利用者さん、スタッフたちが、いろいろと言葉を連ねてくれる。そうやって、共同作業によって静枝さんの読み札は出来上がっていった。
「は――大きな魚に追われたイワシがはっちゃがり、バケツを持って海に跳んでった静枝さん。カワラに干して、乾燥させたイワシを田んぼに刺す。粉にするよりよく効くだ」
最後に、これでいいか?と静枝さんに尋ねると、静枝さんは、「うん、その通り」と頷いてくれた。みんなからは、拍手がわいた。
たった1時間ではあるが、みんなで聞き書きをして、そしてみんなで読み札という形に作品化する、この濃密な時間と空気が、私にはこの上なく気持ちよく、大好きだった。
積み重なった聞き書きの時間
すまいるほーむでは平成27年から今年の2月頃まで、こうやって、開かれた聞き書きによる「すまいるかるた」作りを何度も重ね、利用者さんとスタッフ全員のかるたを作ってきた。中には、思い出が一枚では収まりきらず、何枚も読み札を作った人もいるし、最初に作った時からずいぶんと時間が経った後に、新たに思い出が語られることもあり、それをまたかるたにまとめるということもあった。
それから、新しく利用者さんやスタッフが入ってきたら、少し慣れてきたあたりで、かるたを作ってきた。聞き書きによってかるたを作ることで、みんなが新しい仲間のことを知り、互いの関係を縮めていくきっかけになっていったように思う。
できあがったかるたは、レクリエーションの時に遊ぶこともあるが、最近は、取材や見学のお客さんが来た時や、地域の方が遊びに来た時に、利用者さんとスタッフの紹介として、一人一人の読み札を読んだりすることも多かった。
また、お客さんにみんなで聞き書きをして、かるたを作ってプレゼントもした。何をしている人なのか、何のために取材に来たのか、なぜ今の仕事についたのか、という鋭い質問をする人もいれば、結婚しているのかとか、相手とはどうやって知り合ったのかとか、プライベートなことを質問する人もいて、対象となったお客さんたちは多少なりとも緊張した様子だった。しかし、取材や見学によって一方的に見られる対象であった利用者さんたちやスタッフが、かるた作りをすることで、今度はお客さんを見る側となる。その関係性の逆転は、見られる一方のストレスから少なからずみんなの心を解放したようで、取材や見学の人が来ることを楽しむようにもなっていったように思う。
仲間が亡くなった時には、お別れ会の中で、みんなでその人の思い出やその人への思いを語り合い、それをかるたにまとめても来た。例えば、連載2回目で登場した高木さんのお別れ会では、こんなかるたができあがった。
「わ――ゲームに負けると本気で悔しがり、勝つと大喜びする、わたがしが好きな少年のような人だった。そして、いろんなことを教えてくれて、聞く耳も持っている人だった。もっとたくさん話を聞きたかった。議論がしたかった。高木さん、もう会えないけれど、肉親のように、今でも傍に感じているよ」
そうやって様々な場面でみんなで作ってきたかるたの読み札は、改めて数えてみると118枚になっていた。その中には、現在も元気にすまいるほーむで活動する人のかるたもあれば、亡くなった人やここを去った人のものもある。一期一会のお客さんのかるたもたくさんある。一枚一枚には、それぞれ一人一人の思い出の一場面とその思い出をみんなで聞いた時の空気がぎゅっと凝縮されているし、それが重なった118枚のかるたの厚みは、まさに地層のようにすまいるほーむという場に流れ、積もっていった時間の厚みでもあると言える。
現在のすまいるほーむに、何か他のデイサービスと異なる雰囲気、そこに居ることの心地よさのようなものがあるとしたら、たぶん、118枚の厚さまで、この聞き書きの時間が積み重ねられてきたことによるものが大きいのではないかと私は思う。開かれた聞き書きとかるた作りを重ね、互いの歩んできた道やその思いを共有してきたことによって、幾つもの人と人とのつながりを結ぶ場が育まれてきた。ここで結ばれたつながりが、すまいるほーむに集う人たちにとっての一つの希望や力となってきたのではないだろうか。
※後半は10月10日(土)に掲載予定




























