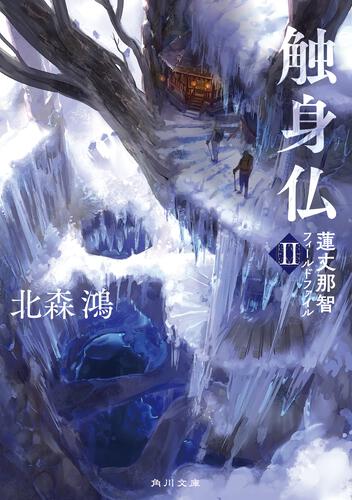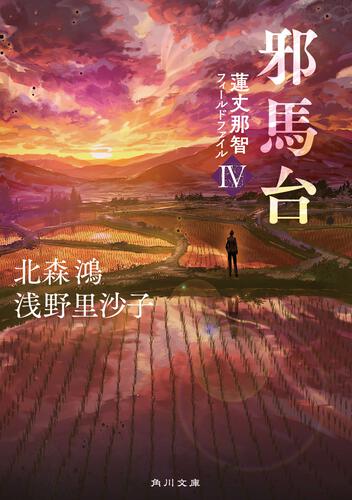北森 鴻・浅野沙子『天鬼越 蓮丈那智フィールドファイルV』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
北森 鴻・浅野沙子『天鬼越 蓮丈那智フィールドファイルV』文庫巻末解説
解説
千街 晶之(ミステリ評論家)
北森鴻を代表するシリーズであり、歿後は彼の公私に亘るパートナーだった浅野里沙子が書き継ぐことになった〈蓮丈那智フィールドファイル〉の角川文庫からの復刊も、本書『天鬼越 蓮丈那智フィールドファイルⅤ』(二○一四年十二月、新潮社から刊行。二○一六年四月、新潮文庫版が刊行)が最後の一冊となる。
今回の復刊を追ってきた(あるいは、リアルタイムでこのシリーズを読んできた)方ならご存じと思うが、東敬大学で教鞭を執る民俗学者・蓮丈那智とその助手・内藤三國が活躍する民俗学ミステリ〈蓮丈那智フィールドファイル〉は、二○○○年に一冊目の『凶笑面 蓮丈那智フィールドファイルⅠ』が刊行され、翌年に第一回本格ミステリ大賞にノミネートされた。続いて、『触身仏 蓮丈那智フィールドファイルⅡ』(二○○二年)、『写楽・考 蓮丈那智フィールドファイルⅢ』(二○○五年)と中短篇集が刊行され、二○○○年代に入ってからの北森の本格ミステリ路線を代表する人気シリーズとなった。ところが、《小説新潮》二○○八年十月号から連載が始まっていたシリーズ初の長篇「鏡連殺」は、二○一○年一月二十五日に北森が逝去したため未完となったのである。それを引き継いで二○一一年に『邪馬台 蓮丈那智フィールドファイルⅣ』というタイトルで完成させたのが浅野だったのだ。
かくして、北森鴻の作家生活最後の十年を代表する名シリーズはフィナーレを迎えた……と思えたが、実はその時点で、〈蓮丈那智フィールドファイル〉の単行本未収録作として、「鬼無里」(初出《小説新潮》二○○五年四月号)、「|奇偶論」(初出二○○六年六月号)の二篇が残っていた。本書はその二篇に、浅野里沙子が執筆した「祀人形」「補堕落」「天鬼越」「偽蜃絵」の四篇(いずれも単行本版書き下ろし)を追加したものである。
北森執筆の二篇のうち「鬼無里」は、蓮丈那智と内藤三國のコンピュータにそれぞれ届いたメッセージから、二人が五年前に東北某県のH村で体験した事件を思い出すところから始まる。フィールドワークのため二人が訪ねたH村では、鬼哭念仏と呼ばれる祭祀が伝わっていたが、その年は祭祀の最中に殺人事件が起きたのだ。鬼哭念仏のあいだ人々は外出禁止となっているため目撃者もなく、結局事件は未解決となったが──。現在と五年前とをパラレルに描いた点は異色ながら、祭祀の起源と現代の殺人事件とを那智が同時解明する展開は、〈蓮丈那智フィールドファイル〉の典型ともいうべき仕上がりを見せている。私はかつて『狐闇』(二○○二年)の徳間文庫版の解説で、「『北森史観』と言うべき独自の壮大かつ伝奇的な歴史観」について触れておいたけれども、本作の祭祀の起源に関してはそれとリンクする部分がある。
一方「奇偶論」では、内藤が「フィールドワークへの誘い」と題した市民講座の講師を引き受ける羽目になる。受講者の中には、教務部主任の高杉康文の姿もあった(彼はシリーズ初期は融通の利かない人物として登場したが、次第に人間的な側面や意外な過去が描かれるようになった)。ところがフィールドワークの最中、受講者たちの会話は妙な方向へと脱線してゆく──。この作品では、那智が内藤の話をもとに「安楽椅子探偵」として事態の背後の秘密を推理するスタイルとなっており、彼女の出番が最初と最後だけという点も含め、〈蓮丈那智フィールドファイル〉の中でもかなり異色の構成である。
「鬼無里」と「奇偶論」が最後まで単行本未収録のまま残っていたのは偶然にすぎず、北森としては「鏡連殺」を完結させた後、新たに幾つかの中短篇を執筆して一冊にまとめる予定だったと推測されるが、奇しくもこの二篇が、いかにも〈蓮丈那智フィールドファイル〉の典型とも言うべき作品と、シリーズのフォーマットから逸脱した作品であることは興味深い。『触身仏』角川文庫版の解説で法月綸太郎は、シリーズが軌道に乗るまでは敢えて定型の力を借りていたが、次第にそこから逸脱した作品が増えている点を指摘しているけれども、この二篇からも、フォーマットへの従属と逸脱という二つの指向が北森の中で鬩ぎ合っていたことが読み取れるのではないか。
浅野が執筆した四篇のうち、表題作「天鬼越」は北森が遺したプロットをもとにしている。〈蓮丈那智フィールドファイル〉の「凶笑面」は、二○○五年九月、フジテレビ系列の「金曜エンタテインメント」でドラマ化され、蓮丈那智を木村多江が、内藤三國を岡田義徳がそれぞれ演じた。実は、このドラマの好評を受けて第二作の企画が立ち上がり、北森自らプロットを手掛けることになったのだ(今回、そのプロットも初めて収録されることになった)。それをもとに脚本が書かれたものの、何らかの事情で結局ドラマ化は実現しなかったが、その時のプロットを浅野が小説化したのが「天鬼越」なのである。通常、〈蓮丈那智フィールドファイル〉では内藤三國は「内藤」と表記されるが、遺されたプロットでは「三國」となっていたので小説でもそれを踏襲した……という差異はあるものの、在野の民俗学研究者からの依頼で某県の村を訪れ、そこに伝わる古文書を調査することになった蓮丈那智研究室の面々が不可解な連続殺人事件に巻き込まれる展開は、〈蓮丈那智フィールドファイル〉の基本的フォーマットをなぞっている。犯罪と因習が織り成す構図は大胆そのものであり、読者を戦慄させるに充分だ。
A4数枚程度とはいえ、一応北森が遺したプロットが存在した「天鬼越」に対し、残り三篇は浅野の完全なオリジナルである。文体を似せ、レギュラー陣のキャラクター造型を違和感なく継承するといった作業だけでも大変だが、北森同様の民俗学の知識や本格ミステリとしての一定の水準も求められるとなれば、あまりに高いハードルであり、普通なら二の足を踏むだろう。それを浅野が敢えて引き受けたことからは、並々ならぬ覚悟と、北森への敬愛が窺えるではないか。
三篇のうち「祀人形」と「補堕落」は、「鬼無里」がそうであるように〈蓮丈那智フィールドファイル〉の基本的フォーマットを踏まえた作品だ。前者では、那智と内藤は中部地方のG県にある村の旧家の女性から調査を依頼され、現地を訪れるが、そこで殺人事件に遭遇する。「補堕落」は宮崎県の海辺の町が舞台で、そこでは昔から伝わる補陀落渡海を町おこしの材料にしようとしていたが、行事の最中、渡海船の中にいた行者役の人物が他殺死体となって発見される。その船には伴走船しか近づけない状態であり、事件は不可能犯罪の様相を呈する。
三重県の名張を訪れた蓮丈那智研究室の面々が、旅館にあった掛軸の来歴を辿る「偽蜃絵」は珍しく犯罪が起きない作品だが、実は本作発表の翌年の二○一五年は、作中の最終ページで言及される人物の歿後五十年にあたる年だったのである。それに合わせて執筆されたボーナストラック的作品であることを説明しておく必要があるけれども、シリーズのフォーマットに、時には従い、時にはそこから逸脱する──という北森の姿勢を浅野が継承していることも窺えるだろう。
普通はミステリ作家がこの世を去ると、その作家が創造したキャラクターが登場するシリーズも同時に終了してしまうものだが、シャーロック・ホームズやエルキュール・ポアロ、明智小五郎や金田一耕助など、他の作家によってパスティーシュが盛んに執筆される例もある。蓮丈那智もまた、そうした名探偵たち同様、作者の歿後も活躍の場を得られたことは実に慶ばしい。このシリーズがこれからも長く読み継がれることを願ってやまない。
作品紹介
書 名: 天鬼越 蓮丈那智フィールドファイルV
著 者: 北森 鴻・浅野沙子
発売日:2024年10月25日
歴史民俗学ミステリー、堂々たる終幕。
旧盆に山の神・鬼哭様の面をつけた若者たちが、奇妙な念仏を唱えながら練り歩く〈鬼哭念仏〉の最中に起きた5年前の惨殺事件の真相に蓮丈那智が挑む「鬼無里」など全6篇。内藤三國が率いたフィールドワークでの恐ろしき推理。ひんな神伝承と殺人事件の忌まわしい関係。昭和初期、絵師の恋の謎を解いた人物とは――。民俗学とミステリへの敬愛に心震える最終巻。北森鴻の書いたドラマ用「天鬼越」のプロットを本書に初収録。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322305000305/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら