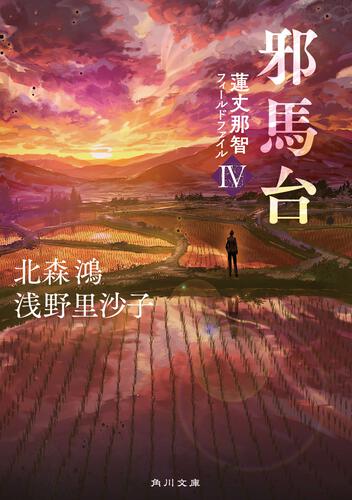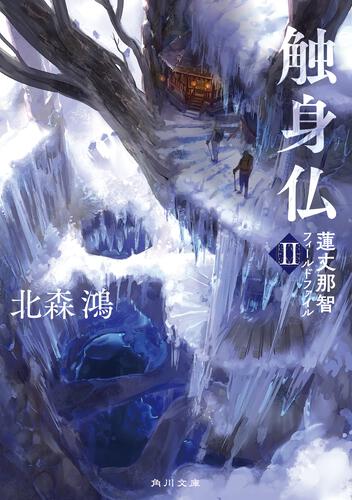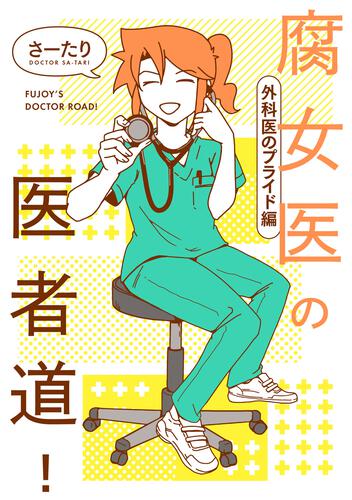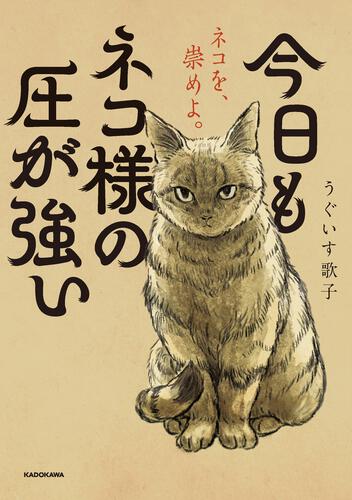北森 鴻・浅野里沙子『邪馬台 蓮丈那智フィールドファイルIV』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
北森 鴻・浅野里沙子『邪馬台 蓮丈那智フィールドファイルIV』文庫巻末解説
解説──唯一の長篇に相応しいシリーズ最大の謎の物語
村上 貴史(ミステリ書評家)
■未完の連載
北森鴻の長篇ミステリ『鏡連殺』は、『小説新潮』の二〇〇八年一〇月号に連載が始まり、二〇一〇年二月号で終わった。完結したのではない。著者が亡くなったためだった。四八歳の若さだった。
未完の連載作──それを書き継ぎ、完成させたのは、浅野里沙子である。二〇〇九年に『六道捌きの龍 闇の仕置人 無頼控』で光文社時代小説文庫からデビューした作家であり、北森鴻とは、結婚を約束した間柄でもあった。彼女が『鏡連殺』を完成させる役割を担うに至った経緯は、本書にも収録された「あとがき」に記されているので、そちらを参照されたい。
完結させるための手掛かりが乏しいなか、浅野里沙子が担当編集者たちの協力の下で完成させた作品は、『邪馬台』と改題の上、二〇一一年一〇月に単行本として新潮社から刊行された。《蓮丈那智フィールドファイル》シリーズの第四弾である。
このシリーズでは、東敬大学の助教授である蓮丈那智という異端の民俗学者と助手の内藤三國が、フィールドワークを通じて専門分野である民俗学の問題の謎を解き、同時にそこで遭遇した事件の謎解きを進める。その鮮烈な二重構造が初めて世に示されたのは、『小説新潮』一九九八年五月号に掲載された「鬼封会」という短篇でのこと。続いて四ヶ月後の『小説新潮』に発表された第二短篇「凶笑面」は、後にシリーズ第一弾の単行本の表題作となり、また、日本推理作家協会賞の短編および連作短編集部門の候補となるほど高く評価された。ちなみに「凶笑面」は残念ながら受賞を逃したのだが、受賞作はなんと北森鴻自身の連作短編集『花の下にて春死なむ』(一九九八年)であった──という余談はさておき、《蓮丈那智フィールドファイル》シリーズは、第二弾『触身仏』(二〇〇二年)、第三弾『写楽・考』(二〇〇五年)と、順調に巻を重ねてきた。その三冊は、いずれも短篇集だったのだが、第四弾に至って、北森鴻はシリーズ初の長篇に挑むことを決意した。そしてその連載が、冒頭に記したように二〇〇八年に『小説新潮』で始まったのである。
この第四弾で扱われている題材は、改題後のタイトルでも明らかなように邪馬台国である。はたして邪馬台国はどこにあったのか。畿内かあるいは九州か。魏志倭人伝の記述はどう読み解くべきか。様々な説が乱立している題材であり、長篇に相応しい題材である。北森鴻はさらにこの題材に、三國が着目した廃村の民俗学──集落の形成が民俗学の中で重要な系統であるように、その逆もまた研究対象となってしかるべきではないのか──というテーマも添えている。明治期に消滅した阿久仁という村に関する文書を入手したことを契機に、那智と三國は、巨大な事件に巻き込まれていくのである。
文庫にして六〇〇ページ超。『邪馬台』はシリーズで突出して長大なボリュームとなったが、《蓮丈那智フィールドファイル》らしさ、すなわち、民俗学上の謎と、那智や三國が遭遇する事件の謎を重ねて断ち切るという構造を考えると、この長さは必然といえよう。なにしろ、民俗学上の謎が邪馬台国の謎なのだ。事件にもそれなりの大きさや深さが求められるのである。その詳細は、是非とも本書で愉しんで戴きたいのでここでは伏せるが、旗師(店舗を持たない骨董業者)の宇佐見陶子を主役とする《旗師・冬狐堂》シリーズの第二弾『狐闇』で描かれた事件と関連があることは記しておこう。『狐闇』では、陶子だけでなく那智も三國も、日本の歴史に深く絡んだ事件に巻き込まれたのだが、その余波は本作にも及んでいるのである。ちなみに『狐闇』は愛媛新聞に二〇〇〇年から翌年にかけて連載され、二〇〇二年に刊行されており、《蓮丈那智フィールドファイル》の第二弾『触身仏』とほぼ同時期の作品だ。第四弾の本書に連なってくるのも自然な流れといえよう。なお、北森鴻と浅野里沙子は、この『邪馬台』を『狐闇』よりも先に読んでも問題ないように仕上げているのでご安心を。もちろん『狐闇』を読んでおくのが望ましいが。
そうした大きな事件もあれば、暗号解読的な、ド直球の謎解きも本書には仕込まれている。それが民俗学的な解釈の深掘りと重ねて解かれていく様は実にスリリング。「凶笑面」に代表される本シリーズの短篇の持つ凄みが、本書にも宿っているのだ。とくとご堪能あれ。
そしてもちろん“邪馬台国はどこか”である。北森鴻と浅野里沙子は、彼らなりに答えを出しているのだが、その際、本書に先だって《蓮丈那智フィールドファイル》として発表してきたいくつもの短篇(『凶笑面』の「双死神」など)で行ってきた考察を補助線としているのだ。本書のなかでも著者はロジカルに説明を尽くしているが、シリーズの読者は、本書が示した邪馬台国の位置に、その補助線故になお一層の説得力を感じられるのである。愛読者ならではの特権だ。
さらに三國にも着目したい。彼は、シリーズが始まった時点では那智の助手でありワトスン役だったが、本作ではかなり独り立ちしているのだ。廃村の民俗学というアイディアもそうだし、自分なりの意見を、それも、那智にも認められる意見を披露する場面も多々ある。そう、本書ではシリーズキャラクターの成長も愉しめるのだ。また、高木彬光が『邪馬台国の秘密』(一九七三年)で入院中の名探偵・神津恭介に邪馬台国の謎を解かせたように、本書の三國も入院中に推理を巡らせているのも、なんだか愉しくなる。
■浅野里沙子
本書の成立に極めて重要な役割を果たした浅野里沙子についても、もう少し触れておこう。二〇〇九年のデビュー作に始まる《闇の仕置人 無頼控》シリーズ全四作において、第四弾が刊行されたのが二〇一一年九月のこと。本書『邪馬台』が二〇一一年一〇月の刊行なので、自身のデビューシリーズという重要な作品と並行して、北森鴻の未完の原稿の“謎解き”を行っていたことになる。なかなか出来ることではない。しかも、本書の単行本の刊行にあわせて『波』の二〇一一年一一月号に寄稿したエッセイによれば、彼女は、二〇一〇年一月からの半年間に、北森鴻だけでなく二人の肉親を失っていたのだという。その辛さのなかで、浅野里沙子は北森鴻の未完の原稿を書き進めたのだ。その情熱も本書から感じ取って戴ければと思う。
彼女はその後、《蓮丈那智フィールドファイル》シリーズの第五弾である短篇集『天鬼越』に、オリジナルの短篇を三篇書き下ろしている。この短篇集には、北森鴻が『鏡連殺』の連載に先立って『小説新潮』に発表したまま単行本未収録となっていた二つの短篇と、北森鴻がTVドラマ用に準備したA4数枚程度のプロットをもとに浅野里沙子が執筆した短篇も一本収録されている。全六話の短篇集というわけだ。こちらもまもなく角川文庫版で読めるようになる予定なのでご期待を。
浅野里沙子は、単独の著書としては、その後も時代小説を書き続け、さらに、質屋が舞台の『白い久遠』(二〇一七年)といった現代ミステリも発表している。質屋を支えてきた目利きの祖父の病を契機に、店に出ることになった三十二歳の涼子の心の揺れを、客が持ち込むアンティークの陶製人形などの謎と絡めて瑞々しく描いていて好感が持てる。彼女の著作も一読をお薦めしたい。
彼女の直近の活動として特筆すべきは、この本である。角川文庫版の『邪馬台』だ。なんと浅野里沙子は、今回の角川文庫版において、肝心な部分で、具体的には終章の一部に、十ページ以上に及ぶ改稿を加えたのだ。
その改稿により、那智や三國が示す真相が、より磨かれることとなった。浅野里沙子は、おそらくは最初に『邪馬台』を書き上げてからもずっと、この“真相”について考え続けてきたのであろう。それがここにこうして結実したのである。浅野里沙子の執念なのか、あるいは北森鴻がなんらかのかたちで彼女を導いたのか。いずれにせよ、ひとしずくの情念がこの一冊に加わっていることを、ここに明記しておきたい。
■北森鴻
本稿の締めくくりに、北森鴻の作品世界について。
本書には《旗師・冬弧堂》シリーズや《バー・香菜里屋》シリーズでお馴染みのキャラクターや店も顔を出すなど、北森鴻の他のシリーズとの繫がりが埋め込まれている。そうした人気者・人気店の繫がりを辿って他の作品に読み進んでいくことを、是非お薦めしたい。あるいは、同じく未完に終わった『暁英 贋説・鹿鳴館』(二〇一〇年)へと読み進むのもよかろう。こちらは、未完の連載を未完のままで単行本化すると版元が決断して出版された一冊だが、そう判断するだけあって、未完でも評価は高い。その他、鮎川哲也賞受賞作にしてデビュー作の『狂乱廿四孝』(一九九五年)をはじめ、本稿では言及できなかった作品にも触れれば、この著者の知の深さや発想の冴えを、そしてときにユーモアを、執筆から十年以上経過した現在でも色褪せない魅力として十分新鮮に味わえるはずだ。
北森作品を読んで、読んで、読んでほしい。
作品紹介
書 名: 邪馬台 蓮丈那智フィールドファイルIV
著 者: 北森 鴻・浅野里沙子
発売日:2024年08月23日
触れてはいけない領域がある。 だが、触れなければ真実は見えない――。
古代、魏の書に登場する邪馬台国は、優れた製鉄と酒造技術を誇りながらも消えた、謎の国だ。民俗学者・連丈那智に届いた「阿久仁村異聞」は明治時代に地図からも抹消された村の記録だが、邪馬台国への手掛かりとなる文書だった。だが、調査を始めた矢先、次々と不穏な出来事が襲いかかる――。歴史の壮大な謎に、異端の民俗学者と助手が意外な「仮定」や想像力を駆使して挑む。怒濤の知の奔流に圧倒される本格民俗学ミステリ!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322305000304/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら