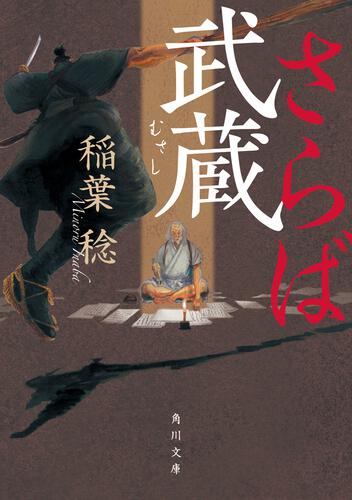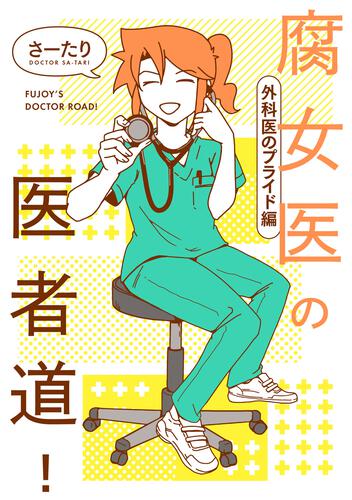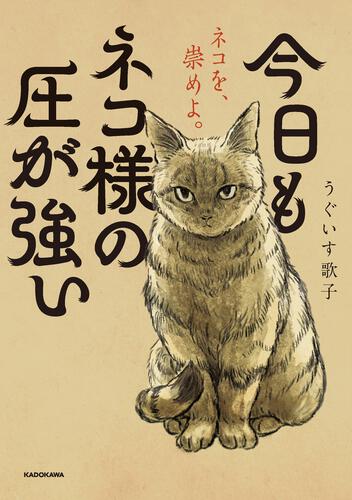稲葉 稔『さらば武蔵』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
稲葉 稔『さらば武蔵』文庫巻末解説
解説
六十余度の生死を懸けた
ところが、本作で描かれた武蔵は、一味も二味も違います。
武蔵は五十歳のとき、「兵法至極を得た」と信じ、『
物語は、この四年後。
武蔵の人生のクライマックスは、もっと前にあったと考える人が多いのではないでしょうか。吉岡一門との戦いや
しかし稲葉氏は、これ以降の死ぬまでの七年間にこそ、この男の人生の山場を見出し、連戦連勝の男が「負けた」と感じることによって、武蔵の新たなステージをスタートさせるのです。
もちろん、物理的に負けたわけではありません。しかし、「喜んで殺され死んでいく」弱者であるはずの「百姓や女子供たち」の「心」に、敗北感を覚えます。
それまでの武蔵は「稚拙」でした。なぜなら、武蔵が「至極を得た」のは「あくまでも剣の道における術理論」──形にすぎなかったからです。武蔵は、『円明三十五ヶ条』に足りなかったものを、島原の乱で「微笑さえ浮か」べて死んでいった弱者の中に見たのです。
このときから武蔵は「心」というものを強く意識し始めます。そして、「おのれの生き方をあらためて考えるときが来たのではないか」と思うようになります。
「心」はこの物語のキーワードの一つです。最初に読むときは、エンターテインメントとしてのストーリーを楽しんでいただきたいのですが、ぜひとも再読して、二度目には「心」という文字が出てきた前後をじっくりと読み込んでみてください。武蔵が命を削って挑んだ、これまで誰も描き得なかった最後の名勝負が見えてくるはずです。
挑んだものは人ではありません。それはやはり、「心」なのです。
本書は武蔵が「後生に残る
それは
武蔵の『五輪書』は、今でも
稲葉氏はこの普遍とは
物語の中で、武蔵も懊悩します。そして、
この問答が武蔵の懊悩を助け、また、さらに新たな懊悩を生みます。そうして武蔵の中に眠る考えが輪郭を持ち、この世の万物に通じる普遍性が「おのれで知るもの」となるのです。
つまり、武蔵の最後の戦いは孤高なだけでは成し得ず、人との温かな縁の中、「鬼のような執念の作業」を行うことで実を結ぶのです。
稲葉氏が探り出した、この晩年の知られざる新たな武蔵像でなければ結実しない、この男の真の偉業を見せられたとき、読者は大きな感動に胸を熱くすることでしょう。
本書には、稲葉氏「自身の言葉をもって」次のように書かれています。
「人は百人百様。先達の教えがいかに正しかろうが、間違っていようが、そこに新しき工夫が必要になるのではないか」
これもまた、すべてのことに通じる教えではないでしょうか。稲葉氏も本書に、武蔵の『五輪書』同様、普遍を打ち出しているのです。敬愛する作家の教えとして、私は自分の小説を生み出すときは、これからは「新しき工夫」を座右の銘として襟を正すつもりです。
ところで、本書には私の大好きな
武蔵は清に語ります。
「人は後悔しながら生きるものだ」
武蔵が言うからこそ深い意味を持つ、作中の大好きな言葉です。後悔してもよいのだと、何か救われた気がするのです。
清との場面はどれも良いのですが、ことにラスト三行を読んだ後は、感動でしばらく本を閉じることができませんでした。
読み終えるころには、稲葉氏の故郷でもある、本書で描かれた素朴で美しい熊本が好きになります。武蔵の命日に文庫を携え、ひとり熊本を歩いてみるつもりです。
作品紹介
書 名: さらば武蔵
著 者: 稲葉 稔
発売日:2024年09月24日
宮本武蔵を描いた決定版!
「この一冊に一気に引き込まれ時を忘れた・・・まさに渾身作」
俳優・武道家 藤岡弘、
泰平の世を迎えた江戸初期――戦国の動乱を生き抜いた宮本武蔵も老境に達していた。将軍家剣術指南役の柳生宗矩に嫉妬し、生半可な仕官の道を選ばなかった武蔵も、島原の乱で負傷したことで老いを自覚し終の棲家を求める。やがて熊本藩主・細川忠利に迎えられた武蔵は、自らが究めてきた兵法の極意を伝えるべく、岩戸霊巌洞に籠もり『五輪書』の執筆を始めた。最後に到った境地とは? 知られざる宮本武蔵像を描いた決定版!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000784/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら