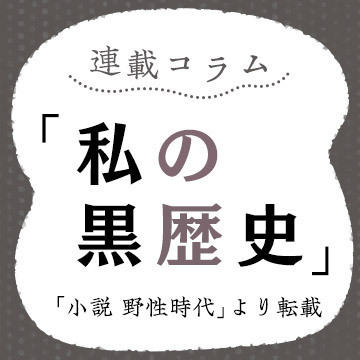六車由実の、介護の未来06 利用者さんが入院する、ということ(前編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
タケコさんが入院した
すまいる劇団のお芝居「富士の白雪姫」が文化祭で上演されてからほぼ一週間が経った月曜日の早朝、白雪姫の厳しくも優しいお母さん役を見事に演じたタケコさんのご主人から電話が入った。タケコさんが、土曜日に自宅前の路上で転んで、大腿骨頚部を骨折し市内の総合病院に入院した、というのだ。
タケコさんはここのところ視力の衰えが著しく、そのためか歩行がおぼつかなく、これまでも何回か自宅で転倒を繰り返していた。けれど、タケコさんは60代後半でまだ若い。それもあって、今までは顔や腕や手に打撲や擦り傷を負う程度で済んでおり、骨折してしまう、しかも、歩行に重要な大腿骨頚部を骨折してしまうとは、私たちは予想もしていなかったのである。電話で入院を知らせてくれたご主人の声も暗く、かなりショックを受けているようだった。お芝居ではあんなに上手にお母さん役を演じていたし、数日前まではいつもと変わらずにみんなと共に過ごしていたこともあって、私が、タケコさんが骨折して入院したことを伝えると、利用者さんたちもスタッフも一様に驚き、「嘘!」「信じられない」と動揺していた。
脚の付け根にある大腿骨頚部は、高齢者が転倒をした際に骨折しやすい部位の一つである。しかも、腕等の骨折の場合はギブスで固定して自然に骨折部が接合されるようにする保存的治療が行われることも多いのだが、大腿骨頚部骨折に関しては保存的治療による治癒は難しく、骨折部を金属等の器具で固定する手術が行われるのが一般的である。そして術後は、急性期を過ぎると、リハビリテーション専門の病院に転院して、三か月を目途に歩行訓練等のリハビリが行われるのである。だから、手術が成功して、リハビリが順調に進んだとしても、タケコさんが自宅に戻り、すまいるほーむにまた来られるようになるのは、早くても来年2月になってしまうだろう。
ただ、高齢者で、既に介護を受ける状態にあった方の場合は、必ずしもそのように順調にリハビリが進み、自宅へ戻れるわけではない、というのが介護現場で10年間働いてきた私の実感である。
一般社団法人日本骨折治療学会のHPの説明には、「受傷前に屋外活動を一人で行うことが可能であった患者さんでも、半年から1年後に元通りに近い歩行能力を獲得できるのは、全体の50%程度」に過ぎず、「本人のリハビリテーションに対する努力と、家族の励ましが重要」だと記されている。身体機能や認知機能が衰えてきている要介護の高齢者であれば、更にその確率は下がるはずである。
すまいるほーむでも、これまでにも自宅で転倒して大腿骨頚部を骨折した方が何人かいたが、在宅生活に戻って、すまいるほーむの利用を再開できた方は一人もいないのが現実である。いずれも、リハビリを経ても歩行機能は以前と同等には回復せずに、自宅での生活が困難だと判断され、施設へと入所されていった。
生きることへの意欲をなくしていたタケコさん
まだ比較的年齢の若いタケコさんに内在する力を信じて、何とかリハビリを頑張って、また歩けるようになることを、そして、すまいるほーむへ戻ってきてくれることを私たちは願うばかりだが、そう楽観視できないという気持ちも正直ある。
タケコさんは、すまいるほーむで過ごす時も、「目が見えないから嫌だ」と言って、午前中にそれぞれの利用者さんが取り組んでいる塗り絵や貼り絵、縫物、編み物、新聞折り等の物づくりや手作業をしないことが多かったばかりでなく、体操や機能訓練の時に体を動かすことに対しても消極的だったからだ。また、ここ1年くらいは、トイレや浴室まで歩くことさえも億劫がっていた。その大きな理由は視力が低下し、見えにくいということがあるのだろうが、生きることに対しての意欲も楽しもうという気持ちも低下してきているように私たちには思えていた。
だから、タケコさんが希望を持って生きていけるようにしていくにはどうしたらいいのか、何が必要なのかを、これまでスタッフ同士で何度も話し合い、試みてきたのだが、その難しさに歯痒い思いを重ねてきたのである。
術後のタケコさんがやはりそのように意欲や希望を持つことができなかったら、リハビリも思うようには進まないだろう。そして、もし歩行機能が回復せず、車いすを利用することになってしまったら、家の外も中も段差が多く、廊下も狭い自宅には戻ることはできないに違いない。いろいろと想像していくと、タケコさんがすまいるほーむに戻ってくるというのは絶望的なことのように思えてくる。
何とかタケコさんを励ましたい。いつもだったら、利用者さんが入院したらスタッフみんなでお見舞いにいくのだが、再び新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、タケコさんが入院している病院では面会は家族だけに制限されている。そこで、利用者さんたちやスタッフにタケコさんへのメッセージを色紙に書いてもらって、それをご主人からタケコさんに渡してもらうことにした。
色紙には、お芝居「富士の白雪姫」の時に撮った笑顔の集合写真を真ん中に貼りつけ、その下に、「タケコさん、みんなで待っているよ!」とピンク色の色鉛筆で大きく書いた。そして、その周りに、タケコさんを励ますメッセージを書いてほしいと、利用者さんたちやスタッフにお願いし、みんなに色紙をまわして書いてもらった。
それぞれ快くタケコさんへの思いとあたたかな励ましの言葉を記してくれた。中でも、タケコさんのことが大好きで、隣や真向いにタケコさんが座ると上機嫌だったテンさんは、脳出血による左上下肢の麻痺が強く、視野障害もあって、思うように字を書くのは難しいのだが、「自分で書くよ」と言って、右手でペンを固く握り、体を斜めに傾け色紙に顔を近づけて、一文字一文字ゆっくりと丁寧にメッセージを書いてくれた。
「タケコさんかいないとさみしいよ はやく元気になてきてね テン」
誤字も脱字もあるし、字は大きくなったり、小さくなったり、ゆがんだりしているけれど、でも、渾身の力で記したテンさんのメッセージはきっとタケコさんの心に届くに違いない。
みんなの気持ちが込められた色紙は私が預かり、帰りの送迎の後にタケコさんの自宅へと届けた。ご主人は病院へお見舞いに行っているのか留守だったので、色紙を入れた紙袋の外にメモを貼り付けて、玄関先に置いてきた。この色紙を読んで、タケコさんが少しでも気持ちが前向きになり、リハビリを頑張ってくれればいいと思う。
「今日も超ボケだけどよろしくね」
タケコさんがすまいるほーむに通い始めたのは平成30年の2月からだ。アルツハイマー型認知症の診断を受けていて、家事もほとんどできなくなっていた。家に閉じ籠ることが多くなり、このままでは認知症の症状がより進行してしまうのではと心配した娘さんが、すまいるほーむの利用を薦めてくれたのであった。
娘さんからも本人からも長年自宅で和裁の仕事をしていたと聞いていたので、午前中の手作業の時間は、当初は、他の利用者さんにいただいた反物で暖簾を縫ってもらったり、巾着袋や雑巾を縫ってもらったりした。その手つきは速く、丁寧だった。けれど、タケコさんは、「目が見えにくいからできない」と言って、3か月もしないうちに針仕事をすることに対して、意欲も興味もなくしていった。そんなタケコさんに、これだったら楽しく取り組めるのではないかと考え、ちぎり絵を薦めてくれたのは、若手女性スタッフのモッチーだった。スタッフたちは、いつも私が気づかない利用者さんたちの体調や状態の変化、心の動きを素早く察知し、私よりもずっと柔軟な思考でいろいろと対応を考えてくれ、試みてくれる。モッチーにもいつも助けられている。本当にありがたい。
とはいえ、ちぎり絵の工程は意外と複雑だ。まず何色もの折り紙を細かくちぎってもらって、色別に小皿に入れておく。そして、それらを季節の塗り絵のモチーフの枠に沿って貼り付けていく。折り紙を何色もちぎる作業、どこに何色の色紙を貼るのかを考える作業、塗り絵の台紙に糊を塗る作業、そしてちぎった色紙を一片一片貼り付ける作業。縫物よりもよほど作業工程は多く、完成までに時間がかかるものだったが、タケコさんはしばらくはこのちぎり絵に熱心に取り組んだ。そして、作品が完成する度にすまいるほーむの壁に貼ると、他の利用者さんたちが、「上手だね」「きれいだね」とタケコさんに声をかけていた。タケコさんも、「そうかなあ」と言いながらも、嬉しそうな表情を見せてくれたものである。
一方で、タケコさんは、既にその頃から、視力の低下や認知症の進行により、できなくなることが増えていくことに強い不安を感じているようだった。自分のことを「ボケ老人」と言い、朝の送迎時、車に乗り込んだ途端に、「今日も超ボケだけどよろしくね」とまるで口癖のように毎回言った。こうして文字にすると、「超ボケ」という言葉を自虐ネタ的にあっけらかんと使っているようにも思えるが、本人は「超ボケ」であることを酷く深刻にとらえていて、「お父さん(ご主人)にはすまいるのみんなに迷惑かけるなよって言われるけど、超ボケだから何が迷惑だかわからないだよ」と涙ぐむことも多かった。それに対して、同乗していたアルツハイマー型認知症のみよさんが、いつもこう励ましてくれていた。
「大丈夫だよ、私もおんなじだよ。自分でも本当にバカをやっているなってやんなっちゃうよ。でも、こうしてさ、みんなで集まってさ、楽しくやれるのはありがたいじゃん」
「そうなんだけどね……」
不安は拭えないものの、「同じだよ」というみよさんの言葉にタケコさんも少し落ち着きを取り戻しているようだった。
励ますことの難しさ
他の利用者さんたちもそうだ。タケコさんが、「超ボケ」であることの不安を口にすると、それぞれが、特に認知症の利用者さんたちが、「大丈夫」「私も同じだよ」と優しく声をかけてくれていた。同じような不安や生き辛さを抱える利用者さんたちのこうした言葉は、私たちスタッフのどんな励ましよりも、タケコさんの心をあたたかく包み込んでくれるものだったように思う。
スタッフたちも、それぞれがタケコさんを励まそうといろいろと考え、声をかけてくれていた。タケコさんが、「もうボケ老人でしょうがいないよ。どうしてこんなになっちゃったんだろう」と言うのに対して、「タケコさんはボケてなんかいないよ。自分でご飯も食べることができるし、トイレにだって行くことができるじゃん」と言ってくれるスタッフもいた。でも、認知症の進行を自覚し、絶望している本人が、「ボケてないよ」と言われたことで励まされたかどうかはわからない。
私も、どんなふうに声をかけたらいいのかと悩み続けていた。悩んだ末に、こんなことを言ってみたことがある。
「タケコさんは不安なんだよね。気持ちはわかる気がするよ。でもね、ボケたっていいんだよ。ここは、ボケたっていいところなの。安心してボケていいの。何かできないことがあれば、私たちがお手伝いするし、不安なときはいつも一緒にいるよ」
「でもそれじゃあ、情けないし、みんなに迷惑をかけるだけじゃ」
「迷惑かけたっていいじゃん。タケコさんだって、おばあちゃんやお母さんの面倒みたでしょ。今度は私たちの番だよ。それに私だって、みんなに迷惑をかけているよ。お互い様だよ」
「あなたは、本当に優しいね」
認知症になっても、認知症が進行しても、互いに助け合って、安心して共に過ごし続けられる場。すまいるほーむがそんな場所になればいい、とずっと思ってきた。タケコさんへとかけた言葉も、私のそんな思いから出たものである。けれど、タケコさんは、「あなたは、本当に優しいね」と言って会話を閉じてしまった。結局、私には、不安と絶望の中にあるタケコさんを安心させることも、勇気づけることもできなかったのだと思う。
私を含め、スタッフの言葉が、利用者さんたちの言葉に比べて、タケコさんの心に届かなかったのはなぜか。それは、タケコさんが、私たちスタッフと自分との関係の非対称性を敏感に感じ取っていたからではないだろうか。
私たちは、利用者さんとの関係が、介護する/されるという関係を超えた、人と人とのつながりとして結べるようになりたいと考えてきた。そして、聞き書きをベースとして、様々な試みを通して、いくつものつながりを作ってきたつもりだ。タケコさんとも、それぞれのスタッフが人と人として向き合おうとしてきたのである。
けれど、認知症の進行に対して絶望しているタケコさんを励まそうとするとき、自分の気づかないうちに上からの物言いになってしまっていたのではないか。それが、かえってタケコさんを追い詰めていたのではないか、とも思うのである。
※次回は1月9日(土)に掲載予定