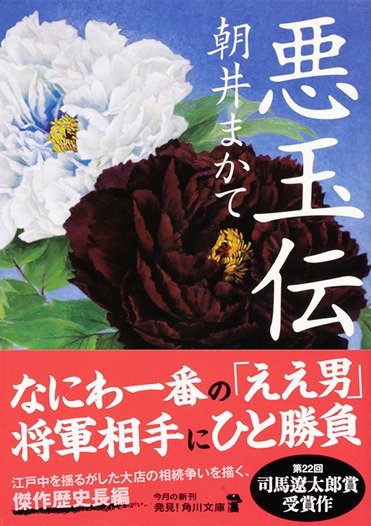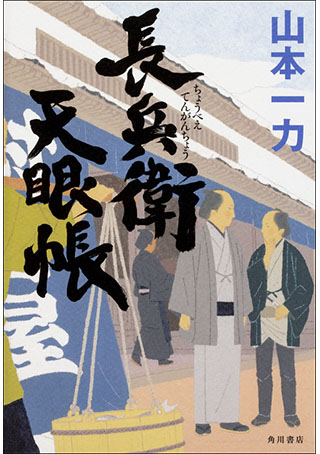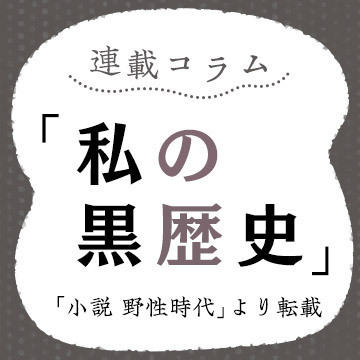時代小説でしか書けない不可能犯罪ミステリ。『雪旅籠』杉江松恋の新鋭作家ハンティング
杉江松恋の新鋭作家ハンティング

書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。
今回は珍しく、捕物小説です。
珍しく、捕物小説を採り上げようと思う。
戸田義長『雪旅籠』である。
版元レーベルの創元推理文庫は、名前からもわかる通り、ほぼミステリーに特化しており、時代小説の点数は少ない。『雪旅籠』がこの文庫に入ったのは、本作が第二十七回鮎川哲也賞の最終候補に残り、戸田のデビュー作となった『恋牡丹』(創元推理文庫)の姉妹篇に当たるからだ。ミステリー色の強い作品なのである。鮎川哲也賞の第二十七回受賞作は単行本が刊行されるやベストセラーになった今村昌弘『屍人荘の殺人』(創元推理文庫)だった。また、優秀賞として一本木透『だから殺せなかった』(東京創元社)も刊行されている。この二作と善戦したわけで、『恋牡丹』は選考委員の評が高かったのだろう。受賞には至らなかったものの、文庫オリジナルの形式で二〇一八年に刊行された。このとき同じく最終候補に残った「幽霊は時計仕掛け」の作者・朝永理人は、同作を後に全面改稿して第十八回『このミステリーがすごい!』大賞に応募し、優秀賞を射止めている(刊行時の題名は『幽霊たちの不在証明』宝島社文庫)。つまり、稀に見る高水準の回だったのである。
で、『雪旅籠』だ。実は『恋牡丹』を読んだとき、おもしろいのだが思ったことを原稿にしにくい、と感じて書評はしなかった記憶がある。ミステリーとしては十分水準作なので、これは単純に好みの問題だ。
『恋牡丹』は四篇から成る連作小説で、主人公は北町奉行所定町廻り同心の戸田惣左衛門と清之介の父子である。こう書くと父子鷹的な設定に見えるが、惣左衛門が捜査に当たるのは「花狂い」「願い笹」という最初の二篇、後半の「恋牡丹」「雨上り」で彼は隠居しており、跡を継いだ清之介が代わって同心の勤めを果たす。最初の「花狂い」は西暦一八五〇年代の出来事で、最後の「雨上り」は上野で彰義隊が闘った後と明記されているので西暦一八六八年、慶応四年の話だとわかる。物語の中で十数年が経過しているのだ。編年体ではあるものの間は飛び飛びで、話が進むごとに登場人物たちの境遇が変化しているおもしろさがあった。
主要登場人物は惣左衛門と清之介の他にもう一人いる。「願い笹」で顔を出して、後に惣左衛門の妻となるお糸である。親子ほどに歳の差のある夫婦で、真面目一徹で初老にさしかかった貧乏同心にそんな若い娘が惚れるはずがあろうか、という点に、初読時の私は引っ掛かった。
実はこの点が連作の重要な主題になっている。惣左衛門は病気で前妻に先立たれているのだが、亡くなってみて初めて、自分が武家のしきたりとして彼女を娶ったのであり、男女の情愛はそこになかったということに気づいたのだった。息子・清之介の婚姻も、言われるがままにしたもので、そこに恋愛という感情は介在しなかった。自身の感情で生きることのない武士が初めて愛の存在に気づく。お糸は惣左衛門を人間の側に引き戻す役割だ。
清之介の物語である「雨上り」でも、同じように彼が武士から人間になる場面がある。価値観の転変が激しかった幕末に時代を設定したのはこの、武士か人間か、という問いを発するためだったのだろう。その構成は大いに評価するものの、前出のお糸と惣左衛門のなれそめに私はどうしても納得できず、『恋牡丹』には乗り切れなかったのだった。これは男性の願望小説なのではないか、という疑念をどうしても消しきれなかった。
悪い癖で、前置きが異常に長くなってしまった。
以上のようなことを踏まえて『雪旅籠』である。『恋牡丹』と同じ連作形式で、今回は八篇が収録されている。おもしろいのは、『恋牡丹』の続篇ではなく、その隙間を埋める構成になっている点だ。最初の「埋み火」は、作中のある一文から『恋牡丹』に収録された「花狂い」の五年後に起きた事件であることがわかる。惣左衛門が家作の修繕を任せている男が話の主役で、彼が毎晩外に出掛けていくのはなぜか、という動機が謎になる。男は夜鷹(夜間、道端で客を引いた私娼)を求めて歩き回っているように見えるのだが、やがて起きた小さな事件から別の可能性が浮き上がってくる。
「埋み火」と続く「逃げ水」「神隠し」の三篇には、「花狂い」で惣左衛門が自覚した、自分は亡き妻を本当の意味では愛していなかったのだ、という悔恨が影を落としている。登場人物たちが鏡となって、惣左衛門はそこに至らぬ自分の姿を見ることになるのだ。ちなみに「逃げ水」は井伊直弼暗殺事件に題材を採った不可能犯罪もので、鶴屋南北原作の『東海道四谷怪談』から謎を解くヒントを得る趣向がおもしろい。
「神隠し」の後には『恋牡丹』の「願い笹」が挟まる。したがって、そのあとの「島抜け」「出養生」に登場する惣左衛門は、すでにお糸と出会って彼女を後添えに貰うことを決意しているのである。この二篇も不可能犯罪トリックがよく考えられており、ともに監視中の建物の中で事件が起きて犯人がどこかに消えうせるという密室的状況が描かれる。似た状況だが趣向は異なり、特に後者は、古典的な探偵小説ファンならにやりとさせられるだろう。
表題作の「雪旅籠」、そして「天狗松」では代替わりをして清之介が主役を務める。『恋牡丹』の「願い笹」では、父である惣左衛門が密室殺人事件の犯人にされかかったのだが、「雪旅籠」では清之介が同じ目に合う。「天狗松」も人間消失ものなのだが、『恋牡丹』所収の「雨上り」、及び本作の最終話「夕間暮」につながる道筋をつける作品でもある。武士の存在意義とは果たして何かという問いが、このへんから顕在化してくるのだ。『雪旅籠』の最初の三篇が惣左衛門の自問を背景にしていたように、「雪旅籠」「天狗松」は清之介の未熟が隠れた主題になっている。ここでの迷いが、「雨上り」の動揺につながるのである。本書は短篇集として独立した作品だが、登場人物のその後が気になる人は、『恋牡丹』にも目を通したらいいと思う。
最終話「夕間暮」は大政奉還が成立し、明治の御代が到来した後の物語だ。とある理由から清之介は脇に退き、もう一度惣左衛門が謎解き役を務める。時代の流れによって武士という階級が存立の根拠を失っていくという『恋牡丹』『雪旅籠』の物語は、本篇によって完全なる幕引きとなるのだ。大団円の演出もいいが、作中で語られる不可解な死に関する謎解きが興味深い。第一の回答が出た後に事件の異なる側面が見えるようになる。この連作全体で、夫婦とは、家族とは何か、という問いがたびたび投げかけられてきた。それが最後につきつけられるのである。
振り返ってみると、実に手数の多い連作だと感じる。『恋牡丹』収録の四篇は、動機の謎、密室殺人、推理の誤謬が物語の鍵となる展開、人間心理の不思議な動きと、各篇それぞれ異なる興趣で読者を楽しませた。『雪旅籠』は不可能犯罪ものを多く取り上げてミステリー色をさらに濃くしている。前作では時間の流れが飛び飛びだったために主人公たちの人生模様も咀嚼しにくい欠点があったが、今回はそれを十分に補う内容である。惣左衛門や清之介の内面描写にこだわらず、事件捜査を優先した点もいい。時代小説でしか書けない素材だが、夫婦・家族という普遍的な主題に言及しており、届く読者の層も広いはずだ。十分に余力のある作家、他の題材でも書ける人材である。戸田義長の名を覚えておくべし。