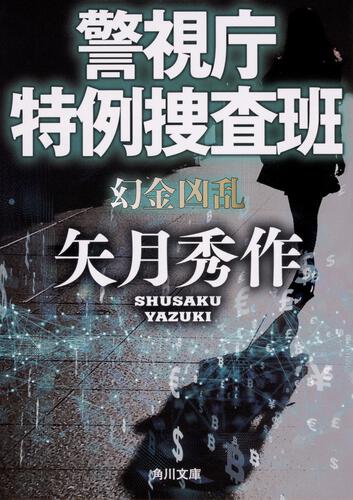【連載小説】株価が急上昇している会社の正体は? ──女性刑事二人が特殊犯罪に挑む。 矢月秀作「プラチナゴールド」#7-1
矢月秀作「プラチナゴールド」

※本記事は連載小説です。
前回のあらすじ
警視庁刑事部捜査三課の椎名つばきは、捜査の失敗から広報課に出向となった。合コンが大好きな後輩・彩川りおと交通安全講習業務に従事していたところ、通信障害が周囲に発生。現場で二人は携帯通信基地局アンテナを盗みだそうとしている犯人を捕らえた。そのことで椎名は捜査課復帰となり、彩川は異動して椎名とともに専従捜査班に加わることとなった。捕らえた犯人や容疑者たちから、事件解決のヒントを得た二人は、怪しい企業の捜査に乗り出す。
第3章
1
有刺鉄線で囲まれた、殺伐としただだっ広い敷地の奥に寂れた大きな倉庫が二つあり、倉庫の左脇に設置された二階建てのプレハブ小屋が本社屋だ。
周りには住宅もなければコンビニもない。会社へ向かう道路にも人影はなく、本当にここが会社なのか? と、疑いたくなるほど閑散としていた。
つばきは運転してきた車を、会社の東側の路肩に
「本当にここなんですか?」
助手席にいるりおが
「登記簿の住所ではここだね」
つばきは、スマートフォンに収めた登記簿の写真の住所とナビの住所を確かめ、言った。
二人は、
彼らは、それぞれに怪しいと
それも、左右田と同じく、仕手が入ってはいるが、自分たちとは毛色が違うと答えた。
その道のプロたちが口をそろえて同じことを言うということは、それなりの根拠があるという証左でもある。
つばきとりおは、永正鉱業社について調べてみた。
創立は一九六五年、
当時はまだ大量消費時代で、リサイクル事業は決してうまくいっているとは言い難かったが、太一郎はいずれ大量生産・大量消費の時代は終わると見て、借金しながら事業を継続していた。
しかし、一九八六年から始まったバブル景気が大量消費を加速させ、バブル崩壊前の一九九〇年に一度倒産した。
創立者の太一郎は、長年の苦労がたたり、会社を畳んだ二カ月後に病死。後を追うように太一郎の妻も病気で他界した。
再び、永正鉱業社の名が登場したのは、それから十年後の二〇〇〇年だった。
立ち上げたのは、太一郎の一人息子、永正
母亡き後も夜学に通い続け、
耕太の経営する新生永正鉱業社は、第三次平成不況の追い風もあり、瞬く間に軌道に乗った。
関東一円から廃品を集め、再生できる物は中古品として販売し、一つの製品としては使えなくなった物からは部品を取り出し、必要な人々に供給した。
今では当たり前となっているリサイクルだが、当時はまだ大規模に行っている業者はめずらしく、東証一部にも上場を果たし、経済新聞に新世代のリーダーとして取り上げられたこともあった。
が、順風だった経営に水を
系列の一部の廃品回収業者がリサイクルを行わず、引き取った廃棄物を不法投棄していたのだ。
さらに、一部の直営店舗では、まともな修理を行っていない中古家電を高値で売り付けていた事実も判明した。
耕太の名前が世に出ていた時だけに、風当たりも強かった。
耕太の社長としての管理監督が不十分だったことは否めないが、悪評は拭えず、事業規模を縮小せざるを得なくなった。
それでもリサイクルに対する機運は高かったので、なんとか一部指定の条件だけはクリアし続け、細々と経営を続けていた。
それがここへ来て、リサイクルからリデュースへと流れが変わってきた。
リデュースというのは、無駄なゴミそのものを減らそうという理念のこと。つまり、食品でも電化製品でも必要のない物は買うのを控え、ゴミを出さないようにしようということだ。
大量消費と逆行するこの考え方は、特に若者に浸透し、物自体が売れない時代に突入した。
集めた廃品を使える商品にしても売れなくなり、大量の在庫を抱えることになった。
そして、リサイクル品の販売からは撤退して店舗はすべて閉じ、今は廃棄物処理と廃品からの部品や素材の回収販売に特化して、事業を継続している。
そのような状況なので、一時は五千円を超えていた株価は急落し、五百円にまで下がった。
時価総額は十分の一となり、東証二部に降格した。
本来なら上場廃止でもおかしくない状況にもかかわらず、なんとか踏みとどまったのは、銀行や一部ファンドが流通株を買い、時価総額を支えたところによる。
筆頭株主も耕太からファンドに変わり、事実上、ファンドに買収された形だ。
その後、株価は五百円前後を推移し、日々の出来高数も少なく、市場では“終わった株”と目され、見向きされなくなった。
そこまではよくある話でもある。
ところが、三カ月前あたりから、左右田たちが言うように、突然株価が上昇し始めた。
会社の業績が良くなったり、市場を刺激するIR情報が出されたりということはなく、ただただ上昇し始めたのだ。
筆頭株主である〈アジアンリテールキャピタル(ARC)〉が保有株数を徐々に増やし始めたのをきっかけに、複数の投資ファンドが同社の株を買いあさり始めた。
そこに大口の個人投資家や銀行が乗っかり、さらなる上昇を演出し、値上がりに小口の個人投資家も群がってきて、出来高急上昇の活況銘柄となってきた。
今では、五百円以下だった株価も三千円を超すまでになっている。
当然、この不自然な値動きを見て、日本取引所グループが調査に入っている。
ARCが不当に株価を操作した疑惑がもたれたが、同社は回収した部品や素材の中国や東南アジアの新興国への輸出が堅調で、売り上げを伸ばしており、株価に反映される理由がまったくないわけでもなかった。
投資ファンドや銀行が、事業の成長性を見込んで先行投資するのもおかしなことではないからだ。
最終的に、グレーゾーンではあるが確固たる株価操作の証拠はないと結論付けられた。
しかし、今、つばきとりおが目にしている永正鉱業社の光景は、とても成長性のある活況な企業とは言い難い。
閑散としていて、人がいるのかいないのかもわからない。
倉庫脇に停まっている二台の二トントラックも、ボディーは
「行くよ」
つばきはスマホをジャケットの右ポケットに入れ、運転席のドアを開けた。
「ほんとに行くんですかー?」
「何寝ぼけたこと言ってんの。行くに決まってるだろ。早くしな」
「やだなー。今日の服、卸立てなのにー」
りおは、明るいグレーのパンツスーツを着ていた。スカートでないのはめずらしい。
「服なんてのは、着てりゃ汚れるんだよ。汚れたら洗えばいい」
「えー、クリーニング代もバカにならないんですよー」
「なら、汚れてもいい服を着てこい。さっさと降りな」
つばきが先に車を降りる。
りおはため息をついて、渋々後に続いた。
敷地の様子を見ながら、正門へ向かう。三メートルはある鉄格子の門が見えてきた。
「えー!」
りおが駆け寄る。
鉄格子にはチェーンが巻かれ、南京錠でがっちりとロックされていた。
「本当にここ、やってるんですか?」
塗装が剥がれて錆びた格子を見上げる。
「うーん……」
つばきは足元に目を向けた。
支柱にインターホンがある。つばきは押してみた。ボタンがスカスカする。音も聞こえない。故障したままのようだ。
プレハブ小屋に目を向ける。人の気配はない。倉庫の方も見てみる。やはり、人がいるような様子はない。
「休みみたいですね。先輩、帰りましょう」
りおはホッとした様子で、一足先に車に戻り始めた。
「……仕方ないね」
つばきも
と、目の端に光が飛び込んできた。
「ん?」
立ち止まって、倉庫の方を凝視する。
「どうしたんですか、先輩!」
りおが声をかけた。
つばきはしばらく倉庫を見つめたが、視線をりおに向けた。
「気のせいか」
つぶやき、りおと共に車へ戻っていった。
▶#7-2へつづく