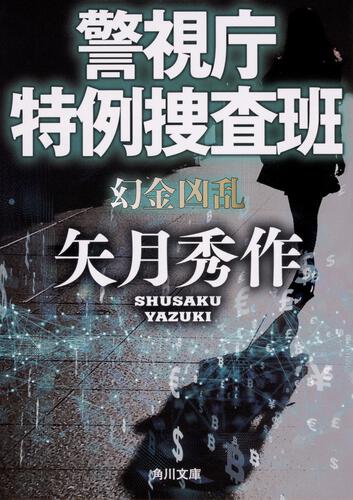【連載小説】株価に事件の糸口が!? 女性刑事二人が特殊犯罪に挑む! 矢月秀作「プラチナゴールド」#6-4
矢月秀作「プラチナゴールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「今、開けます」
左右田は返事をし、モニターのある部屋に鍵をかけ、玄関に出た。
ドアを開ける。椎名は左右田を睨む。隣にいる小柄な女はにこにこしながら、ぺこりと頭を下げた。
「同じく、警視庁の
つばきとは違い、気の抜けた女だった。
「ちょっと訊きたいことがあるんだよ。吉祥寺の件で」
つばきが言う。
「吉祥寺? 何の話ですか?」
「吉祥寺でー、携帯基地局が盗まれそうになった話、知ってます?」
りおが言う。
「ああ、ニュースで見たけど」
「その件で、ちょこっと協力してほしいんですけどー」
「協力って。オレは何も知らないけど」
「引っ張ろうか?」
つばきが言う。
「何もしてねえのに、それは──」
「叩けばいくらでも
じっと下から見上げる。
やがて、左右田は大きくドアを開いた。
「どうぞ」
「悪いね」
つばきはにやりとし、部屋へ入った。りおも一礼し、続いた。
広々としたリビングには、大きなL字型のソファーが置かれていた。大きな冷蔵庫に立派なシステムキッチンがあるものの、生活感はない。キッチンにはデリバリーものの容器が転がっていた。
「いい部屋じゃない。高いだろ、ここ?」
「まあ、そこそこです。飲み物とかないですけど」
「いらないよ。座って」
つばきが言う。
左右田が渋々右手に座る。つばきは左端、りおは二人の間に腰かけた。
「さっそくだけど、吉祥寺の事件のことは知ってるね?」
「さっきも言いましたけど、ニュースで見ただけですよ。オレは本当に何も関係ない」
「わかってる。知りたいのは、鉄骨や金属、中古部品なんかを扱ってる会社で、このところ値動きがあった銘柄」
「株ですか?」
「そう。あんた、仕手やってんだから、そっちは詳しいだろ?」
「オレはそんなことは──」
「だから、その件は問わないと言ってんだろ。あんたらが仕込んでいるわけでもないのに妙な動きをしている銘柄はない?」
つばきが睨む。
左右田はため息をついてうつむいた。いきなりの訪問に多少混乱しているようで、頭をかく。そして、やおら顔を上げた。
「いくつかありますよ、妙なのが」
左右田は観念したように答えた。
「ちょっと出してくんない、そのデータ」
「わかりました」
もう一度ため息をついて立ち上がり、奥の部屋のドアの鍵を開けた。少しだけ開いて、中へ入る。ちらりとモニターが覗いた。
ドアを閉めようとすると、いきなり、りおが開いた。
「おい、ここには──」
「すごーい! これがトレード部屋ってやつですねー!」
りおの甲高い声に、左右田は拍子抜けした。
りおはするすると中へ入った。
「このモニター全部使うんでしょ? どうなってるんですかー?」
「説明する必要はないだろ。出てってくれよ」
「あ、これ、なんですか?」
デスクにあったプリントをひょいっと
「ちょっと待ってくれ!」
取り返そうと手を伸ばす。が、りおはひらりとかわし、中身に目を通した。
「えー! 三億も損したんですかー! 信じられない! どれだけお金持ちなんですか!」
「返せ!」
左右田はプリントをひったくった。
「勝手な
りおを睨む。
「ごめんなさい、そんなに怒んないで」
眉尻を下げ、両手を合わせる。
「いいから、出て行ってくれ」
左右田はりおを追い出した。
りおが出ると、すぐにドアが閉まった。つばきの隣に戻る。
つばきは顔を寄せた。
「何かあったか?」
「取引関係のプリントがありました」
「中身は?」
「三億の損失と名前と電話番号らしきものが書いてありました」
「覚えてる?」
「ばっちりです!」
りおは自分の頭を指さし、
つばきが頷く。
左右田がプリントを数枚持って出てきた。
自分の座っていたところに戻り、テーブルにプリントを置く。
「五社分です。さっきの条件に合うのはそのくらいかと」
「なぜ、この五社を選んだんだ?」
「どれも、特別な理由がないのに株価が大きく上下しています。振れ幅も大きいので、ある程度資金を持った連中が入っています」
「特に怪しいのは?」
「
左右田が言う。
つばきは永正鉱業社のプリントを上に出した。りおが横から覗き込む。
「三カ月前あたりから、材料もないのに急に上下に振れ始めました。あきらかになんらかの仕手が入っているとは思うんですが、オレらとは違うかな、と」
「違うとは?」
つばきが訊き返す。
左右田はしまったという表情を覗かせたが、口を滑らせたものは仕方がない。あきらめて、話を続ける。
「仕手は、上げきったあとに落とすのが一番儲かります。同じ銘柄で短期間に何度もやれば目を付けられますから、一発勝負で抜くことが多いんですけど、そこをいじってる連中は、上げきらず下げきらずでうまく操作しています」
「そういう仕手をする連中を知らない?」
「すみません、それはわかりません。仕手仲間は、基本、やり口が似てて信用できる者としか組まないんで」
「調べられない?」
「勘弁してください。刑事さんも知ってると思いますけど、仕手筋にはヤバい連中も多いでしょう。ヘタに探りを入れてるのがバレれば、危ない」
左右田が渋い表情で言った。
これは左右田の言う通りだ。
近頃は、一般の個人投資家でも、資金を持てば仕手筋の真似事をするが、本物の筋には暴力団や政治家が絡んでいることも多い。
調子に乗って足を踏み入れれば、困ったことになるのは目に見えている。
左右田はそのあたりの立ち位置はわきまえているようだった。
「わかった、ありがとう」
つばきは立ち上がった。りおも立ち上がる。
「トレード中に悪かったね」
「いえ」
左右田は立って、ホッとしたように愛想笑いを浮かべた。玄関まで送る。
つばきはドアノブに手をかけ、振り返った。
「あ、そうそう。仕手まがいのことをするなとは言わないけど、あんまひどいことしてると、損した素人から刺されるから、気をつけな」
「そんなひどいことはしてませんよ」
左右田は言うが、笑みは引きつっていた。
つばきとりおは左右田のマンションから出た。
「さっきの名前と電話番号覚えてる?」
「はい」
「すぐ、照会して。そっちにも乗り込むよ」
「了解です!」
りおはすぐさまスマートフォンを出した。
つばきは手にしたプリントを見やり、バッグに収めた。
▶#7-1へつづく
◎第 6 回の全文は「カドブンノベル」2020年12月号でお楽しみいただけます!