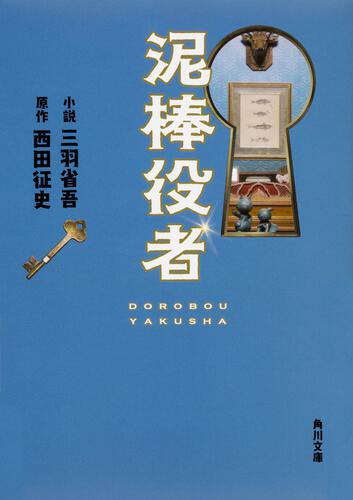死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#16-3
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
夏樹は、八号線沿いのコンビニ前で待っていた。
まだ蒸し暑い季節だというのに、凍えるように自分の肩を抱いていた。酷く
駐車場に車を
「布村留美……樹理亜が死に場所に選ぶとしたら、どこだ」
助手席に乗り込んだ夏樹は五秒ほど考えて、ハッと顔を上げた。
「白川村の遺棄現場」
「実の父親を遺棄した現場を、最期の地に選ぶか? お前も彼女も、恨んでいたんだろう」
「うん、だけど、他には考えられない」
これは、かなり以前から疑問に感じていたことだ。
佐合が妻と二人の子供とともに、
大人になった布村留美が、微かな記憶を辿ってあの場所を特定した可能性はある。
だが、遺体を遠くへ運ぶのはかなりリスキーな行為だ。県を
更に現在のあの場所は、産業廃棄物などの不法投棄場ではなくなっている。二十数年振りにそこを訪れた布村留美は、驚いたことだろう。奥飛驒土建は
昔なら限られた人間しか足を踏み入れず、不審なものがあっても誰も気にしなかっただろうが、今は山歩きや散歩をする者もおり、事実、第一発見者は犬を散歩させていた
宮治には、布村留美がそれを承知の上であの遺棄現場を選んだように思われる。だとすれば、あの場所は布村留美にとって、なにか特別な意味があった筈だ。
「分からないのは、その特別な意味だ」
SUVは金沢西ICから北陸自動車道に乗り、
「あの場所は……」
夏樹は説明しようとしたが、どこから言うべきか迷っているようだった。
雨が降り始めていた。時刻は午後十時になろうとしている。幸い車の通行量は少ない。道路事情が普通なら、白川村まで一時間半ほどだ。
「前に言った風呂場での
決心が付いたらしい夏樹が、今更ながらシートベルトを締め、助手席で言った。
「もちろん覚えてる」
「あれには、言ってなかったことがあるんだ」
反射的に宮治は「それは遺棄現場の話に戻るんだろうな」と訊こうとしたが、愚問だと判断して
「あれは、樹理亜の実母の嫉妬が原因だったんだ」
話し終わるまで質問は差し挟まないようにしようと思っていた宮治の口から、さっそく「嫉妬?」という言葉が漏れてしまった。
「あぁ、嫉妬だ」
樹理亜は人気があった。金を得られればなんでもいいという考えだった筈なのに、あの母親は自分以上に人気がある実の娘、それもまだ四歳か五歳だった娘に、嫉妬したのだ。
ある種の猿の社会では、若い雄が老いた雄を群れから追い出し、子猿を
それよりも酷い所業を、樹理亜の実母はやろうとした。これは夏樹も後から気付いたことだが、あの女は佐合以外の新しい雄と交尾をする為に、実の娘を邪魔者と判断したのだ。
「ちょっと待ってくれ」
前を向いたまま、宮治はもう一度「嫉妬ってなんだ? それに、樹理亜が人気があったって、なんのことだ?」と訊ねた。
「あぁ、悪い。説明が下手だな……前は、風呂といえば冷水か熱い湯を浴びせられるだけと言ったけど、たまには普通に温かい湯に入ることもあったんだ。けどそれは、いつも知らないおじさんとだった」
樹理亜の実母は、佐合も合意の上で売春をやっていた。その客の何人かに、小児性愛者がいた。彼らは金を払って樹理亜と風呂に入った。たまに、夏樹が選ばれることもあった。
「まぁね、さすがに幼過ぎたんだろう。あちこち触られるだけだったけど……」
横目で見ると、助手席の夏樹は笑っていた。話の内容にはまったく
そう思い、宮治は「すまん」と話を止めた。
「その件については、もう話さなくていい。それで、あの遺棄現場にどうつながるんだ?」
「まぁ、そういう事情であの大火傷の件があった。それから数ヶ月後だ」
高熱が治まってやっと自由に動けるようになった頃、樹理亜がいなくなった。佐合が問い質すと、樹理亜の実母はなんでもないように「捨てて来た」と答えた。
樹理亜が実母の手によって捨てられたのが、あの山の中だった。
「ここからはね、俺もちょっと意外だったんだけど」
夏樹の記憶では、樹理亜の実母を何発か殴って場所を聞き出した佐合が「
「俺は
佐合が樹理亜を探しに行ったのも、大火傷をした時に激怒したのも、決して優しさからではない。「大事な
「でも俺、どうしても〝あれは
「そうか……」
「それに俺、あの山の中でひとりぼっちだった樹理亜の気持ちを想像して想像して、同じ夢を繰り返し見るようになったんだ」
「夢?」
「あぁ。五歳の子が真っ暗な山の中でさ、雨の中でたった一人、捨てられたことを自覚しながら、ただ自分が死んでいくことを考え続けてる。そんな夢だ」
雨が強くなってきた。しかし宮治の視界が
無言のまま十数分が過ぎた。助手席の夏樹は、両手で頭を抱えていた。少し前傾するだけで、ダッシュボードに額が付きそうだった。宮治には聞き取れない声で、なにかブツブツと呟いている。
車は小矢部砺波JCTを経て、東海北陸自動車道に入った。
「まだ一時間ほど掛かる。彼女を匿うようになった経緯と、お前が知ってる事件の内容を聞かせてくれないか」
指の間から飛び出した夏樹の髪の毛、自分には似ていない緩い天然パーマを横目で見て、宮治が訊ねた。
夏樹は上体を起こし、一つ鼻をすすり上げてから「うん」と頷いた。
樹理亜から電話があったのは、今年に入ってすぐのことだった。近くの温泉街で働いているので、時間があれば会えないだろうか。そんな内容だった。
その時点で、夏樹は白川村殺人死体遺棄事件の被害者があの男──夏樹にとっては
だから、
外で会うのは危険だと判断し、樹理亜を自宅コーポに案内した。
「あの人、殺してしもた」
樹理亜は、いきなり結論から告げた。戸惑う夏樹に対し、彼女は顔や指を潰したのも、あの場所に遺棄したのも、全部自分だと補足するように言った。
「殺したって、ええやない。兄ちゃんなら、分かってくれるやろ?」
その言葉に、夏樹はなにも答えられなかった。
「なにがあったんだ?」
数分の沈黙の後、夏樹はそう訊ねた。それで樹理亜は初めて、あまりに説明不足であることに気付いたらしく、「そうやね」と殺害に至る経緯を話し始めた。
昨年十月の中頃、どこで番号を知ったのか分からないが、樹理亜の携帯電話に佐合から電話があった。
電話番号と同様に、どこでどうやって突き止めたのか分からないが、佐合は樹理亜の現在の名前、離婚歴があり男児を育てていること、そして清掃会社の代表として働いていることまで知っていた。
樹理亜は
どうすべきか
『一目、会いたいだけだ。一度でいい』
樹理亜は断わった。佐合は寂しそうに『ま、そうか』と呟いた。そして電話を切る前に『元気でいろよ』と言ったという。
しかし、佐合はやって来た。『タカオカ・ハウス・クリーニング』の名前は知らなかったようだが、高岡市内の清掃業者を調べて一軒ずつ訪ね歩こうと思えば、ネットを使うまでもなくタウンページで事足りる。
遠くで見るだけでいいと思っていたのだが、直接、話をしたくなってしまった。
佐合はそう言って、樹理亜が一人で終業後の片付けをしていた事務所にやって来た。
「それで殺してしまった、らしい」
「え?」
「いや、どんなふうに殺してしまったのか、遺体の損壊や遺棄をどんなふうにしたのかについては、聞いてないんだ。さすがに俺も、問い質すことが出来なくて」
「うん、まぁ、それもそうか……」
樹理亜は、来年の三月までは逃げ続けるつもりだと言った。三月が過ぎれば自ら出頭するつもりだが、それまでは北陸の温泉街を転々とするつもりだとも言った。
だが夏樹が「それは危険過ぎる」と止めた。
そして、自分の名義で小さなアパートを借り、そこに樹理亜を住まわせた。
「なんで三月なんだ? 来年の三月に、なにがある」
「ごめん、それも聞いてないんだ」
また重苦しい沈黙が始まりそうになった。
夏樹の方からは、新たな発言はありそうになかった。ゆっくりと前傾する夏樹に向かって、宮治は思い切って訊ねた。
「お前が聞いた話の中に、息子の光くんは出て来なかったんだな?」
その問いに、夏樹が「そういえば」とダッシュボードに届きそうだった頭を上げた。
「光のことは出なかった。だから俺、この間の和兄の話に驚いたんだ。光が関係してるってのは、確かなことなのか?」
宮治は「確かと言えるかどうか分からないが」と前置きし、前回の説明にはなかった部分を話した。
捜査本部は、なにがなんでもこの事件から世間の目を遠ざけようとしている。公開捜査で布村留美の身柄を押さえようとしないのは、そのせいだろう。光は今も連日のように、児童相談所に呼び出されている。そして、
「最も気になったのは、光くんの目だ」
「目?」
「あぁ。一度会っただけだが、彼はとんでもなく沈んだ目をしていた。小学生に、あんな目をさせちゃいけない。だから俺は、どんな事情があるにしたって、樹理亜……布村留美は間違ってると思うんだ」
夏樹は「そっか」と呟き、シートに背中を預けて首だけを前傾させた。そして二分ほど考え込んだ後で、上体を宮治の方に向け「なぁ和兄」と言った。
「あの記事、俺の噓をそのまま信じ込んで書いたのか? 噓だと分かっていて、敢えて書いたんじゃないのか?」
「どっちでもいいよ、そんなこと」
「よくない。ゴシップ誌の間抜けな記者が身内の言葉をそのまま信じ込んで、裏も取らずに馬鹿な記事を書いた。白川村殺人死体遺棄事件に関する世間の興味関心を、その一点に集中させる。それが和兄の狙いじゃないのか?」
「だったら、それでいいよ」
「よくないって。それが本当なら、和兄がやってることは……」
言い淀み、夏樹はフロントガラスに顔を向けた。
「なぁ、夏」
まったく答えにはなっていないのだが、宮治は言わざるを得なかった。
「やっぱ、俺達は似てるよ」
「え?」
「似てるんだよ、どうしようもなく」
意味が伝わっているかどうか宮治には分からなかったが、夏樹はなにも答えずに前を睨み続けていた。
白川村の遺棄現場まで、あと三十分ほどで到着するところだった。
雨は、ますます強くなっていた。
▶#16-4へつづく
◎第 16 回全文は「カドブンノベル」2020年3月号でお楽しみいただけます!