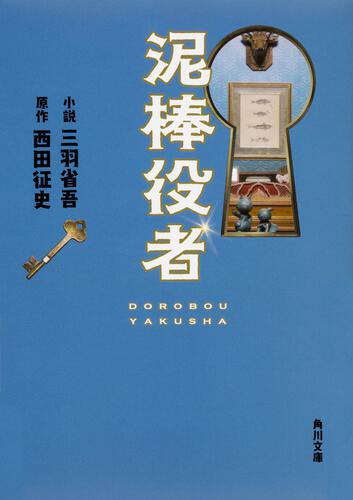死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#16-2
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
ここ一週間、睡眠時間は取れているし酒量も抑えめだったのだが、宿直室での連泊でさすがに疲れていた。
眠気覚ましに濃いコーヒーを
布村夫妻と坪内には、出来るだけ早い時間に会いたい。その為には、今夜中に富山入りしておきたかった。
コーヒーを飲みながらスマートフォンをチェックすると、BAZOOKAの早刷りを読んだらしい新聞・出版関係の知人数名から『これってマジかよ』『事件の全容ってのを詳しく聞かせてくれ』といったメールが入っていた。
更にPCからの転送ボックスには、七時頃に出した長文メールに対する返信もあった。
さっき石塚に言った「取材協力の礼とか、新たな取材依頼とか」というのは噓だった。一件の礼と二件の依頼ではあったが、いずれも取材に関するものと言うよりも、事件そのものに関する内容だ。
返信は、二つの依頼に対してのものだった。両者とも、宮治の頼みを『出来る範囲で』との注釈付きで引き受けてくれた。
もう一つの礼に対して、返信はない。その代わり、その相手からの着信履歴が三十分置きに四件も残されていた。留守番電話に、メッセージは入っていない。
どうしても直接、話をしたい。その気持ちは、宮治にも痛いほど分かった。
『読んだよ、早刷り。ウチじゃ取り寄せてねぇから、他社からファックスで送ってもらった』
折り返し電話を掛けると、相手は開口一番そう言った。
『いいのかよ。お前……と言うかBAZOOKA的に大丈夫なのか?』
「えぇ、そっちは問題ないです。それより、お礼が遅くなってすみません。無理を通してもらって、ありがとうございました」
『いやいや、こっちとしちゃ
相手の言葉を遮り、宮治は「利用させてもらったのはこっちなんで」と、改めて礼を言った。
電話の相手は、『週刊ホウオウ』の
ホウオウの先週号に掲載された、白川村殺人死体遺棄事件と宮治家に関する記事は、宮治本人が書いたものだった。
発行部数たかだか三万部のゴシップ誌に今回のような記事を載せたところで、世間の注目度は知れている。そこで宮治は、三十万部の『週刊ホウオウ』を利用したのだ。
菊地原圭祐のことは今でも嫌いだ。事件記者として軽蔑すらしている。だが同時に、彼ほど世論をあおることに
以前、菊地原が『ウチはこの件から手を引く』と言っていたのは、本当のことだった。だから最初は、宮治の依頼は言下に断られた。それでも構わず記事を送ると、菊地原は『なんか狙いがあるんだな』と引き受けてくれた。
『お前の弟は、本当に事件に絡んでいないのか?』
「変な質問ですね。絡んでた方が、菊地原さんにとっては喜ばしいでしょう」
『喜ぶわけねぇだろ。お前が根拠としてるのは、きょうだいから聞いた話だから間違いないってことだけだ。殺人や死体遺棄に絡んでないとしても、布村の逃亡を助けてるとしたら、なんだっけ、捜査妨害? そういうのになるだろう』
「えぇ、犯人蔵匿罪と隠避罪。但し本件の場合は公開捜査になっていないから、事情を知らずにどこかに住まわせたり金を渡したりしても、それには当たらないみたいです」
電話越しに、菊地原が小さく
確かに、自分の実父が変死体となって発見されたと報道で知り、その直後に実の妹が
まだ残暑が厳しい季節とはいえ、山の中はかなり涼しい。コーヒーから立ち上っていた盛大な湯気は、五分ほどでしずまってしまっていた。
『ホテルはもちろん、サウナやネットカフェなんかも使ってる形跡がないんだろ? 協力者がいると見るのが自然だ。弟を信じたい気持ちは分かるが……』
菊地原が、そこで口を
幡野や石塚とは、鋭さの種類が違うんだな。
冷たくなり始めたキャンプ用マグカップを包むように持ち、宮治はそんなどうでもいいことに感心していた。
『お前、ひょっとして』
言い
『お前には、弟が事件に絡んでるという確信がある。しかし問い
声が少し反響している。かつて勤めていた会社なので、この時間帯は殆ど使われることのない吹抜け階段だとすぐに分かった。
『さらりと書かれていて分かり
さすが、世の中を
石塚は、事件の全容をすべて摑んでいるという噓を書くことによって、焦った布村留美になんらかの行動を起こさせるのが狙いでは、と言った。幡野の「誰に向かって書いたんだ?」という言葉も、その裏には「布村だな」というニュアンスがあった。
これも外れてはいないのだが、二人とも夏樹の証言については、なにも引っ掛かっていないようだった。
『おい、なんとか言えよ』
肯定も否定もせず黙り続ける宮治に、
『弟の言うことを一〇〇パーセント信じ切ってる体を装って、実は弟を試してるんだろう。自分の噓が記事になってるのを読めば、驚いた弟が真実を話してくれることを期待して』
マグカップは、みるみる冷たくなっていった。いつの間にか、疲れも眠気もすっかりなくなっていた。肌寒く感じられる夜気と濃い目のコーヒー、菊地原の話が、絶妙にブレンドされているような気がした。
『ネット掲示板やSNSは、想像力を膨らませて好き勝手に書くぞ。〝きょうだいだから盲目的に信じるとは記者失格だ〟なんてのは優しい方で、〝警察を欺こうとしてあの記事を書いたんじゃないか〟〝記者本人も事件に絡んでるんじゃないか〟ってな具合……』
宮治はわずかに残った黒い液体を飲み干し、「それはそれでいいんです」と口を挟んだ。
「ああいうのは、好きに言わせておけばいい。いくらこちらが正論で応じたところで、向こうは顔も名前も晒さず、安全な場所にいて、発言に責任を取る度胸も覚悟もない。そもそも、ルールが違うんですから」
『そりゃそうだが、今日日はどんな無責任な発言だろうが、その数によってはそれが世論と捉えられるじゃねぇか。そんなことになったら、最悪の場合、社会的に抹殺されるぞ』
「そうなったらなったで、その時に考えます」
今度は菊地原が『お前なぁ……』と呟いて黙り込み、その隙に宮治が続けた。
「そっちはどうだっていいんです。でも今回はやりますよ。あの時、やらせてもらえなかったこと」
菊地原はなにも言わなかったが、「あの時」だけで充分に伝わったようだった。
宮治が
一家心中について取材をしていた宮治は、どうすればこの悲劇を避けることが出来たか、どこに問題があったかを書くつもりだった。
生活困窮者が受けられる数々の公的助成がある事実、それらが公務員を除く多くの国民に周知されていない事実、知ったとしても役場の窓口では門前払いが横行している事実、それをクリアしても手続きが恐ろしく煩雑である事実。そのくせ、ずる賢く声の大きい──佐合優馬のような──輩が不正に受給している、というどうしようもない現実。
しかしそれは編集長の「つまらん」の一言で却下され、宮治に代わって担当した菊地原の記事によって、あの公務員自殺という最悪の展開となった。
『大人になろうぜ』
「は?」
『前にも言ったが、こんな俺でもあの件に関しては人並みに後悔も反省もしてるんだ。しかしそれでも、なんでもかんでも公にすることで大衆がなにかを学び取り、次の悲劇を防ぐなんて、夢物語としか思えない。この社会は、そこまで成熟してねぇんだよ。どんな悲劇だって、たいていの人間にとっちゃ、ただの暇つぶしのネタに過ぎない。お前だってそんなこと、嫌んなるくらい分かってんだろうが』
「だから都合の悪い部分は伏せる。そういうのが大人になるってことなら、俺はずっと子供のままでいいですよ」
そんなことを言いながら、石塚が言った「最悪の場合、自殺も考えられる」という言葉が生々しく思い浮かぶ。
もうあのような失敗は繰り返さないと決意しながら、あの記事は、一人の人間に自死を決意させるかもしれないのだ。
この賭けは、危険過ぎる。そんな考えが頭を
『格好付けんなって』
たまたまだろうが、菊地原の言葉が宮治の
「どっちがですか」
気の早い秋の虫が、あちこちで鳴いていた。パートナーを探すにも、この季節では絶対数が少な過ぎる。そのせいか、鳴き声はどこか寂しげに聞こえた。
『今回は、お前の弟も絡んでることじゃねぇか。弟が自分に噓を吐いたのが許せないってことなら私怨だし、捕まっても微罪で済む可能性が高い弟をわざわざ世間に晒すような
「ご忠告には、感謝します」
会話に集中したいのに、寂しげな虫の声が、どうでもいい昔のことを思い出させる。
平塚の実家の庭でも、秋になるとスズムシやコオロギが鳴いていた。小学生の頃は夏樹と一緒に数匹を捕まえ、虫かごに入れて観察していた。けれど宮治はすぐに飽きてしまい、キュウリやナスを忘れずに与えるのは夏樹の役目だった。
その秋の習慣は数年間続いたが、捕まえた虫が最終的にどうなったのか、宮治の記憶にはない。夏樹のことだから、途中で
なぜ覚えていないのだろう。夏樹のことはなんでも知っているつもりだったが。
そこまで考えて、ハッとした。
宮治家の養子となる前の夏樹に関しては、今回の件で初めて知ったことが沢山ある。それは、夏樹の過去をあれこれ詮索しないという弘貴の方針があったせいでもあるが、そもそも俺は、夏樹のことを積極的に知ろうとしてきただろうか。
「記事には書かず、これから先も言うつもりのない事実もあるんで、この辺りで勘弁して下さい」
宮治のその言葉に、臨戦態勢だったらしい菊地原は『お? おぉ……』と声のトーンを落とした。
最後に「とにかく、ご協力ありがとうございました」と告げて、宮治は電話を切り、大きく伸びをした。
宮治が考えている通りなら、布村留美は明日の『真相 BAZOOKA』発売から数日以内に、なんらかの行動を起こす。
それに伴って、宮治夏樹もなんらかの行動を起こさざるを得なくなる。しかし有効な手段は思い浮かばず、困り果てて
ついさっきまでそう確信していたのに、急速に自信がなくなって来た。菊地原が溜息混じりに言った『お前なぁ……』という言葉のせいかもしれないし、気の早い秋の虫のせいかもしれない。
「だからって、今更どうすんだよ」
そう声に出して呟くと、虫の鳴き声が一斉に止んだ。
腹斜筋を伸ばしながらSUVの回りを二周し、両腕を回す。大きく
布村留美の養父母、布村
二人ともまだ『真相 BAZOOKA』最新号を読んでおらず、宮治の突然の訪問に戸惑いつつも、最新号を手渡すと「ありがとうございます」と丁寧に頭を下げ、額を寄せ合って読みふけった。
昼休みを狙って正午過ぎに訪ねた坪内史哉は、出勤途中にコンビニでBAZOOKAを買ったらしく、既に宮治の記事を読んでいた。
「根拠を聞かせてくれ」「やっぱり留美は」「あんたまで、こんなことを書くのか」
宮治が想定していたそれらの言葉は、三者から出なかった。
むしろ彼らが気にしたのは、宮治の〝きょうだい〟の存在だった。
布村正雄と薫は「いつかお会い出来ればいいんですが」「遠い親戚、みたいなものなんやろか」と言った。決して喜ばしいシチュエーションではないのに、二人とも無理をして笑おうとしていた。
坪内も「前回お会いしたときは、まだ分かってなかったの? 不思議なご縁ですねぇ」と、油まみれの作業着姿で困ったような顔で笑い、宮治の肩を痛いほど叩いて握手を求めて来た。
布村留美が事件に関わっていると読める記事内容については、養父母も元夫も、非常に冷静に受け止めていた。
宮治は少し意外な気もしたのだが、状況を見れば事件と無関係だと断言する方が不自然で、その思いは恐らく最初に会った時から彼らの中にもあったのだと改めて気付いた。
養父・正雄が激高して話も聞かずに宮治を追い返したのは、宮治が訪ねる前にメディアの取材攻勢があったせいだったのだろう。宮治の知らないところでは、薫や坪内も同じような対応をしていたのかもしれない。
そして時が
自分の母親が、殺人死体遺棄事件の容疑者として逮捕される。しかもその被害者は母親の実の父親。そんな事実が公になった場合、世間の好奇の目に晒される光は、どう感じるだろう。地域は、学校は、同級生達は、光をどう扱うだろう。
またどこかに引っ越しをして、可能ならば名前も変えて、新しい人生を送らせるべきだろうか。
布村夫妻も坪内も、異口同音にそれを宮治に訊ねた。
宮治は過去の事例をいくつか挙げつつ、本人にとって著しく不利益な事態が想定される場合、公立の小中学校でも越境は認められるし、苗字の変更も通常よりは簡単であることなどを説明した。
その光本人には、会うことが出来なかった。布村薫が言うには、夏休みも最終盤なので宿題の
坪内にもそれとなく光の最近の様子を訊ねてみたが、夏休みはなにかと忙しいようで今月は会えていない。なんでも頻繁に児相に行っていて宿題をする時間もないらしい、との返答だった。
児童相談所に呼び出されるのは、心のケアなどではなく──それもあるかもしれないが──事件に関して知っていることを話すよう説得されているのではないか。
富山訪問はその確認も目的だったのだが、布村夫妻も坪内も、なにかを誤魔化しているという感じではなかった。
光が事件に関わっている可能性を、
そんなふうに思いながら、しかし宮治はこの先に想定される事態を説明することは出来ず、富山を後にした。
その日の夜から、宮治は石川県金沢市のビジネスホテルに腰を据えた。
ホテルに缶詰では気が
いつ事態が動いても車の運転が出来るよう、酒は完全に断っていた。夕食も、おでん屋や焼鳥屋では誘惑があるので、食事メインの定食屋などで済ませた。
ベッドではすぐに起きられるよう、着信音を最大に設定したスマートフォンを顔の
待望の連絡があったのは、寝不足の蓄積を感じ始めた五日目の午後九時過ぎのことだった。
宮治はその時、近江町市場の外れにある古い定食屋で遅い夕食を摂っていた。抜群に
『なんだって、あんな記事を書いたんだ』
名乗りもせず、
『
夏樹らしくない大声に、宮治はスマホを数センチ耳から離さなければならなかった。そして、意識的に冷静な声で「なに言ってんだ」と返した。
数秒、沈黙が続いた。
噓を吐いていたと白状しているようなものだ、と夏樹が気付くまでの数秒だったのだろう。
『ごめん。和兄、今どこ?』
事件記者としての本能が「来た」と喜ぶ。反面、夏樹の兄という立場が「当たってやがったか」と嘆く。
巨大な矛盾を内包したまま、宮治はなんとか「どうした?」と答えた。
『ホントごめん』
歩きながら
『俺……和兄に……とんでもない噓を……』
言葉が途切れ途切れになり、風の音が徐々に大きくなる。小走りか、ひょっとしたら全速力で駆け出したのかもしれない。歩いている時は殆ど分からないが、走るとはっきり分かる、左足を引き
「足、大丈夫か? 無理すんな」
場違いかもしれないそんな気遣いの言葉が、つい宮治の口を突いて出る。
『俺、和兄に噓を……』
声が
「その
『樹理亜がいなくなった。俺、本当はあいつと会ってた。事件のこと本人から打ち明けられて、身を隠すことに協力してたんだ』
「分かった。いなくなったことに気付いたのは、どれくらい前のことだ」
『和兄の記事を読んでから様子がおかしくて、それで昨日も今日も電話で変なこと言ってて、気になって、仕事が終わってアパートを訪ねたらいなくて、電話にも出なくて……』
「だからそれは、どれくらい前だ」
『気付いたのはついさっきで、けどあいつがアパートを出たのは、いつなのか分からない。四時頃の電話には出たから、それ以降だと思うけど。あ、廃工場に隠してたミニバンがなくなってたから、たぶん日が暮れてからだ。あいつ、車を使うのは夜と決めてたから。〝早く終わらせないと〟なんて言ってたから、あいつ死ぬ気かもしれない』
「落ち着け、
『あいつが死んだら、俺……』
「いいから落ち着け。お前は兄貴だろうが。樹理亜を、ずっと守って来たんだろうが」
活を入れるつもりで強く言ったのだが、夏樹はパニックに陥っているようだった。施設で離れ離れになる時、まだ字が読めなかった樹理亜にメッセージを託したこと、三年後に手紙のやり取りを始めたこと、樹理亜の妊娠をきっかけに直接会うようになったことなど、今言ったところでどうしようもない兄と妹の
「不義理なんてことはない。家族の中に、義理もなにもあるもんか。お前は間違ってない。お前が樹理亜にそうしたように、俺はいつだってお前の側にいる。今だってそうだ。金沢にいる」
詳しいことは会ってから聞くからと諭すと、過呼吸気味だった夏樹は『うん……うん……』と呼吸を落ち着かせた。
「よし、よく聞けよ」
宮治は夏樹に、タクシーを拾って国道八号線を金沢方面へ向かえ、
そして宮治は「すんません急用なんで」と立ち上がり、味噌焼きを半分ほど残して会計を済ませた。
▶#16-3へつづく
◎第 16 回全文は「カドブンノベル」2020年3月号でお楽しみいただけます!