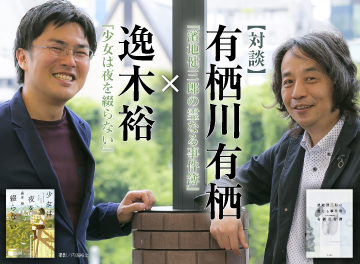【連載小説】真夜との一夜。真夜は駿に本当の気持ちをぶつける。少女の死の真相は? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#24
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
一瞬で声色が変わる。威圧してくるレナの声を聞くと、問答無用で胃がきゅっとする。郷原の弟もそうだった。修羅場をくぐってきた人間だけが持つ、底の見えない
「『マンドラゴラ』の店主は
「何か、怪しい商売をしてたって、聞いたことがあります」
「たぶんそれだよ。川崎が仕入れたものを郷原さんがあちこちで売って回るみたいなことをしてた。
「その川崎って人は、どういう人なんですか」
「郷原さんの先輩。まだ二十五歳くらいなんだけど、五年前に親が死んで、あの店を受け継いだみたい。あそこはもともと『川崎書店』っていう、昔からある古本屋だったんだよ。でも、あいつが継いでからどんどん趣味が入ってきて、いまじゃアダルトグッズとか媚薬とかなんでも置くイカれた店になっちゃった」
店内を思いだす。見ているだけで恥ずかしいものがごちゃまぜに陳列された、カオスな空間だった。
「で、あるとき、郷原さんは川崎と揉めた」
「揉めた? なんでですか」
「詳しくは教えてくれない。その結果、郷原さんは川崎をボコボコにして、病院送りにしちゃったわけ。それ以来ふたりは絶縁してる。でも最近、
「そんなに嫌なら、止めればいいじゃないですか」
「いま、一緒に暮らしてないからね。公輝くんはさっき言った父親と暮らしてて、郷原さんはひとりで暮らしてる。父親は相変わらずだし、郷原さんも金欠だから、公輝くんも金に困ってそんなところに出入りしてるのかもしれない。川崎にしても、あんな店、働いてくれる人がいないんだろうね」
とにかく、とレナは念押しのように言う。
「『マンドラゴラ』には触らないでほしい。そもそも川崎も変なやつだから、近寄らないほうがいい。店内、見たんだろ?」
「ええ、まあ……」
「武器のコーナーがあるの、見た?」
頷いた。雑多な店内に、ナイフやエアガンが並んでいる一角があった。
「気持ち悪いよな。あれは、川崎の趣味。ほかのものは商品だけど、あれだけはあいつのコレクション。本人はただのオタクだから、ああいうの使いたがるのかもね」
「使う?」
「ああ、川崎、武器を集めるだけじゃなくて、使いたがるんだよ。エアガンで撃たせてほしいとか言われて、ほんと無理だった。ほら、街で猫とか子供とかを撃ってる変質者がいるって噂、聞いたことない? あれ、川崎がやってたらしいよ」
その話は、聞いたことがあった。三年くらい前に、変質者が出るからひとりで下校するなと、通達がきたのも覚えている。
「郷原さんが川崎なんかと合うはずがないんだよ。縁切ってくれてよかった」
そこで、ぼくは不意に気づいた。
考えてみたらこれは、一番知りたかったことを、聞けるチャンスだ。
「郷原さんと公輝くんって、仲が悪いんですか」
会話の流れに手を突っ込むように、ぼくは聞いた。
「郷原さんと公輝くんは仲が悪くて、弟を虐待したりしてる。そういう話ってありますか?」
「はあ? 何それ。どこから聞いたの」
「そういう現場を見たことがある人が、いるらしくて」
「人違いじゃない? 別に仲よくはないけど、そんなこと絶対にないよ」
レナの答えに、ぼくは拍子抜けした。
「公輝くんがどう思ってるか知らないけど、郷原さんは弟を可愛がってる。郷原さんが金に執着するのって、公輝くんを支えようとしてるところもあると思うしさ」
「郷原さんが、髪の長い子供に暴力を振るってたって話を、見てる子がいるんです。それが公輝くんなのかと思って」
「なんだよそれ、郷原さんは児童虐待なんかしないよ。公輝くんもずっと短髪だし、人違いでしょ」
欲しかった言葉が出てきた。
似顔絵アプリで作ったあのアバターと、公輝は雰囲気が似ていた。郷原が公輝を荒川で虐待していて、そのときの彼の髪型が女子と間違えるくらいの長髪だったなら〈子供〉だった可能性はある。だけど、短い髪をすぐに伸ばすことはできない。
「とにかく、もうあたしたちには触らないほうがいい。判ったね?」
「……判りました」
じゃあなと言って、レナは去っていく。ぼくは軽くため息をついた。
見つかりかけていたように見えた〈子供〉は、また闇の奥に消えてしまった。
手がかりが消えたことに、ほっとしている自分がいる。醜い感情から目を
明日は、真夜と一晩を明かす。いまはとりあえず、そのことだけを考えればいい。
4
翌日は、朝から雪だった。
天気予報では一日晴れるはずだったのに、海のほうで低気圧が突然発達したらしい。明日の朝までじりじりと雪が降り、空は雲に覆われ続けるのだという。
放課後の河原は、薄雪が積もっていて白くなっていた。いつもは一面の緑に覆われた芝生が真っ白になっていて、赤いパーカーが一輪の
「残念だなあ」
真夜は体育座りをして、川を見つめていた。雪が川に次々と吞み込まれ、下流に流されていく。美しいけれど、今日を楽しみにしていた真夜にとっては残酷な光景だ。
「この雪は、夜になったらやむの?」
「いや、やまないって」
「そうだよねえ……」
ぼくのせいではないのに、落胆をする真夜を前に、非情な宣告をしている気になる。天体観測という口実が使えなくなった以上、夜に家から出るわけにはいかない。
ぼくは学校から持ってきた新聞紙を敷いて、その上に腰を下ろした。
「寒いよ、大丈夫?」
「大丈夫」
本当は寒い。でも、真夜に喜んでもらえるなら、これくらいはなんでもない。
「本でも読もっか」
鞄の中から文庫本を取りだすと、真夜が身を寄せてくる。本に雪があたらないように傘を調整して、ぼくはページをめくりだした。
読書の時間は、貴重だった。本は映像と違って、読むスピードに合わせてめくっていかなければいけない。真夜に読ませるには、彼女がどんな速度で読んでいるのかが判らないといけないので、読書のお供はぼくにしかできない。
今日持ってきたのは、スティーヴン・ホーキングの『ホーキング、宇宙を語る』という本だった。「次」「めくって」真夜が声を出すのにつれて、ぼくはページをめくっていく。真夜の読書スピードは、速い。下手すると、ぼくが五行くらい読む合間に見開きの二ページを読み終えてしまったりしている。
読書って、空想に似ている。
映像と違って、文字の羅列から何をイメージするかは人によって違うし、それを共有することもできない。思い描いたものを絵に描いて説明したとしても、文章が頭の中に描くすべてのイメージ全部をシェアすることは絶対に無理だ。
ホーキング博士の本は、ブラックホールやビッグバン、空間と時間に素粒子と、難しい話題が次々と登場する。これでも入門書とのことだが、ぼくには何が書いてあるかよく判らない。
それでも、難しい本を読む時間は好きだった。真夜はぼくには理解できない文章を読みとり、何らかのイメージを自分の中に作っている。それはどんなに複雑で
「真夜?」
ぼくは異常を感じて、問いかけた。
いつもはすごいスピードで次のページを求める真夜が、さっきから黙りこくっている。
「知ってる? ホーキング博士って、タイムトラベルは不可能だって主張してたんだよ」
唐突に、真夜は呟いた。
「『時間順序保護仮説』って言ってね。この宇宙では、時間は一定の方向にしか流れないっていう説を生涯唱えてた。私も、同意見。宇宙の因果律が逆に流れたら、全部がめちゃくちゃになっちゃうから」
すでに何を言っているのか、ぼくには難しい。でも、口を挟めないほど真夜は真剣だった。
「ホーキング博士の説は、〈空想次元〉にも当てはまるよね。吉見くんはいま現在の色々な世界を見ることはできるけれど、未来や過去を見ることはできない」
「うん。それがどうしたの?」
「私は、過去に戻ることはできない。あの、川に落ちる前には」
真夜がこんなことを言うとは思わなかった。いつになく、彼女の声が沈んでいる。
「私、一度死んだんだよね。〈空想次元〉に留まれなかったら、あのまま死んでた」
死。
ぼくと真夜を分かつ、黒い川。
「死ぬと、どんな風になるか、吉見くんには判る?」
「突然、何も感じなくなる、とか? それがどういう感じかは、よく判らないけど」
「私が体験した死は、嵐みたいだった」
真夜は目をつぶる。ぼくは、本を静かに閉じた。
「川に落ちてよく判らなくなったあと、私は嵐に吞み込まれた。ものすごい力にめちゃくちゃに振り回されて、それが何時間も続いた。たぶん、あれが死だったんだ」
「意識があったってこと? 肉体が死んだのに」
「いまの私にも肉体はないよ。これは仮説だけど、たぶん私たちの意識って、もっとその辺に遍在しているものなのかもしれない。そっちの次元に生きているときは、肉体にそれを留めることができる。でも、死ぬとそれが解放されて、嵐みたいな現象の中に吞み込まれて、ひたすらその中を引きずり回される」
考えただけでつらそうだった。死とは、そんな
「嵐に吞み込まれている最中、私はいつかこれに慣れるんだろうなって思った。人間が重力に引っ張られてても何も感じないように、いつか嵐に巻き込まれ続けることに慣れて、それが当たり前になるんだって。何も考えない、何も感じない、そういうことができるようになって、すべてを忘れて、バラバラになって、宇宙を漂い続けるんだなって」
「また別の人間に生まれ変わったり……そういうことも、あるのかな」
「判らない。でも、バラバラになったあとにそんなことが起きても、もうもとの私じゃない」
何を言えばいいのか判らなかった。真夜は、なんでこんな話をしているんだろう。
「でもさ、関係ないじゃん、死なんて」
重い空気を吹き飛ばすつもりで、ぼくは、気軽に言った。
「真夜は死なない。〈空想次元〉の中で、引力から自由になって生き続ける」
ぼくはあたりを見回す。
「ぼくには見えないけれど、そっちの次元にはほかの人もいる。みんな自由に生きていて、友達と交流したりしてる。真夜がもう嵐に巻き込まれることはない。そうだろ?」
真夜は目を開けた。
死の世界を覗いてきた人間の、暗い目だった。
「いないよ、ほかの人なんて」
心が、砕ける音がした。
「いない? だって前は、そこらに人がいるって……」
「噓だよ。吉見くんたちを安心させるために言っただけ」
「どうして? なんで、そんな噓を?」
言葉がきつくなってしまう。真夜はごめんね、と呟いた。
「引力から解き放たれたら、私は死ぬ可能性がある。正直に言ったら、〈子供〉を捜してくれないかもしれない。そうでしょ?」
「それは……」
「私も、そんな酷なことは頼めない。私を殺すための調査なんて」
「なんで……どうしてそこまでして〈子供〉を見つけたいの? だって、死ぬかもしれないのに……」
「ここに取り残されるより、マシ」
真夜は雪に覆われた河原を見る。
「吉見くんが友達じゃなかったら、私はどうなってたんだろう。そんなことをたまに考えて、心の底からぞっとする。こっちからはみんなのことが見えるのに、触ることもできない、声をかけることもできない。おなかも
「でも、もう大丈夫だよ。真夜には、ぼくがいるから」
「吉見くんが、突然能力を失ったら?」
ぼくに降りかかる雪よりも、冷たい口調だった。
「吉見くんの〈力〉は、いまの科学じゃ説明ができない。どういう原理で成り立ってるか判らないんだから、ある日突然なくなってもおかしくない。全然大丈夫じゃないんだよ。私はその瞬間に、誰とも話すことができなくなる。
「大丈夫だよ。
「吉見くんがもし、車にはねられでもしたら?」
安易な反論を寄せつけないように、真夜は論理の壁を作る。
「ご両親が何かの理由で引っ越しをしたら? 高校や大学で地方に行っちゃったりしたら? 私はそれだけで、全部を失うんだよ」
「ここにいるよ。大学に行っても就職をしても、ぼくは笹倉から出ない」
「吉見くんが、私のことなんかどうでもいいと思うようになったら?」
「そんなこと、思うわけがない」
「本当にそう?」
真夜は疲れ切ったみたいに目を伏せた。その目に何が映っているのか、ぼくにはよく判る。
涼子だ。自分に
「吉見くんだって歳を取る。四十歳、八十歳、百歳になってもここにきてくれる? 変わらないって、誓うことができる?」
真夜は、体育座りをしている
「もし変わらなくても、吉見くんはいずれ死ぬ。私は、死ぬこともできない……」
ぼくは思わず、真夜の肩を元気づけるみたいに叩こうとした。
でも、駄目だった。ぼくの手は、彼女の肩を素通りするだけだった。
──真夜は、強い。
河原で再会してから、そのことにずっと驚いていた。自分が死んでしまって、こんなところに取り残されているというのに、真夜は明るく前向きだった。それどころか、死の原因になってしまった〈子供〉のことを案じていて、いまの境遇を抜けだそうとパワフルに頑張っていた。そう思っていた。
違う。それは、違った。
真夜は、ずっと怖かったんだ。
どうしてそんなことも判らなかったんだろう。いくら真夜だって、ぼくと同じただの中学生だ。わけも判らないうちに死んで、意味も判らずにこんなところに取り残されて、平気なはずがないじゃないか。
ぼくは、真夜が強いと思い込みたかったんじゃないのか。真夜はなんでも乗り越えられるタフな人間で、どんな境遇に陥っても前向きに生きられる。そんな風に決めつけたかったんじゃないのか。
ぼくが、安心するために。
ぼくが、真夜のことを重荷に感じないために──。
「ごめん、こんな話をするつもりじゃなかったんだ」
気がつくと、真夜が顔を上げていた。
「今日の夜が駄目になっちゃって、ちょっとネガティブになってた。いきなり重い話をしちゃって、ごめんね」
謝ることなんかないのに、真夜はぼくを安心させるみたいに、気軽な口調になる。
「案外、上手くいくかもしれない。〈子供〉の無事が判ったら、私は空を飛んで、あちこちに行って、いままで見られなかったものをたくさん見る。そういう生活が待ってるかもしれない」
「さっきと言ってることが全然違うよ」
「私たちは、この世界のことを何も知らない。なら、
ささやかな、可能性──。
幾度となく真夜が口にした言葉が、こんなにも絶望的に響くなんて。
「前に進もう。この宇宙では、時間は戻らないんだから」
すべてを
▶#25へつづく
◎後編の全文は「カドブンノベル」2020年9月号でお楽しみいただけます!