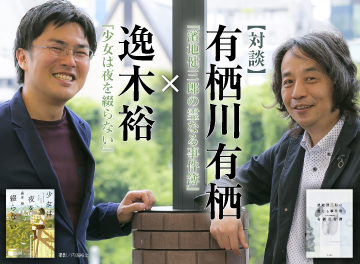【連載小説】教室で一人、奇妙な格好をする少年。彼の目的は――? 少女の死の真相は? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#7
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
2
〈だから、これから、吉見くんを研究させてもらう。いいよね?〉
空想クラブは、真夜のそんな一言からはじまった。
最初はクラブなんてものじゃなく、真夜がひたすらぼくにつきまとっていただけだった。真夜は〈ハンター〉の目を向けて、ぼくを質問責めにした。
実際に見たことがない景色も、見えるのか。
過去に見たものを色々組みあわせて、新しいビジョンを作りだせるのか。
過去は見える? 未来は?
見える範囲は? 深海の底や、火山の火口みたいな、人が立ち入れないところは?
ものが突然見えることがあるらしいけど、その頻度は? 空想は、見たいときにいつでも見られるのか? 体調は影響しないのか──?
尽きることのない真夜の好奇心を制限なしで浴びるのは、きつかった。ゴールの決まっていないマラソンを、延々と走らされている感じだ。ぼくの言葉を書き留める真夜のノートは、文字を盛った器をぶちまけたみたいにぐちゃぐちゃに埋まり、これだけの言葉が自分の中から引きだされたんだと思うと、大量の血液を抜かれたようにクラクラとした。
〈お前ら、いつも何やってんだ?〉
周囲のクラスメートは真夜につきまとわれるぼくを気の毒そうに見ているだけだったけれど、中には興味を覚える子もいた。例えば、隼人だった。真夜が説明をすると〈あんまりしつこいと駿も迷惑だぜ〉と軽くたしなめてくれた上で、真夜の研究に関心を持ったようだ。
〈いままで駿の話は冗談だと思ってたけど……真夜が本気なのを見ると、本当な気がしてきたな〉
隼人は柔軟な思考で、そう考えたようだ。それからちょくちょくと、行動をともにするようになった。
隼人が加わることで、周囲のぼくたちを見る目はガラリと変わった。吉見と久坂は、何か面白いことをしているらしい。みんな、期待を持ってぼくたちに接するようになってきた。
空想クラブ。
真夜はある日から、集まりのことをそう呼びだした。
人数が増えるにつれて、空想クラブの形は変わっていった。最初のように、真夜がぼくにマシンガンのように質問を浴びせかけるだけの会じゃなくなっていた。
活動の中心になっていたのは、ぼくの空想だった。
〈見せてよ〉
その四文字が、合い言葉になった。誰かがぼくに、見たいものをリクエストする。ぼくはアマゾンの奥地や、エベレストの頂上や、マリアナ海溝の底を見て、何が見えるか、何が聞こえるかを問われるがままに答えていく。
〈力〉を封印して長かったので、最初は上手くいかなかったけれど、何度かこなしているうちに、できるようになってきた。ぼくが何を聞かれてもすらすらと答えるのを聞いて、みんなは光景を想像する。一冊の本を読むみたいに、ぼくの言葉から、見たいものを空想する。
みんなから〈見せてよ〉なんて言われるとは、思っていなかった。噓つき。薬やってる。気持ち悪い。白い目で見られてきたぼくの〈力〉が、みんなから求められる日がくるなんて。真夜のおかげで、ぼくの空想は、クラスのみんなに認めてもらえたのだ。
〈吉見くんの《力》は、シャルル・ボネ症候群ってやつだと思う〉
三ヶ月くらいが経って、真夜は結論を出した。
〈本物と同じくらいリアルに幻視ができるっていう症状が、あるみたいなんだ。そう考えると辻褄が合う。どこをリクエストしても答えが返ってくるのは、地名や過去に見た写真や映像から、イメージが湧き上がってるんだと思う〉
微妙に違う気がしたけれど、真夜が真剣に出した答えに口を挟むのも野暮な気がした。ぼくは〈そうかもね〉と、その結論を受け入れた。
真夜が調査を終えたころ、ちょうどブームも一段落した。本は読み終えたら本棚にしまう。みんな、ぼくという本をひと通り楽しんだのだ。
だけど、いつまでも本を読み続ける人もいる。最終的に、ぼくと真夜を入れて、五人のメンバーが残った。
ぼくたちは色々なことをした。ぼくの〈力〉の研究や、ぼくに空想をリクエストする時間もあったけれど、めいめいが好きなことをしていることも多かった。ぼくと真夜が話している横で、隼人が筋トレをしたり、涼子が音楽を聴いたり、スマホでゲームをしたり。それでいて、まとまるときは一致団結して、全員で遊ぶことも多かった。要するにぼくたちは、気が合ったのだ。
伊丹
「最近、圭一郎と話してた?」
翌朝、一時間目がはじまる前、ぼくと隼人は廊下を歩いていた。
「ぶっちゃけ、あんま話してないな。去年も今年も、クラス違うし」
「ぼくも圭一郎とはしばらく遊んでないなあ。似顔絵、描いてくれるかな」
「くれるだろ。あいつの教科書、覚えてるだろ?」
覚えている。圭一郎の教科書には、余白にびっしりと絵が描き込まれていた。
圭一郎は絵を描くのが好きで、何を頼んでも断られたことがない。無理難題を出すと燃えるタイプで、難しいお題になればなるほど挑みかかるように描ききってしまう。
そう、圭一郎は、絵が上手かったのだ。
それも、半端な上手さじゃなかった。小学校一年生のころからコンクールに入賞して、毎年のように全校児童の前で表彰されていた。
彼がコンテで直線を一本引くだけで、もうほかの人とは全然違う。圭一郎の線は生きているというか、曲線にしても直線にしても、どういう意図を持って引かれたのかを線自体が主張しているみたいな、明確な意志が発散されていた。
一方で、圭一郎は偏屈な人だった。
小学六年生のころ、埼玉県のコンクールで賞を取り、全校児童の前で表彰されたときのことだ。
片方の前足のない猫が広場を走り回っている絵だったのだけど、「障害に負けずに頑張っている猫の生命力が素晴らしい」という講評が気に入らなかったらしく、圭一郎は不機嫌そうに片手で表彰状を受け取って逃げるように壇の下に降りてしまった。「ぼくはあの猫が可愛いと思ったから描いただけなのに、そんな前向きなメッセージを受け取られてムカつきました」あとで先生にきつく怒られたらしいが、圭一郎は一歩も引かずにそう主張を繰り返したらしい。
孤独な、オランウータン。
ぼくの圭一郎への印象は、そういうものだ。
小さなころ動物園に行ったとき、猿山の反対側、通路を挟んだところにオランウータンの
圭一郎にも、そんなところがあった。クラスの児童たちがはしゃぎ回っているのを、少し離れた暗いところから静かに見つめている感じが。それは、絵の題材を探していたから、ということもあったのかもしれない。
でも、ぼくは、少し違う印象も持っていた。
「着いたな」
ぼくたちは、美術室の扉の前に立っていた。
一時間目がはじまる前、圭一郎は早めに登校して美術室で絵を描いていると、彼のクラスの子が教えてくれた。ぼくは隼人と頷きあい、引き戸をゆっくりと開けた。
「え?」「は?」
同時に、声が出た。
美術室の隅に、ぽつんと圭一郎が座っていた。絵を描いているのではなく、画集らしき大きな本を読んでいる。顔を上げ、薄い眼鏡の奥から、ぼくたちのほうを見た。
「何」
冷たい声を放つ。
圭一郎は、エスキモーの恰好をしていた。
昼休み。
ぼくと隼人は二人で二年B組を覗き込んだ。圭一郎は窓際の席にいて、そんな彼を好奇の目が取り囲んでいる。自由な恰好をしている東中の生徒の中でも、圭一郎の服装は明らかに異常だった。
朝と同じく、何度見ても彼が着ているのは、エスキモーの衣装だ。
焦げ茶色でぶかぶかの上下を着て、手にはミトンを
〈美術部の活動の一環だよ〉
朝の美術室で、圭一郎は面倒くさそうに言っていた。
〈ちょうどこれから、アラスカの自然を題材に絵を描こうと思ってる。異国の題材を描くには、きちんと文化の中に入り込む必要がある。昨日から、この恰好をして暮らすことにしてるんだ〉
圭一郎は当たり前のように語っていた。いまも冷やかすようなクラスメイトの真ん中で、ミトンをしたままパンを頰張っている。周囲なんか関係ないとでもいうような、強い意志をまとって。
その姿を見て、ぼくは胸がざわつくのを感じた。
「圭一郎」
前の席に腰掛け、隼人が小声で話しかけた。ぼくはその脇に立つ。
「今朝の話、どうだ。考えてくれたか」
「しつこいな。もう答えただろ」
「真夜が困ってるんだよ。お前の力が借りたいんだ」
「死んだ人間は困らない。誰の助けも必要としない」
「だから、真夜の魂だけがこっちに残ってるんだ。駿の〈力〉のことは知ってるだろ? こいつには真夜が見えるんだよ」
「いつから吉見はイタコになったんだ。
圭一郎は切れ長の目でぼくたちを
「真夜が言ってたんだ。駿の〈力〉は、別の世界にアクセスできる力なんじゃないかって」
隼人は、〈空想次元〉のことを話した。あらかじめふたりで復習してきたので、隼人の説明はスムーズだったけれど、圭一郎はそもそも聞く気すらないみたいだ。パンを食べ終え、紙パックの牛乳を飲みはじめる。
判ったよ、と隼人は話を打ち切った。
「じゃあ、真夜の件は信じなくてもいい。河原にきて、俺たちの指示通り似顔絵を描いてくれ。それならいいだろ?」
「嫌だよ」
「どうして。昔はよく絵、描いてくれてただろ」
「いま忙しいんだ。アラスカの勉強をしてて、放課後も時間がない」
「ならその勉強、ぼくが手伝うよ」
こういう流れになったときのために、ぼくたちはあらかじめ作戦を考えていた。
「絵を描いてくれるんなら、ぼくがアラスカの光景を空想して、圭一郎に伝える。何時間でもつきあうし、いつでも何回でも構わないよ。絵を描くのに参考になるだろ?」
「別に、吉見の〈力〉は必要ない」
にべもなく断られたことに、少し驚いた。
「自分の内面と対話して、湧き上がったイメージを絵に落とし込んでいく。そのためには、余計な情報は摂取しないことにしてる。吉見の空想を聞いちゃったら、それを模倣するだけで終わっちゃう。それじゃぼくの絵にならない」
「だって、アラスカの勉強をしてるんだろ?」
「実際の写真とかは見ないようにしてる。文化に触れて、自分のイメージを膨らませてるだけだ」
ぼくは隼人と視線を交わした。こんなことになるとは思っていなかった。圭一郎は空想クラブの中でも飛び抜けて〈見せてよ〉が多いメンバーだったからだ。ぼくの空想を味わい尽くして、それを自分の絵に昇華させていくのが、昔の彼だった。
「そもそも、吉見の〈力〉って本物だったのか?」
圭一郎が冷たく言い放つ。
「前は死者が見えるなんてことは言ってなかった。真夜が死んだタイミングで、どうして都合よく能力が増えるんだよ」
「それは、さっき隼人が説明したじゃない」
「もっと簡単に説明できる。吉見は小学生のころも、適当なことをベラベラ話してただけだった」
「おい、そりゃないだろ。あれだけ駿に空想させてたくせによ」
隼人が怒ったようにたしなめたが、圭一郎はフンと鼻を鳴らしただけだった。
──大丈夫だろうか。
ぼくは、不安になっていた。ぼくの知る圭一郎は、偏屈だったけれど、こんなに閉じた人じゃなかった。
ぼくの知る圭一郎は、絵が呼気のように循環している人だった。暇があると画集を眺め、空いているスペースがあるとそこを絵で埋める。空想クラブでもしつこくぼくに質問を続け、得たものを絵に落とし込む。圭一郎を中心に、インプットとアウトプットがぐるぐると回っていた。
いまの圭一郎は、そういう循環が全部滞って、ひたすら水たまりのように
「圭一郎、信じてよ」
真夜のためにも、ここで引くわけにはいかない。
「覚えてるだろ、〈稲妻の日〉のことを」
ぴくりと眉が動く。そう、あの日のことを、忘れるはずがない。
「あれを経験した圭一郎なら、ぼくの〈力〉が本物だって、判ってるはずだよ。違う?」
「さあ、よく覚えてないな、そんなの」
「どうして噓を言うんだよ。ぼくたちは、あの日──」
勢い込んで言ったところで、昼休みの終わりのチャイムが鳴った。圭一郎はしっしっとミトンを嵌めた手を振る。
「小瀬ー、吉見ー。もう昼休み終わってるよ。早く自分のクラスに戻りなさい」
B組の担任の
その目が、剣先を突きつけるみたいに、圭一郎に向いた。
「伊丹、昼休みに着替えろって言ったよね」
「言われはしました。それを聞くかどうかはぼくの自由です」
「判った。放課後、職員室にきなさい」
東中では基本的に自由な服装が許されているけれど、圭一郎のそれはどう見ても「基本的に」のラインを越えている。ルールを悪用する人が出てきたら、もっときつい制限をかけなければならなくなるだろう。岡本先生の怒りの中には、どうして上手くやらないんだという
「はい、判りました」
ニホンザルに何を言われても平気だと、オランウータンがうそぶくみたいに。
▶#8へつづく
◎前編の全文は「カドブンノベル」2020年8月号でお楽しみいただけます!