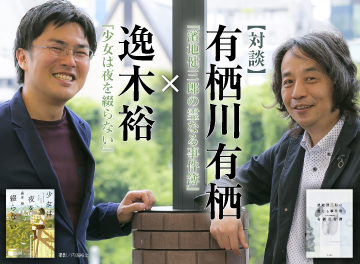【連載小説】謎を追いかける真夜。辿り着いた涼子の「真実」とは? 少女の死の真相は? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#27
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
*
甘い果物の匂いがした。
暖かくてカラッとした風が、ぼくの身体を撫でていく。いい風だ。陽の光の、一番柔らかい部分にくるまれているみたいに、気持ちがいい。
「のぼせるねえ」
ぼくの隣には、真夜がいた。赤いパーカーとジーンズじゃなく、アロハシャツに半ズボンという男子みたいな恰好だった。いまよりも背が低くて、顔もだいぶ幼い。小学生のころの真夜だ。
時間が、戻ったんだ。なんだ、ホーキング博士は間違えてたんだな。
真夜の後ろから、ぞろぞろと人がやってくる。
「暑いけど、暑くねえな。不思議な感じ」
「本土とは植生が違うだろうから、面白い絵が描けそうだ」
「いい匂いだねー、真夜」
隼人と圭一郎と涼子は、それぞれに感想を言いながら歩いてくる。そうだ、ぼくはこういうことがしたかったんだよ。空想クラブのみんなと一緒に宮古島にきて、コバルトブルーの海で泳いだり、海ぶどうやソーキそばやマンゴーを食べたり、陽のあたる軒先で昼寝をしたり。
「宮古島の星空は、綺麗だよ」
みんなで、星空観察をしたり。
「この島は、夜になると暗いから。埼玉で見る空とは、比べものにならないよ」
「そっかあ。それは楽しみだなあ」
真夜は手を後ろに組んで、ふふっと笑った。
「でも、いつか見たあの星空も、綺麗だったよね」
「いつか?」
「ほら、あの
真夜が手を振ると、あたりの景色が一変した。
南国の光に満ちていた空が、夜に落ちた。ぼくたちは泊まっているホテルの庭にいて、大勢の生徒があたりに溢れていた。テンションが上がってその辺を走り回っている子もいれば、双眼鏡を持っている子もいる。
真夜は星座早見表を持っている。それと照らしあわせながら、何かを計測するみたいに空を見つめている。
「
真夜は圭一郎と話していた。
「彫刻室……って、何?」
「美術室みたいなもの? 一応、この部分が部屋で、こっちの部分が彫刻らしいけど」
「ただの細長い六角形にしか見えないけどな。どっちかというとクジラみたいな形じゃない?」
「その上にあるのが、くじら座だよ。ほら、これ」
「これはクジラというよりオットセイだなあ」
「昔の人は想像力が豊かだったんだろうね。星の連なりから色々なものを想像してたんだ」
「それ、想像力っていうの? 線を見て何かを適当にでっち上げるのなんか、誰でもできると思うけど」
「細かいなあ。伊丹くんのそういうクールなところ、嫌いじゃないけど」
傍で聞いている隼人が、ぷっと吹きだす。「あれでさ、意外と気が合ってんだよ、あいつら」その横では、涼子が嬉しそうに笑っている。
なんだか、星座みたいだな。
「どうしたんだよ、駿」
隼人がぼくを見ている。それだけじゃない。涼子も、圭一郎もぼくのことを見ている。
「さっきから黙っちゃって。調子でも悪いのか」
「吉見なんかマイペースなんだから、ほっとけばいいよ」
「マイペースなのが吉見くんのいいところだと思うけど」
真夜も、ぼくのことを見ていた。星座早見表を掲げて、手招きする。
「よかったら星座、教えてあげるよ? 一緒に見ない?」
こんな夜を、ぼくはこれから何回迎えられるだろう。星の数ほどにものすごい大勢の人間が地上にいるこの地球で、こんな風に、大切な人とつながることができる夜を。
星がばら撒かれた空を見た。ぼくたちの関係は、たぶんこの星空ほど確かなものじゃない。ぼくたちはいずれ、バラバラに人生を送るようになる。そのうち誰かが病気になったり、遠くに行ったりしてしまうこともあるだろう。人類が生まれるずっと前からこの星空があり続けているのに比べて、ぼくたちはとても
現実は不可逆で、唐突で、いつでもぼくに襲いかかって引きずり回す。ぼくはその気まぐれな怪物が許してくれる範囲で、なんとか生きているだけだ。
いつまでも、こんな夜が続けばいいのに──。
ぼくは心の底から願いながら、星空を見続ける。
目の前に、黒く影の落ちた灰色が見えた。駐車場の、アスファルトの色だった。
ずいぶん前から、目は覚めていた。でも、気づかないふりをしていた。
郷原たちはもういなくなっていて、さっきまでバイクがあった場所には何もない。取り巻きの女子たちの姿もなくて、涼子だけが残って介抱をしてくれるなんて都合のいい話もなかった。
雪が降っている。身体が氷みたいに冷えている。ぼくはどれくらい気絶していたんだろう。一分のようにも、一時間のようにも思える。
もう一度あの夜の中に飛び込みたかった。でも、全身に電気みたいに走る痛みがそれを許してくれない。
雪で冷やされたアスファルトが、ぼくの痛みを少し和らげてくれる。それが唯一の救いみたいな感じがして、ぼくは地面に頰をこすりつけた。
遠くから、誰かの声がする。ぼやけた視界の隅で、薄く白い光が点滅する。現実から入ってくる新しい情報がうざったくて、ぼくは目を閉じた。痛みだけが、ぼくの世界に残った。
うるさい。
声も光も痛みも、全部うるさい。もっと静かな場所に行きたい。もっと暗くて落ち着ける場所に。
でも、そんな願いすらも、この現実が
5
幸い、ぼくの怪我は軽傷だった。
あのあと、ぼくはパトロールをしていた警備員さんに見つけられて、ショッピングモールの医務室につれていかれてから救急車で近所の総合病院に運ばれた。
病院では脳の検査やらなんやらつれ回されたけれど、骨にもどこにも異常がなく、軽い打撲程度で済んだ。〈よかったねえ、殴り慣れてるやつだったのかもねえ〉というお医者さんのデリカシーのない言葉に、連絡を受けてやってきた母さんが怒って詰め寄っていた。
翌日。ぼくは、河原へ向かう道を歩いていた。
薄く積もっていた雪はすっかり溶けて、いつもの景色が戻っている。平日の昼間に、学校じゃない外にいるのは、小学生になってから初めてかもしれない。でも、そんな非日常の興奮は、ギシギシと鳴る痛みの中に吞み込まれてしまう。
土手を越えて、反対側に出る。薄く白い雲がかかっている冬の空の下、真夜は寝っ転がって上を見ていた。
「真夜」
少し離れたところから声をかける。真夜は身体を反らせて、首でブリッジをするみたいにしてぼくを見た。
「ひどい遅刻だなあ、十二時間以上遅れてるぞ、吉見駿」
「ごめん」
「どうしたの? 何かあった? 夜に出かけようとして、お母さんに見つかっちゃったとか」
「なんでもない。ごめん、約束破っちゃって」
「本当だよ。これないなら、一言これなくなったって言ってほしかったな。寂しかったよ、一晩中」
殴られて病院に行ったことは言いたくない。絶対に勝てるカードを出して、相手に怒りの矛を収めさせるのは、
目が合った。真夜はガバッと、素早く起き上がった。
「怪我してるの?」
真夜の観察力の前には、ぼくの気遣いなんか何の役にも立たない。
「ほっぺたが
言い訳をする前に、真夜はどんどん理由を見つけてしまう。ぼくはそれを見ていることしかできない。
「何があったか、教えてくれない?」
「うん……」
こういう話になることを、ぼくは想定していた。だから、噓を用意していた。
エノルメを歩いていたら、突然変なやつに絡まれた。そして、因縁をつけられて、駐車場でボコボコに殴られた。幸い軽傷に終わって、今日は念のため休んでいる。
郷原の名前を出すつもりはなかった。それを出すと、涼子の名前も出さないといけなくなる。そんな話、いまの真夜に、聞かせたくない。
「そう……」
真夜はそれだけを言った。ぼくが下手な噓をついていることは、判っているのかもしれない。でも、それ以上突っ込んでこようとしない。
「まあ、生きててよかったよ」
「大丈夫だよ。ちょっと殴られたくらいで、大げさだな」
「判らないよー。私を見なさい」
「真夜の、何を?」
「人はいつ死ぬか判らない。あたりどころが悪かったらどうなるか判らないよ。私がそれを証明してるでしょ?」
「だから、そういうの、笑えないって」
ブラックすぎるジョークに突っ込むと、真夜がにしししと笑った。ぼくたちは、ごまかした。つらい現実をユーモアのゴミ箱に放り込んで、
──ん?
そのとき、胸の奥が、ぴくぴくと
何かを思いだしかけている。なんだろう。
「どうしたの?」
さっきまで笑っていた真夜が、心配そうな顔を見せる。昔よりは上手になったかもしれないけれど、やっぱり真夜は噓やごまかしが下手だ。すぐに本音が表れてしまう。
そんなことよりも。
そんな真夜の言葉が、ぼくの心の奥の何かと響きあっている。
〈人はいつ死ぬか判らない〉
「涼子だ」
その名前を口にした瞬間、真夜の顔が曇った。ぼくの顔を、心配そうに覗き込む。
「やっぱりそれ、涼子たちにやられたんだね?」
真夜はとっくに、ぼくをやったのが郷原だと気づいていたんだろう。でも、ぼくが言いたいのはそのことじゃない。
「ちょっとおかしなことに気がついたんだ」
「おかしなことって?」
「ほら、最初に真夜と会ったとき、涼子が変なことを呟いてたって言っただろ?」
告別式のときだ。
真夜は、去年死んでいた。涼子はそんなことを言っていた。
「でも、そのあと涼子と何度も話したけど、そういう話は二度としなかった。涼子は、真夜が最近事故で死んだという前提で話してた」
〈真夜は死んだよ。葬式もやっただろ。何考えてんだよ〉
〈いきなり、何? 現場に郷原さんがきたからって、なんなの?〉
涼子は何度も、真夜が川の事故で死んだと話している。
じゃあ、あの告別式の言葉はなんだったんだろう?
「確かに……」
真夜は口に手を当てて、黙り込んだ。ぼくへの心配が吹き飛んでいることに、胸を撫で下ろす。これ以上、怪我の話なんか続けたくない。謎を見つけた〈ハンター〉は、
「そもそも、吉見くんと涼子は、なんでそんな話になったんだっけ?」
ええと……と口ごもりながら、ぼくはあのときのことを思いだす。
「真夜の告別式で、涼子と会ったんだ。ぼくは涼子に、最近真夜と会ってたのか、会ってたならどんな感じだったのかって質問してた。そしたら、涼子が突然言った。真夜は、事故で死んだんじゃない。去年なくなってたって」
「でも、涼子は、私が事故で死んだと思ってる」
「うん。ぼくの聞き違いだったのかもしれないけど」
「そんな聞き間違い、あるかなあ」
ぼくは思いだした。
確かあのときは、真夜の死因の話をしていた。いまでもそうだが、世間的には、真夜は光害調査をやっていて、その最中に足を踏み外して川に落ち、死んだことになっている。
「真夜がこんな事故を起こすなんて思わなかったって、ぼくは言った。何かに夢中になってる最中に足を踏み外すのも、真夜らしいなって──ごめん、無神経なことを言って」
「いいよ。そのあとに、涼子は言ったんだね」
〈真夜は、事故で死んだんじゃない。去年もう、なくなってたのに。噓なんだよ〉
「どういうことだろう……」
真夜はすっくと立ち上がった。
「告別式から時間が経って、やっぱり事故で死んだと思い直したのかもしれない。でも、少なくとも、そのときの涼子は、私が事故で死んだんじゃないと思ってた」
「何か事件に巻き込まれたと思ったのかな?」
「根拠もないのに、そんなこと思うかな? 私が自殺なんかするわけはないし、なんで涼子は最初、事故じゃないと思ってたんだろう?」
顎に手を当てて、その場をくるくると歩きはじめる。
真夜のこんなところを、また見られることが嬉しかった。謎を追いかけるように、その場を歩き続ける真夜。その姿を見ていると、思わず顔がほころんでしまう。
「去年なくなってた。どうして去年? 去年、何があったっけ。それに、〈噓〉って……」
ぶつぶつと呟く。いつも外界の観察に向けられているその目は、自分の内面を覗き込むように、虚空の一点を見つめている。
真夜は空を見上げた。そのまま白い空を眺めていたと思ったら、突然、軽くジャンプした。
「星座、だ」
「え?」
「誕生星座だよ」
何かに気づいたみたいに、真夜は小刻みに頷く。真夜の頭の中で、イメージが作り上げられていくのが判る。ぼくにはそれを見る
「吉見くん。私、勘違いしてた。涼子に謝らなきゃいけないことを」
「は?」
「私、淳子にひどいことを言っちゃったんだ……」
何かの結論にたどり着いたみたいだった。でもそこには、前に圭一郎の問題を解決したときのような、晴れやかさはない。
真夜は、深刻な目をしていた。苦しそうに唇を引き結んで、ぼくを見つめる。
「またひとつお願いしたいことがあるんだけど、いいかな?」
▶#28へつづく
◎後編の全文は「カドブンノベル」2020年9月号でお楽しみいただけます!