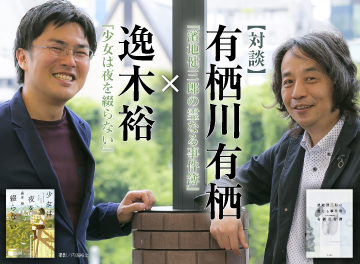【連載小説】溺れてはいなかった――? その夜、仮説は覆される。少女の死の真相は? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#15
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
2
夜の河原は、思いのほか暗かった。
マンションから漏れる光が、サイクリングロードのあたりまでを薄く照らしている。でも、その奥の河川敷に入ると、一気に視界が悪くなる。
闇は、有機的だ。
ただの味気ない黒じゃない。闇の中には川や虫や草むらの影が溶け込んでいて、複雑なひとつの生命体みたいになっている。遠くから聞こえる川の音が、ぼくたちを招く不気味な音楽のように、絶え間なく鳴り続けている。川を挟んだ両側にマンションが建ち並び、空を煌々と照らしているけれど、その間の空間だけが谷底のように闇に落ちている。
真夜は、ずっとこんなところにいるのか。
「どうしたんだよ。行くぞ」
隼人は何事もないように川に向かって歩いていく。隼人の勇敢さに引け目を感じつつ、ぼくはその背中に続く。
「真夜ー。いるかー」
川のほうで、何かが動いた。
真夜の手だった。川を向いて体育座りをしていて、右手だけがすっと伸びている。
真夜は、空を見上げていた。
空は、笹倉セントラルパークのものよりも若干明るい気がする。両岸にあるマンションから出る上方光束比の高い光が、空に漏れ光を
〈あのころは空も暗くて、星が綺麗に見えてた〉
幼いころ、涼子と一緒に見た空のことを思いだしているのだろうか。真夜はぼくたちのほうを見ようともしない。
「夜空って、見てて飽きないんだよね」
いつもの口調じゃない。夜に酔っているみたいに、真夜はとろんとしていた。
「同じ本をずっと読んでたら飽きるし、すごい絵だって何時間も見続けられない。でも、夜空だけはいつまでも見ていられる。なんでだろうね」
「……さあ」
「私の仮説はね、夜空は、めちゃくちゃ綺麗だから、だと思う」
単純なことだよ、と真夜は言った。
「夜空には、見ても見ても飽きないくらいの膨大な『綺麗』が詰まってる。この空は、最初の人類が見上げたころからほとんど変わってないはずなのに、たぶんその間ずっと見ていたとしても、私は飽きないと思うんだ。こんなにも白んだ空であっても」
真夜にしては幼稚な理屈だ。論理の鬼みたいな彼女がこんなに崩れたロジックを唱えているあたりに、夜の魔力を感じた。
「星空ってね、タイムマシンなんだよ」
「タイムマシン? どういうこと?」
「例えば……冬の大三角形ってあるでしょ。プロキオン、シリウス、ベテルギウス。三つは同じ空、同じ平面にあるように見えるけれど、それぞれ地球からの距離が全然違う。シリウスは八・六光年離れてるから、あの光は八年前、私たちが小学校に入る前くらいに生まれたものがいま見えてるの。プロキオンは十一・四六光年だから、二歳か三歳のころの光」
真夜はオリオン座のほうを指差す。
「でも、ベテルギウスだけは、六百四十二光年も離れてる。
白く濁った空の中、明るい星が点々と存在している。全然違う場所の、全然違う時間に生まれた光たちが、いま集結してひとつの夜空を形成している。
数え切れないほどの時間が空に溶け込んで、混ざりあっている感じがした。いままで何気なく見ていた夜空が、ものすごく複雑に、多層的に見える。
「ね、タイムマシンみたいでしょ」
真夜は、ぼくに笑いかけた。
とくんと、心臓がはねた。
真夜が、いつもよりも大人びて見える。
真夜は、ぼくとは違う風に世界を見ている。夜空を見るにしても、ぼくが考えもしなかった情報を同じ空から読みとっている。長い時間をかけてたくさんのものを観察してきた真夜は、ぼくが見つけられていない色々なものを、この世界の中に発見しているのだろう。
真夜の目には、この世界がどんな風に見えているんだろう。それはぼくが見ている世界よりも、どれほど豊かなんだろう。
胸がドキドキする。なんだろう。真夜の知らなかった一面を見られたことが、なんだか苦しい。
隼人に話しかけようと思ったが、彼はリュックを置いてどこかに行ってしまっていた。夜の河原に、ぼくたちふたりしかいないみたいだ。心臓の音が聞かれそうで、ぼくはゆっくりと呼吸をしてそれをなだめた。
「真夜、怖くないみたいでよかったよ」
雑談を装うように言った。
「怖い?」
「だってここは暗いし、ひと気がないだろ。怖がってるかと思って心配してた」
「怖くないよ。この身体だと、猛獣がきても殺人犯がきても絶対に安全でしょ」
「それはそうかもしれないけど」
「むしろ、こんなにじっくりと夜空を見られる機会がなかったから、それを味わってる。この身体は眠くならないから、ずっと起きてられるしね。昼間は退屈だけど、夜は楽しいよ」
真夜は鳥のように、空全体をゆったりと見渡す。
「私、暗いところは怖くない。でも──この空は、怖いかな」
甘く酔っていた声に、少し影が差した感じがした。
「どういうこと? さっきは綺麗だって言ったのに」
「例えば──私たちが肉眼で見える一番遠い天体って、何だと思う? ハッブル宇宙望遠鏡を使っちゃ駄目だよ」
「ええと……アンドロメダ銀河?」
正解、と真夜は微笑む。昔、理科の授業でやったのを覚えていた。
「私たちはいま、太陽を中心にした太陽系ってところにいる。で、こういう恒星系とかガスとかダークマターとかが交ざって、銀河を作ってるわけね。宇宙には私たちの住む
「気が遠くなるような長さだね」
「長い? まさか。すぐそこだよ」
真夜の声に、少し挑発的な色が混ざった。
「私はいま、二十メートルしか動けない。それに比べたら地球ははるかに大きくて、赤道を回るか、極方向に回るかで誤差はあるけど、一周大体四万キロある。私の動ける距離の百万倍くらい」
その場で計算をしているというより、何度も反復して考えたせいで反射的に出てくる感じだ。
「その地球は、太陽系の中にある。地球上の生物が生きていられるのは、太陽が熱や光をくれるから。私は神様は信じてないけど、我々の命を握ってるって意味では、太陽は神様みたいなものかもしれない。その直径は、地球の百九倍」
と言われても、大きさが上手く想像できない。まだまだ行くよという感じで、真夜は続ける。
「でも、そんな神の化身だって、天の川銀河全体では
「千倍?」
「そんな恒星が、天の川銀河の中には二千億個くらいある」
どんどん膨らんでいく数にクラクラとする。だが真夜はまだ止まらない。
「このくらい大きな銀河が、宇宙にはいくつあると思う?」
「さあ……一万個くらい?」
「いま言われているのは、二兆個」
「えっ? 兆?」
「しかも、この宇宙の外には、別の宇宙があるって説もある。そこまで行くと、もう観測する方法すらない。宇宙がほかに、百兆個あってもね」
真夜は、怖いくらいに真剣な表情になっていた。
「この宇宙の主役は、生物じゃない。ガスとか、金属とか、岩とか、元素とか、ダークマターとか、ダークエネルギーとか、
真夜には珍しく、シニカルな意見だった。真夜には、こんな顔もあるのか──。
「宇宙の果てって、あるんだよ」
真夜は空の上を指差す。
「私たちは、四つの系外銀河しか見ることができないけど、その奥には二兆個の銀河があって、そのさらに向こうには、宇宙の果てがある。人類がこの先滅亡を回避して、資源が枯渇する前に地球の外で活動できるようになったとしても、宇宙の果てなんて遠すぎて、私たちは永遠にそれを観測できない。でも、それはいまも確実に、空の
真夜はふっと微笑んだ。今日の真夜は、色々な顔をする。未知の世界に挑みかかるその笑みに、また胸がドキドキした。
「よっと」
真夜が立ち上がりぐっと背伸びをする。筋肉の疲れなどないはずだけど、癖なのだろう。
「スカートが嫌いでよかったな。パンツじゃなかったら、こんな風にフランクに座ったりできないもんね」
真夜はものを受け取るように手を伸ばした。
「写真、撮ってきてくれたんだよね。見せてくれる?」
「あ、うん」
隼人は、相変わらず姿を見せない。リュックが地面に置かれている。
「
目を凝らすと、川辺を歩いている隼人の影が見えた。ぼくは仕方なく、リュックを
写真を切り替えながら──ぼくは、自分でも判るほどに上の空だった。真夜の言葉を聞いてから、ぐるぐると頭の中が回っている。
ぼくはいままで、空を本当に見ていたのだろうか。
例えば、
悔しさが心の奥ににじみ出てくる。何が悔しいのか、よく判らない。夜空の奥を見ようとしなかった自分に対してだろうか。真夜のようなことが考えられない、出来の悪い頭に対してだろうか。
もっと早く、真夜とこういう会話がしたかった。そのことが悔しいのだろうか。
モニタの光に照らされて、真夜の顔が浮かび上がっている。大きな眼鏡の奥、昔と変わらない〈ハンター〉の目がすぐそばにあることに、ぼくはまた胸が苦しくなった。
「どうしたの? 次見せてよ」
真夜が小石を飛ばすように言う。ごめんと言い、ぼくはボタンを押す──。
「わっ!」「きゃっ!」
ふたり同時に声を上げた。
いつの間にか、隼人がそばに立っていた。モニタのバックライトに浮かび上がったその顔は、陶器の作りもののように白い。
「なんだよ、脅かすなよ。真夜もびっくりしてるよ」
「悪い。身体が冷えちまってさ。ちょっとぼーっとしちまった」
「冷えた?」
「ああ。川に入ってた」
足元を見ると、ジーンズの
「水温はたぶん十度前後だな。うちのウォーターサーバーの水温が十度なんだけど、同じくらいだった」
「危ないよ、隼人。足滑らせたりしたら、流れに
「俺がそんな下手打つかよ。あ、真夜のことを馬鹿にしてるわけじゃないからな」
隼人は、川のほうを指差した。
「例の〈子供〉があの川で何をしてたか、考えてたんだ。真夜さ、その〈子供〉が
「えっと……たぶん、三メートルもなかったと思う」
「川岸から顔が見えたなら、まあそのくらいか。でも、いま五メートルくらい奥に入ってみたけど、水深が深いところでも俺の膝丈、五十センチくらいしかなかった。川が深くなるのは、もっと先だ。そんな浅瀬で溺れるなんて、変じゃないか」
「小瀬くん、それは違う。足がつく深さでも、溺れることはあるよ」
真夜の言葉を隼人に伝えると、判ってるという風に両手を挙げた。
「小学生のころ水泳やってたから、判るよ。人は三十センチくらいの深さでも、溺れるときは溺れる。ましてや、川の危なさはプールとは次元が違う」
「じゃあ、それだったんじゃないの?」
「そう説明をつけると、別の問題が出てくるんだよ。浅瀬で溺れるくらいパニックになってたのに、なんで〈子供〉は助かった?」
確かに……と、真夜が
「耳の奥に、
「真夜の身体にしがみついて、なんとか助かったとか」
「真夜が助かったんならそれも判るが、今回はそうじゃない。しがみついたまま、一緒に沈んじまうはず」
「さっきから、何が言いたいんだよ、隼人」
ストレートに聞くと、隼人の目が暗くなった。
「決まってるだろ。〈子供〉は、溺れてなかったんだ」
▶#16へつづく
◎前編の全文は「カドブンノベル」2020年8月号でお楽しみいただけます!