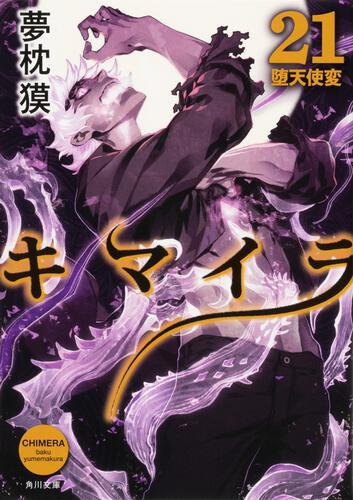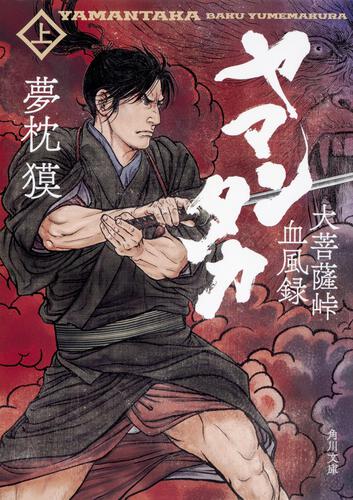遣唐使・井真成に降りかかる数々の試練。 旅に出た真成一行の行く手にあるものは? 夢枕獏「蠱毒の城――⽉の船――」#100〈前編〉
夢枕 獏「蠱毒の城――月の船――」

※本記事は連載小説です。
これまでのあらすじ
閉ざされた城内での殺し合いに参加した遣唐使の井真成は、仲間を得て試練を克服する。かつて城内では、人間を贄に使った呪法「蠱毒」が行われ、自分たちの殺し合いもまた蠱毒であったと告げられた。死闘を生き抜いた十二名を含む四十九名は、杜子春と共に旅に出る。一行が立ち寄った屋敷で、真成は呼び出され、この地に伝わる太公望の釣り鉤を探すよう命じられる。翌日、姿を消した陶友章の遺体が見つかるが、王菲は昨晩、陶友章の異常な様子を目撃していた。
二十二章 黄帝本紀
采薇歌
登彼西山兮
采其薇矣
以暴易暴兮
不知其非矣
神農虞夏忽焉沒兮
我安適歸矣
于嗟徂兮
命之衰矣
(一)
それを、何と呼んでいいのかわからない。
それを、国と呼べばいいのか、文化、あるいは文明、大陸と呼べばよいのか。このことについての、明確な答えは、おそらく、ない。
この海のような広大な地域では、歴史上、幾つもの名称の異なる国が生まれては滅び、滅んではまた生じたりしてきた。そして、何度となく、幾つもの名の違う国が同時に並んで存在してきた期間も、この土地にはあった。
ここでは、それら全てをひっくるめて、あえて国と呼びたい。
この国は、古い。太古から存在してきた巨大な脳のようでもある。その脳のシナプスの、無数の明滅や光芒のひとつずつが、幾千、幾万、幾千億もの物語としてこの地に生じ、そして消えていった。
そもそものことで言えば、あらゆる物語は、生命の誕生以前──この宇宙の創世の時から語り始められるべきだと考えているのだが、その物語を表現するものが、人が操る言語、言葉である以上、哀しいことに限界がある。原理原則から言えば、それは、その形式上、それがどれほど長大なものであろうと、それを語る人間の一生のうちに語り終えられるべきものであり、それを読む人間の一生のうちに、読み終えられるべきものであろう。あえてそれを一切考慮しないという書き方ももちろんあるであろうが、それも含めて、かようのことを思う時、物語を紡ぐ人間は、そのあまりの深み、混沌に立ちすくまざるを得ない。
物語を書き始める時、もしくは書きながら、そこまで考えずにはいられないというのは、これは、おそらく書き手としては少数派であろうし、書き手の有する変態的性癖であろうと、自分で自覚してはいるのである。
少なくとも、人類が二本の足で立ちあがり、二足歩行して、足を地に、頭部を天に所属させた時、空いたふたつの手で抱えていたのが、物語というものであったろう。
国の話にもどりたい。
この国の、物語という泉は深い。
あるいは、沼と呼んでもいい。
その泉の底知れない深みに手を差し込んで──その沼の視線も届かない深みの底に心を潜り込ませてゆくと、そこには、もはやかたちのさだかでない淡く光る生き物のような物語や、その物語の断片が、あるいは浮遊し、あるいは分裂し、あるいは融合しあいながら、互いに異なる言語の主成分を呼吸しあっている。そこへ潜ってゆく者は、それらの生き物と、時に
それがどのような物語であるべきなのかは、もはやこの深い泉の潜水士には、測りようがない。
ここに、『史記』という異常の書がある。
漢代に、
もともとのことで言えば、この仕事は、父である司馬
全百三十巻。文字数、およそ五十二万六千五百字。四百字詰めの原稿用紙に換算すると、改行なしで千三百十七枚。漢字一文字あたりの情報量は、世界のどの民族の文字と比べても、とび抜けて多いので、日本語にすると、この枚数はさらに増えるであろう。
司馬遷自身は、この大著を『太史公書』と名づけていたのだが、後世それが『史記』と呼ばれるようになり、その名称が歴史の中で定着した。
中国の神話時代から、司馬遷の生きた漢の時代まで、仮に
“この地上の歴史の全てのことを記す”
そういった司馬遷の覚悟の太さが見えてくるような書である。
先に存在した全ての書を、司馬遷は、おそらく読み尽くして、そこから引用しただけでなく、自らの足で大陸の隅々まで歩き、土地の古老や庶民に取材し、書を読んだだけではわからぬ歴史の隙間を埋めていったものと思われる。しかも、これは、官としての仕事ではなく、司馬遷個人の仕事としてやりとげたものであった。
武帝によって腐刑──男根を切られてしまうという刑にあい、死さえ覚悟した司馬遷であったが、この仕事のために命を長らえることを選んだのである。
(後編へつづく)