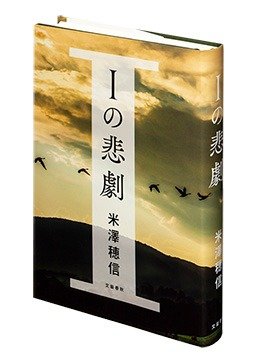米澤穂信「花影手柄」

1
天下は春で、彼方に望む箕面や中山の山々には花の色が見えた。有岡城にも梅が咲き、やがて萎んで散っていった。荒木摂津守村重は畿内一円にその名を鳴らす狷介な武士だが、利休門下にその人在りと謳われた茶人でもあり、歌にも無論のこと嗜みがある。春に心誘われることがないではなかったが、遠巻きに織田の旗が翻るのを見れば、何となく興醒めて歌を詠むこともしなかった。
煙花三月のはじめ、有岡城の西を守る上﨟塚砦に、一騎の母衣武者が馳せてきた。柵木の合間から無数の弓鉄炮が狙いをつけるのを知ってか知らずか、武者は馬手の大弓を振りかざし、悠揚迫らぬ調子で大音声を張り上げる。
「籠城衆に物申す。それがし、滝川左近将監家中の佐治新介と申す者。これなるは主よりの文にござれば、摂津守殿にしかとお届けあれ」
きりりと弦を引き絞りやっと叫んで矢を放てば、矢は狙い過たず砦の門を飛び越える。馬上武者は小気味よさげに笑い、馬の首を巡らして去った。地に突き立った矢を足軽雑兵が物珍しげに取り囲むのを押しのけて、砦の守将中西新八郎が近づくと、矢柄の中ほどに文が結んである。新八郎は何となく嫌な顔をした。敵味方で使者の遣り取りをするのは、戦であっても尋常のことである。それをわざわざ矢文などを放ってくるというのは、いかにも芝居がかって気に入らない。
滝川左近将監一益は、織田家中にあって隠れなき名将である。由緒はつまびらかでないが、信長が尾張にあった頃から仕えており、おそるべし、その武略をもって伊勢一国を織田の手に落とさしめた。その滝川からの文ともなればいかにも胡乱だが、とはいえ、主君への文だと言われて捨て置くわけにもいかない。新八郎はむんずと矢を抜いて、近くの小者に馬引けと命じた。
有岡城を空から見ればおおよそ、西に大きく膨らんだ胴膨れの月に似ている。東の端に天守を備え堀で囲まれた本曲輪があり、それを半月型に包むように侍町が作られ、さらにそれを包んで町屋が連なって、その外側に敵に接する砦が普請されている。北、西、南にはそれぞれ砦を備えているが、東に要害は築かれていない。新八郎は馬を駆り、上﨟塚砦から町屋、侍町を抜け、堀を越えて本曲輪に入った。
そのとき村重は自らの屋敷で、あぐらをかいて茵に座し、諏訪大明神の神棚に手を合わせていた。村重はさして信心深い方ではないが、戦にあって味方の気勢が下がらぬよう、城が不運に見舞われぬよう、流れ矢や流れ弾がおのれに当たらぬよう神仏に祈ることは武士として当然の習いである。拝礼のあいだは些事を取り次がないことになっていたが、戦にかかわることはすべて大事である。新八郎が注進に上がったという報せを受け、村重はすぐに出向いた。
がらんとした板の間で、村重は新八郎に会った。中間を介して矢文を受け取り、村重はそれを解いて一瞥する。
「矢文を放った者は、滝川家中だと名乗ったのだな」
「は」
床に両の拳をつけて、新八郎が平伏する。
「滝川左近将監殿の家中、佐治新介と名乗りましてござりまする」
「一益の身内であったかな。ふん……矢文とは」
苦々しげにそう言うと、村重はそれきりむっつりと黙り込む。焦れた新八郎がついに「殿。いかに」と問うと、村重はおもむろに文を折りたたんで、
「信長が来る」
と呟いた。
新八郎は虚を衝かれ、「はあ」と声を洩らす。有岡城の謀叛は織田にとって一大事であり、信長自身が参陣するのはもっともなことだ。現に、昨冬も信長は摂津に滞陣した。そんなことをわざわざ矢文にしたためたのかと新八郎が訝るのも無理はなく、かれはぼそりと付け加えた。
「それだけにござるか」
村重はちらと新八郎を見た。主君に宛てた文の中身を問うのは、差し出がましいことである。家中の者が村重を軽んじることは決して許されない。軽んじれば侮りを招き、侮りは寝返りを呼び、寝返りはそのまま城を亡ぼす。
いま村重は、新八郎の目つきに怒りを見て取った。つまらぬことを矢文に仕立ててきた、滝川左近に腹を立てているようだ。出過ぎた言葉はただの粗忽から出たものであろう。村重はこたび一度に限り、新八郎を許すことにした。
「……それだけではない」
と、村重は言った。
「左近は、信長が鷹狩りをするゆえ儂に供をせよと言ってきおった」
「なんと」
新八郎の顔がみるみる赤くなる。
「無礼な」
鷹狩りは領内で行うものである。信長が北摂で鷹狩りをするというのは、村重は既に敗れたと天下に広く報せるようなものだ。信長の供をしろと言うに至っては、挑発にしてもあまりにあからさまであった。
「おのれ滝川、筋目もあやしき下郎が図に乗りおって」
「動ずるな。下らぬ小細工、取り合わねばそれまでよ」
「しかし殿、かような侮辱を」
「取り合うなと言うておる。左近将監ほどの上将がこのような細工を仕掛けてくるのは、この有岡が力攻めでは落ちぬと身に染みたゆえとは思わぬか。してみれば痛快よ」
新八郎は顔を赤くしたまま、しかし、ぐっと頭を下げる。
「……そこまでは、考えませなんだ」
「よし。下がれ。左近は儂が出てくるとは思うておらんだろうが、城内が浮き足立つとは思うておるかも知れん。堅く守れよ」
新八郎は再度平伏し、去った。
村重は敢えて新八郎に口止めをしなかった。その日が暮れる頃には、信長が鷹狩りに来るという噂を知らぬ者は、城内に一人としていなかった。