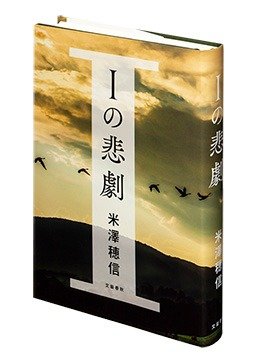【集中掲載 米澤穂信「花影手柄」】織田方からの挑発に荒木村重は……。堅城・有岡城が舞台の本格ミステリ第二弾!#1-2
米澤穂信「花影手柄」

2
本曲輪にそびえる天守では日に一度必ず軍議が行われ、主立った将が参集する。
籠城の中で相談すべきことが毎日
「殿。信長めの
涙を流さんばかりにして訴えたのは、宿将の荒木
「無論、滝川左近の無礼は許せるものではござらん。……さはさりながら、
と分別らしい顔をする。和泉は、城内の武具
「毛利毛利と言うが、その毛利はいつ来るのじゃ。待てど暮らせど来ぬではないか」
久左衛門がそう問えば、
「今日明日にも来るやも知れぬ、いやきっと播磨辺りまで来ておる。軽挙妄動こそ戒めるべき」
と和泉が言い返す。
籠城とは、城の堅さで時を稼ぎつつ加勢を待ち、加勢と城方で挟み撃ちにしようという軍略である。その加勢が来ないままに合戦に及んでは必敗であり、いまは戦おうにも戦えない──それは誰もがわかっている。織田をどうするこうすると言い争ってもすべては無益であり、軍議は、やはり軽侮は許せぬという顔をするか、ここは耐えるべしという顔をするか、ただただ建前を突き合わせるばかりの場となった。
「皆々様」
下座の方で、中西新八郎が胴間声を張り上げる。
「どうか、ここをお考えあれ。滝川左近ほどの上将がかような小刀細工をいたすのは、この有岡城が力攻めでは落ちぬと身に染みたからではござらぬか。左様ならば、かえって痛快と存ずる」
そう言って、新八郎はどうだとばかりに村重を見る。村重の言ったことをそのまま繰り返し、それで役に立ったと言いたげであった。村重は心のうちで、新八郎がおのれに向ける信をどこかおかしくさえ思っていた。旧主池田氏を滅ぼし、この地に根づいた
新八郎の言葉と村重の頷きは、諸将に感銘を与えた。久左衛門が新八郎を
「控えよ、新参の分際で」
と言いはするが、
「……まあ、左様な見方もないではなかろうが」
続けてそう呟きもすると、打って出ようという意気は水を掛けられたように鎮まっていく。軍議もこれで
「摂津守様。異見をお許し下されますか」
言葉を発したのは、まばらに
「
男は深々と頭を下げた。かれは
孫六は雑賀の頭目と目される孫一の弟らしいが、詳しいことは村重も聞いていない。籠城の前、有岡城に入る折も、孫六は「大坂門跡の下知により合力つかまつる」と言っただけであった。村重は孫六のことを、戦ばかりを専一に考える男と見ている。つまり、武士らしくない──武士は領地をどう営むかも考えるからだ。
村重は雑賀衆から兵を借りている身ではあるが、摂津守である村重と紀州国人に過ぎない孫六とでは身分に差がありすぎて、本来ならば孫六は村重に直答することもはばかられる。はじめて軍議で物を言った孫六に、荒木の諸将が好奇と僅かばかりの批難を込めた無遠慮な目を向けるが、孫六は別段気負う風もなかった。
「われら雑賀衆は三年前、
軍議の座は水を打ったように静まり返った。雑賀衆が信長に手傷を負わせたことは、誰もが知っている。なんとなればその戦いには、その頃織田に属していた荒木勢も加わっていたからだ。織田を敵に既に八年戦い続けている雑賀衆に
矢文一通の誘いに乗ってうかうかと城を出るというのは無謀だが、雑賀の者どもなら、あるいは本当に信長を撃ち抜くかもしれぬ……そしてかれらだけで合戦に及ぶなら、われらとしてはありがたい。家臣たちの胸をよぎったそんな思いを、村重は鋭敏に嗅ぎ取る。
「いや、待たれよ鈴木殿」
しゃがれ声が、これはやや上座に近い方から上がる。
「合戦に及ぶとあらば、われら
かれは
先陣を命じられるのは新参者というのが戦場の習いである。仕えて日が浅い者を陣の後ろに置いて、もし寝返られては挟み撃ちされるからだ。ただ、高槻衆が先陣に立つのなら、有岡城の将卒が戦わぬということはあり得ない。将たちの顔が
村重は岩のような
やがて、村重は重い声を発する。
「ならぬ。雑賀衆は守りに欠かせぬ。高槻衆も犬死にはさせられぬ。出るな、守れ」
孫六と大慮は別段不満そうな顔もせず、板張りに両拳を突いて平伏し、声を合わせたように、
「は」
と応じた。諸将がほっと息を
屋敷に戻った村重は、廊下を踏みならす足音も荒々しく、中間を呼んで命じた。
「
御前衆は村重が直率する武士であり、戦いにあっては村重自身を守るほか、伝令として戦場を駆けたり、場合によっては少数の兵を率いることもある。他家ならば
「十右衛門、参じました」
歯切れの良い物言いであった。かれはもと伊丹氏に連なる者で、
「よし。十右衛門、警固の任を解く。高槻衆と雑賀衆を探れ。早いほど良い」
「は。何を探りましょう」
「あの者らの、城中での立場」
「承知
「
「御意のままに」
十右衛門は立ち上がり、小走りに去る。春の日は中天に差しかかっていた。