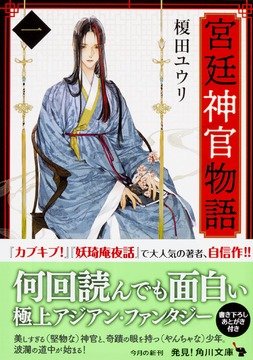【新連載 榎田ユウリ「武士とジェントルマン」】現代日本に武士(本物)が!? 英国紳士が居候先で見たのは……#1-1
榎田ユウリ「武士とジェントルマン」

1.ある意味、未知との遭遇
「先入観を持たずに行きたまえよ」
尊敬する師であり、同時に数少ない友ともいえる人物のアドバイスである。ありがたい助言に従うべく努力は怠らないが、染みついた先入観の排除は容易ではない……という返答を私がするより早く、
「まあ、無理だろうがね」
そう言い継いで、彼はにんまりと笑った。
「きみはすでに、かの国について一般の英国人よりずっと詳しい。それどころか会話もペラペラの域だ」
「叔母から教わったのは子供の頃ですから、かなり
「なんの。子供時代に学んだものは根強い。おまけにきみは語学のセンスがある。それにしても、かの国を訪れるのは初めてだとは。東洋美術史を学んだというのに!」
「ご存じのように、私の専門はインドですから」
だいぶ冷めた紅茶を飲みながら答えた。少し薄いなと思ったが、この人は昔からあまり濃い紅茶が好きではないのだ。
「今まで、訪れる機会はなかったのかね?」
「何度か叔母に誘われたんですが……しかし、現代のかの国に、さほどの興味を感じられなくて。
「
彼は楽しげに
なにを? 私の無茶を、だ。
たいした準備も目的も情熱もなく、しかももう若くもないというのに、異国で数年を過ごそうという計画を面白がっている。気持ちはわからなくもない。私自身、この投げ
「さほど興味のない国で、きみは貴重な数年をすごそうとしているわけだ」
「向こうの大学が、講師を探していると聞きましてね。
「そのつまらなそうなすまし顔は、学生の頃と変わらないなあ。わかってる、アンソニー、わかってるとも。人はなにかにうんざりした時、遠い場所に行きたくなるものだ」
「私はうんざりしてるように見えるんですか?」
「だいたいきみはいつもそんな顔だね」
「確かに、積極的にかの国を選んだわけではありませんが、それなりに興味は……」
「とにかく! これは素晴らしい機会なのだよ!」
この恩師はしばしば人の話を最後まで聞いてくれない。
「いいかい、アンソニー。準備するな。なにも調べるな。大丈夫、私はきみのために完璧なアレンジメントをしておいた」
「私はきみに特別な体験をしてもらいたいんだ。そして特別な体験というのは、鮮度が要求される。そう、フレッシュでなければ! ぜひとも白紙で行ってくれたまえ。少なくとも現地に到着するまでは、まっさらでいてほしい。約束してくれるかね? ああ、まったく、『ググらない』ことがこうも難しい時代が来るなんて、誰が予測できた? みんなどうでもいいことばかりを検索しまくっている。七秒で知り得たことなんて、四秒で忘れてしまうというのに!」
「ご安心ください。白紙で行きますよ」
私は立ち上がりつつ言った。今一度「決して、ググりません」と繰り返し、右手を差し伸べる。そろそろ戻って、フラットの荷物の整理をしなければ。
「うむ。よい旅を、アンソニー。
恩師の手はかさついて、だが温かく、指先にビスケットの屑が少しついていたのも昔同様で、私はさりげなくそれを払い落としながら感謝を述べたのだった。
Googleという巨大企業の固有名詞が『検索する』を意味する動詞として使われるようになり、どれくらい経つだろう。そしてこの
言葉の変化は世の常にしろ、今やその速さはあまりにめまぐるしい。言うまでもなく、情報化社会とSNSの発達によるものだ。ちなみに日本語の「GUGURU」にも「検索する」という意味があるそうだ。まさしくワールドワイドである。
襲い来る情報の波をどう乗りこなすか、あるいはそこからあえて遠ざかるか、判断は人それぞれだろう。ヒースローから
暇である。
タイムズもガーディアンもデイリー・テレグラフも読み、すべてのクロスワードも解いてしまい、いよいよやることがなくなった。
私は恩師との約束を守り、モバイル機器をいじることは控え、その代わりに東京の地図を広げてみることにした。折りたたみになっているそれは、十年前に叔母が帰郷した折に買ってきたものだ。保存状態は良好だが、問題は地名の表記であり、私は漢字がほとんど読めない。優しい叔母はいくつかの地名をマーカーで書き入れてくれていた。TOKYO、SHINJUKU、SHIBUYA……UENOは大きな美術館がある街と聞いている。私のお気に入りの北斎が充実している美術館も都内にあるらしいが、どこなのか……。電話として使うため、スマートホンは手元にある。だがググれない。約束したのでググれない。黙っていればいい話なのだが、私は性格的に約束を破ることに居心地の悪さ──というか、なにかに負けたような気分になるという、我ながら面倒くさいタイプなのだ。恩師もそれを承知で「約束してくれるかね」などと念押ししたわけである。
私はシートの角度を起こし、アテンダントにオレンジジュースを頼んだ。機内は乾燥しているのでいつもより喉が渇く。モニタの時計を見ると、あと三十分ほどで着陸態勢に入る頃だ。
羽田空港には迎えが来てくれる手はずになっている。
誰が来るのかは知らない。顔もわからない。
荷物を送る必要があったのでアドレスはもらい、その時に家主の名前は判明した。
今回、
日本の大学で教えることになったと、電話で報告した三日後、「きみの住む家が決まったよ」と連絡があったのだ。この時点で丁重に断るという道もあったのだろうが、私はそうしなかった。異国のフラットを探すのは面倒だし、恩師は「きみの美意識を満足させる邸宅だ」と自信満々の様子だった。確かに、彼は私がなにを美しいとするかを正しく理解している
東京の住宅事情は叔母から聞いていたので、荷物はなるべく少なくした。本と服と日用品が少し。ずいぶん迷ったが、愛用のマグカップは手荷物に入れた。やはり紅茶はこれで飲みたい。INO氏についての追加情報はないまま英国を離れる日が迫り、二日前に恩師に挨拶に
白紙で行け、か。
恩師はいったい、私になにを見せてくれるというのだろう?
しかしさすがに懸念もあった。そもそも、空港で落ち合えなかったらどうするのか。私が知っているのは、INO氏の自宅の電話番号だけで、携帯番号は知らない。先方が私の番号を知っているのかどうかも、わからない。ならば私の顔は知っているのだろうか。恩師に確認してみたところ「いいや。顔は知らないよ」とあっさり言われてしまった。
──問題ない。特徴は伝えてある。茶色い髪にヘーゼルアイの白人男性。
──空港だと、該当者は結構いるかと思いますが。
──便名もちゃんと知らせてある。それに、仮に彼がきみを見つけられなくても、きみは必ず見つけられるさ。
──まさか。いったいどうやって?
──簡単だ。一番目立つ人を探せばいい。
そう言うと、恩師は「おっと、マフィンが
一番目立つ人?
これまた曖昧なヒントだ。なにがどう目立つのかわからなければ探しようがない。まさか
揺れの少ない巧みなランディングで、飛行機は羽田空港に到着した。
荷造りをする前、叔母に東京の三月中旬の気候を聞いた。親族の中で、私が最も会話しやすいのがこの叔母である。日本人だが、とうに英国暮らしのほうが長い。彼女は少し考え込んだあと「ちょうど半端な時期ね」と答えた。まだ冬をひきずる寒さもあり、そうかと思うと初夏の陽気になったりもするそうだ。そのへんはロンドンも変わらないので、あまり意識せずともいいと判断した。レインコートにもなる上着を選び、念のためにマフラーを持っておく。叔母
羽田空港の清潔さは、私にとって心地よいものだった。
午後三時すぎ、外の気温はわからないが、大きな窓からの景色は明るく晴れている。小型のスーツケースは機内に持ち込めたので、ピックアップの必要はない。入国審査を通過し、税関も抜ければ出口だ。
ロビーを見渡した私は、軽く
これは、無理だろう。
到着した人、迎えの人……ごった返しているとまでは言わないが、かなりの人だ。考えてみれば当然、ここは大都市東京なのだ。この状況では、互いに顔を見知っている者同士ですらすんなり会えるとは思えない。実際にみな携帯電話を使いながらきょろきょろと、待ち合わせ相手を探していた。この状況からして、いくら目立つ人物とはいえ……。
「わ、見て、アレ」
私のすぐそばにいた日本人女性が言った。私にではなく、一緒にいた友人に話しかけたのだ。声をかけられた女性は、友人が示す方向を見て、「あらあら」とやはり驚いて、小さな目を見開く。ふたりとも老婦人と言える
「なんだか久しぶりに見たわぁ」
「私も。昔はもっといたわよねえ」
「かなり減ってるんですって。レア、っていうやつよ。写真をスマホの壁紙にしとくと、お守りになるって孫が言ってたもの」
「確かに効きそうだけど、勝手に撮るのは失礼よねえ」
「それはダメだと思うわぁ。あらやだ、こっちに来る。聞こえちゃったかしら」
彼女たちの注目していた人物が、歩き出した。
私もまた、その人物を凝視していた。
……なんだ、あれは。
いったいどうして。
いや待て、そういえば。だがしかし。なるほどこれは、かなり……。
といった言葉が、文にまとまらないまま私の脳内を旋回している。ほかにもチラチラとその人物を気にしている人は多い。噂話をしていた老婦人たちはそそくさとその場から立ち去り、その人物は私のすぐ前で止まった。
本当に、真正面だ。
「失敬。アンソニー・ハワード殿とお見受けいたす」
やや高い声で彼は言った。
年若い男性である。背丈は私より十センチほど低いだろう。少し顎を上げ、真っ直ぐこちらを見る目は、誠実、という言葉を思い出させた。聞き慣れない語彙もあったものの、なにを聞かれているのかは
キモノ。
カタナ。
チョンマゲ……?
「……あの、貴殿は」
青年はやや戸惑った様子でこう続けた。
「……ユー、アー……違……アー、ユー、ミスタ……」
こちらがちっとも反応しない為、日本語が通じないのだと誤解したらしい。私は慌てて「いえ、わかります」と答えた。
「そう、アンソニー・ハワードです。ではあなたがINOさん?」
「左様。正しくは、イノウ、と発音いたします」
「失礼。イノウさん」
「は」
「……ひとつ、お聞きしても?」
「なんなりと」
「あなたは、その、つまり──サムライなんですか?」
腰の刀に軽く左手を添え、イノウ氏は一度姿勢を正し、「いかにも」と答え、
「
いくらかの緊張を伴う
▶#1-2へ
※「カドブンノベル」2019年9月号収録「武士とジェントルマン」第1回より