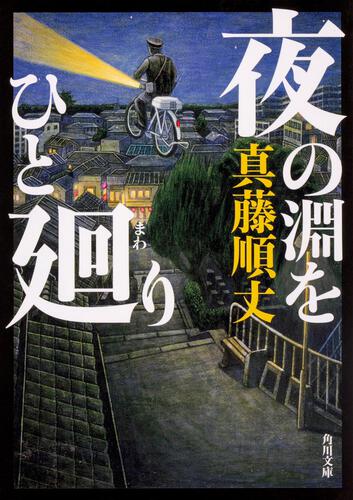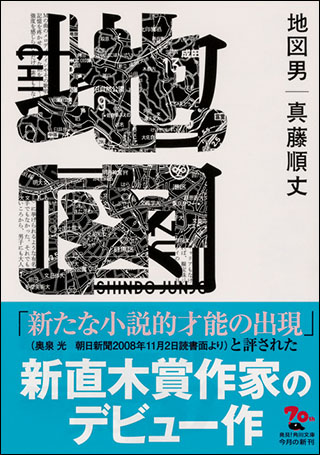【連載小説】日系ブラジル人の家族が捜している女性。そのサンバのお弟子さんの女性に会いに、秩父を訪れた。真藤順丈「ビヘイビア」#11-1
真藤順丈「ビヘイビア」

※本記事は連載小説です。
前回までのあらすじ
タクシー運転手の城之内とウズベキスタン出身の青年ガフは、技能実習生として来日したガフの恋人・シトラの死の謎を追っている。外国人のための調査事務所を開業した二人は、日系ブラジル人一家の依頼で風祭喜久子という人を捜す。一家の娘・カレンは、彼女の腹の傷痕のわけを喜久子が知っているのではと言う。調査途中、一家と絶縁中のカレンの兄のアッシュと会った城之内とガフは、一家の通訳の鹿賀とアッシュが何か共謀しているのではと考える。
詳しくは 「この連載の一覧」
または 電子書籍「カドブンノベル」へ
§
オーバーステイの名探偵か──
フェイスブックのアカウントに載せたコピーが、あながち誇大宣伝ではなくなる日も遠くないのかもしれない。現段階ですらおおよその調査方針を決めているのはガフだし、こうして手分けをすることもいとわず、パートナーの機動力や土地勘にも頼らなくなってくると、城之内はいよいよワトソン役、というよりも専属の運転手、移動の足といった以上の存在価値をみずからに見いだしづらくなってくる。
面白くない、というわけでもなかった。
ガフール・ジュノルベク。
あの男の知性や行動力は、探偵という役割にこそふさわしい。
城之内の人生で、他人に自慢できることは数えるほどもない。姓を
もちろん本人には、そんな真情を打ち明けたことはないけど。
オリヴェイラ一家の依頼──
半世紀以上も昔の恩人を探してほしい、というわりと無茶な依頼でもガフはまるで手を抜いていない。思いの強さだけではなく集中力を高めて、着実に手がかりを集め、確かな結果を導きだそうとしている。ブラックな職場の実習生として泥水をすすりながら生き残ってきた、一途にこつこつと目の前の課題と戦ってきた足腰の強さは、並の日本人の調査員なんておよびもつかないほどの適性に結びついている。
都内を離れた遠出すらもいとわない。ガフは
せいぜい水をあけられないようにしなくっちゃな、城之内は車を運転しながら思いをめぐらせる。
あいつともう少し、この仕事をつづけたいのなら。
秩父鉄道の
受付のおばちゃん職員に「ご家族の方ですか」と訊かれた。城之内が見慣れない顔だからか、視線で値踏みして
「こちらに入っている
「ああ、それなら聞いていますよ」
職員はカウンターのこちら側に出てきて、玄関フロアに飾られた額入りの集合写真に目を向けた。ここの入所者とおぼしき高齢者たちが、手製の衣裳や飾り帽子をまとってしわくちゃの笑顔を並べている。きわどいビキニを着ているばあさんはさすがにいなかったが、写っているだれもが介護施設のシニアとは思えないほど、
「室越さん、ひさしぶりに思い出深い人の話ができるというので、数日も前から面会を楽しみになさっていたんです」
遠いところをようこそいらっしゃいましたとねぎらいの言葉までかけられて、本人を呼んでくるので一階の食堂で待っているように言われた。室越さんが施設に知らせておいてくれたおかげでとんとん拍子だ。このぶんなら不承知の相手をおだてたり、騙しすかしたりして話を聞くような難儀なミッションにはならなそうだった。
施設の介護職員のなかには、アジア系の技能実習生の姿もあった。特定技能〈介護〉で職につけば、たしか就労できる在留期間も他の職よりも長くなるはずだ。のっぴきならない高齢化に直面するこの国の介護の現場で、実習生たちにも真にメリットのあるかたちで就労が実現しているかどうかはあやしい。だけどこの鹿乃苑では、技能実習生たちは入所者ともよく馴染んでいるように見受けられた。
昼食時をすぎた食堂にちらほらと残っている老人たちは、めいめいで車椅子に座ったままおしゃべりをしたりゼリーを食べたりしている。カーテンの透き間から差しこむ午後の光がまばらな破線となって、老人たちの白髪や肩の線を柔らかく縁取っていた。
城之内はみずからの母親の総白髪を思い出した。死を看取ってやれなかった母は、最期まで介護の世話にはならなかったが、くも膜下出血で倒れてからはあっという間だった。娘の
凜子の二歳の誕生日に、母がセキセイインコを買ってきたことがあった。凜子はすごく気に入って、おしゃべりもまだおぼつかないのに鳴き真似は上手になって、鳥と一緒になって楽しげにピイピイとさえずっていた。後にも先にもペットを飼ったのはあの一度きりだったが、小学生になったころに聞いてみたら鳥を飼った記憶も、お祖母ちゃんの思い出とともにすっかり
「踊りが上手って言ってくれたでしょ、お父さま」
食堂に入ってきた老女が、城之内に話しかけてきた。
「お父さま、わたくしの踊りを見ていってくださいね」
この人が室越さん? と思ったが違った。男の介護士が別の名前を呼んで、やんわりとたしなめて食堂の端の席へと彼女をいざなった。この鹿乃苑では、認知症のシニアも受け入れているとホームページに記載があった。彼女もあるいは室越さんのレッスンを受けているのかもしれない。認知症とサンバか──
メメント・モリ、という言葉が城之内の脳裏に浮かんだ。
〈死を想え〉とか〈死ぬことを忘れるな〉とか、たしかそんな意味だった。
ああそれだ、サンバの文化にふれるとき、城之内がつねにうっすらと感じているのは、メメント・モリにも一脈通じる死生観だった。
人はすべてを忘れ、いずれは死ぬ。明日には訪れるかもしれない死によって、貧富や身分の差も、国籍や人種の区別もなく〈無〉に統合される。だったら指をくわえて見ているよりもたったいまこの瞬間を踊らなきゃ損じゃないか、というエネルギーの発露を感じるのだった。
ラテンの文化にかぎらず、あらゆる舞踏芸術には多かれ少なかれ相通じる性質があるのかもしれないが、どういうわけかサンバにはそうした感覚を強くおぼえる。だとしたら、転倒や怪我といったリスクにもかかわらず最晩年にサンバに熱中するというのも、あながち不自然なことではないのかもしれなかった。
「お待たせしました、わたしが室越です」
ややあって姿を見せたのは、白髪をシニヨンにまとめて、卵形の顔にきちんと化粧もした老婦人だった。胸元にカメオを留めたワンピースが細身の体によく似合っている。介護士がコーヒーとお茶うけまで出してくれて、日当たりの良い窓際の席で向かい合った室越さんは、
▶#11-2へつづく
◎第 11 回全文は「カドブンノベル」2020年10月号でお楽しみいただけます!