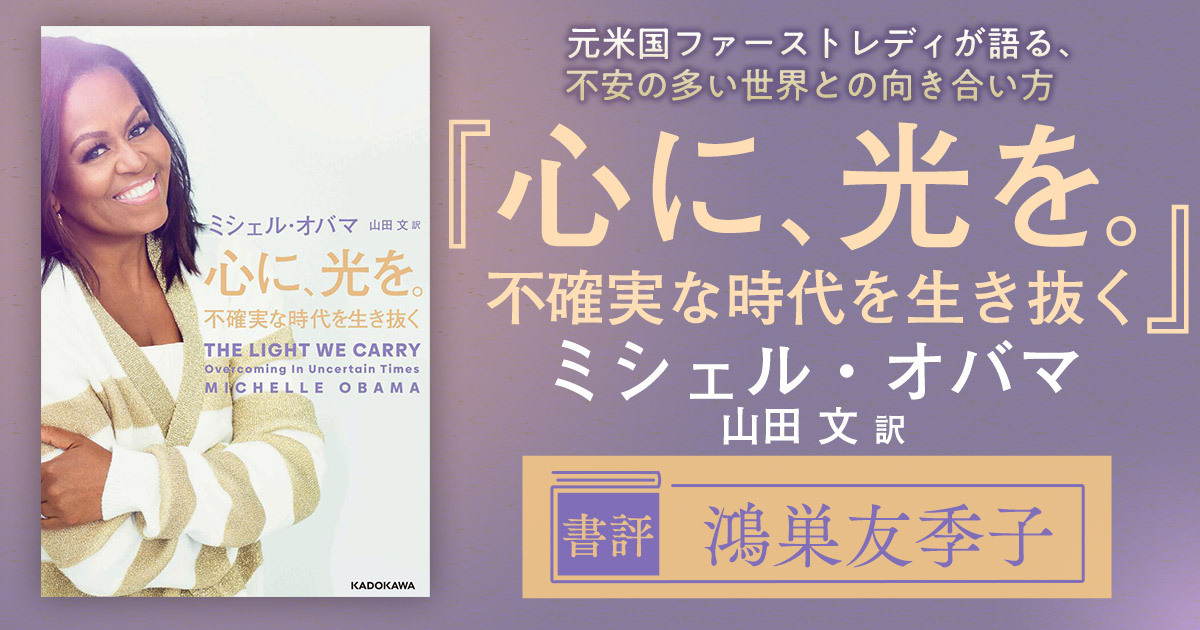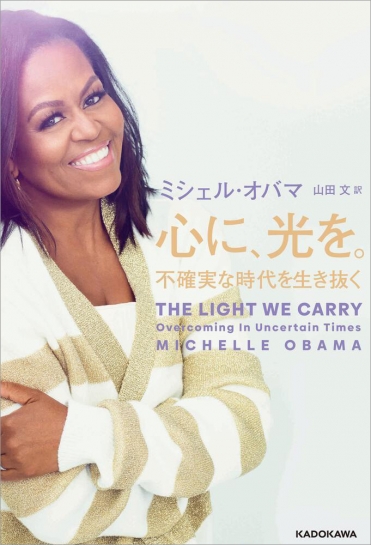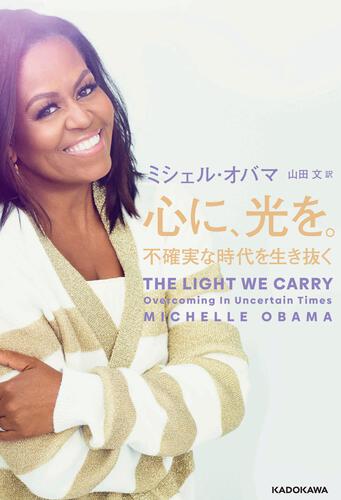元米国ファーストレディが語る、不安の多い世界との向き合い方
ミシェル・オバマ『心に、光を。 不確実な時代を生き抜く』レビュー
書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
『心に、光を。 不確実な時代を生き抜く』
著者:ミシェル・オバマ
書評:鴻巣友季子
ミシェル・オバマの『心に、光を。』はアメリカの光と影が生みだした名著だ。
二〇二一年一月二十日、第四十六代米国大統領就任式の緊張した空気をわたしは忘れない。そこには希望と明るさとともに、不安と闇があった。まさに光と影がせめぎあっていた。一年近くもつづくコロナ禍の恐怖と息苦しさ、経済停滞、失業、そのなかでいっそう顕著になった人種差別やヘイト、階層間の分断。そうした亀裂の結果として起きた連邦議会議事堂襲撃事件……。元米国ファーストレディとして式に出席したミシェルは『心に、光を。』のなかで、このときの様子をこう表現している。
その朝のナショナル・モールでは、空気中にありとあらゆるものが感じられた――緊張と決意、変化を求める切実な気持ち、パンデミックによる不安、連邦議会議事堂で経験した暴力の恐ろしさ、その先についてのもっと大きな心配、新しい一日の太陽の光。ことばにされることなく、すべてがずっとそこにあった。矛盾して、少し落ちつかない状態で。
わたしは式に出席した元大統領バラク・オバマとミシェル夫妻の姿もよく覚えている。式典の進行中、ミシェルの落ち着いた笑顔が映しだされるとなぜかほっとした。それは、彼女が苦境のなかでつねに聡明に戦い、不安を乗り越えてきた人だからだろう。
不安は人を守る本能だ。ミシェルいわく「ロケット燃料」にもなる。しかし御しがたく暴れることもある。だからこそ、彼女は冷静に分析する。疑念は外からではなく自分のなかからやってくること、不安が限界をつくること、怒りが犠牲を生みかねないことを。偏見は不安から生まれることも知りつくし、みごとに言語化することができる。
彼女のこうした力は生まれ育ちからも来ていることが、『心に、光を。』を読むとよくわかるのだ。ミシェルの祖父は父母方とも悪名高いジム・クロウ法(黒人を隔離する差別的な法体系)下の南部からより良い生活を求めてシカゴの街にやってきた。父は彼女が幼い頃に病気を発症し、次第に身体が不自由になっていった。また、一家は白人の多い居住区において、いつも周りと「ちがう」人たちだった。ミシェルにとって進路指導の教師の言葉と態度は、今でも屈辱の火柱のようになって心に残っている。プリンストン大学を志望校に挙げると、「出願するだけ無駄だ」と言下に否定されたのだ。
アメリカのとくに名門大学には今も「レガシー入学」という卒業生・在校生の身内を優先する制度があり、難関を突破しても、恵まれた同級生たちのなかで彼女は人とちがうという疎外感を味わう。最近ハーバード大学におけるマイノリティ人種への優遇措置が最高裁で違憲とされたとき、ふだん政治行動をあまりとらないミシェルが遺憾の声明を出したのもこういう経験があったからだろう。
そうしたなか、父母はいつも感情的にならず、つねに理論的にものごとを説明してくれたという。幼い彼女が雷を怖がれば、父はそれが起きる仕組みを教えてくれた。平等や正義をめぐる問題についても説いてくれた。
ミシェルは「自分にやさしく声をかける」とか「小さな達成を大事にする」(彼女の場合は編み物)など大事なアドバイスをくれるが、なかでも重要なのは「物語を書きなおす」ということだ。これは今のアメリカを二分しているLGBTQ+や「禁書戦争」の問題とも深く関わってくるが、これをミシェルはvisibility(人の目にとまること)の観点から見ている。そうした論争のなかで「だれの物語が語られ、だれの物語が消し去られているのか」ということを見極めよと。それによって、歴史すらも変わっていく。「わたし」の物語を固定観念から解き放ち、書きなおすことができるのは自分だけだ。
そうしてアメリカという国の物語を語りなおして国民をエンパワーしたのが、アマンダ・ゴーマンという前述のバイデン大統領就任式で自作の詩を朗読した黒人の女性詩人だった。あの日の舞台には、アメリカの政治と文化において重要な役割を
きっと二十二歳のアマンダはミシェルが近くにいることを心強く思っていただろう。アメリカが辿ってきた苦難の日々と、来る未来への希望を謳う詩のなかに、彼女はこんなお茶目な一節を盛りこんでいた。「痩せっぽちの黒人の少女、奴隷の末裔でシングルマザーに育てられたそんな娘も、大統領になる夢を見られるような(国をつくろう)。もっともその子は目下、大統領に詩を暗唱する役回り」
このくだりでテレビカメラはすかさずオバマ夫妻のアップ映像を抜いた。ミシェルは果敢な若い女性のユーモアに微笑み、力強く肯定するかのように頷いていた(わたしの記憶違いでなければ)。緊張と不安を孕んで始まった就任式は、ポジティヴな色合いを強めていった。
アマンダが朗誦した「わたしたちの登る丘(原題:The Hill We Climb)」はミシェルの『心に、光を。(原題:The Light We Carry)』にも長く引用されているが、暗闇から踏みだして希望の光へと向かう国のイメージが謳われる。そしてその後にアマンダが発表した詩集はCall Us What We Carry(仮題:「わたしたちの担うもの」)という。
ここに、若いアーティストと、法律家であり元米国ファーストレディである年長の女性の、魂の応答が聞こえる気がする。ふたりともcarry(背負う、担う、運ぶ)すべきものをcarryしながら差別や憎しみや不安という怪物と戦い、自らが光となってまわりを照らす存在となったのだ。
作品紹介
心に、光を。 不確実な時代を生き抜く
著者:ミシェル・オバマ 訳者:山田 文
発売日:2023年09月26日
元米国ファーストレディが語る、不安の多い世界との向き合い方
58年、わたしは不安を抱えて生きてきた。
場ちがいだ、ここにいるべきじゃない、誰もわたしを気にとめていない。
まわりから浮いている。
でも、ちがう。
どんな世界に暮らしたい? 誰を信頼する? 子どもはどうやって大人になる?
人生の大きな問題に、わかりいやすい解決策なんてない。
不安を抱える人たちに、心から安らげる場をもたらしたい。
少し自分の世界を広げるために、リスクを取ることを恐れない。
誰かといっしょに自分の問題を考えることには、意味がある。
さあ、心の中にある光を、見つけよう。
特設サイト:https://kadobun.jp/special/michelle-obama/the-light-we-carry/
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322301001060/
amazonページはこちら