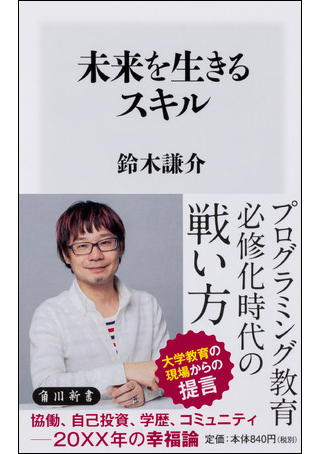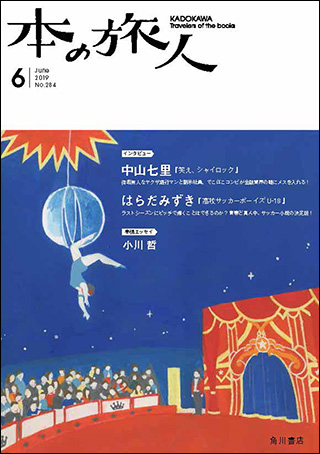人工知能やロボット技術など新しいテクノロジーが普及することで、雇用のあり方が大きく変わるとか、従来の価値観が通用しなくなるといった話を聞くことがある。経済産業省も二〇一六年に公表した「新産業構造ビジョン」に関する資料の中で、「痛みを伴う転換か安定を求めたジリ貧か」と問いかけ、近年の変化に乗り遅れることが日本の長期的な衰退を招くと主張している。
社会全体として見れば、産業の効率化や新しいテクノロジーの導入は必要なことだろう。だがそのような「日本は変わらなければならない」という物言いが溢れかえるほどに、「では私たち個人の生き方は、どのように考えればよいのだろうか」という疑問が、ますます深まっているように思える。
その疑問に対するひとつの答えは、人びとがみな自分の意思で不透明な未来を切り開くことをよしとし、人生をあたかも経営者のようなマインドでコントロールしていくように促すというものだ。あるいは、この変化を抗えない波と受け入れ、たとえ社会が衰退していくとしても、ささやかな幸せを日常の中に見出して生きていけばいいのだという言い方も、よく目にするところではないか。
このような言説は、私の専門とする社会学の立場からは「自己啓発」の一種であるとみることができる。自己啓発とは、個人の前に現れる様々な状況を、その人の考え方や捉え方に由来するものとみなし、認識の仕方を変えれば世界も変わるとする因果帰属の技法である。自己啓発の技法は、社会の発展と個人の豊かさの達成が同時に進行した経済成長の終わりと前後して日本社会に広まり、現在では前述のようなビジネス的言説から人生論に至るまで、幅広い分野における考え方の基盤となりつつある。
本書『未来を生きるスキル』は、私自身の大学での教育経験に基づき、この「自己啓発の時代」にあって不足している考え方——「協働」の価値について述べた本である。いわゆる学術書のたぐいとは違い、種々の研究によってすでに明らかになったことだけではなく、それらをもとに「私たちはこれから、どのような生き方をすべきなのか、そして、そのような生き方が可能になる社会は、どのようにして実現されるのか」について書いた、いわば社会ビジョンの提案になっている。
その提案を貫くコンセプトである「協働」とは何か。それは、決して優れたところばかりではない普通の人々が、それぞれにできることを持ち寄って、ひとりではなしえないことを達成する、そのような関わり方のことである。「自分の頭の中を変えればすべてうまくいく」という自己啓発に対して、他者との協力を促しているところが、協働というコンセプトのユニークな主張ということになるだろう。
協働が必要になると考えられるのは、まず産業の分野で言えば、人工知能やロボット技術などによる自動化が進むこれからの社会では、ひとりの天才の発想ではなく、多様なアイディアを持ち寄ることが求められるようになるからだ。また教育においても、アクティブ・ラーニングなどの手法が導入され、新たな教育スタイルへの転換が進みつつあるからだ。そして何より、所得のない高齢期が長く続くようになるこれからの社会では、他者の手を借りなければ生きていけない人が、ますます増加すると考えられるからだ。
もちろんこれまでも「他者と協力する」ことの価値は言われてきた。だが産業社会の生産システムを前提に「みなで一斉に同じことをする」のが求められた社会では、協力といっても「自分勝手なことをしない」「集団が目指す目標に個人が合わせる」のが当然だとされていた。本書で提案する協働はそのようなものではない。個々の多様性を否定することなく、それが長所となるような関係性を築くことが、協働の目指すところなのである。
本書が提案する協働がどのようなものであるか、ぜひご一読いただければ幸いである。
ご購入&試し読みはこちら>>鈴木 謙介『未来を生きるスキル』
紹介した書籍
関連書籍
-
特集
-
特集
-
試し読み
-
レビュー
-
レビュー