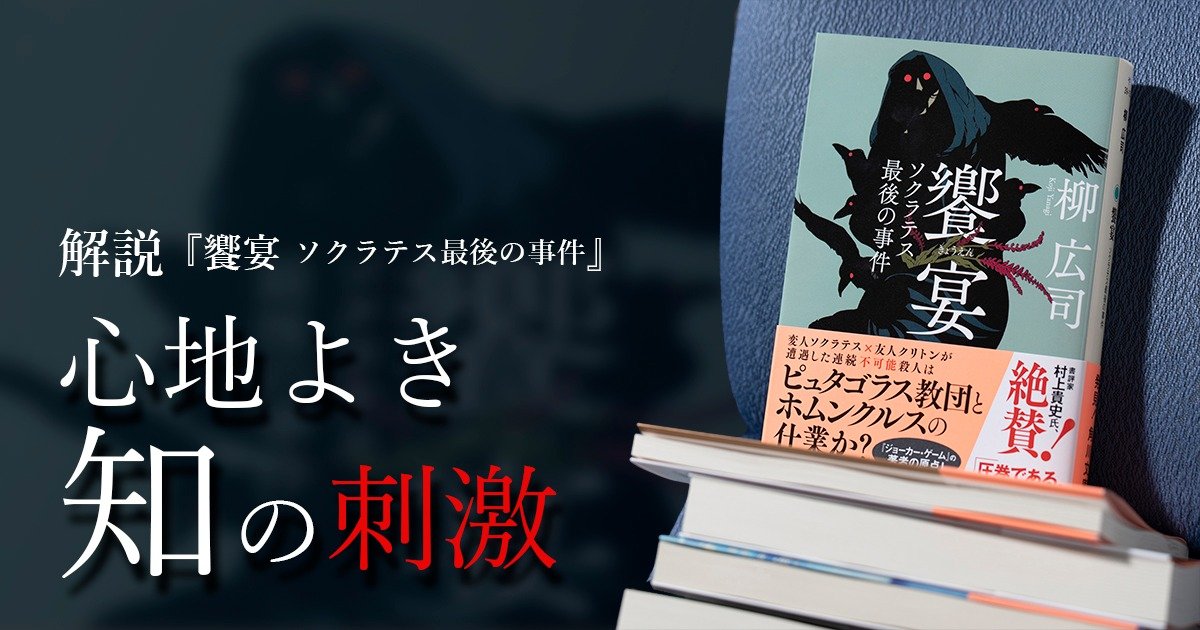文庫巻末に収録されている「解説」を公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:村上貴史 / 書評家)
■知の刺激
いやはや心地よい。
圧倒的な知の刺激を浴びて、著者の操る言葉に振り回されて、脳みそをぐちゃぐちゃにかき乱された気がする。そのぐちゃぐちゃがまず心地よく、しかもそれが最終的にはしっかりと収まるべきところにきちんと整列するのも心地よい。
しかもその知の刺激は、さらに余韻を残すのだ。
人間ってなんなのだろう。
文化ってなんなのだろう。
そんなことを考えさせられる余韻を。
■柳広司『饗宴 ソクラテス最後の事件』
古代ギリシアのアテナイを舞台とするその小説『饗宴 ソクラテス最後の事件』において中心に据えられているのは、ソクラテスである。そう、あのプラトンの師である哲人だ。生年は紀元前四六九年頃。没年は紀元前三九九年。
そんな著名人に、本書でまず提示されるのは、炎を近づけたわけでもないのに訴訟掲示板の蝋がドロドロに溶けてしまうという謎だ。小粒といえば小粒だが、れっきとした不可能犯罪である。
柳広司は、その謎をソクラテスに解かせる。それも序盤に、あっさりと。結果として読者の心には、哲人であると同時に、名探偵としてのソクラテスの存在が刻まれることになるのである。
そしていよいよソクラテスが挑むのは、アテナイで起こる連続怪死事件だ。ソクラテスの知人の青年は衆人環視のなかで奇妙な死を遂げ、異国風の男性のバラバラ死体も登場する。死は二人では終わらず、かたちを変えてさらに続く。そんな奇怪な事件に影を落とすのが、ピュタゴラス教団――あの三平方の定理で知られるピュタゴラスが組織した秘密主義の教団――と、教団が生み出すというホムンクルスだ。ホムンクルスは、身体の大きさは通常よりも非常に小さいが不死の神々にも匹敵する力を持ち、言葉を交わすことなく互いに意思疎通が可能で、動物をも操り、さらには姿を消したりもするという……。
ずいぶんと怪しい存在である教団とホムンクルスだが、不思議なことにこの著者の手にかかると、物語のなかで存在感をしっかりと確保してしまう。序盤において、ソクラテスが参加した宴での議論のなかで様々な視点からその存在がしっかりと吟味されており、しかも物語が転がっていくロジックともその存在が矛盾しないように見えるからだろう。こうした丁寧な法螺話が、読む者を嬉しくさせる。
そしてその存在を踏まえて――あるいは梃子にして――推理対決が終盤で繰り広げられるのである。〝物語〟と〝言葉〟の対決でもあるその勝負は、ⅠからⅩまで、十の章で構成された本書において、最後の二つの章を費やして描かれている。連続した怪死事件の真相が、ここできっちりと吟味され、真相なるものが語られるのだ。圧巻である。ミステリを読む醍醐味をたっぷりと味わえるのだ(Ⅸ章における謎解きの見せ方にも要着目)。
その謎解きの鮮やかさ、真相がもたらす驚愕に加えて、真相に至る過程でソクラテスが語る言葉も、ミステリ読者にとっては非常に興味深かろう。「世界の探求にはふたつの方法がある。言い換えれば〝どうやって?〟を求めるやり方と、〝なぜ?〟を求めるやり方だ」とソクラテスは述べているのである。ミステリで言うところの、ハウダニットとホワイダニットだ。読者はその後、ソクラテスが〝誰が殺したのか、そんなことはどうでもいい〟という趣旨の発言をする様も読むことになる。フーダニットの否定である。およそミステリといえば古今東西フーダニットを重視する作品が多かっただけに、実に刺激的だ。こうした言葉を並べながら、柳広司が、あるいはソクラテスが、ハウ、ホワイ、フーをいかに駆使し、いかに真相に到達するのか。本書は、そうした視点でも愉しめるミステリである。
■プラトン『饗宴』
さて、柳広司『饗宴 ソクラテス最後の事件』は、大枠では、プラトンが『饗宴』に記したソクラテスの行動に則って構成されている。柳広司がソクラテスというキャラクターだけを歴史から借りてきて、全くのオリジナルで自由に彼を動かしたというわけではないのだ。
例えば、友人と連れだってアガトンの屋敷を訪れたり、その饗宴の席で女性たちを退けて議論を行うといった展開は、プラトンの記述ときっちり重なっている。また、饗宴で議論に参加した顔ぶれも、ソクラテスに加えて、アガトン、パウサニアス、エリュクシマコス、アリストパネスが共通している。
そうした共通の構造のもとで、アガトンの饗宴にソクラテスとともに参加した人物の一人を、柳広司は別の人物と置き換えた。プラトンによれば、アリストデモスが参加したとなっていた史実を、柳広司は、友人クリトンに置き換えたのである。そしてそのクリトンを本書の語り手に据えた。後に、死刑が決まったソクラテスに脱獄を勧めた人物だ。こうすることで、ソクラテスを探偵役にすることと、彼が死刑を甘受したということがスムーズにつながるように仕立てたのである。
また、プラトンの『饗宴』では、ソクラテスたちの議論はエロスをテーマとするものだったが、柳広司は、ピュタゴラス教団やホムンクルスの話に差し替えた。これもまた本書の謎においてソクラテスがソクラテスらしさを失わずに名探偵として役割を果たすうえで、効果的に機能した。
そう、柳広司は、実に巧みに史実を改変したのである。
ちなみに『二度読んだ本を三度読む』(一九年)というエッセイにおいて柳広司は、ソクラテスが死刑を受け入れたことについて、〝史実に基づいて〟語っている。こちらもまた本書の味わいを深くさせてくれるテキストなので、機会があれば一読されるとよかろう。
■柳広司
さて、本書『饗宴』は、柳広司にとって三作目の著作であり、二〇〇一年に発表された。この二〇〇一年という年は、柳広司にとってデビューの年でもある。『黄金の灰』という長篇ミステリで、彼は、シュリーマンによるトロイアの遺跡発掘を背景に、彼の妻を語り手に密室殺人事件の謎を描いてデビューしたのだ。さらにこの年の彼は、夏目漱石の小説内の世界を舞台に『贋作「坊っちゃん」殺人事件』という長篇ミステリも発表、そしてそれに続く作品が本書なのだ。他の二作も実に密度の濃い小説で、そのうえでの本書だ。柳広司の小説家としてのエネルギーを強く感じることのできる一年である。
ちなみに三作のうちの二作品でギリシアを舞台とした柳広司だが、彼は、二〇世紀が終わろうとするころにバックパックで訪れたことがあるという。会社を辞め、有り金をはたいて欧州に渡った柳広司は、〝押し出されるようにして〟ギリシアに辿り着き、そこで一年あまりを過ごすことになったというのだ。その模様は『パルテノン アクロポリスを巡る三つの物語』(〇四年)に記されているので、本書読者は、こちらにも目を通して戴ければと思う。ミステリファンの心に訴える要素を備えた三篇が収録されており、法廷ミステリ趣味など、三つの異なるテイストを愉しめるはずだ。
本書を発表した柳広司はその後、二〇〇二年にダーウィンが遭遇した怪事件を描いた『はじまりの島』を上梓。さらにその後、原子爆弾の開発や、シートン動物記に夏目漱石あるいはシャーロック・ホームズといった文学などを題材に、史実や小説内の事実をふまえたうえで、その世界にオリジナルのミステリを融け込ませた作品を放ち続けた。
そして二〇〇八年が来る。この年に柳広司は『ジョーカー・ゲーム』を放った。この一三番目の著作は、旧日本軍のなかに昭和十二年に設立された異色のスパイ養成学校――D機関――やその出身者たち、あるいは中心人物である結城中佐の暗躍を、世界各国を舞台に活写した連作短篇集であり、第六十二回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を獲得し、さらに、第三十回吉川英治文学新人賞も獲得し、各種のベストテンでも上位にランクインするなど、非常に高く評価された。この作品のシリーズ化を求める声は強く、その期待に応えて柳広司は、『ダブル・ジョーカー』(〇九年)、『パラダイス・ロスト』(一二年)、『ラスト・ワルツ』(一五年)と、日本の戦局の変化を重ねつつ発表を続け、それらは合計で一二〇万部を超える人気シリーズとなった。映画化やコミカライズ、アニメ化もされている。
そうした人気シリーズの執筆を経て柳広司が発表したのが『象は忘れない』(一六年)である。東日本大震災を題材とした短篇集だ。全五篇からなるこの作品、いずれの短篇も原発事故に振り回された様々な人々にフォーカスしている。原発で働く男、避難した男たち、被災者として東京で幼い娘と暮らし始めた女、トモダチ作戦に従事した米軍の男、幼なじみとの仲を断ち切られた男。さらに、政治や企業の思惑、あるいは〝絆〟〝アンダー・コントロール〟といった聞こえのよい言葉、被災地以外の人々の関心と無関心、そしてもちろん放射能、そういったものが、各篇の中心人物を振り回す様を、この『象は忘れない』は、ヒステリックになるのではなく冷静な視点で、結果的に様々な人々の残酷さを浮き彫りにするかたちで描いている。なかには今日の日本の状況を先取りしたような「卒都婆小町」という短篇もあったりして、やはり柳広司は油断のならない作家だと痛感させられる。
そのなかで本書の読者に注目して欲しいのは、唯一の書き下ろし作品である「善知鳥」だ。トモダチ作戦に従事した米兵と医師の会話で成立しているこの短篇、『ジョーカー・ゲーム』に通じるサスペンスをたっぷりと味わうことができる。そして、その短篇の最後の三行だ。本書『饗宴』とは内容面では全く繋がりはないのだが、本書を読んでから読むと、より一層深く響くだろう。その三行に記された言葉が。
また、「善知鳥」に代表されるように、ソクラテスを死に追いやった紀元前三九九年の民衆(あるいは集団)の〝愚かさ〟が、それから二四〇〇年以上が経過した後にもほぼ変わらずに存在していることを感じさせてくれたりもする。
柳広司はその後、二〇一六年に短篇とエッセイを収録した『柳家商店開店中』(本書への言及もある)を発表し、続いて、二〇一七年に『風神雷神』を発表した。江戸時代初期の天才的な画家の生涯を描いた大作である。
この小説はまったくミステリではないのだが、本書読者には興味深いであろう特徴をいくつも備えている。
まず、俵屋伊年(後の宗達)は、経典絵巻を見て音を聞いた。ピュタゴラスがその考えの根底において〝音と音との純粋な関係性――音楽こそが世界を律する原理の発露〟と捉えていたように、絵師は絵から音を聴き、それを判断の基準にしたのだ。そしてその音は、後に伊年が本阿弥光悦に通ずる道を拓く。なんとも気になる符合である。
また、徳川家康がキリシタンの存在を憂慮したことも書かれている。キリシタンに先立って存在した一向宗徒の存在が、その背景にあった。極楽浄土を信じる彼らにとって、現世の死など取るに足らないこと。それ故に、権力者の支配が及びにくいのである。それと同様の厄介さを、家康はキリシタンに感じたのだ。同様の厄介さは、本書のアテナイにも宿っているのである。
さらには、当時のアテナイにはびこり始めた〝スパルタ風〟という風習に染まった面々は、力を持つ者が弱者を支配して当然という考えを持ち、それはそのまま男が女を支配して当然という考えに繋がっていた。ひるがえって俵屋宗達の時代の我が国では、江戸幕府が、あるいは武家社会が、女性天皇を嫌がった。こんなところにも一致が見てとれるのである。
繰り返しになるが、『風神雷神』はミステリではない。ではなにかといえば、現代の視点から俵屋宗達の生涯を丁寧に語っていて非常に愉しく結末まで一気に読める小説である。そしてまた、ミステリの魅力というカードを使わずとも、ワクワクする小説を生み出せるという、作家・柳広司の実力を確認できる小説でもある。
その力は、もちろん本書でも発揮されていて、例えば探偵役であるソクラテスは、変わり者ではあるが、実に人好きのする存在としてしっかりと描き出されているし(俵屋宗達もそう描かれている)、また、ワトスン役であるクリトンとの会話も抜群に愉しい。
つまり、だ。この『饗宴 ソクラテス最後の事件』は、本稿前半で述べたミステリとしての魅力だけでなく、登場人物たちの言動行動だけでも読ませる小説なのである。しかも、そこで語られている問題意識は、俵屋宗達の時代とも、そして現代とも共通している。要するに、二〇〇一年の刊行から二十年近くが経過した現在でも、全く錆びていないのだ。いやはや、大した一冊である。
▼『饗宴 ソクラテス最後の事件』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321905000422/