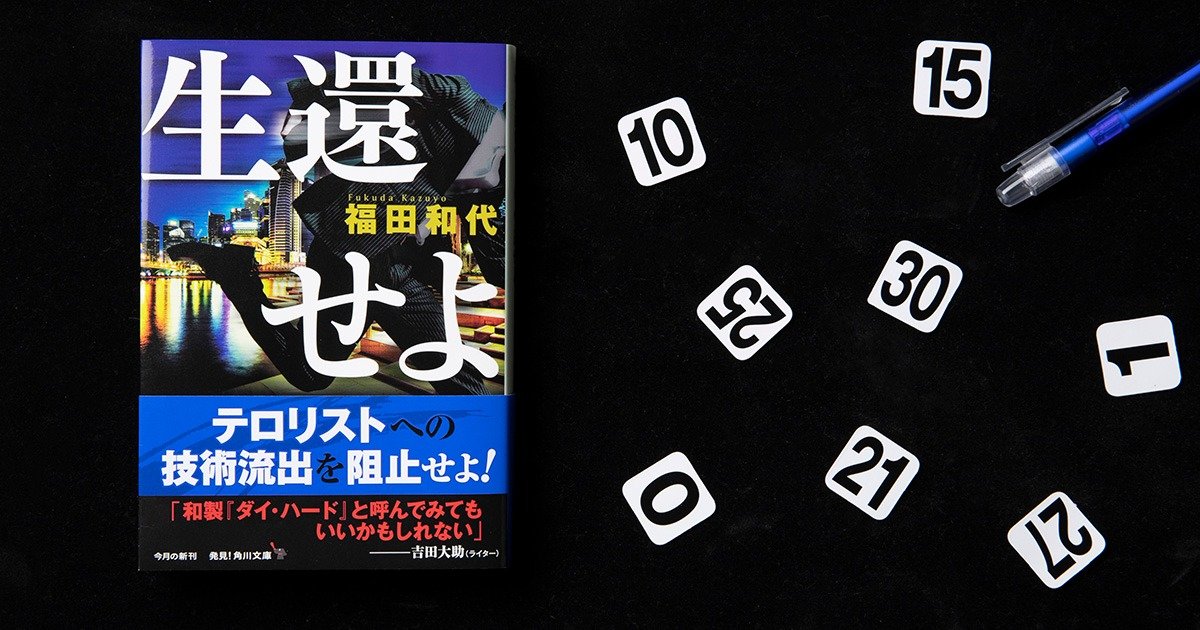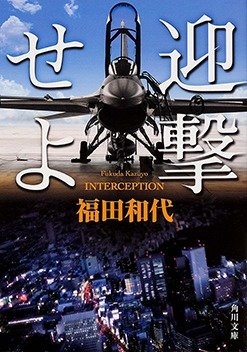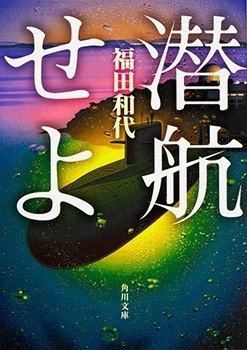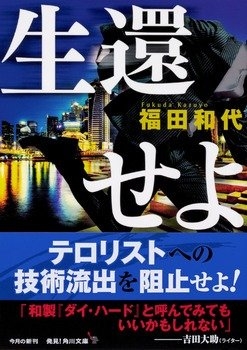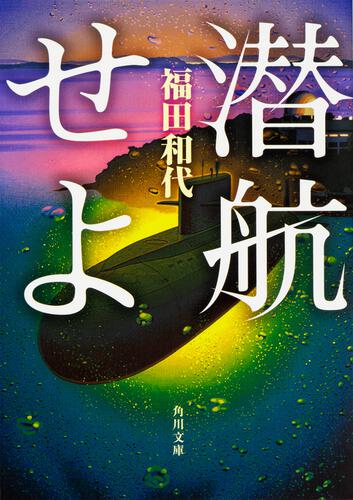文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:
【あわせて読みたい】
▷文庫化記念インタビュー! 作品の着想はどこから?
なんて驚きと感動に満ちた物語だろう! だが、偶然でもなければ、突然変異でもない。福田和代という作家がこの頂に
一つ目は、本作が「安濃将文シリーズ」の第三部であるという事実。二つ目は、デビュー作からまっすぐ「和製冒険小説」のトライアルをし続けてきたという事実。そして三つ目は、執筆時期に関わるものだ。本作の原稿はもともと、月刊誌の二〇一五年二月号から二〇一六年一月号にかけて連載されていた。雑誌の発売日で表記し直せば、二〇一五年一月から二〇一五年一二月だ。つまり、「戦後七〇年」の節目に執筆された作品であるという事実。
全ての始まりはもちろん、二〇〇七年六月刊のデビュー作『ヴィズ・ゼロ』だ。香港発福岡行きの旅客機がハイジャックされ、一五〇名の乗客とともに関西国際空港に着陸した。警視庁捜査第一課でサイバー犯罪の捜査を専門とする
この一作を執筆した経験が、「安濃将文シリーズ」の第一作に当たる二〇一一年一月刊の『迎撃せよ』へと
主人公の不遇極まりない「巻き込まれ体質」は、二〇一三年一〇月に刊行されたシリーズ第二作『潜航せよ』でももちろん健在だ。前作の一連の事件のほとぼりがようやく冷め、安濃は長崎県
この二作を踏まえたうえで、時系列の先に展開される物語はどんなものとして構想されるべきか。作家にとって手がかりは、自衛隊が「陸海空」の三部門に分かれているという事実にあったと思われる。第一作『迎撃せよ』は「空」の物語だった。第二作『潜航せよ』は「海」だ。ならば第三作は当然、「陸」でいく。しかし、ここで作家はこれまでと異なる想像力のルートを辿った。「陸」の一語から「陸軍」へと連想をジャンプさせ、「陸軍中野学校」に接続。先の大戦中に実在した、日本で初となるスパイ養成学校を物語の基軸に盛り込んだのだ。そうした想像力の裏には、この作品がこのような物語として書かれた三つ目の要素として冒頭で挙げた、「戦後七〇年」の節目に執筆されたという事実があったはずだ。作中時間も二〇一五年であることが明記されたこの物語はさまざまな点で、二〇一五年だったからこそ書かれた意味がある。
もう少し事実関係を確認しておこう。二〇一六年六月に単行本が刊行された本書、「安濃将文シリーズ」第三作『生還せよ』は、過去二作にはなかった想像力を「解禁」している。まず、主人公の安濃が活動する主舞台は日本ではなく、外国だ。そして、現実には存在しない(と現実の日本政府は「公式発表」している)、政府お抱えの「スパイ」組織がひそかに立ち上がっていた……という世界改変の想像力を発動させている。
物語の冒頭、第一作の肩書きから(ついに)一階級昇進し「三等空佐」となった安濃は、同期の泊里三等空佐とともに、シンガポールが誇るマリーナ・ベイ・サンズホテルのカジノで人を待っている。二人は航空自衛隊から内閣府の遺骨収容対策室へと出向中の身だ。建前上は、先の大戦におけるシンガポールの死者の遺骨を調査するための出張だが、その内実は、内閣府が極秘裏に立ち上げた
しかし、現地協力者である
……という要約が通用するのは、最終二二章およびエピローグを読む前までだ。それらを読むことによって、それまで読み進めてきた物語は、新たな可能性へと切り開かれていく。
以下、ネタバレ込みで記述していきたい。
最終二二章は全編、ある人物が安濃に宛てて書いた手紙だ。日本の厚生労働省が進める戦没者慰霊事業および内閣府の遺骨収容事業と、大戦下に実在した日本初のスパイ組織・陸軍中野学校、両方に関わる人物がこれまで誰にも言えずにいた「告白」の記録だ。そしてエピローグでは、その人物と別の人物との七〇年ぶりの「再会」が描かれる。
単行本刊行直後に読んだ際にも、最終二二章およびエピローグで開示される一連のドラマに、大いに驚き感動を味わった。だが、三年後(作中時間で記せば五年後)の二〇二〇年の初めにこうして文庫化されるにあたり、再読してみると、ラストの驚きと感動が倍増している事実に直面した。理由は二つある。一つ目は、エピローグの時点で「再会」の当事者たちは九〇歳前後(=終戦時に二〇歳前後)だった。彼らの二〇二〇年の姿を想像する時、鬼籍に入っていると考えるのが自然ではないだろうか? 少なくとも、この物語を二〇二〇年の時代設定で書くことは、リアリティの問題で
もう一点は、それまで二年半に一冊ペースで刊行されてきた「安濃将文シリーズ」が、本作を機に休止している事実と関わってくる。最終二二章の手紙の中で、書き手は己の実存を懸けて、安濃にこんな言葉を記している。〈引き返せるのは、今しかない。──もし、あなたがそれを望むのなら〉。もしも本作の時系列の先にある物語を執筆するならば、安濃が引き返したか否かの選択を描かなければならない。作家は「続編を書かない」という選択肢を三年間選び続けたことによって、この物語自体が求めてくる余韻を、物語のためにたなびかせたのではないか。その意志を感じて、大いに驚き大いに感動したのだ。二〇二一年、あるいはもっと未来に読んだならば、なおさらだろう。
とはいえ、今後「安濃将文シリーズ」の続編が書かれることは、まったく不思議ではない。本作の余韻を愛する読者にとっては不安かもしれないが、そんなことは百も承知な作者が書き出す続編に、マジックがかかっていないわけがない。とりあえず二〇二〇年の今は、三作を頭から読み返すことからまた、新たに始めてみよう。
▼福田和代『生還せよ』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321906000218/