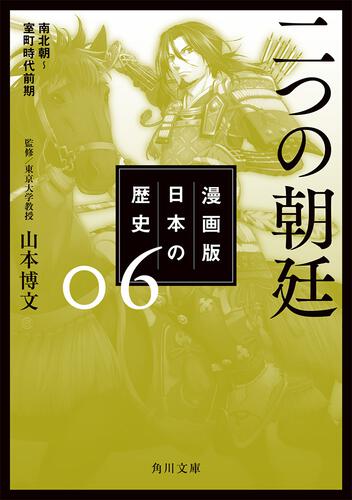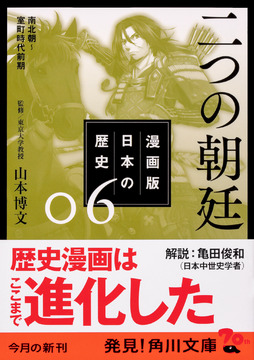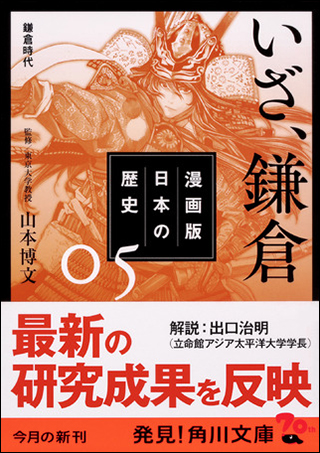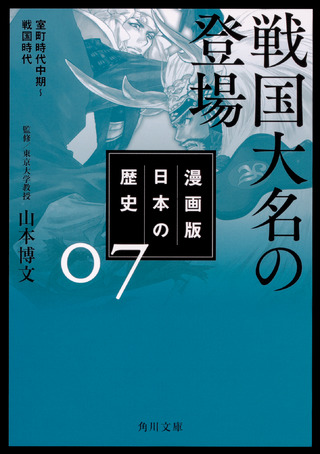本書は、二〇一五年六月に刊行された角川まんが学習シリーズ『日本の歴史6 二つの朝廷 南北朝~室町時代前期』の文庫版である。一四世紀の鎌倉時代末期から始まり南北朝時代を経て、一五世紀前半の室町幕府四代将軍足利義持の時代に至る日本史を扱っている。
この時代の概要を簡単に説明すると、朝廷が分裂し、大覚寺統と持明院統から交互に天皇が即位する状況となった。大覚寺統の後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼし、天皇を頂点とする公武統一政権を樹立するが(建武政権)、足利尊氏の裏切りにあってわずか二年あまりで倒壊する。尊氏は京都で持明院統の天皇を擁立し(北朝)、第二の武家政権・室町幕府を樹立する。だが後醍醐は大和国吉野に亡命して南朝を発足させ、以降約六〇年にわたって南北朝の内乱が続く。明徳三年(一三九二)、三代将軍足利義満がようやく南北両朝を合体させ(南北朝合一)、以降しばらく室町幕府の全盛期が続く。
戦乱の時代であることもあり、本書は当然政治史がメインに叙述されているが、蝦夷代官安藤氏とアイヌとの北方交易、二毛作の普及、商業の発展、連歌・能などの発達といった経済史・文化史にも言及がある。子どもたちに日本史に興味を持ってもらうための入門書として最適である。しかしながら、この時代の研究は近年急速に進展しており、従来の通説も大幅に見直されつつある。
文保の御和談。近年の研究では、「一〇年ごとに両統から交代で天皇を即位させる」という約束は交わされていなかったとされる。「御和談」どころか、大覚寺統が持明院統に仕掛け、後醍醐天皇即位を実現させた激しい権力抗争だったのである。
正中の変。「後醍醐は実は倒幕を企んでおらず、冤罪であった」とする説がある。後醍醐は親幕派の公卿西園寺氏の血をひく世良親王(後醍醐皇子)を皇位継承候補とするなど、当初はむしろ鎌倉幕府との協調路線をとることで皇位を維持し、自分の子孫へ継承させようとした形跡がある。
建武の新政。「後醍醐が武士を冷遇したため、武士層の不満が高まり短期間で倒壊した」とするのが通説である。しかし近年の研究では、「建武政権は武士に対する恩賞充行に積極的だった」ことが指摘されている。それだけではなく、建武政権の政策の多くも朝廷や鎌倉幕府の政策を継承し、改良を加えた現実的なものであり、後進の室町幕府も模倣したことが判明している。
新田義貞。「新田氏は足利氏と並ぶ清和源氏の嫡流であり、義貞と尊氏は武家の棟梁の座をめぐって戦った両雄である」と描かれることが多い。しかし、「新田氏は足利一門であり、平安以来足利氏に臣従した家」とする見解が近年登場した。にもかかわらず、義貞が尊氏と敵対して最後まで激しく戦った理由については、今後の研究課題であろう。
草創期の室町幕府における尊氏と弟直義の二頭政治。両者の権限は、直義に大きく偏っていた。恩賞充行と守護職補任を尊氏が行う以外は、軍事指揮権を含む幕府のほとんどすべての権限を直義が行使した。「二頭政治」と言うよりは、「直義が事実上の幕府最高権力者として君臨する体制」であったと考えるべきである。
直義と執事高師直の対立の原因。本書も描くように、「直義が前代鎌倉幕府を模範として保守的な政策を採ったのに対し、師直が武士の権益伸張に努めて公家や寺社の荘園侵略を推奨したため」とするのが通説であったが、近年はこの見解も再検討を迫られている。残された史料を網羅的に俯瞰する限り、「師直もまた鎌倉幕府的な価値観を踏襲する保守的な武士で、あくまでも合法的な恩賞給付にこだわったため、それから漏れた武士の不満が高まったことが対立の根底にあった」と解釈した方が、当該期のさまざまな現象を整合的に解釈できるのである。
正平一統。「尊氏は直義を打倒するため不本意ながら南朝と講和し、講和条件も最初から守る気がなかった」とするのが通説である。しかし、実際には尊氏は南朝との講和交渉をきわめて熱心に進めている。私見によれば、元来「後醍醐天皇の承認の下に幕府を開く」のが尊氏の政策目標であった。少なくともその点に関しては、かつて果たせなかった夢に限りなく近い正平一統を尊氏は積極的に支持した。実際本書も描写するように、先に講和を破棄して攻め込んだのは南朝である。
南北朝合一。本書では、義満が両統迭立の講和条件を破ったことにされている。しかし、旧北朝後小松天皇が称光天皇(後小松皇子)に譲位し、その破棄が明確となったのは応永一九年(一四一二)で義満の死後である。義満存命中は一応旧南朝の皇族たちも迭立の履行に望みをかけており、細かい点であるが訂正が必要である。
義満の皇位簒奪計画。かつて、「義満が皇位を狙っていた」とする学説が一世を風靡した時代があった(厳密には、子息義嗣を天皇に即位させ、義満自身は太上天皇として君臨する構想)。その後、この学説には多数の批判が寄せられ、現代ではこれを支持する研究者はほとんどいない。本書も、近年の研究成果を反映し、義満の皇位簒奪の意図については曖昧な描写となっている。だが結局、足利義満の権力とは何だったのか。義満自身がそれを語らないまま急死したこともあり、統一的な通説をなかなか出せない状況である。今後も、活発な議論が続くことが予想される。
上杉禅秀の乱と足利義嗣。本書では、禅秀と義嗣が結託していたことになっている。実際、当時からそうした見方が存在したが、近年の研究は両者の提携には懐疑的である。
以上、近年の見解を紹介したが、それらは本書の入門書としての価値を下げはしない。長年受け入れられてきた従来の通説をまずはしっかりと理解して初めて、新説の斬新さや意義を正しく理解できるからである。繰り返しになるが、本書は初学者にとって最適の入門書である。