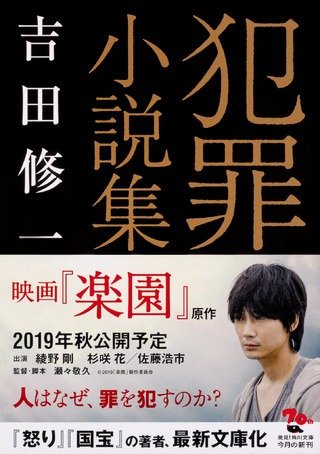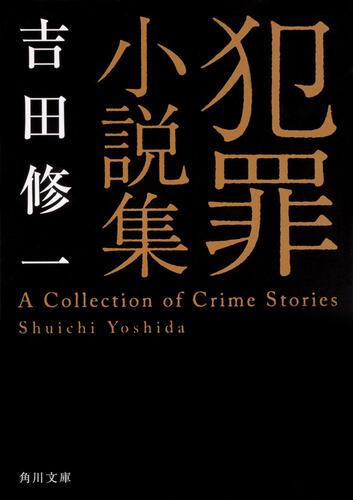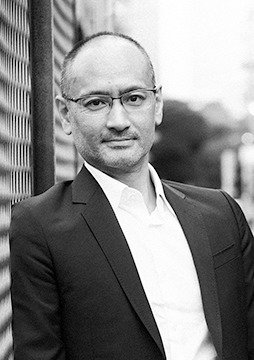吉田修一氏の小説には登場人物たちの生きる空間がいつも丹念に描かれている。以前から、そこに強く惹きつけられてきた。映像化された小説に限っても、『悪人』の主人公は博多方面から峠を越えた地方に住んでいて、そこに暮らす主人公の心象が博多という煌びやかな街への憧憬とねじれた意識として行動の源泉を培っていた気がした。『横道世之介』にしても東京へ出た地方の大学生の、中央へ出た高揚感が相まって作品の根底を作っている。『さよなら渓谷』は東京近郊の渓谷沿いの町というものが、そこに住む人々の感情の渦と共にヒロインに影響を与え、寄る辺ない空気を描き出していた。『平成猿蟹合戦図』にしてもそうだ。歌舞伎町のバーテンダーが故郷の秋田県大館市から国会議員に立候補するという物語であり、ここでも中央と地方という場所の比較と移動が物語の主軸に大きく貢献している。
僕の大好きな氏の小説で『元職員』がある。これもまた横領事件を起こした公社職員がバンコクの地に嵌っていくという物語であり、ニッポンとアジアという空間の移動と対比が物語を象っていく。だが、そこにある空間、たとえば中央と地方というものが旧来の対立概念としてではなく描かれているのが、吉田修一氏の小説の面白さだ。地方を搾取する中央、中央に媚びへつらう地方、そういった対比とは違うレベルで小説の中では場所が設定されていく。もっと複雑化しているといっていい。実際に僕らの生活に現れる地方には、国道沿いに大型量販店が並び、駅前は閑散とした同じような景色がある。アメリカナイズされた大型量販店に人々がひしめき、かつてのディスカバージャパンなどとうに存在しない。一方ではインターネットやテレビで情報は瞬時に日本中に回る。地方は、地方だけでは存在しえない。都会からUターン、あるいは移住者、そういう人々を迎えることでやっと存在できている。対立、拮抗という世界観はもはやない。平たいのだ。平たい同じ延長の中で地方と中央があり、そこで登場人物たちは、行動し生きていく。吉田修一氏の小説のイメージは常にそういうところが基本にまずあった。自分自身が九州の片田舎に生まれ育ったということも理由なのか、その空間設定に常に惹かれていた。
そこに生きる登場人物にも特徴がみられる。彼らは世間の中で生きている。世間とは彼らを取り巻く地縁、血縁、仕事関係の縁、人々の噂話と他者への容赦ない視線、それらが渦巻く場所であり、それは前近代にも共通するともいえる。そこは大概の人間がそうであるように社会とは一見、無縁のように存在する。だが、それらムラの共同体で生きていたと思われた主人公が事件に巻き込まれ、行動、あるいは流されていくときに社会的な人間として見られていき本人の意思とは関係なく社会的人物へと変貌をとげる。自我や自意識という主人公が持つべき特色はそこにはないのにだ。そういう主人公たちこそが、今、この時代を生きている感じが、ずっとしてきた。そこに魅了され吉田修一氏の小説を読んできた。
だが、犯罪をめぐる五つの短編からなるこの『犯罪小説集』を本屋で手に取り読んだとき、今までとは少し違う感覚を覚えた。今ということだけではないものが、そこにある気がした。
ある小説が思い出された。中上健次の『千年の愉楽』だ。中上が描き続けた被差別地域「路地」を舞台に、そこで生きる血の薄い歌舞音曲に長けた中本の一統の男たちが生きて、死んでいく様子を路地の産婆であるオリュウノオバの語りで書きあげられた連作短編集。『犯罪小説集』にも差別という根幹があるのだが、それにもまして登場する〈犯罪者〉たちの姿が『千年の愉楽』の男たちの生まれ変わりのように思えて仕方なかった。
「青田Y字路」で少女失踪事件の犯人ではないかと容疑を掛けられ、同様の事件が再び起こった時、焼身自殺してしまう豪士は、『千年の愉楽』の「天狗の松」の主人公、文彦に似ている。文彦は、幼い頃、神隠しにあい数日間、行方が分からなくなるが、やがてひょっこり現れる。成長し、修行中の巫女を路地に連れ帰り情交中に殺してしまい、やがて自分が幼い頃神隠しにあったところに植わっていた松の木に首をくくって自殺する。神社を近くにもつ杉の木の下にあるY字路と松の木、それら象徴的な空間とともに失踪をモチーフにし、二度起こる事件、そして主人公の自死。『犯罪小説集』を読んだとき、現代の物語でありながら、どこか寓意性に富んでいて、それこそ前近代の説話集を読み進めるような感興があった理由がこれだと思えた。
「曼珠姫午睡」は唯一の女性主人公だ。テレビを賑わすスナックママが殺人の容疑で逮捕されたというニュースを見て、幼い頃の同級生を発見する普通の主婦、英里子が主人公となる。やがて英里子は、毛嫌いしていたゆう子の人生を追体験していくことになり、その情交と色欲の世界に自ら踏み込もうとしながら、すんでのところでとどまるところで物語が終わる。『千年の愉楽』の「半蔵の鳥」を思い出した。中本の一統の中でも最も男ぶりのいい半蔵が、色欲に動かされ情交を重ね、それが原因となって刺殺される。一方、英里子はこちらの世界に踏みとどまる。ラストは違うのだが、オリュウノオバと情交したとされる達男が北海道の炭鉱に行き、アイヌの若い衆と知り合い暴動を起こそうとして失敗し殺されるという「カンナカムイの翼」と語りの方法が似通っている。この一編では、唯一達男の最後はアイヌの若い衆から語られる。「曼珠姫午睡」の語りの重層性、主人公の二重性に共通点が見られる。
「百家楽餓鬼」は運送会社の御曹司として過不足なく暮らしてきた永尾がマカオのカジノに嵌り、破産寸前までいく姿をカジノでの賭博プレイと過去との回想を交えながら描いている。同じく『愉楽』では「六道の辻」で、中本の血を引く三好が、ヒロポンをうったり盗みをしたりの生活を繰り返しついには目が見えなくなり、首をくくって死ぬ。だが永尾は死なない。「曼珠姫午睡」の英里子と同様に、死の一歩手前で、こちら側にとどまるのだ。とどまりながら尚も修羅的な世界を生き続けようとする。そこに明らかな違いがあり、より現代的な主人公の在り方が見られる。
だが、続く「万屋善次郎」は再び主人公の自死で物語が閉じられる。限界集落、そこに住む老人たちの中で最も若い善次郎、といっても彼自身、人生の晩年に既に踏み出した年齢、彼が養蜂で村おこしを行おうとするが、ボタンの掛け違いで集落の人間たちから村八分にあった果てに、集落の人々を次々に殺し、最後に自死を図る。殺人を行う一歩手前の時期、善次郎は飼い犬のレオと共に体が弱っていく。『千年の愉楽』の「天人五衰」の主人公、オリエントの康が題名の「天人五衰」通りに身体の隅々まで弱っていく様とよく似ている。「天人五衰」とは生まれ変わりをテーマにした三島由紀夫の小説『豊饒の海』第四巻の題名でもあり、六道最高位にいる天人が死の間際に訪れる衰退のさまを指した仏教用語だ。人間と飼い犬の交流と事件の関わりは地上の論理のレベルを超える魂の交感の様まで見せてくる。レオの目線によって語られる叙述。「万屋善次郎」において、吉田修一氏の『犯罪小説集』における目指すものが明らかになった気がした。今日の犯罪を描きながらも過去へも未来へも飛べる視点と視座を小説内に内包しようとした物語集。
最後を飾る「白球白蛇伝」、この題名に示される白蛇が、重要なモチーフとして小説内には用意されている。記者の山之内が早崎弘志の生まれ故郷に何度となくインタビューに訪れるが、そこにはかつて遊郭があった中州があり、そこには白蛇神社がある。早崎に傷害事件を起こされる相手の田所が酔って早崎と歩く帰り道、その神社の境内で立ちションをし、「心の中で罰当たりなことをして申し訳ないと詫びる」と思いをこぼす。『千年の愉楽』にも〈浮島〉と呼ばれる中州地域が何度か出て来て重要な空間として機能している。
ただ、ここまで『千年の愉楽』との比較を試みながらも、『犯罪小説集』は説話系物語集からは大きく飛躍している部分があって、そこが現代の物語として成立する魅力だと思える。犯罪という非日常を描きながらも、日常の間の中にしっかりと根付いたような佇まい。果たしてこれは何だろうと思った時、映画化に当たって何度か吉田さんと会っていった中に、ふと吉田さんが言った言葉が印象的だった。『犯罪小説集』はワイドショーのような感じ、正確な言葉ではないが、そのような発言だった。確かに僕たちが今、現在、現実の犯罪に触れる機会がもっともあるとすれば週刊誌やネットやテレビのニュース、とりわけワイドショーである部分が多い。そういう映像を通して、僕らは犯罪を知っていく。犯罪を行う人、行わなかった人、その両者の閾に存在しているのがワイドショーともいえる。この短編集の中にもワイドショーは頻出してくる。登場人物たちは、そこで扱われ、社会的人間へと変貌し、あるいは、そこで事件を見た人は、逆に犯罪に魅了されたかの如く境界地へと冒険の旅に出ようとする。『犯罪小説集』がワイドショー的だと言っているのではない。ワイドショーの犯罪報道をめぐる人々の生活と変貌が、報道される側、それを受け取る側、両者の境界点に存在するように、この小説集もあるのだと思う。
そして、それら犯罪をめぐる犯罪者たち、あるいはそこに踏み込もうとしながらすんでのところで止まった人々、それらの人々全員が何かを求めて、何かを欲して生きているように見えるのが『犯罪小説集』の魅力なのではないか。僕には思えた。よって映画のタイトルは僭越ながらも『楽園』とさせていただいた。
やはり誰もが何かを求めているのだ。
レビュー
紹介した書籍
関連書籍
-
試し読み
-
試し読み
-
特集
-
試し読み
-
特集