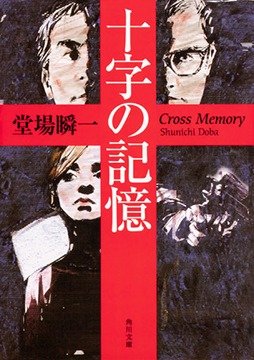日本の会社や組織に最も欠けているのが危機管理ではないだろうか。
危機管理の要諦は、あらゆるリスクをリストアップし、その対応方法を充分に練り込み、いったんことが起きれば用意されたマニュアルに従い毅然と実行することであろう。
言葉にすれば簡単だが、この三つのフェーズのどれが欠けても危機管理は破綻せざるを得ない。事件や事故が起きるとすぐに「想定外」という言葉が出る。これは最初のフェーズである予測されるリスクの網羅に漏れがあるからだ。そしてそれに沿ったマニュアルがないから場当たり的な対応を取ってしまい、ダメージがより大きくなる。さらにこの二つのフェーズが整っていても、実行が伴わなければなにも準備がないことと同じになってしまう。
最近でも有名大学の運動部監督のパワーハラスメントや、文学部教授のセクシャルハラスメントが表に出たが、被害者の訴えを受けて対応する義務がある大学上部組織の不手際によってより問題が広がり、いっそう世間の耳目を集めたことは記憶に新しい。この二つの事例は、あらゆるフェーズに問題があったように思えるが、特に日本人に特有の権力者への阿りと忖度が顕著だった。
堂場瞬一が本書で挑んだのは、日本社会がもっとも苦手とする危機管理に関する問題だ。
大手総合商社テイゲンに脅迫文書が届いた。現会長である糸山が三十年前の営業部長時代にソビエト連邦と不適切な関係を持ち、不当な利益を得ただけでなくスパイ行為も行っていたという、衝撃的な内容の文書だった。テイゲンの総務部から報告を受けた危機管理専門会社「TCR」(Tokyo Crisis Response)はさっそく調査に乗り出し、「TCR」社長の光永護は、入社三ヶ月の新人、長須恭介を調査の中心に抜擢する。
三十年前に、亡命希望のパイロットが操縦するソ連の最新鋭機Su―25MMが、レーダー網をくぐり抜け、宍道湖に不時着した事件があった。糸山はその事件の直後、現地におもむき、パイロットと接触した。脅迫状にはそのように読み取れるワープロで作成された業務日誌のコピーも添付されていた。その用紙はかつてテイゲンが使用していた公式用箋であり、脅迫の内容には信憑性があった。やがて現金十億円を要求する第二の脅迫状が届く。
宍道湖へのソ連機不時着事件のモデルは、一九七六年九月に起きたペレンコ中尉事件である。ペレンコ中尉が操縦する当時最新鋭のMiG―25戦闘機が函館空港に着陸したのだ。自衛隊は領空どころか国土を侵犯されても気づかなかったわけで、当時は大騒ぎになったものだった。ペレンコは希望通りアメリカに亡命、MiG―25は解体され航空自衛隊百里基地に運ばれ、精細な調査の後にソ連へ返却された。当時は緊張緩和が醸成された「デタント」の時代だったとはいえ、東西冷戦は続いていた。まかり間違えば、一触即発の事態も考えられた出来事だった。
本書の主人公である長須は三十四歳。前職は神奈川県警の捜査一課の刑事だった。長須には二つの問題があった。一つはいわゆる精神的外傷である。警察を退職した理由が、身内に起きたある事件(その詳細は物語の終盤に判明する)に衝撃を受けたからなのだ。それが彼の心身を蝕み、神奈川県警の先輩である光永に拾われなければ、人間として駄目になっていたのではないかという自覚があった。光永はそれを見越して三ヶ月の間、仕事らしい仕事をしていなかった長須の復活ももくろみ、企業恐喝という大事件に投入したのだ。
もう一つの問題が、「正義」に関する解釈だ。長須のいう正義は警察官時代の考えを踏襲していて実にシンプルである。そこに犯罪があれば、それを暴き、実行した者を捕まえる。その考えが身にしみ込んでいるのだ。だが「TCR」ではそうはいかない。あくまでもクライアントの要望を通すことが一義になるのだ。といってもそれは犯罪を見逃すことではない。作中でも、危険ドラッグの売買に関わっている疑いがある社員という事例が語られる。クライアントから相談を受けた「TCR」は、それが事実であることを調査した上で、社員を馘首した後に、会社から警察に密告することを提案したとある。元社員ということで会社のダメージを減らし、警察に報せることで社会通念上の正義を守ったことになる。このように、これまで考えもしなかった複雑な「正義」のあり方に、長須は困惑し戸惑いを見せるのだ。
ともあれ長須は、添付文書で使われているワープロの機種特定をはじめとして、三十年前の事件の手がかりを求め、不時着事件が起きた宍道湖のある松江市に赴くなど調査を進めていく。だが、なかば強制的に証言を求めることができた警察官時代と違い、民間企業の調査員という立場での聞き込みに往生するのである。しかも調査の理由は当然ながら相手に明かすことはできない。隔靴掻痒の調査に苛つくこともしばしばなのだ。これも正義のあり方とともに、長須が初めて経験する事態である。
さらに第三者への聞き込みだけでなく、協力すべきテイゲン側も一筋繩ではいかない。担当である総務部長の藤原、脅迫の当事者である糸山会長らも、都合の悪い事実を隠し、すべての事情を明かそうとしないのである。このように、警察官時代とはまったく違う環境の中での調査を通じて、本当のやる気を失っていた長須が、徐々に変貌を遂げていくのである。
本書は「復活」がテーマの物語でもあるのだ。脅迫犯の正体をめぐる謎、会社や自分の立場を守ろうとする者たち、さらに出世争いがからんだ企業内の複雑な人間関係。さまざまな要因による障碍が長須の前に立ちふさがる。長須は自分自身の壁を破るのと同時に、その障碍にも挑んでいく。その過程こそが本書の最大の読みどころであろう。
さらにサブキャラクターが曲者ぞろいな点にも注目したい。長須の調査に同行する堺美和は、弁護士資格を持つ調査員だ。物怖じしない性格のシングルマザーで、相手の懐に飛び込み、情報を得るのが巧みなのだが、どこか危うさを感じさせる女性なのだ。また本島という男は長須と同じく警察を中途退職した調査員だ。物静かで頼りになる先輩なのだが、退職の原因となったある出来事により、身を持ち崩した経験がある。そして光永社長の娘で調査以外の部門で会社を取り仕切る専務の光永碧も存在感が抜群だ。おそらく本書がシリーズ化されれば、彼らが抱える問題などがもっとクローズアップされ、キャラクターの深みも増していくのではないかと思う。
余談であるが、本書ほど煙草を吸う人間が登場する作品も最近では珍しい。社長以下、「TCR」の調査員たち、テイゲンの関係者、不時着事件に関わった松江の警察官など、多くのシーンで煙草が吹かされるのだ。作者が愛煙家かどうかは知らないが、「嫌煙」になびく社会へ向ける何かの思いがあるのだろうか。
本書の作者堂場瞬一は二〇〇〇年に『8年』(集英社文庫)で第十三回小説すばる新人賞を受賞してデビューを果たした。この作品はメジャーリーグに挑戦する日本人野球選手を描いたスポーツ小説である。一読三嘆し、ミステリーではないのに、当時連載を持っていたミステリー専門誌でさっそく取りあげたことも懐かしい。続く第二作が後にシリーズ化される刑事・鳴沢了が登場する『雪虫』(中公文庫)だったことも印象的だった。後年になればわかるのだが、堂場瞬一は主にスポーツ小説と警察小説を両輪として、次々と話題作を発表し続けるようになる。そのことは最初の二作で決まっていた道だったのかも知れない。
すでに堂場瞬一の著書は百冊を超えているが、その中心は先述したようにスポーツ小説と警察小説である。その中で本書は、警察小説と同様の調査過程が中心となる物語であるが、主人公を民間企業調査員に据えたところに新たな展開がある。本書ではまだまだ心許ない点が多々ある主人公であるが、彼が一人前の調査員になったと胸を張れる物語をと、本書の読者ならば誰もが思うだろう。続編を鶴首する次第である。
>>堂場瞬一『黒い紙』
レビュー
紹介した書籍
おすすめ記事
-
レビュー
-
レビュー
-
特集
-
レビュー
-
レビュー