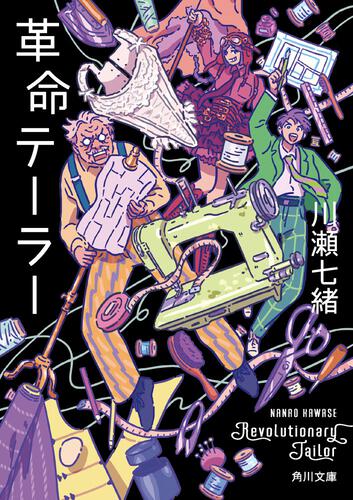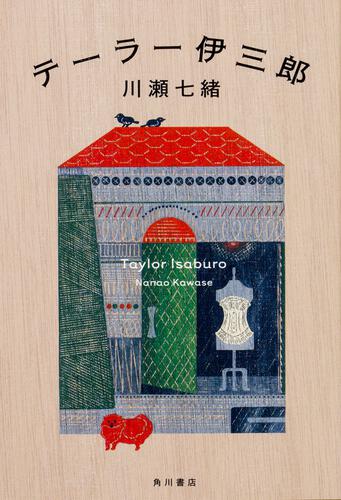3月1日に刊行された川瀬七緒さんの書き下ろし長編小説『四日間家族』。帯の「徹夜必至」という言葉どおり、圧倒的一気読み小説だと評判になっています!
物語は、自殺を決意して集まった四人の男女が、森に置き去りにされた赤ちゃんを保護したことで犯罪に巻き込まれてゆく、というストーリー。
「最初は暗い話かなと思ったけれど、全然違ってびっくり!」
「中盤からどんどんスピードアップしてゆく展開にのめり込む」
「ネットの炎上、集団の無関心。知らないうちに自分も加担しているかもしれない。心がざわついた」
などリーダビリティと読み応えに賞賛の声が集まっています。
好評御礼企画として、第一章「最悪への扉」を全文公開!
『四日間家族』第一章公開#01
1
室内灯に照らされた車内はじめじめと湿っぽく、古い機械油のような刺激臭が漂っている。足許には丸められた軍手や煙草の空き箱などが散乱し、身じろぎをするたびジャリジャリという砂を踏むような音が耳に障った。何よりも、窓やドアが赤いビニールテープで目張りされているさまが異様ではないか。不衛生な環境と相まって、嫌というほど恐怖心を搔き立ててくる。
ここがわたしの人生最期となる場所……臭くて汚いこの場所が。
わたしは落胆しながら肩越しに後ろを振り返り、バンの後部にある荷室へ目を走らせた。左右に渡された紐には真っ黒に汚れたタオルが何本もぶら下がり、何かの部品や工具の入った箱が無造作に重ねられている。さらには得体の知れない褐色の液体がこぼれているのが目に入り、背筋に悪寒が駆け抜けた。
トートバッグからハンドタオルを出して口許に強く押しつけ、柔軟剤のケミカルな匂いを胸いっぱいに吸い込んだ。今日身につけている衣類はすべて洗い立てで、出掛けにはシャワーを念入りに浴びてきた。万が一の嘔吐に備えて昨日から何も食べていない。それもこれも、死後に無様な姿を晒したくなかったからだ。それなのに、よりにもよって自分はこんな場所にいる。
あまりのみじめさに奥歯を強く嚙み締めたとき、運転席にだらしなくもたれていた男が、がらがらにかすれた声を出した。
「この辺りの山は国有林で滅多に人は来ない。私有地で死ねば残された身内に賠償請求がいく場合もあるが、その点、国の管理なら安心だぞ」
「だけど、人が来ないんじゃ見つけてもらえないのかね」
助手席から老女のしゃがれ声が聞こえた。
「心配すんな。出掛けに俺の妹宛に手紙を出してきたからな」
「そうかい……なら気を揉むことはないね。人知れず朽ち果てるのは、いくらなんでも切ないからねえ」
老女が安堵したように胸に手を当てると、男は緊張感の漂う車内に目を走らせた。垢じみたねずみ色の作業着には「有限会社長谷部鉄工所」との刺繡が縫いとられ、先ほどからひっきりなしに貧乏揺すりをしている。男は運転席から後ろを振り返り、過剰なほど探るような視線を向けてきた。
「俺はこの会の発起人だ。おまえさんらの命を握ってると言っても過言ではない。なんせ、こうやって集団自殺の場を設けたんだからな」
男は脂ぎった大きな顔を両手で叩き、あらためて順繰りに目を合わせてきた。が、わたしの隣に座っている少年は身じろぎひとつしなかった。
「ここまでの道すがらずっと考えてたんだが、俺は自分の責任を果たすべきだと思ってる」
「責任? なんの責任だい」
老女が助手席から運転席へ顔をやると、男はごくりと喉仏を動かした。
「ここにいる三人が死ぬのを見届けてから、俺も後を追うってことだ。だれかひとりでも生き残っちまったら、俺は発起人として死んでも死に切れねえ。でも安心してくれ。俺はだれも置いていくことはしねえからよ」
男は何度も喉を鳴らし、汗の浮く額を手の甲でぬぐった。突出気味の濁った目は常にあちこちへと動き、心なしか指先が震えているようにも見える。
わたしは何度も男を盗み見て、今さらながら後悔した。待ち合わせ場所で車に乗り込んだ瞬間から、この男は憑かれたように喋り通しだった。自分の人生観を語り、急に場違いな説教が始まり、挙げ句に意味のない自慢話を延々と聞かされた。恐怖心の裏返しだと思おうとしたが、そうではない。この男は死への覚悟ができていないのだ。いざ自死を決行するとき、怯えるあまり騒ぎ出すのではないだろうか。
わたしはため息をついてスマートフォンに目を落とし、圏外の表示を見て久しぶりに声を出した。
「突然ですみません。タクシーが拾えるところまで車で送ってもらえませんか?」
とたんに男と老女が振り返り、隣でうつむいていた少年も目だけを向けてきた。
「気持ちの整理がつかなくて、もう少し考えてから結論を出したくなったんです。土壇場でご迷惑をかけて本当にすみません」
わたしはもっともらしい理由を口にし、申し訳ありませんと再び頭を下げた。気持ちの整理はすでについているが、ひとりで死ねるのかと言えば今の自分にはできそうにない。人の力を借りなければ到底無理だった。しかし、ここにいても決意が揺らぐだけなのは確実のような気がした。
わたしは上目遣いで男を見やったが、彼は引きつった薄笑いを浮かべて言い放った。
「そんな義理はねえよ」
想像していなかった答えに「え?」とわたしは顔を上げた。
「これだから女は面倒なんだ。最後まで人を振りまわすつもりかよ。俺は引率の教師じゃねえし、気が変わったんなら今ここで車を降りろ」
「いや、スマホが圏外でつながらないんですよ」
「そんな理由はここにいるだれにも関係ねえ。ケータイがつながるとこまで山を下りればいいだけの話だ」
情け容赦のない言葉を受け、わたしは恨めしい気持ちで男を見つめた。外灯ひとつない漆黒の山道を歩いて下りろというわけか。まあ、送る筋合いがないというのはその通りなのだが。
男はにやにやしながらなおも言い募った。
「夜の山を歩くのが嫌なら朝までここにいればいい。三人がくたばってから悠々と山を下りるって手もあるぞ」
「それだと自殺幇助に問われます。下手すればもっとややこしい罪を着せられかねない」
冷ややかな切り返しに、男はいささか意外そうな顔をした。
「へえ、これから死ぬってときにずいぶんと冷静じゃねえか。どっちにしろ、あんたの都合で事は動かねえってことだ。若い女だからってわがままが通ると思うなよ」
すると助手席に座る老女が、アイラインの濃く引かれた目で男を見やった。髪は茶髪というよりオレンジ色に近く、染めすぎのせいか枝毛が目立つ。しかし美容院でアップにセットしてきたようで、襟足にあしらわれた紫のバラの飾りがひどくなまめかしく見えた。
「ちょっとあんた。言いたいことはわかるけども厳しすぎるんじゃないかい? タクシーが呼べるとこまで乗せてってやんなよ。死に際の善行は大事だぞ」
「物理的にできねえから言ってんだ。この車はバッテリーが寿命でよ。エンジンを落としたら最後、もう二度とはかからんのさ。ここまで来れたのは奇跡に近い」
男はハンドルをぽんと叩いた。
「要するに、ねえちゃんはビビっちまったんだろ?」
「ビビって何が悪いの?」
わたしはペットボトルの水を口に含んだ。これから命を絶つというときに、平常心でいられるわけがないだろう。いくら水を飲んでも喉はカラカラだし、胃のあたりを摑まれているような鈍い痛みがずっと続いている。
男はじろじろと無遠慮にわたしの顔を見まわして、こめかみから流れる汗を肩口になすりつけた。
「とりあえず自己紹介でもすっか。見ず知らずの人間がこうやって集まったのも何かの縁だからよ。人の話でも聞いて気持ちの整理とやらをしたらいいんじゃねえか」
そういう問題ではない。わたしが焦っている理由は、時間を置けば置くほど覚悟が鈍るという点だ。集団自殺において、自己紹介ほど無意味なものがあるだろうか。
この男は出会った瞬間から煙草をふかし、人の迷惑も考えずに灰と煙を閉め切った車内に撒き散らしている。黒ずんだ大きな顔には折り込まれたようなシワが刻まれ、ぎょろりと血走った目が不摂生を物語っていた。
「ちなみに俺は長谷部康夫だ」と男は親指を立てて自身を指差した。「先月還暦を迎えたばっかでな」
そのとき隣から「あの」という覇気のない声が聞こえ、わたしは横に目を向けた。青いギンガムチェックのシャツを羽織った顔色の悪い少年が、うつむきながらぼそぼそと唇を動かした。
「自己紹介とか、自分はそういうのはいいんで」
少年はそう言ったきり口を閉ざしている。作業着姿の長谷部は今にもつながりそうなぼさぼさの眉をしかめ、煙草の煙とともに盛大に息を吐き出した。
「最期ぐらい素直になったらどうだ。名前を名乗んのも今日で終わりなんだから、感謝の気持ちをこめて思いの丈を全部ぶちまけろ」
「感謝? だれに?」
「だれって名前をくれた親にだろうよ。ガキひとりを育てるってのは容易なことじゃねえんだ。なのにガキは親の苦労なんざ知らねえからな。いっちょまえなことをほざくわけだよ」
長谷部はまるで恐怖を退けるように早口で語り、吸い殻が山となっている灰皿にさらなる一本をねじ込んだ。すると助手席にちんまりと収まっていた老女が何度も頷いた。
「あたしもあんたに賛成だよ。ここにいる四人はこれから一緒に旅に出る大事な仲間だ。簡単な自己紹介だけじゃなくて、ここに来たいきさつも洗いざらい話そうじゃないか」
「よし!」と男は急にけたたましく手を打った。「みんなして己の人生を振り返るべきだな。そしてこの世の未練を断ち切ろうじゃねえか」
安っぽいパワーストーンのブレスレットを幾重にも着けた老女は、過剰なほど大きく頷いた。わたしの隣では、少年がこれみよがしに耳にイヤホンをはめて窓のほうへ目をやった。
「じゃあ、ばあさん。あんたからだ。つうか、なんでマスクしてんだよ」
老女は隣に座る男を流し見た。
「なんでって、あんたは世間の騒ぎを知らないのかね。ウィルスにやられて世界じゅうで何人死んだと思ってんだか」
「俺が言ってんのは、これから死のうって人間がウィルスなんぞを怖がってどうすんだって話だ。だいたいな。どいつもこいつも大げさに騒ぎやがって、ちょっとした風邪みてえなもんに振りまわされてこのザマだ」
「何言ってんだ。ウィルスは恐ろしいもんなんだ。感染すれば家族にも会えずに骨になって帰るしかなくなるんだからな。あんたまさか、注射も打ってないのかい?」
老女は細く描かれた眉根を寄せて、エラの張った長谷部の大きな顔を凝視した。
「ワクチンなんざ製薬会社と政治家と、利権に群がる悪党どもがひと儲けするためのインチキだ。わけのわからん薬を世界じゅうの人間に打ちやがってよ。見てな。十年後には世界の人口が半分になってっから。生き残んのは注射を打たなかった賢い連中だけだ」
長谷部は外を眺めている少年に目を留め、「人が喋ってんのに音楽なんて聞いてんじゃねえぞ」と嚙みつくように窘めた。そしてひしゃげた煙草の箱からもう一本を出してくわえ、ガス切れ間近のライターに顔を寄せて火を点けた。
お願いだからだれかこの男を黙らせてほしい。わたしは疼きはじめたこめかみを指で押した。口数が異常に多くて場を仕切りたがり、加えて一貫して中身のない話しか出てこない。喋り続けることで、恐怖をまぎらわそうと必死だった。死への怯えを見せることは恥だと考えているのだろう。今こそリーダーシップを発揮すべきだという間違った男気に縛られている。
「じゃあ、もう夜も更けたしあたしから始めるよ」
咳払いをした老女に、わたしはすかさず割って入った。
「わたしはパスします」
「ねえちゃん。ちっとは空気読めや。女はこれだから面倒なんだよ」
「面倒で結構。死に際まで人に従う理由はない」
わたしはぴしゃりと撥ねつけ、浅黒くて大きな長谷部の顔を見てからさっと目を逸らした。この男のせいで、何ヵ月もかけてようやく固めた死への覚悟にひびが入ったのがわかった。こんな精神状態で他人の人生に触れれば、反動で自身の内面にも波風が立つのは必至だろう。
死へのモチベーションをなんとか保とうと躍起になっているとき、老女がマスクを外してローズピンクに塗られた唇を動かした。
「あたしは寺内千代子、二月で七十三歳になったよ。江戸川区の一之江で小さいスナックをやってたんだ。二十年間たったひとりで店を守ってさ」
するとまたもや長谷部が手を上げて話を遮り、くわえた煙草を揺らしながら千代子の顔を覗き込んだ。
「一之江の小さいスナックだって? ちょっと待てよ……一之江のスナック……」
長谷部は何事かを考えあぐね、じっと一点を見つめている。やがて思い出したとばかりに顔を上げた。
「思い出したぞ。まさかあんたあれか? あのクラスター騒ぎのスナック千代子か?」
とたんに千代子はシワの目立つ顔を強張らせ、アイラインで囲まれた瞳をみひらいた。
「図星か? いやはや、とんでもない大悪党がまぎれ込んだもんだ! あれだろ? 年寄りを六人も殺したやつだよな?」
「こ、殺したって、いくらなんでもそんな言い方はひどいじゃないか……」
「ひどいも何も、感染対策もしないで客を裏口から入れてたんだよな? 世間じゃ吞み屋がバタバタと潰れてんのに、あんたの店は客の年寄りと示し合わせてこっそり闇営業し続けた。挙げ句に感染した年寄りが六人もおっ死んだだろうよ」
長谷部は嬉々として捲し立て、千代子は唇の端をぴくぴくと震わせた。この騒ぎには聞き覚えがある。当時はSNSですぐに場所が特定され、千代子の名前や顔写真も晒されていたはずだ。
男はさも愉快そうに先を続けた。
「なんかの週刊誌で読んだが、年寄り連中を毎日通わせるために、皆勤賞なるもんを作ってたんだってな。しかも、昼夜二回店に来ればダブル皆勤賞だっけ? まあ、年金暮らしのじいさんなんて大金を落とさねえからな。生かさず殺さず小口で金を巻き上げるにはなかなかうまいやり方だよ」
長谷部は肩を揺らしながら笑った。なるほど、老人たちの競争心と連帯感を利用するという、ある意味、戦略的な経営をしていたのがこの千代子だったのか。わたしは白浮きするほどファンデーションを塗りこめている老女に目を向けた。
「あ、あんなことになるなんて思ってなかったんだよ。うちの客は常連ばっかりで、とにかく毎日店に通うことが生き甲斐だったんだ。み、店を閉めたら、あの人たちの居場所がなくなる。年寄りのたったひとつの楽しみを奪うことがどうしてもできなかったんだよ」
「とんでもねえ言い種だな」と長谷部は鼻を鳴らした。「生き甲斐どころか、年寄りをまとめて地獄送りにしておいてよ。なのに自分はマスクでしっかり感染対策ときたもんだ」
容赦のない言葉に千代子は涙を浮かべ、堪え切れずにさめざめと泣きはじめた。すぐにアイラインが溶け出して、真っ黒な涙が頰に二筋の線を描いた。
「こ、心から申し訳なかったと思ってる。あたしはあの人たちに謝りたいんだ。ウ、ウィルスを軽んじたばっかりに、取り返しのつかないことをしてしまった……」
「何が悪いの?」
依然として窓の外へ目を向けている少年が急に小声で言った。
「むしろ最期に楽しめてよかったと思う。先のない老人なんだし」
すると千代子が泣き濡れた目をきらりと光らせ、首を伸ばして後部座席へ振り返った。
「そ、そう思うかい? あの人たちは満足してあの世へ旅立ったと思うかい?」
老女は都合のいい意見にすがろうと必死だ。少年が無表情のまま口を閉ざしていると、またもや長谷部が耳障りなかすれ声を出した。
「おい、ガキ。年寄りどもは老い先短いんだから、少しばっかり早く死んでも同じだって言いてえのか?」
「それ以外にどう聞こえたのか教えてもらいたいけど」
少年は淡々と答えた。
「あのな。おめえみてえなクソ生意気なガキが日本をぶち壊してやがるんだ。ちっとは素直になれよ。おまえさんは寂しいんだろ? ホントは死にたくなんかないが、親とか先生に心配してもらいたくてこんなとこにいるんだろ? だれかに本気で怒ってもらいてえんだよな?」
長谷部は勝手に盛り上がり、どこかで聞いたような話を披露しはじめた。
「俺ら四人はネットで知り合った集団自殺志願者だ。縁もゆかりもねえ人間なんだから、おまえは心ん中をぶちまけていいんだ。で、気が変わればいつでもこの車を降りればいい。未来を背負って俺らのぶんまで生きろ」
少年はようやく振り返って耳からイヤホンを引き抜いた。奥二重の目にわずかな苛立ちをにじませたが、食ってかかる気力はないようだった。左目をこすりながらしばらく長谷部を見つめ、やがて何事もなかったかのように目を伏せた。
「ばあさん、続きだ」と長谷部が隣に顎をしゃくると、助手席の千代子は小さく頷いた。
「うちでクラスターが起きたことはニュースで何回も流れたから、朝から晩まで電話が鳴り止まないほどだった。疎遠になってた娘からも電話がかかってきたよ。今度こそ縁を切るってな」
千代子はぶるっと肩を震わせた。
「今だから言うけど、あたしには一億以上の貯金があったんだ」
「一億だって? よくもまあ、じいさんどもからそれほど搾り取れたな」
「あたしは二十年以上、一日も休まないで働いたんだ。昼も夜も店を開けて、寂しい年寄りの居場所を作ってやった。法外な金をせびったわけじゃない。こつこつと貯めてきたんだよ。だ、だけど……」
千代子は洟をすすり上げた。
「死んだ客の遺族から訴えられたんだ。それまで年寄りをないがしろにしてきたような家族が、ここぞとばかりに団結して賠償金を求めてきた。ひとり頭四千四百万」
「まあ、金が取れるとわかれば引く理由がないからな」
「あ、あたしはもう何をする気力もない。本当にひとりぼっちになったんだ……」
千代子は再び涙を流して血管の浮く手を強く握り締めた。もはや化粧がどろどろに溶けているひどい顔を、わたしはぼうっと眺めていた。退屈だ。泣きじゃくる小さな老女を見てもわたしの心は微塵も動かなかった。
長谷部は声を出して泣く千代子を見下ろし、煙草をくわえたまま骨ばった彼女の肩を力強く叩いた。どこかめんどくさそうで適当な様子だった。
「まあ、あれだ。あんたはよくやった。あの世で待ってるじいさんどももたいして怒っちゃいねえだろ」
「そ、そうだろうか」
千代子は肩を震わせて号泣し、見るからに偽物のシャネルのバッグからティッシュを取り出した。洟をかんで涙を拭き、細く長く息を吐き出している。そしてぱっと上げた顔は実に晴れやかで、今さっきとは見違えるほどすっきりしていた。
「話を聞いてくれてありがとうねえ。久しぶりに胸のつかえが取れたよ。客にいんたーねっとってもんを習って、ここに来られて本当によかった」
無邪気なほど清々しい面持ちだ。長谷部はせっかちに煙草を吸い上げ、揉み消したと同時にまた新たな一本に火を点けた。
「じゃあ次はガキの番だ」
たびたび目をこすっている少年に顎をしゃくると、拒否するだろうという予測に反して一本調子の声を出した。
「丹波陸斗、十六歳」
「十六? 高校生かい? あんた、十六歳なんて人生まだまだこれからだろ? 親御さんが心配して捜してるはずだよ」
すべてを告白したことで身軽になっている千代子は、さも心配そうに眉尻を下げた。
「生きてりゃ楽しいことだっていっぱいあるんだ。早まっちゃいけないよ。子どもは未来そのものなんだから」
「未来?」
陸斗は言葉の意味を考えるように繰り返したが、すぐに自己紹介を再開した。
「千葉の習志野出身。ここに来た理由はネットで見かけたからなんとなく」
「そんな適当な理由があるかよ」
今度は長谷部が口を挟んだが、陸斗は何も答えずなぜかわたしに顔を向けてきた。表情が乏しく覇気が感じられないのに、どこか警戒心が煽られるような薄気味の悪さがある。過去に遭遇した痴漢がこんな顔をしていたことをふいに思い出して嫌悪感が湧いた。
わたしは眉根を寄せながら問うた。
「何?」
「どうせ死ぬんだし一回ヤラせて」
「は?」
わたしは勢いよく隣に顔を向けた。小作りな蒼白い顔には幼さが残り、黒目がちな丸い瞳はことのほか澄んでいて邪気がない。しかし、その奥に失意や情欲がないまぜになっているのが垣間見え、わたしは心の底からぞっとした。大人とも子どもともつかない奇妙な面持ちだった。
無言のまま少年からわずかに距離を取ると、陸斗は再び張りのない声を出した。
「子どもの最期のお願い聞いて」
「キモすぎる。頭おかしいんじゃないの」
足許にあるバッグを取り上げ、二人の間に勢いよく置いた。すると、煙草をくわえながら下卑た笑いを漏らした長谷部が、わたしと陸斗の顔を交互に見くらべた。
「今生の願いってやつだな。ねえちゃん、一回ぐらい相手してやれ」
「ふざけないでよ」
「そう言わずによ。こんなガキはものの数分で終わっから。あんたは欲求不満かもしれんがな」
わたしはにやにやと含み笑いをしている長谷部をねめつけた。案の定だ。わたしは浅黒い顔をした男から目を離さなかった。見知らぬ者が集う集団自殺というものにおいて、この手のことは何よりも警戒していた。言ってみれば死を免罪符にすべての悪行が正当化される異常な状況なのだ。レイプも暴力も、いや、なぶり殺しでさえも自殺すれば帳消しになってしまう。
わたしはワンピースのポケットに手を入れ、ホームセンターで購入した小さなボトムフックナイフを握り締めた。もしものときは躊躇なく使おうと決めている。どうせ死ぬのだ。無法地帯という条件は四人とも同じだった。
汗で滑る右手で刃を出しかけたとき、助手席の千代子が場違いなほど暢気な声を出した。
「あんた、相手するのが嫌なのかい?」
「あたりまえのこと聞かないでよ」
「そうかい。ほら、陸斗ちゃんって言ったっけか? 表に出な。あたしが付き合ってやっから」
千代子はドアを目張りしているビニールテープを剝がしにかかり、一同はそろってぽかんと口を開けた。わたしに助け舟を出したのかとも思ったけれども、老女の白塗りの顔はわずかに上気して、ローズピンク色の唇には笑みが浮かんでいる。なるほど、こういうことにはなんの抵抗もないらしい。場末の小さなスナックで一億以上の貯金ができたのも頷ける。相手が十六の子どもだろうとまったくためらいがないことには驚かされるが、だからといって不快感はなかった。千代子にとっては日常的な仕事なのだ。
「ここは山ん中だしだれも来ないから心配しなさんな。あたしが男にしてやるよ」
千代子は堂々と言って陸斗に手招きをした。少年は今さっきまでの不気味さが消えており、内向的な子どもの顔に戻っていた。
「いや、もういいです……」
「なんだよ、もういいって。それだけが心残りなんだろ? あんたの願いは真っ当だ」
「冗談なんで」
陸斗は半ば怯えたようにに身じろぎをし、背中を丸めて窓の外に顔を向けた。なんともいえない気まずい空気が流れたとき、運転席にもたれていた長谷部が急に割れるような笑い声を上げた。わたしたち三人は驚いて同時に肩を震わせた。
「ばあさん、何やら手慣れてんな」
男は笑いながら短くなった煙草を灰皿で潰した。もはや死ぬために来たことなど忘れているかのように、少し前まで見せていた怯えは見えなくなっていた。
「しかし、いつの時代も女は楽でいいわな。ガキだろうが年寄りだろうが、寝っ転がってりゃ簡単に金になる」
「楽なわけないだろう。なんだよ、その失礼な言い種は」
千代子が語気を強めて吐き捨て、同意を求めるような目をわたしに向けてきた。同じ女として、今の言葉は絶対に許せないだろうと言わんばかりだ。確かに長谷部の言葉は差別や侮辱に満ちているものの、単にそれだけだった。子どもの悪態と同じで、怒りが湧き上がってくるほどの熱量もない。
黙っているわたしに業を煮やしたらしい千代子は、たるんだ顎を上げて憤った。
「あんたもなんとか言ってほしいね。女をここまで馬鹿にされて悔しくないのかい?」
「別に。それより、次はわたしのばんですよね。坂崎夏美、二十八歳。南小岩の生まれで仕事はある種のボランティア活動」
そう言った瞬間、木立の間からちらちらと動く光が見えた。長谷部は間髪を容れずにルームライトを消した。
(つづく)
作品紹介
四日間家族
著者 川瀬 七緒
定価: 1,870円(本体1,700円+税)
発売日:2023年03月01日
誘拐犯に仕立て上げられた自殺志願者たちの運命は。ノンストップ犯罪小説!
自殺を決意した夏美は、ネットで繋がった同じ望みを持つ三人と車で山へ向かう。夜更け、車中で練炭に着火しようとした時、森の奥から赤ん坊の泣き声が。「最後の人助け」として一時的に赤ん坊を保護した四人。しかし赤ん坊の母親を名乗る女性がSNSに投稿した動画によって、連れ去り犯の汚名を着せられ、炎上騒動に発展、追われることに――。暴走する正義から逃れ、四人が辿り着く真相とは。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001445/
amazonページはこちら