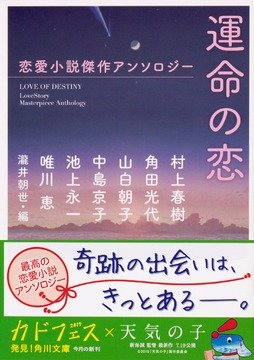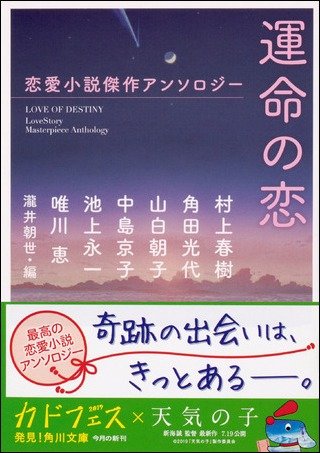11 月 12 日(火)発売の「小説 野性時代」2019年12月号では、中島京子さんの新連載「ムーンライト・イン」がスタート。
その冒頭を公開します!
都心を出たのがもう夕刻だったし、特急を降りて高原鉄道に乗るまでに三十分も待たなくてはならなかったから、着いたときはすっかり夜になっていた。
予報に反して降り始めた雨は、風と共に勢いを強め、本来なら降るばかりの星空が見られるはずのその街はただただ暗く、駅前は誰もいなくて閑散としていた。
とうぜんのことながら、観光案内所も閉まっていた。
栗田拓海は駅の構内で、バックパックから全身をすっぽり覆うレインスーツを取り出して着こみ、折りたたみ式の自転車を広げて、外に出た。すっかりお腹が空いていたから、なにか食べて腹を膨らませようと思ったが、そこは見事なほどに無人で、腹を満たそうにも店など開いていなかった。
降り募る雨の中、自転車を手で押しながら駅前を転がし、ライトを外してそこらを照らしつつ歩いていて、巨大なコーヒーポットのオブジェだか店だかにぶつかったときはギョッとした。こういうものが、昼間はかわいく見えるのだろうかと一瞬思ったけれど、そのオブジェの横の建物のガラス戸の内側に鎮座している古びた巨大なぬいぐるみを見ても、とてもそれが昼には開いて人を招き入れている店だとは思えなかった。
自転車を転がして高原鉄道の線路をわたり、それ以上行っても何もなさそうだったので引き返した。ちょうどポットのオブジェの道を隔てた反対側には工事でもするのかトタン板で覆われた一角があり、「SGF」という看板がかかっていたが、細く空いた隙間からハンディングライトを差し入れて照らしてみても、放置された自動車と雑草と、廃墟じみたショッピング施設の入口のようなものが見えるだけだった。手元のスマートフォンで施設名を検索すると、それが「サバイバルゲームフィールド」の略であることがわかった。かつてはブティックやフードコートだったらしい駅前のショッピング施設が、居ぬきの形で、エアガンを持って敵と撃ち合う「大人の戦争ごっこ」のフィールドとして再利用されていることが、手元のネット情報でわかった。なるほど「廃墟」は廃墟なりの、活用方法というのがあるらしい。でも、曲がりなりにも観光地として知られる街の駅の真ん前に、大人がミリタリーウェアを着てエアガンを撃ちまくるフィールドがある事実には驚いた。そのフィールドはほんとうに、使われることがあるんだろうか。
駅前の通りに並ぶ建物は、土産物屋だったり、喫茶店だったりしたのだろう。ライトを当てると暗がりから浮かび上がるそれらは、「アメリカン」とか「カントリー」とか呼ばれるスタイルが流行したころに建てたと思われる店舗で、長年そこに放置されている建物の醸し出す恨めしさのようなものが漂っていた。
大きく組まれた改装工事のための足場が、カントリー調の三階建ての白っぽい建物の一つを覆っていたが、その足場じたいも、新しく組まれたものには見えなかった。雨もさることながら、風が吹きつけて、足場を覆うビニールシートがずさずさと音を立てた。シートが剥がれ落ちてきたら、という不穏な想像が頭をよぎる。
人っ子一人いない駅前通りを折れて、ハンディライトで無造作に左右を照らしながら進むと、一瞬、頭をいくつもつけた化け物が見えた気がして、ひるんで自転車を止めた。
聴こえるのは風雨の音ばかりで、猫の這い出す気配もないので、そっと足元からゆっくり化け物のいそうな方向にライトを向けると、そこにはなんのことはない、また別の少し変わったオブジェがあって、それは木のような人のような形をした立体で、木なら幹、人なら胴にあたる部分と、枝か腕にも見える部分が、それぞれ色の違うペンキで塗り分けられていた。枝にも、肘を曲げて上に向けた腕のようにも見えるその着色された金属パイプの突端には、丸い白い電球めいたものが載っているので、そう、それはつるんとのっぺらぼうの人の顔のようでもあり、そのせいで、枝や腕に見えていたものが、ちょっと人の首にも似て見えるのだった。
夜中でなければ、これを見て、いくつもの首と顔を持つ人などという連想はしなかっただろう。昼間見ればファンシーなオブジェなのかもしれないのに、例によってカラフルに塗り分けられたように見えるペンキも剥がれがちで、錆びも出て手入れのされていない雰囲気が、哀愁というよりは夜闇の中に薄気味悪さを浮かび上がらせる。
次にハンディライトが探し当てたのは、どうやら小さなホテルの残骸のような建物だった。壁は崩れ果て、錆びた鉄骨がむき出しになり、一階のエントランスだったと思われる部分には布団やらテレビやらが投げ出されており、空気の抜けたタイヤを嵌めた自動車が地面に半分めり込むようにして放置されていた。
脳裏には、さっき手元のスマホで見たサバイバルゲームフィールドの光景が蘇ってきて、この高原列車の駅前全体がそのフィールドで、篠つく雨の中、カモフラージュ柄の戦闘服を着てエアガンを手にした男たちが、どこかで息を潜めているのではないかという、あまり楽しくない妄想が浮かんだ。拓海はそれを払うように身震いした。
雨なんかに降られるはずではなく、景色も空気もいいはずのこのよく知られた高原のどこかで、小さなテントを張る予定だった。大通りを避けて路地に入ると、すでにもう林の中の小道といった風情になり、野宿には悪くなさそうな公園に出くわしたが、この雨の中では宿泊施設を探したほうが無難だと感じられた。
駅前の廃墟感のあるエリアも、天気さえよければそれなりにご愛敬かもしれないし、なにより星空さえ眺められるなら、自転車乗りには悪い旅じゃない。
しかし、雨だ。
閃光が近くの山に走り、一瞬の後、雷鳴が轟いた。
これはもう、早いところどこかの宿にと思って、びしょぬれになった顔を同じようにびしょぬれの手で拭いながらハンディライトをかざすのだけれど、宿のように見える施設はどれも、とても営業しているとは思えない暗さで、そこにも地面にタイヤのめり込んだ廃自動車を見つけるに至って、このあたりに泊まれるところなどないんじゃないかという気がしてきたのも事実だった。ぽつん、ぽつんと見当たる家も、別荘なのか、その成れの果てなのか不明ながら人の気配はなく、雨でぬかるんだ地面に、自転車のタイヤが重くめりこむのを腕に感じるばかりだった。
拓海の目に、ある家の灯りが飛び込んできたのは、宿を探すのはあきらめて駅まで戻り、屋根のある構内で一夜を過ごすしか方法はなさそうだと思った矢先だった。窓から漏れる光の暖かさと、自分以外に人間がいる感触に力をもらって、その家まで行ってみようという気になった。近くに泊まれそうな宿泊施設がないか聞いてみて、ないと言われたらあきらめて駅まで戻ればいい。
そのうえ、近づくとなんとなくいい匂いがしてきた。スープでも煮込んでいるらしい。とうぜんのことながら、腹が妙な音を出した。とにもかくにも、人の声を聞きたくなって、垣根に自転車をもたせかけてレインスーツのフードを外し、髪を撫でつけながら玄関に駆けよると、軒先にぶら下がった看板が目に入った。
「――――――NN」
楕円形の板に、文字が書かれていて、ほとんどは消えていたが、最後の二つのNだけは白く残っていた。拓海は目を斜め下に動かして考えた。
NN。
「INNか!」
なんだよ、ここ、ペンションじゃないか。
客室が空いているかどうかを確かめてもいないのに安堵で口元が緩んできて、拓海は、ちょっと伸びたヒゲを撫でた。そして、たしかめるように深呼吸してスープの匂いを吸い込んでから、呼び鈴を押した。
▶このつづきは「小説 野性時代」2019年12月号でお楽しみください!
関連記事
・【文庫解説】村上春樹、角田光代、山白朝子など恋愛小説の名手たちが紡ぎ出す傑作アンソロジーをあなたに。『運命の恋』
・【レビュー】村上春樹、角田光代、山白朝子らが紡ぐ人生の冒険。日常を打破する原動力が得られる『運命の恋』