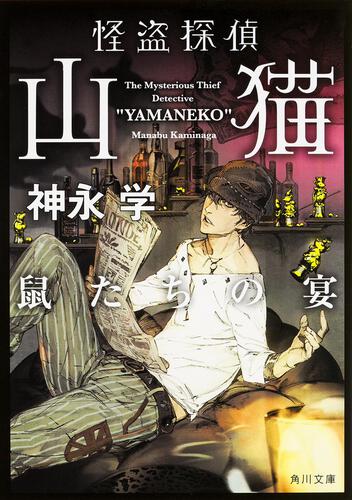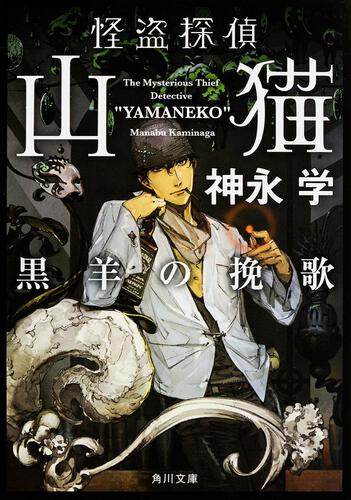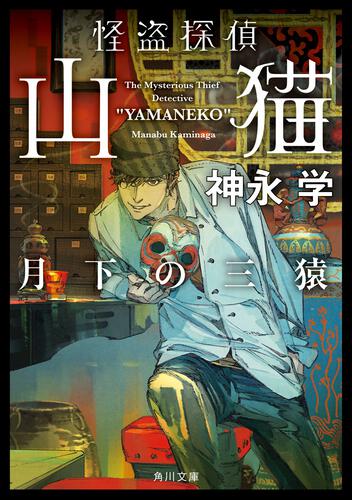The second day
二日目 盗みのルール
1
──どうしてなの?
さくらは、疑問を抱えたまま、会議室のパイプ椅子に座っていた。
部屋の中に残っているのは、さくら一人だ。
ついさっきまで、この会議室では、昨晩の強盗殺人事件の捜査会議が行われていた。
刑事課長である
そのことに抗議すると、森田から「会議室で待つように」と指示が出た。
──嫌な予感がする。
男社会である警察組織において、女性は職務差別の対象となる。
数十年前まで、女性警察官には逮捕権がなく、交通課勤務という限られた職務につくことしかできていなかったほどだ。
表向きの体制は変わっても、その根底に流れるものは、そう簡単には変わらない。
警察に入ってから、さくら自身、何度もそういった職務差別を受けてきた。
「待たせたな」
ドアが開き、森田が顔を出した。
五十歳という年齢にしては、身体が引き締まっていて、血色もいい。
彼は、ノンキャリアの
「説明して頂けますか?」
さくらは、立ち上がりながら、じっと森田を見返す。
「そうせっつくな。まずは座れ」
森田に促され、さくらは椅子に座り直した。
それを見届けてから、森田も近くにある椅子を引き寄せ、さくらと向かい合うようにして座った。
「まさかとは思いますが、捜査から外すつもりですか?」
さくらは、すぐに話を切り出した。
「なぜ、君を外す必要がある?」
森田は、余裕のある笑みを浮かべた。
「なぜって……」
さくらは、言葉に詰まった。
自分の早とちりを指摘されたようで、恥ずかしさから顔が熱くなる。
「霧島を捜査から外せるほど、うちに人的余裕は無い」
森田が、白髪の交じった髪をかき上げるようにしながら言った。
過剰に褒めているように聞こえるが、悪い気はしない。だが、そうなると逆に分からない。
「では、なぜですか?」
「君には、事件に関係したことで、別のことを頼みたいんだ」
「別の?」
さくらは、首を
「実は、ちょっとデリケートな問題で、他の人間には頼み
さくらは、森田の言葉を受け、下っ腹がむず
デリケートな問題とは、
「どういうことです?」
「山猫が、窃盗を行っているのは、うちの管轄だけじゃないことは知っているね」
さくらは黙って
それが、山猫がなかなか捕まらない理由の一つにもなっている。ほとんどの窃盗犯は、土地鑑のある一定地域で犯行を行う。
犯人からしてみれば、その方が動き易いのだろうが、同時に警察側からすれば、捜査がし易い。次の犯行予測もたつし、情報も
だが、山猫の行動範囲は、東京都内だけでなく、神奈川県、埼玉県、千葉県と、南関東全域にわたる。
まさに神出鬼没の窃盗犯。
今回のように同じ管轄内で、連続して犯行を行ったのは初めてのことだ。
「本庁に、以前から山猫を追っている刑事がいる。今回、その刑事が捜査協力要員として、うちの署に派遣される」
そこまで言われれば、その先の展開が読める。
「その捜査官とチームを組めと?」
「気に入らないだろうが、うちとしては、本庁から大挙して人が押しかけるような事態だけは避けたい」
細められた森田の目に、
本庁との間で、どんなやりとりが行われたかは分からないが、ギリギリの
森田の心情は、さくらにも理解できる。だが、だからといって、納得できたわけではない。
「あたしは……」
さくらの言葉を遮るように、森田が視線を入り口の方に向けた。それにつられて、さくらも入り口に目を向ける。
ドア口のところに、一人の男が立っていた。
年齢は、四十代前半だろうか──エラの張った四角い顔だった。角刈りにした髪が、より一層それを強調している。
口には火の
「彼が、
森田が、申し訳なさそうに言った。
「森田さんよ。本庁からの要請を、ちゃんと聞いてなかったのか?」
関本が、巻き舌ぎみに言う。
「どういう意味です?」
関本は、森田の質問に答えることなく、さくらの前まで歩み寄ると、臭いを
「うちから要請したのは、キャバ嬢じゃねえ。使える捜査官のはずだ」
関本が、ギロリと目を
──誰がキャバ嬢よ!
さくらは、叫びそうになる気持ちを苦労して抑え込んだ。
少しでも気を抜いたら、その鼻っ面に
「彼女は、使える捜査官だ」
森田が、真っ直ぐに関本の目を見ながら言った。
「俺には、そうは見えないね」
関本が、すぐに反論したが、森田は意に介さないといった感じだった。
「第一印象だけで人の能力を判断するのは、危険なことだ。警察学校で習わなかったかね。関本警部補」
森田は、あえてゆっくりとした口調で言った。
関本の顔が、みるみる
「言うじゃないか。森田警部」
関本と森田が、
中年の男が二人、見つめ合っている様を見るのは、あまり心地いいものではない。
「あたしが、役立たずの女かどうかは、行動を見てから判断して下さい。もし、関本警部補が、足手まといだと感じたら、すぐにでも外して頂いて結構です」
さくらは立ち上がり、二人の間に割って入るようにして宣言した。
口であれこれ言えば、ただの言い訳になる。認めてもらうためには、実力を示すしかない。さくらは、そう心得ていた。
関本は、一瞬だけ驚いた表情をしたが、すぐに真顔に戻る。
「そこまで言うなら、好きにしろ」
笑い飛ばすように言うと、関本は足早に会議室を出て行った。
重苦しい空気から解放されたさくらは、椅子に座り直しながら、長いため息をついた。
これから、あの男と行動を共にしなければならないと思うと、心底うんざりする。
「能力はあるようだが、かなりクセのある人物らしい」
森田が、落胆したように肩を落としながら言う。
「優秀な刑事が、なぜ今まで山猫を逮捕できなかったんでしょうね」
さくらは皮肉を込めて言った。
関本に、どれほどの経験があるかは分からないが、結果を残せない人間は、優秀だとはいえない。
「問題はそこなんだよ」
「というと?」
まさか、ここで森田が話に乗って来るとは思っていなかった。
「何の確証もないから、明言はできない。ただ、気になるんだ。彼は、何年も山猫を追い回している。それなのに、なぜ、今まで逮捕できていないのか?」
森田の言葉を聞き、さくらは電気を流されたような感覚を味わった。
「彼に問題がある……そういうことですか?」
「それは、まだ分からん。とにかく、今後、彼の行動を監視し、もしおかしなところがあれば、すぐに報告して欲しい」
さくらは、返事に詰まった。
──監視と報告。
その言葉が意味するところの大きさを、実感したからだ。
〈第3回へつづく〉
ご購入はこちら▶神永学『怪盗探偵山猫』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
▶神永学シリーズ特設サイト