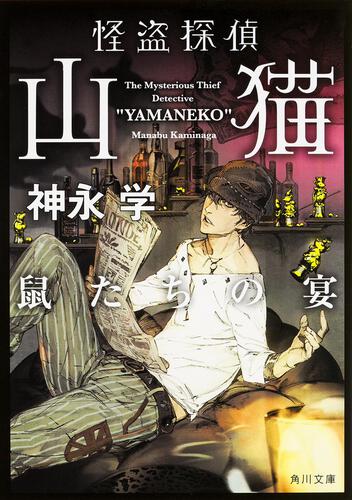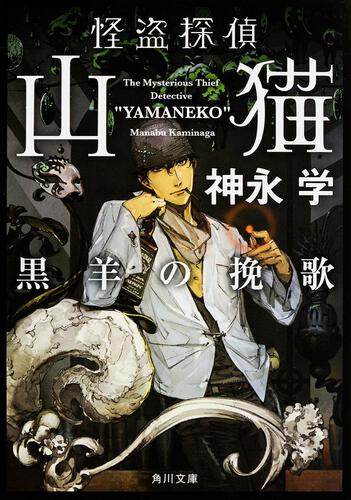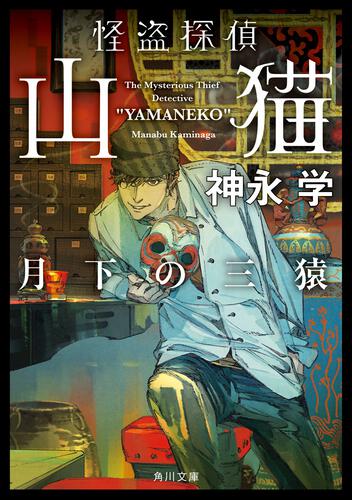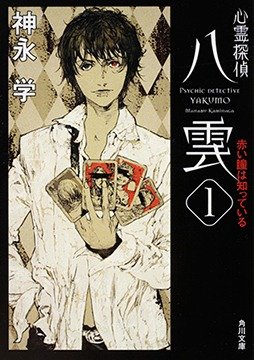さらば、山猫――!?
最強の敵が現代の義賊に襲いかかる。累計90万部の話題シリーズ、堂々完結!
ドラマ化もされ、話題になった「怪盗探偵山猫」シリーズ完結巻、
『怪盗探偵山猫 深紅の虎』がいよいよ刊行。
シリーズ完結を記念し、カドブンでは、シリーズ1冊目の『怪盗探偵山猫』の
試し読みを公開します。
希代の名盗賊の活躍をぜひお楽しみください。
>>前話を読む
2
勝村は、呼び鈴の音で目覚めた。
──ここはどこだ?
意識が混濁したのは、最初だけで、すぐに住み慣れた六畳一間のアパートであることに気づいた。
頭に締め付けられるような痛みがあった。
昨晩、調子に乗って飲みすぎたようだ。山根と二軒目のバーに足を運んだところまでは覚えているが、その先の記憶がない。
どうにか立ち上がったものの、視界がゆらゆらと揺れていた。
それが、二日酔いからくるものなのか、うだるような暑さからくるものなのか、勝村には判断できなかった。
勝村は、頭を押さえながら玄関に向かい、ドアを開けた。
ジーンズにTシャツ姿の若者が、無言でA4サイズの封筒を差し出して来た。
茶色に染まったボサボサの髪で、客先だというのに、ケンカを売りに来たようなふてぶてしい態度だった。
だが、勝村にそれを注意するような気概はない。
無言で荷物を受け取り、伝票にサインをしてドアを閉め、封筒を持ってデスクに座る。
差出人は、今井の会社になっていた。
中身は、今井の会社で発行されている月刊誌だった。
表紙には、手錠でつながれ、現場検証に立ち会う誘拐犯の写真が使われていて、タイトルである〈REAL〉という赤い文字が躍っている。
通常の週刊誌にあるような、水着で微笑むグラビアアイドルの写真も、お薦めラーメン店の情報もない。
そのほとんどが、文字と必要資料で埋め尽くされている。
今井は、この雑誌を刊行するために、大手出版社の編集長という、安定した生活を捨てた。
会議で決まった、商業ベースに乗るであろうと思われる記事だけを扱う。
実際の事件を扱ったとしても、売れるように、面白おかしく記事にしなければならない。
物事の本質は、そうやって
雑誌は、ジャーナリズムでないことは、今井も充分に分かっていた。
だが、都合のいい部分だけ切り取って、読者に真実と異なる解釈をさせるという手法に、
自分の信念にそぐわない会社の中で、腐っていくくらいなら、自分のやりたい雑誌を、自分で創る──。
今井らしい決断といえた。
勝村は、汗ばんだ手をTシャツで
満開の桜の写真が掲載されていた。
朽ちた流木のような幹から、大きく二手に枝が分かれている。
「この桜……」
勝村は、思わず声を上げた。
そこに写っている桜に、見覚えがあった。日本三大桜の一つで、山梨県にある
満開の桜が、圧倒的な迫力で迫ってくる。
勝村は、かつて今井とこの山高神代桜の撮影に行ったことがある。
今井から、創刊する雑誌の表紙の撮影を手伝って欲しいと頼まれ、休日を利用して足を運んだ。
勝村は、懐かしさから、その写真を指でなぞった。ざらざらとした感触。特殊な紙を使用しているのだろう。
──でも、なぜ今になって、創刊号の表紙と同じ写真を?
勝村のその疑問の答えは、すぐに見つかった。
雄大な桜を背景に、白文字で文章が書かれているのが目に留まった。
誠に残念ながら、本号をもって休刊とさせて頂きます。
しかし、我々の理念が終わってしまうわけではありません。
真実は、あなたの目の前にあります──。
勝村は、奇妙な符合を感じた。
──雑誌の休刊と同時に、自分の命まで終えてしまうとは。
それを思うと、勝村の中に悔しさがこみ上げてくる。
──今は、ここで悲しみに暮れているときではない。
勝村は、自分に言い聞かせると、今井から送られてきた雑誌をカバンの中に押し込み、身支度を始めた。
今井を殺害した、山猫という窃盗犯の真実に迫る。
勝村は、それが、今井のためにできる唯一の弔いのような気がしていた──。
3
さくらの運転する白いカローラは、
車内は、キンキンに冷房がきいていて、鳥肌が立つほどだった。
さくらは、手を伸ばし、冷房のスイッチを切った。だが、すぐに助手席の関本が入れ直す。
──冷房を止めてください。
さくらは、口に出して言ってみようかとも思ったが、止めておいた。
さっきの会議室でのやり取りで、関本が、どんなタイプの男かは、充分過ぎるほどに理解できた。
意見などしたら、手痛いしっぺ返しを受けるに違いない。
「お前は、女のくせに、なんで警察官になろうと思った?」
関本が、腕組みをしながら不機嫌そうに言う。
まるで、女は警察官になってはいけない、みたいな言い方だ。
「父が、警察官でした」
さくらは、怒りを抑えながら答えた。
関本に、軽い気持ちで警察に入ったと思われるのは
「父親のコネか」
関本は、突っかかるような言い方をした。
「いいえ。父は殉職しました」
「殉職……」
さくらの言葉を聞き、関本の表情が一変した。
「新宿のマンションに立て
さくらは、感情を込めずに
今でも、霊安室で対面した父の顔が、鮮明に脳裏に
父親が、警察官であることは知っていたが、あの瞬間まで、それがどんな意味を持つかも理解していなかった。
さくらにとって、職業がなんであれ、父親は父親で、ずっと一緒に生活していくものだと思っていた。
翌日は、一緒にディズニーランドに連れていってくれることになっていた。
当たり前に繰り返されると思っていた日常は幻想で、危険な綱の上を渡っていたのだ。
「父親が死ぬところを見て、それでも警察官になりたいと思ったのか?」
関本が、煙草に火を
「いけませんか?」
さくらは、怒りを堪えて口にした。
確かに、警察官は死と隣り合わせの仕事だ。
さくらの父親は、強盗犯が人質にとった女性を救うために、凶弾に倒れた。
犯人が許せなかったし、他の警察官が、代わりに死ねば良かったとも思った。ずっと泣きじゃくっていた。
だが、葬儀の日、ある若い警察官の一言を耳にしたとき、さくらの考えが変わった。
──他人のために死ぬなんて、あんたはバカだ。
若い警察官は、そう口にした。
さくらは、我を忘れて、その若い警察官に
──お父さんは、バカじゃないもん!
泣きながら、若い警察官をぶった。若い警察官は、周りの人間が、さくらを引き
なぜか、その若い警察官も泣いていた。
今のさくらなら、その若い警察官の言葉の本当の意味が分かる。だが、当時は分からなかった。
──父親のような、誇りある警察官になりたい。
さくらが、そう願うようになったのは、必然だったのかもしれない。
「あたしも、一つ
さくらは、湿った空気を振り払うように、関本に
関本は、煙を吐き出しながら、ぼんやりと窓の外を見ている。さくらは、返答が無いことを了承と判断して、話を続ける。
「山猫は、どういう男なんです?」
「誰が男と決めた?」
関本は、舌打ち混じりに言った。
「え、でも……」
「お前みたいな、
──誰が女狐よ!
さくらは、突っ込みたくなる衝動を、どうにか堪えた。
関本の言葉には、いちいちトゲがある。女性
「関本警部補は、どちらだとお考えですか?」
「男だよ。間違いなく男だ」
関本は、
さっきまで、どちらか分からないと言っていたとは思えないほど、関本は自分の考えに自信を持っているようだった。
「なぜ、そう思うんです?」
「奴は、用心深くて頭が切れる。俺たち警察の動きも、計算ずくなんだよ。今、この瞬間にも、俺たちをどこかで監視しているはずだ」
「でも……」
それは、質問の答えになっていない──。
「女の空っぽの頭では、そこまで考えが回らない」
さくらの疑問を先読みしたように、関本が言った。
女性蔑視も、ここまでくると筋金入りだ。
思春期に女性に相手にされなかった
モテない男のひがみは、周囲に不快感をばらまく。
聞き流してしまいたいところだが、今の関本の話の中に、引っかかる部分があった。それは──。
「山猫が、監視しているというのは、どういうことです?」
「言葉通りだ」
「何か根拠があるんですか?」
「感じるんだよ。奴を」
関本が、
まるで、獲物を狙うハイエナのようだ。
「感じるとは?」
「あいつと俺は、宿敵だ。お互いの存在を感じ合う。そういうもんだ」
得意げに語る関本を、さくらは冷ややかな目で見守った。
男には、現実に目を向けず、ロマンチックな幻想に想いを
「あと、何分で着く?」
関本が、新しい煙草に火を点け、話題を切り替えた。
「あと五分くらいです」
「五分だな」
関本は、金メッキの悪趣味な時計に目を向けた。
どうやら、時間を計るつもりらしい。
──ロマンチストで、見栄っ張りで、せっかちで、陰湿。あなたは男の中の男よ。
さくらは、怒りを奥歯で
急いだ
エントランスには、黄色いロープが張られ、制服警官が二人見張りとして立っている。昨日ほどではないが、報道陣の姿もちらほら見えた。
路上に停車させると、関本がさっさと車を降りて歩いていってしまった。
「もう最悪」
車を降りて、すぐに関本を追おうとしたさくらだったが、不意に視線を感じて立ち止まった。
辺りに視線を走らせたさくらだったが、自分を注視している人物はいなかった。
──気のせいか。
関本の「山猫が監視している」という言葉に、過敏に反応してしまっただけだろう。
さくらは、気を取り直してビルに向かった。
〈第4回へつづく〉
ご購入はこちら▶神永学『怪盗探偵山猫』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
▶神永学シリーズ特設サイト