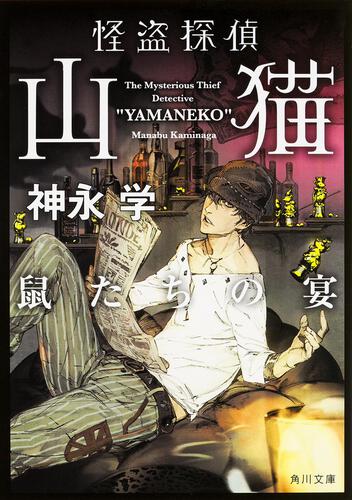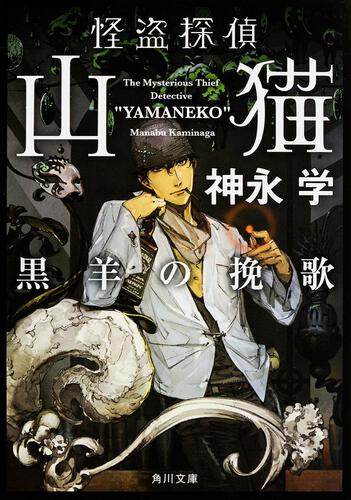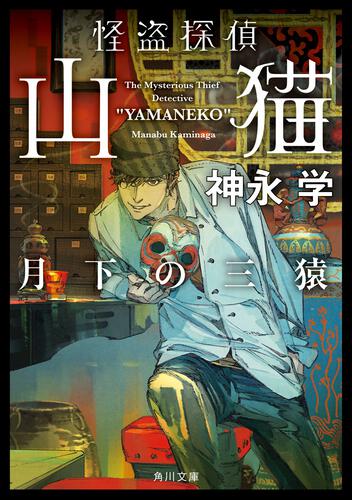さらば、山猫――!?
最強の敵が現代の義賊に襲いかかる。累計90万部の話題シリーズ、堂々完結!
ドラマ化もされ、話題になった「怪盗探偵山猫」シリーズ完結巻、
『怪盗探偵山猫 深紅の虎』がいよいよ刊行。
シリーズ完結を記念し、カドブンでは、シリーズ1冊目の『怪盗探偵山猫』の
試し読みを公開します。
希代の名盗賊の活躍をぜひお楽しみください。
>>前話を読む
3
勝村が、タクシーを降りるのと入れ違いで、ビルの前に停車していた救急車がサイレンを鳴らさずに走り去った。
──妙な胸騒ぎを感じる。
救急車がサイレンを鳴らさないのは、その必要がないからだ。
理由は二つ──一つは、収容する必要がないとき。そして、もう一つは、対象者が死亡していたときだ。
勝村は、今回、山猫が窃盗を働いた会社の住所を確認して驚いた。
今井の経営している出版社と同じ住所だったからだ。
だが、それだけで断定するのは早計だ。
今井の会社が入居しているのは、ビルの七階のフロアだ。山猫が入ったのは別のフロアかもしれない。
勝村は、胸騒ぎを振り払うように自分に言い聞かせ、タクシーの中で今井の携帯電話に連絡を入れた。
だが、呼び出し音が鳴ることなく、留守番電話に切り替わってしまった。
こういうときは、悪い方にしか考えられないのが人間の
勝村は、人ごみを搔き分け、立入禁止のロープの手前のスペースに、強引に身体を滑り込ませた。
「被害者が出たんですか?」
息を切らしたまま、隣にいるカメラマンらしき男に声をかけてみた。
イタリア人のように尖った鼻をしていて、口を囲むようにヒゲを生やしていた。いわゆる泥棒ヒゲというやつだ。
ニット帽を
「らしいね。強盗と鉢合わせて、殺されたんだと」
男は、露骨に不快な表情を浮かべながら答えた。
勝村は、それでもお構い無しに質問を続ける。
「被害者は誰です?」
「さあ、従業員かもしれないし、警備員かもしれない」
「入ったのは、何階ですか?」
「七階らしい」
男の言った一言で、勝村は
「そんな……噓ですよね。噓だって言ってください」
勝村は、男にすがる。
「私に言われてもねぇ……」
男は、面倒臭そうに言うと、カメラを構えて無作為にシャッターを切った。
話は終わりだ──そう宣言されているようだった。
勝村は、男への質問を
「あっ!」
勝村は、ビルのエントランスから出てくる女性の姿を見て、思わず声を上げた。
霧島さくら──。
勝村の大学時代の先輩だ。
──なぜ、さくらが?
疑問を抱いた勝村だったが、すぐに、大学卒業後、さくらが警察に入ったことを思い出した。
アップにした髪で
美人でありながら、飾りっ気がなく、
そんなさくらに、
かくいう勝村も、
「さくら先輩!」
勝村は、大きく手を振りながら声を上げた。
* * *
さくらは、頭の中で情報を整理しながら、ビルのエントランスを出た。
ロープの外にいるヤジ馬が増殖していた。
おそらく、半分の人間は何が起きたのか理解できていないだろう。人だかりがあるから、取り
光に群がる夏の虫のようだ。
「まったく……」
呟きながら、その場を立ち去ろうとしたさくらの耳に、聞き覚えのある声が飛び込んできた。
「さくら先輩!」
まさかと思いながら、ちらっと視線を向けると、ロープのすぐ前で大きく手を振っている男の姿が目に入った。
──やっぱり勝村だ。
大学時代と、全然変わっていない。
興奮気味にぴょんぴょん飛び跳ねている。
大学を卒業してからだから、五年ぶりの再会になる。さくらは、思わず表情が緩んだが、すぐに気を取り直した。
街中で偶然顔を合わせたのであれば、「久しぶり」と、話に華を咲かせるところなのだが、ここは犯行現場で、自分は刑事という立場だ。
さくらは、残念だが、気づかないフリをして、歩き去ることを選択した。
「ちょっと、さくら先輩! ぼくです! 勝村です!」
勝村が、ロープ沿いに、人を押しのけながら追いかけてくる。
ドラマでよくある、駅のホームでの別れのシーンのようになっている。
──恥ずかしいから止めて。
さくらのその願いとは裏腹に、勝村の声は止まらない。
周囲の視線が、自分に集中しているのを感じたさくらは、
「気がついてくれたんですね。良かった」
勝村が、まるで子どものように無邪気な笑みを浮かべた。
人がよさそうで、一見すると頼りない感じに見えるのだが、意外に
そればかりか、後先考えずに突っ走る無鉄砲なところもあったりして、見ていて危なっかしい。
母性本能を、くすぐるタイプだ。
本人に自覚は無いようだが、大学時代、年上の女性に絶大な人気を誇っていた。
さくらは、何度も勝村を紹介して欲しいと友人に頼まれたことがあるが、一度も応じたことはない。
「なんで、こんなとこにいるの?」
さくらは、勝村に詰め寄った。
「なんでって……ぼく、今は雑誌の記者をやってるんです」
「雑誌記者? 誰が?」
「ぼくです」
「噓でしょ」
さくらは、思わず笑ってしまった。
雑誌記者は、刑事と同じで、肉体と精神の
「噓じゃありませんよ。名刺もあります」
勝村は、ジャケットから名刺を出し、さくらに渡す。
その名刺には、大手出版社の社名の下に、ライターとして勝村の名前が書かれていた。
「それで、記者をやっている勝村は、犯行現場で偶然あたしを見つけて、情報を引き出そうってわけ?」
さくらは、わざと意地の悪い言い方をした。
自分が刑事でなければ、声をかけてこなかったと思うと、少し寂しい感じがした。
「そういうわけじゃないんですけど……」
勝村が、困ったように
その顔を見ると、いつもなんとかしてやりたいと思ってしまう。計算してやっているとしたら、なかなかの役者だ。
「教えてあげたいけど、あたしにも、
立ち去ろうとしたさくらだったが、勝村に腕を
「いや、そうじゃないんです」
「なに?」
「ぼくは、今井さんが無事だと確認できればいいんです」
目を見開き、必死の形相で勝村が訴えてくる。
「もしかして、今井社長と知り合いなの?」
「はい。ぼくの恩師なんです」
──そういうことか。
さくらは納得する。
勝村は、雑誌記者としてではなく、知人の一人として、今井の安否を気遣っている。
だとすれば、余計に何が起きたのか話すことが
だが、隠したところで、変えようの無い事実なのだから、いずれは勝村にも知れる。せめて自分の口から教えてやるべきかもしれない。
さくらは、そう考え、
「残念だけど、今井社長は、亡くなったわ」
改めて口にしたことで、その事実が重くのしかかってくる。
「えっ!」
4
犯行現場をあとにした勝村は、
農大通りの途中を曲がった先にある、有名なラーメン屋の隣。カウンター席しかない小屋みたいな店だ。
今井と飲む時には、いつもこの店だった。
飲み物のメニューはビールと
「いらっしゃい」
カウンターの向こうで声を上げたのは、
勝村が「あれ?」という顔をしていると、店長は身内に不幸があったということで、帰省しているのだと説明された。
一人で家にいることに耐えられそうになかった。
だから、この店で店長と今井の死を悼もうと思っていたのだが、肩すかしを食らった。
「何にします?」
勝村は、注文をとる男に、今井と共同でキープしてあったボトルを出してもらった。
いつもはウーロン茶で割るのだが、今日は氷を落とすだけにした。
勝村は、
下戸とまでは言わないが、酒に弱い勝村には、味の善し悪しは分からない。
独特のツンとした臭いが鼻から抜け、空腹の胃にアルコールが染み渡る。
──吐くほど飲まないと、強くなれないぞ。
今井によく言われた。
その度に、勝村は、アルコールに弱い方が、経済的だと反論をした。お決まりの会話だった。
勝村が、こうして雑誌記者としてやっていけているのは、今井のおかげだった。
──将来、小説家になりたい。
そんな夢を抱いた勝村は、大学四年の夏、就職活動もせずに出版社のアルバイトを始めた。
そのとき、配属された雑誌の編集長が今井だった。
今井は
だが、勝村は、それほど苦手意識を抱かなかった。
今井の怒りが悪意ではないことが、理解できていたからだ。彼の言っていることは、いつも正しかった。
勝村からしてみれば、裏表がなく接しやすい人物だった。
自然に今井にからむ仕事は、苦手意識の無い勝村に回されることが多くなり、接する機会が増えていった。
最初は、雑務だけを任されていたのだが、今井は、勝村が小説家志望だと知ると、ライターとしての仕事をさせてくれるようになった。
取材の方法も、記事の書き方も、全て今井から直々に教わった。
──情報を発信する人間は、何があっても噓を吐くな。
それが今井の口グセだった。妥協の無い今井に伝授された技術は、今の仕事の基礎になっている。
大学を卒業する頃、今井の推薦で正社員として今の会社に雇用された。
「クソっ!」
勝村は、急に噴き出した犯人に対する怒りから、カウンターを
グラスの半分も空けていないのに、酔いが回って来たらしい。
この店に来ると、今井はいつも自分の理想について語っていた。
──警察は、事件が表に出なければ、捜査をしない。だから、眠っている犯罪を発掘してやるのが、俺たちの使命だと思っている。
今井は、その理想のために会社を辞めて出版社を立ち上げた。
詳しく理由を
──最後に、今井さんに会ったのは、いつだったろう?
ふと、頭の片隅に疑問が浮かんだ。
ここ一ヶ月は顔を見ていなかった。電話で話したのも、二週間ほど前だった。
──勝村。俺は、信念が揺らぎそうだよ。
そのとき、今井は珍しく弱音を吐いていた。雑誌の売れ行きが、イマイチであることは知っていた。経営に行き詰まっていたのかもしれない。
「何か情報は入りましたか?」
声に反応し、勝村はゆらゆらと顔を上げた。
振り返ると、店の入り口のところに、一人の男が立っていた。ニット帽に
「さっきの……」
「
山根は、勝村の返事を待つことなく、隣に座るとビールを注文した。
「そちらは、何か摑めましたか?」
勝村は、山根の前にビールが置かれるのを待ってから
「いやぁ、全然ダメですね」
山根は、笑顔でそう答えると、グラスに注がれたビールの泡をすする。
「そうですか……」
「失礼な質問なんですが、被害者の今井さんとは、お知り合いだったんですか?」
「ええ」
勝村は、短く答え、メガネを外して涙ぐんだ目を
「そうですか……。実は私も何度か今井さんと仕事をしたことがありましてねぇ」
「そうなんですか?」
「ええ。さっき話を聞いたときは、本当に驚きました。惜しい人を亡くしました」
山根が神妙な顔つきで、泥棒ヒゲを
思わぬところで今井のことを知る人物に会い、勝村は救われた気がした。もしかしたら、今井が山根と引き合わせたのかもしれないとさえ思えてくる。
落胆し、沈んでいた気持ちが一気に浮き上がってきた。
「今井さんに」
山根が、ビールのグラスを掲げた。
「今井さんに」
勝村は、それに応じてグラスを掲げる。
グラスを合わせることなく、二人は同時にグラスの中身を流し込む。
「あの人、厳しかったでしょ」
勝村は、熱い息を吐き出しながら言った。
それと同時に、山根が何かを思い出したらしく、肩を震わせて笑い始めた。
「まったくだ。本当に厳しかった。何度もダメ出しをするんだよね。噓だろうって思いましたよ」
「そうそう、ぼくも原稿が一発で通ったことなんて、一度もないんです」
話し始めたことで、勝村の脳裏に、今井との思い出が次々と
今日は飲もう。今井の言いつけを守って、吐くまで飲もう。