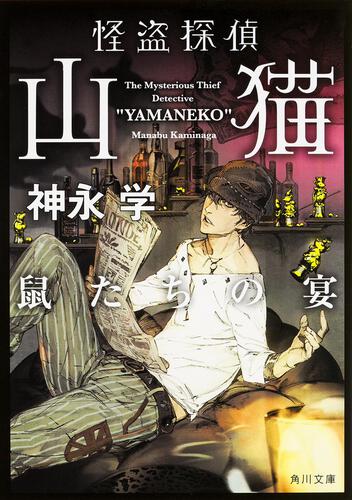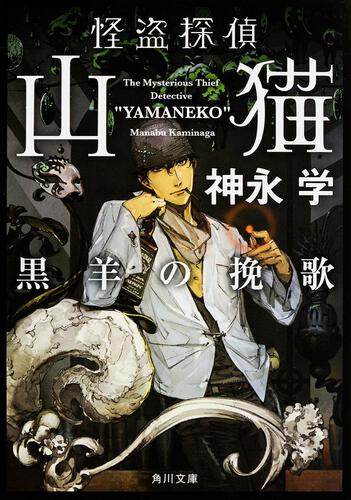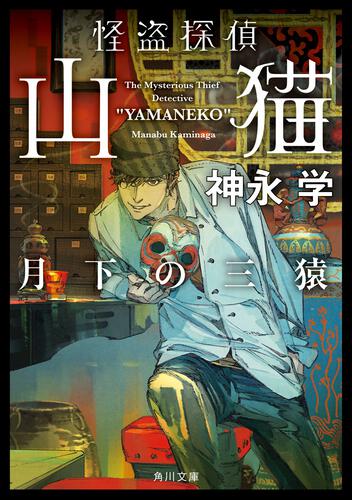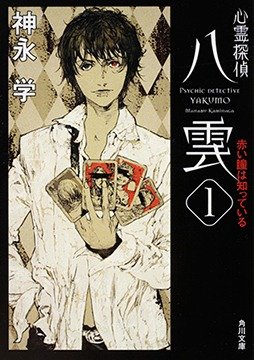さらば、山猫――!?
最強の敵が現代の義賊に襲いかかる。累計90万部の話題シリーズ、堂々完結!
ドラマ化もされ、話題になった「怪盗探偵山猫」シリーズ完結巻、
『怪盗探偵山猫 深紅の虎』がいよいよ刊行。
シリーズ完結を記念し、カドブンでは、シリーズ1冊目の『怪盗探偵山猫』の
試し読みを公開します。
希代の名盗賊の活躍をぜひお楽しみください。
>>前話を読む
14
さくらは、改めて今井の会社があるビルを訪れた。
夜間通用口のある裏口に回ると、そこに制服警官が二人立っていた。
「確認したいことがあるので、中に入らせてもらいます」
さくらは、警察手帳を提示し、裏口のドアからビルの中に入った。
廊下は、蛍光灯の光で満たされていたが、時間帯が違うだけで、ずいぶん不気味に感じられる。
──どこから侵入した?
さくらは、そのことを考えながら、ビルの一階の廊下を隅々まで見て回る。
このビルは、古い建物だ。夜の十時を過ぎると、エントランスは施錠され、出入りは裏口だけになる。
その裏口には、警備員が常駐して、有人警備をしている。
機械による警報システムは導入されていない。
「ここだ」
さくらは、トイレの前まで来たところで声を上げた。
トイレの換気用の窓から、ビル内に侵入できることは、今日、勝村が証明した。
さくらは、廊下を引き返し、エレベーターに乗り込むと、七階のボタンを押す。
ウィンチの巻き上げ音とともに、ゆっくりと上昇するエレベーターの中で、さくらは目を閉じた。
そもそも、今井は、休日の夜に、一人事務所で何をしていたのか?
答えを
さくらは、廊下を歩き、今井の事務所のドアの前に立つ。
目を凝らして見ると、ドアノブの
ドアを開けて中に入り、電気を
それと同時に、部屋の中央に黒い影が浮かび上がった。
「きゃっ!」
さくらは、悲鳴を上げて飛び
そこに立っていたのは、関本だった。
「せ、関本警部補……ここで、何を?」
さくらは、関本に
さっき、森田から聞かされた話が、頭に引っかかっていたからだ。
「お前こそ、何をしている?」
関本が、冷ややかな目で言う。
「確認したいことがあったんです」
「資料を見ればいいだろ」
「自分の目で確認しないと、気が済まない
「いっぱしの口を利く」
関本が、
「関本警部補は、なぜ?」
さくらは、自分の説明を終えたところで、改めて関本に尋ねた。
「お前と同じだ」
関本は、短く答えると、逃げるようにさくらの脇をすり抜け、ドアに向かう。
それが、もの
「あたしとは、捜査をしたくない──そういうことですか?」
さくらの言葉に反応して、関本がピタリと足を止めた。
「さっき、電話でも言った。お前は、刑事には向いてない」
関本の言葉は、さくらの胸を深く
「それでも、あたしは刑事です」
さくらは、振り返り、関本の背中を
関本は、まるで時間が止まってしまったかのように、しばらくそこに立っていた。
「その真っ直ぐさが、自分を殺すんだ」
長い沈黙のあと、関本は独り言のようにポツリと言うと、そのまま部屋を出ていった。
さくらは、その背中を見送りながら、なぜか既視感を覚えた。あの背中、前にも見たことがある。
だが、それが、いつなのかは思い出せなかった。
しばらく、そのまま立ち尽くしていたさくらだったが、息を吐き出して気持ちを切り替え、デスクの間を縫うように、ゆっくりと部屋の中を歩いて回る。
だが、さっきの関本の言葉が引っかかり、集中できなかった。
壁に寄りかかったさくらは、ポケットの奥に突っ込んであった名刺を取りだした。
昨晩、勝村から受け取った名刺だ。
そこには、会社の住所や電話番号の他に、勝村自身の携帯電話の番号も記載されていた。
「今井社長がどういう人間だったか、調べる必要がある」
さくらは、名刺に向かって呟いた。
だが、それが口実に過ぎないことを、さくらは自覚していた。
大学時代もそうだった。何か、
だから──。
さくらは、迷いながらも携帯電話を取りだし、名刺に書かれた番号に発信した。
15
──
不敵に笑う山猫に連れられ、勝村は、経堂の駅から歩いて十分ほどのところにある、路地の角に立っていた。
人通りはあまり多くない。
十メートルほど先には、八階建てのマンションが建っていた。あれが、目指す場所──。
最近建てられたものらしく、外壁もシックな色調で、高級感があった。
半円形のエントランスは、全面ガラス張りで、オートロック式になっている。
黒いパンツに、黒いシャツ、黒いニット帽という、全身黒ずくめの格好をした山猫は、その名の如く素早い動きで路地の角から飛び出すと、マンションを囲う植え込みの中に飛び込んだ。
しばらくして、植え込みの中から、山猫の手だけが出てきて、「こっちに来い」と手招きする。
誘われるままに、走り出した勝村だったが、植え込みの脇で転倒した。
「遊んでんのか」
山猫に襟首を
マンションの植え込みの間にできた、幅五十センチほどの狭いスペースに縮こまっていると、山猫が、双眼鏡のようなかたちをした機材を差し出してくる。
「これは……」
「見れば分かるだろ。暗視ゴーグルだ」
山猫は、バカにしたような口調で言う。
赤外線を使い、暗闇の中でも視界を確保できるという代物だ。それは分かったが、勝村に分からないのは、別のことだった。
「これを、何に使うんだ?」
勝村の質問を無視して、山猫は背負っていたリュックから、次々と道具を取り出し、勝村に手渡す。
先端にフックがつけられ、定間隔で結び目のついたロープ。小型のスプレー缶。さらには、黒い革の手袋。
両手にオモチャを抱えた子どもの気分だ。
暴漢たちに奪われたネックレスを奪還するため、協力すると約束したものの、何だか怪しい雲行きになってきた。
「四階の一番奥の部屋を見てみろ」
山猫が、指差す。
勝村は、言われるままに山猫の指差した四階の窓に目を向けた。
カーテンの隙間から明かりが漏れている。
「あの部屋が、どうしたの?」
勝村は、山猫に視線を移した。
「本当に、鈍い奴だな。あそこは、サキの部屋だ。お前を襲った奴らも、あの部屋にいる」
「どうして、あの部屋だって分かるんだ?」
「お前と同じマーキングだよ」
山猫が、得意げに鼻を鳴らす。
ああ、なるほど。勝村はここに来て合点がいった。
山猫が、勝村を助けに入ったとき、いきなり殴りつけて逃げることもできた。だが、そうしなかった。
おそらく、あの騒ぎに紛れて、どこかに発信機を仕掛けたのだろう。
噂に
「中に、あいつらもいるんだろ。取り返すのは無理だよ」
「泣きごとを言うな。俺が、無計画に正面から突っ込むとでも思ってんのか?」
山猫からしてみれば、こういう状況は日常かもしれないが、勝村にとっては、そうではない。
「いや、だけど……」
「ぐちゃぐちゃ文句を言うな。奪われたのは、お前の責任だろ」
「まあ、そうだけど」
「だったら、きっちり自分で取り返せ」
「ええ! ぼくが?」
勝村は、場所もわきまえずに大声を上げた。
「うるさい」
すかさず、山猫が頭を引っぱたく。
「でも、盗みは、ぼくの専門外だよ」
「だから、せめてもの温情で、俺様が手伝ってやるんだ。ありがたく思え」
「は、はい」
勝村は、山猫の勢いに負け、流されるままに返事をする。
「とにかく、作戦を説明するぞ」
山猫は、ノートを広げ、手早くペンを走らせ、マンションの見取り図を描き始めた。
* * *