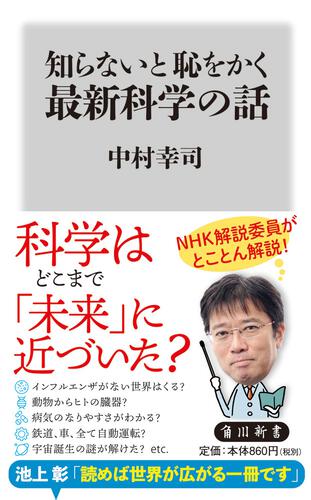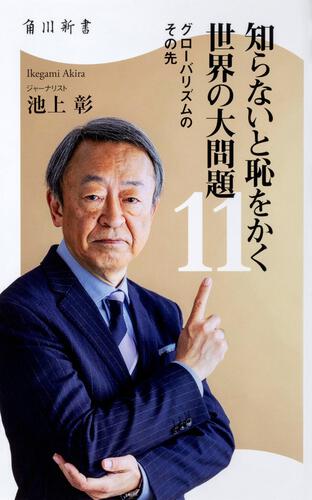緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの影響はまだまだ続いています。そして、心配なのは第2波です。今一度、感染症とどう向き合えばいいのか、人気の科学入門新書『知らないと恥をかく最新科学の話』(2019年3月発売)から抜粋します。
著者の中村幸司さんは、NHKの解説委員として、感染症にまつわる取材を重ねてきています。1年前には、パンデミックを解説するなど感染症への対策の重要性をいち早く訴え、いまあらためて注目を集めています(https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/319587.html)。本書でも、新型インフルエンザのケースを例に、感染症との向き合い方を解説。今あらためて読むべき内容です。
>>『知らないと恥をかく最新科学の話』試し読み【前編】を読む
■新薬と新型インフルエンザ対策への期待
毎年流行するインフルエンザの新しい治療薬が日本の製薬会社によって開発された。「ゾフルーザ」である。何日も飲み続けるのではなく、1回飲むだけで治療効果があるという使いやすさが特徴である。2018年以降、多くの患者に処方されるようになった。この薬で専門家が注目しているのは「使いやすさ」より「薬の作用の仕方」である。
インフルエンザのウイルスがヒトの細胞で数を増やす過程と薬の作用を見てみる。ウイルスは『ヒトの細胞に入り込み、細胞内で増殖し、細胞から出て、細胞膜の外側にくっついた状態になる。このあと、ウイルスは膜から離れて体内に広がる』ということを繰り返す。
タミフルやリレンザなどの薬は、ウイルスが細胞膜の表面から離れる段階でこれを抑えている。これに対して、ゾフルーザは細胞の中で増殖するのを抑えている。作用の仕方が違うため、新型インフルエンザが現われた際、従来の薬が効かなくてもゾフルーザは効果があると期待できる。
しかし、期待とともに心配も指摘されている。臨床試験のとき、この薬が効きにくいように変化した「耐性を持ったウイルス」が見つかったのである。仮にヒトの間で耐性ウイルスが広がると、インフルエンザ治療薬として使えなくなる恐れがある。使いやすいということで、多くの患者に投与する状況が続けば、それだけ耐性を持ったウイルスが出現する機会が増え、新型インフルエンザに対する切り札を失ってしまうかもしれないと危惧する専門家もいる。
この薬を毎年のインフルエンザや新型インフルエンザの治療薬としてどのように位置づけ、どのように使うのがよいのか、幅広い議論が求められる。
■感染対策は基本から
新型インフルエンザがどのようなウイルスなのかわからないだけに対策がとりにくい。
そう考えると、毎年冬の時期に心がけているインフルエンザの基本的な対策を徹底することの重要性も増してくる。手洗いやうがい、アルコールによる手の消毒などである。ウイルスを体内に入れないようにすることが肝心である。
感染拡大を抑えるには、患者の側の対策も一層重要になる。たとえば、マスクは、患者が着けることの効果は大きいとされている。感染の疑いが出てきた段階で周囲にウイルスを広げないようにすることが大切になる。また、インフルエンザのウイルスは、感染から1週間ほどは体内にいるとされている。症状がおさまっても、しばらくは多くのウイルスが体内に残っている。熱が下がっても、すぐ学校や職場に行かずに自宅で静養するなど必要な措置をとり、同時に周囲が患者に守らせることも必要である。
■社会で対策を進めることの重要性
新型インフルエンザによる健康被害を最小限にするには、社会全体で対策を進めることが必要になる。国民一人ひとり、あるいは海外の人も含めて地球規模で全体の対策を進めなければならない。
2009年の新型インフルエンザのときのように、海外で発生した場合は、国内に感染者が入ってくるのを防いだり、遅らせたりする対策がとられる。空港で入国の際、一人ひとりに発症の兆候となる症状がないかどうかや、感染が広がっている国への渡航歴がないかなどの聞き取りをする。旅客機の中で感染の疑いのある人が見つかると、その飛行機で近くに座っていた人を対象に健康状態を観察するなどさまざまな方法がとられる。
水際対策で完全に防ぐことはできなくても、国内に入ることを遅らせられるかもしれない。そうできれば、ウイルスの特徴の把握、効果のある薬の特定、ワクチン製造などの対策を進める時間をかせぐことができる。
■現代社会の新型インフルエンザの課題
当時の新型インフルエンザであったスペインかぜや香港かぜが流行したころと今では社会の構造が大きく異なる。ウイルスやワクチンの製造技術などの科学的研究が大きく進んだ。しかしこの間、グローバル化などによって、外国との人の出入りは桁違いに増え、対策が難しくなっている面があることは、肝に銘じておかなければならない。これは2009年と比べてもいえることである。
そうした中で、新型インフルエンザが出現しても、最小限の被害に抑えられるよう、今この時間を大事に使って、より有効な対策を進めなければならない。
■どうなる、どうする、そのほかの感染症
ここまで、感染症のうちインフルエンザや新型インフルエンザについて考えてきた。しかし、感染症で脅威なのはこれだけではない。
新型インフルエンザは、スペインかぜや2009年の流行のように、われわれはすでに経験している。さらに毎年流行するインフルエンザの対策も重ねてきている。その意味では、難しいといっても対策の準備を進めやすい側面をもつ感染症といえるかもしれない。
地球規模で脅威になる感染症は、ほかに、エボラ出血熱のように死亡率が非常に高いものがある。これまではアフリカなど特定の地域で感染が広がっても、WHOなどによって全世界的な拡大をしないよう抑え込むことができている。しかし、ひとたび地球規模で広がると日本にとっては未知の病気だけに、社会の混乱は輪をかけて大きくなる恐れがある。経験がないウイルスに対しては、ワクチンの備蓄や製造体制ができていない。そもそも有効なワクチンがない感染症もある。そうした病気と闘わなければならなくなるのである。
MERS(中東呼吸器症候群)は2015年に韓国で感染が広がった。この病気の原因となるMERSコロナウイルスは、ラクダからヒトへ感染すると考えられている。韓国では対応が遅れ、病院内で感染が広がった。日本では水際での対策などが進められ、このときは国内に感染者が入るという事態にはならずにすんだ。しかし、サウジアラビアなど中東の感染症と思われていたMERSが、一瞬にして隣国で感染拡大という極めて身近な脅威へと変貌した。感染症対策という側面において、現代社会が難しい問題を抱えていることの一端をみせつけられた。
この経験は決して忘れてはならない。
もはや、感染症対策はひとつの国では成り立たなくなっている。患者を発見したらその国内で感染が拡大しないよう最大限の対応をとり、水際対策を進めるなど世界各国が足並みをそろえて高いレベルの対策を実施することが必要になる。
2009年の新型インフルエンザを受けて、日本では「新型インフルエンザ等」の対策についての法律が施行された。注意してほしいのが「等」となっている点である。新型インフルエンザの対策も簡単ではないが、それ以外の感染症にどのように対処するのか、その対策の検討も進めておかなければならない。
【まとめ】
グローバル化は、感染症の脅威をさらに大きくしている。1980年代以降に世界中の脅威となったHIV(エイズウイルス)による感染症のように、それまで知られていなかった感染症が現れるかもしれない。現にMERSが初めて確認されたのは2012年、つい最近である。
人の行き来が盛んになり、これまで人が足を踏み入れなかったところの開発が進められている。特定の地域に限られていた感染症がその地域の外へと広がり、突然、人類全体の脅威にならないとも限らないのである。
新型インフルエンザに備えることと併せて、他の感染症や未知の感染症にまで視野を広げて対策に取り組まなければならないのである。
書誌情報
角川新書『知知らないと恥をかく最新科学の話』
著者:中村 幸司
定価:(本体860円+税)
発売日:2019年03月09日
ISBN:978-4-04-082224-2
頁数:240ページ
発行:株式会社KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/321711000164/