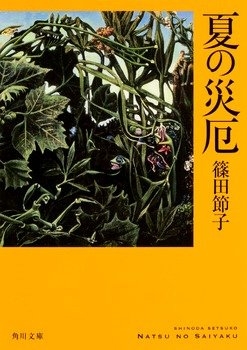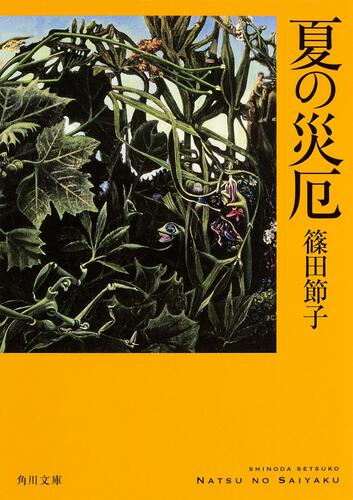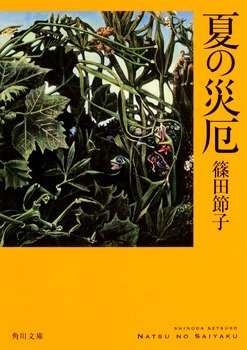コロナウイルスの脅威は未だ収まる兆しを見せません。この未曽有の危機に立ち向かうにはどうすればよいのか――。いまから25年前に発表された篠田節子さんの『夏の災厄』は、未知の感染症をテーマにしたパンデミック・ミステリです。前例の無い事態に後手に回る行政、買い占めに走る住民たち、広がる混乱と疑心暗鬼……。今日の状況を予見しただけでなく、この災厄を乗り越えるためのヒントも提示する本作の、冒頭部分を6回に分けて公開します!
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
1993年 埼玉県 昭川市
十一月も終わり、数日間ひどく冷え込んだ後、初秋を思わせるような陽気になった。午後の陽射しのまぶしさに顔をしかめながら、小西誠は車の揺れに身をまかせていた。
昭川市保健センターの一行を乗せたマイクロバスは、市のはずれ、窪山地区の曲がりくねった山道に入ったところだ。
十ほどある座席は、パートタイムの事務員と看護師、さらに洗面器や注射器の包みやワクチンの箱などで満杯になっていた。カーブにさしかかる度に、ステンレス製の器材がカタカタと音を立てる。
小西誠は、今日の仕事を確認するために、手元の資料に視線を落とす。これからニュータウン内にある小学校に、予防接種に行くのだ。
山の中腹に開かれたニュータウンは、市の東端にある繁華街から西北に向かって峠を二つほど越えたところにある。起伏のある曲がりくねった道を四十分、接種会場まではちょっとしたドライブだ。
一つ目の峠を越した。紅葉に陽光が降り注ぎ、大気が金色に煙って見える。錦織りなす景観と不釣合に、山の中腹に藤色の三角屋根がある。五年ほど前にできたラブホテルだ。
「あらあら、せっかくの紅葉がぶちこわしね」
事務員の一人がいう。
「そうねえ、あたしたちには、もう関係ないものねえ、でも中どうなっているんでしょ」
「さあ、小西君なら知ってるかな」
「はい、はい、なんでしょう?」
小西は笑顔を作って振り返る。彼はこの場でただ一人の二十代の独身男で、正職員だ。
ここにいるのは所詮はパートタイマー。管理するのは自分だ。彼女たちを「使いこなせ」なければ、一人前とはいえない。なめられるのはまずいが、「現場のおばさん」に嫌われたら、この仕事はやっていかれない。くだらない話に調子を合わせることも必要だ。そんなことを思いながら、就職以来五年、小西は予防接種の仕事をしてきた。
それにしても、なぜ自分がこんな中年女ばかりの出先機関に放りこまれたのか、今もってわからない。本庁には、もっとやりがいのある仕事があるはずだ。やはりコネもツテもないのが悪かったのだろうか。市役所などではなく、東京の企業にでも就職すればよかった。あのとき「長男なのだから、地元にいてくれ」と母親に泣きつかれ、いうことをきいたのが運のつきだ。
不満と迷いと後悔を身辺から振り払うように、小西は一つ伸びをした。
二つ目の峠を越え曲がりくねった道を北に折れると、急に目の前が開ける。広々とした丘陵一面に、高層住宅が林立する〝ニュータウン絹が丘〟の入口だ。
小西は、口元を引き締めて後部座席を振り返る。
「えー、それではいろいろトラブルは予想されますが、何かありましたら、私に確認をとって下さい。決して、自分で勝手に判断しないで」
言いかけてやめた。顔だけこっちに向けてはいるものの、女たちはだれも小西の注意など聞いてはいない。パートタイムとはいえ、メンバーは全員古株だ。何を若造が、と腹の中でせせら笑われているような気がしてならない。
しかしこの日行なわれる予定のインフルエンザの予防接種は、対処を誤ればとりかえしのつかない混乱の起こる可能性がある。正職員の自分が締めるべき所を締めなければ、と妙な責任感にかられ再び口を開きかけたとき、マイクロバスは急ブレーキをかけた。大きく車体が揺れて止まる。
外を見て、小西は舌打ちした。予想通り、いや予想よりも早くトラブルは起こった。「効かないワクチンはいらない」「危険なインフルエンザワクチンから子供を守れ」などと書かれたプラカードが目に入った。マイクロバスは、接種会場の小学校を目前にして数十人の主婦たちに止められたのだ。
「よせよな、まったく」
小西は車を降りていく。
妨害は予想していたが、こういう形で来るとは思わなかった。
「恐れ入ります、道を空けていただきたいんですが」
主婦たちに向かい、小西は頭を下げる。
「こんな危険な注射を学童にさせるなんて、あなたがたは、子供の命をなんと心得ているんですか?」
主婦の一人が、金切り声を上げた。
「えー、私は、現場をやっている者ですので、そういったことは、昭川市保健センター、管理課のほうにお願いしたいのですが」
丁寧に言っているつもりだが、相手を見下した態度が表に現れてしまうのは、小西の若さではしかたない。
「私たちは、今日の接種をやめていただきたい、私たちの子供に接種をしないでほしい、と言ってるんです」
「誤解です。あくまでインフルエンザは、希望する人だけに接種するものです」
小西は、詰め寄ってくる女たちを避けるように両手を前に突き出した。
「うちの子、卵でジンマシンが出るんですよ」
「だから受けたくなければ、受けなきゃいいんです」
「そういう問題じゃないでしょう。なんで、市は、こんな危険な予防接種をするんですか。インフルエンザに一番有効なのは、学級閉鎖というのが、定説ですよ」
主婦の一人が片手で眼鏡を直しながら言った。
「説はどうでもいいから、おたくの子供が受けなきゃ、それでいいでしょう」
小西は声を荒らげる。接種時刻が迫っている。
「あなた、市役所の職員? その官僚的な言い方なんなの?」
眼鏡の主婦が、両隣の主婦を押しのけて前に出てきた。
「なぜ、今まで強制的に学童に打っていた注射を任意接種にしたか。それはインフルエンザワクチンの接種事故がたくさん起きたからでしょう。しかも効果がなかったからでしょ。でも役所のメンツでやめられないから、任意接種にして、したくない人はしなくていいなんて、逃げてるだけじゃないですか。明らかに危険なことは、母親の責任において、野放しにできませんよ」
主婦に怒鳴られ、頭に血が上って、小西は早口で怒鳴り返す。
「インフルエンザは、任意接種なんかじゃありませんよ。予防接種法上は、あくまで義務接種です。ただどうしても受けさせたくないって言うから、希望者だけって規定をもうけただけです。母親の責任といったら、法律で定められた接種を受けさせることじゃないですか」
「その言い方が、官僚的だと言うのです。学童のインフルエンザは、寝ていれば治ります。学級閉鎖すれば済むことなんです」
官僚が、こんな行政の末端のそのまた端っこにいるものか。俺と同じ年で、県庁に派遣されて、課長補佐あたりに収まってるのが官僚ってものだ。俺のような下っ端を、吊し上げて何がおもしろいんだ。
心の中で悪態をつきながら、小西は時計を見る。
そのときだ。小西を主婦の真ん中に置き去りにしたまま、看護師たちを乗せたマイクロバスが学校の校門をめざして走り出した。
あっ、と言ったまま、小西はバスの後ろをながめる。
人質にしやがった……。
主婦たちも
冗談じゃない。ワクチンが効くか効かないかなんてどうだっていいことだ。
校門への坂道を一気にかけ上りながら心の中で叫ぶ。
こっちは仕事だ。だいたい検査を通過したワクチンでそんなにぞろぞろ死者が出るはずはない。国立予防衛生研究所作成の手引書には、インフルエンザワクチンがそんな危険なものだとは書いてない。何より自分は、事務職だ。ワクチンの効用や副反応の詳細などわかるものか。
やることはただ、一つ。予防接種法にのっとって、予防接種をすることだ。単純に考えなければ、現場の仕事などやっていられない。
息を弾ませて学校にかけつけると、大方の用意は整っていた。自分が指示する前に、いちばん
「そっちこそ、たいへんだったでしょ」
にっこり笑った房代の自信ありげな二重顎が、ますます気に入らない。
そのとき、もう一つ問題が持ち上がった。
医者が一人足りない。予定していた富士大学付属病院の勤務医が来ていないのだ。接種開始時刻は五分後に迫っている。
小西は腕時計と校門の方向を交互に見ながら、胃の痛くなる思いで待つ。
悠然とやってくる白衣の人影が見えたのは、富士病院に電話をかけようとしたときだ。老人だった。白い髪は不揃いに長く、頭のてっぺんだけ薄い。見慣れない顔だ。かさついた白い肌を通して静脈が透けて見える。目の色もごく薄い茶色で、なんだか爬虫類のような感じがする。
「あの失礼ですが……」
小西は言いかけた。
「富士大学病院だ」
そう答えると、老医師は顎を引いた。眉間にくっきりと縦皺を刻んだ気難しい顔。
「木村先生がおいでになるということでしたが」
小西は、予定されていた勤務医の名を言う。
「急患で手が離せん」
「あの……お名前を」
医師は黙って小西からペンをむしりとると、担当医のサイン欄二段分に、大きな字で自分の名前を書いた。
「辰巳秋水」
小西はぎょっとした。予防接種の登録医ではない。未登録の医師に接種させることは禁止されている。しかし辰巳は富士大学付属病院の医師だ。不用意に断わって機嫌をそこねたら、後が怖い。富士病院は市内にたった一つの大学病院で、数年前、市長が平身低頭して誘致したところなのだ。そのうえ健康診断や伝染病患者の隔離など、市はその保健医療事業のほとんどを委託している。
小西は慌てて保健センターに電話をかけ、担当の永井係長を呼び出し、判断をあおいだ。
「まずいな」
係長は開口一番言った。
「相手が、富士だろ」
「はい」
少し間をおいて指示が返ってきた。
「しょうがない、やってもらえ。来ちまったもの、追い返すわけにはいかんだろ。書類上は、登録医がやったことにしとけ」
「事故があったら困りますよ。ここに来る途中も、接種反対派のおばさんたちに捕まりました」
「あいつらか」
軽い舌打ちが受話器から聞こえた。
「
「ああ、わかります」
小西は、何度か市営の診療施設に派遣されてきたことのある鵜川の小柄な姿を思い出した。ゲイだという噂もあるくらいで、そう思って見れば、その形のいい坊主頭には、それらしい雰囲気が漂っていた。
「ま、とにかく今日のところは、それでどうにか済ませろ」
永井係長からそう言われ、小西は急いで教室に引き返す。
小学生たちが、すでに腕をまくり上げて並んでいる。しかし人数は驚くほど少ない。インフルエンザ予防接種の危険性が叫ばれてから、接種希望者が激減した。この日も全校で十二人しかいない。看護師たちはいささか拍子抜けした顔をしている。
この十二人のために、いったいいくらかかるのだろう、と小西は医者や看護師たちの人件費を頭の中で積算し、舌打ちする。
二、三人の子供が、辰巳秋水の前にやってきた。
やにわに辰巳医師は、カバンから緑色のゴム手袋を出して左手にはめた。その手で、子供の腕を摑む。手術を始めるようなものものしさに、子供と看護師はぎょっとしてその顔に目を凝らす。辰巳は、子供の腕にあらかじめ看護師がぬっておいたヨードチンキの跡をまじまじと見た。
「おい、君」
いきなり傍らの看護師を呼びつけた。
「こんな所を消毒すると、どこで習った?」
看護師は、縮み上がる。堂元がかけつけてきて、「手引書の通りです、先生」と同僚の代わりに答える。
「どこで作成された手引書だ?」
「あの、うち、昭川市保健センターで、その、医師会の指導に従いまして……」
今度は小西が、しどろもどろに答える。
辰巳は、ふん、と鼻を鳴らした。
「近ごろの医者は、予防接種のことを知らんのだ。いい加減にやっていいものだ、と思っとる。いいか、ヨーチンは、ここからここまで」
辰巳は予供の腕を上げて、腕の中程から肘までの位置を示す。子供は、今にも泣きだしそうな顔で辰巳の顔を見ている。
「そして接種する者は、腕を押さえる手から雑菌がつかないように、かならずゴム手袋をはめる。予防接種の基本的な心得だ」
他の医師は、ちらりと辰巳のほうを見ただけで、沈黙している。
そのとき教室の入口で、何やら言い争う声が聞こえた。
さきほどの主婦たちだ。
「なぜ、危険な接種をやめさせないんです」
「子供たちをワクチンから守ってください」
校長と養護教諭が、応戦している。
注射器を右手に持って、中の空気を抜きながら、辰巳医師は鋭い視線を主婦たちに投げかけた。
小西は、入口に走り寄った。
うるさい親に、得体の知れない医者。今日はいったいなんという日なのだろう。
「あの、すみません。お話はあちらでお伺いしますので」
小西は、主婦たちを廊下に押し返す。
そのとき、背後でがしゃりという金属音がした。辰巳が接種を終えた注射器をステンレスバットに叩きつけ、こちらにやってくる所だ。眉間の皺が、いっそう深くなっている。
「お願いします。子供たちのために危険な注射はしないで下さい。あなた方も人の親でしょう」
主婦の一人が辰巳に向かって叫んだ。
小西は辰巳がゴム手袋を左手からむしりとるのを見た。止める暇はなかった。
「ばかもの」という怒号とともに、辰巳は手にしたゴム手袋で、主婦の頰を張った。
声を上げる者もいない。そして今度は反対側にいた先程のインテリ風の主婦の頰をそれで叩いた。金縁の眼鏡がふっとぶ。
このときになって、一斉に悲鳴が上がった。
「先生、先生、やめてください」
小西は、慌てて辰巳の袖を摑み、主婦たちから引き離す。激高した女たちを校長やかけつけた他の教員がなだめる。
自分の椅子に戻った辰巳はこめかみの血管を膨らませたまま、肩で息をしていた。
「どいつもこいつも、ワクチンのありがたみを忘れておる。ほんの少し前までは、日本でも、子供が、年寄りが、若者が、インフルエンザでばたばた死んでいた。七十年前のスペイン風邪の流行のときには、四十万人が、死んだ。その後のアジア風邪では四万、その後の香港風邪のときも似たようなものだ。だれもが忘れておるのだ。あまりに豊かになりすぎて、平和ボケして、何もしなくても、病気になどかからん、と思っておる。我々が命がけで病原体を扱って作り出したワクチンを接種してもらい、病気にかからなくなると、針の穴ほどのことをあげつらい騒ぎ出す。たかだか一千万人に一人死ぬかどうかの問題だ。それだってたまたま弱く、特殊な者だけだ。死ぬべくして死ぬ者が死ぬだけだ」
辰巳は片手に注射器を持ち、針先を睨みつけた。気味悪そうな顔をして辰巳の前に腕を突き出している子供に向かい、もう一人の医者がそっと手招きする。看護師も子供たちを辰巳から離す。
「一度、疫病に見舞われてみれば、わかるのだ」
辰巳は叫んだ。
「何が、エイズだ。本当の疫病はあんなものではない。まず弱いものから死んでいく。はじめは、子供と年寄り、そのうち働き盛りの男や女、毎日毎日、どこかの家から白木の棺桶が運びだされる」
息が切れたらしくちょっと言葉を止めていたが、背もたれによりかかり、視線を宙にさまよわせ、今度は呪詛のように語り出した。
「病院が一杯になって、みんな家で息を引き取る。感染を嫌う家族から追い出された年寄りたちは、路上で死ぬ。知っておるか、ウイルスを叩く薬なんかありゃせんのだ。対症療法か、さもなければあらかじめ免疫をつけておくしかない。たまたまここ七十年ほど、疫病らしい疫病がなかっただけだ。愚か者の頭上に、まもなく災いが降りかかる……。半年か、一年か、あるいは三年先か。そう遠くない未来だ。そのときになって慌てたって遅い」
(第3回へつづく)
▼篠田節子『夏の災厄』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321411000060/