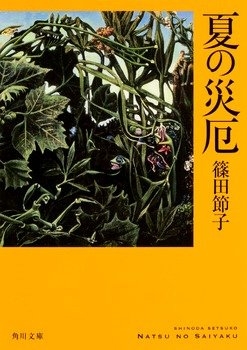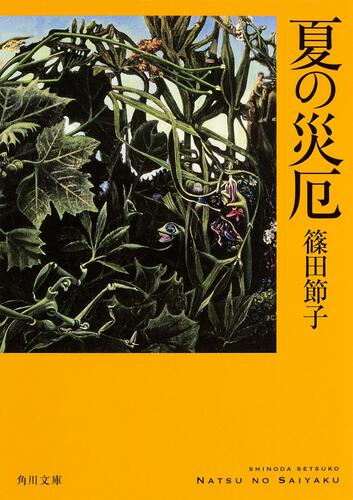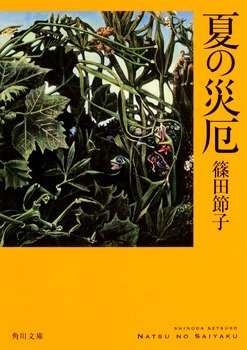コロナウイルスの脅威は未だ収まる兆しを見せません。この未曽有の危機に立ち向かうにはどうすればよいのか――。いまから25年前に発表された篠田節子さんの『夏の災厄』は、未知の感染症をテーマにしたパンデミック・ミステリです。前例の無い事態に後手に回る行政、買い占めに走る住民たち、広がる混乱と疑心暗鬼……。今日の状況を予見しただけでなく、この災厄を乗り越えるためのヒントも提示する本作の、冒頭部分を6回に分けて公開します!
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
第一部 予防法第七条
1
その冬は、保健センターの職員にとっては、肩身の狭い数カ月になった。センターの所長は市議会にひっぱり出されて、革新系の議員にインフルエンザ予防接種の効果の是非について詰問され、一方で上級官庁の役人に呼びつけられ接種率の低下について申し開きをさせられ、製薬会社からはおたくの市には薬を卸さない、と脅された。その上、インフルエンザという病気それ自体が、流行の兆しもないまま、やがて春が来た。
夕闇が迫る頃、堂元房代は愛用のミニサイクルに乗って、昭川市保健センターに向かっていた。自宅から市のほぼ東端、駅前商店街のはずれに位置する保健センターまでは、自転車で約二十分ほどの平坦な道程だ。せっせとペダルを踏んでいると、たちまち汗が噴き出してくる。房代は太っている上、普段からのぼせ性の暑がりだが、この春は特別だ。
数日前から町には春一番どころか熱風が吹き渡っている。それでも四月半ばのことで、夜になれば冷えるかと思われたが、日が暮れてもアスファルトの地面からは熱気が立ち上り、いっこうに涼しくならない。
駐車場脇の並木を見上げれば、遅咲きのはずの大島桜が夜目にも白い花びらを広げている。葉と花が一緒に出る種類なのに、ソメイヨシノのように花だけ開いている様は異様だ。
保健センターの裏手の通用口から入ると、心地よい風が上のほうから下りてきた。エアコンが冷房に切り替わっている。「窓を開ければ済むことなのに」とぶつぶつ言いながら、房代はロッカー室に向かう。
保健センターは、昭川市の保健医療行政の中心的業務を行なっている。管理部門は、車で十分ほど離れた市役所本庁にあるが、いくつかの現場を実際に統括しているのは、この三階建てビルの三階にある事務所だ。二階は乳幼児や妊産婦のための保健施設、そして一階が、堂元房代の勤務している夜間救急診療所になっている。しかし今の時間帯は、二階、三階は、すでに職員が帰った後で戸締りされている。
看護師不足のおりで、房代は、昼は予防接種、夜は夜間救急診療所の仕事、と掛け持ち勤務をしている。忙しいが辛くはない。予防接種の仕事は楽だが、単純過ぎて退屈だ。救急の仕事を房代は気に入っている。次は何が飛び込んでくるか、と身構えるときの、ぴりぴりした緊迫感がいい。
予防衣と呼ばれるエプロン型の白衣を脱いで、救急診療所のワンピース型の物に着替え、帽子をかぶると、気分が引き締まる。
胸にピンタックの入ったしゃれた白衣は、さる有名デザイナーのデザインによるものだ。看護師たちがカタログからこれを選んだとき、小西は「DCブランドの白衣ったって、みなさん3L、4Lでしょう」と、憎まれ口を叩いたが、「ガリガリに瘦せた小娘に夜間救急の看護師など務まるものですか」と看護師の中村和子に一喝され黙ってしまった。
房代は、若い頃の二倍もの太さになった体を白衣に押し込み、鏡に向かい、口紅を塗る。独身時代は、真っ赤な口紅を欠かさなかった。師長に注意されても、これだけは変えなかった。さすがに今はワインレッドにしたけれど、華やかな色の口紅は、白しか着られないナースの心意気だ。沈みがちな病人の心を引き立たせるのも、ナースの大きな使命だ、と思う。
孫の子守に明け暮れていた房代が、復職を決意したのは、五年前、亭主が定年退職したときだ。意気消沈した亭主とは対照的に、房代は、これから自分の本当の人生が始まるような気がした。そして今、様々な苦労はあるにせよ、どしりとした手応えを感じながら、第二の女盛りを迎えている。
ナースキャップをピンで止めつけ、派手な金色のイヤリングを外し、邪魔にならない小型のものに替える。初任給をはたいて買ったダイヤのピアスだ。仕事がら、落ちやすいクリップタイプはまずいと思い、娘が止めるのをふりきって皮膚科に行き、耳たぶに穴を空けた。
支度が終わると、胸ポケットに老眼鏡をつっこんで診療室に向かう。
診療開始時刻が迫り、待合室にはすでに数人の患者がいた。医者も揃っている。医者は、輪番制といって、医師会から日替わりで派遣されてくる。
窓口業務を行なっている事務員の青柳だけが、まだ来ていない。
「ちゃんとした病院なら、とうにクビね」
手早く薬品棚をチェックしながら、中村和子が言う。彼女は独身で、いくつかの総合病院の師長を務めてきた看護師歴四十年のベテランだ。定年退職後にここにスカウトされてきた。青柳が来ないので、房代が代わりに受付をする。
最初に診療室に入って来たのは、初老の男だった。丸椅子にどさりと腰を下ろすなり言った。
「先生、風邪ひいちまって」
「風邪かどうかは、こっちで判断することだよ」
内科医は、笑って言った。ペンライトで照らし、患者の喉を見る。そのとき男が目を閉じたのが受付にいた房代からも見えた。違和感があった。ややのけぞって大きく口を開けたとき、人の目は自然に開かれ、どちらかというと上を向く。しかし男は鼻のつけ根に何本も横皺が寄るほど、きつく目を閉じたのだ。
医師は男のシャツの前をはだけさせる。肌着の襟ぐりのU字形に皮膚が陽に焼けている。
「草刈りやってたら、頭、痛くなって」
男は訴える。
「ちゃんと、日陰で休んだ?」
「そんなことしてる暇ないもんで」
「水は飲んだのかい?」
「いや、草刈り終わるまでは、とてもとても」
「吐き気はする?」
そんなやりとりが始まった所に、「どうもどうも」と頭をかきながら青柳がやってきた。
房代は青柳の頭を叩く真似をして、持ち場につく。
「ちょっと熱計って」と医者に言われ、房代は患者を長椅子のほうに連れていった。顔は発熱のせいか真っ赤だ。
そのとき男は、房代に向かいぽつりと言った。
「いい匂いがするなあ」
「えっ」と言って、房代は首を
「何だろう。甘い、花みたいな匂いだ」
診療室の中に花はない。不思議に思いながら、体温計を手渡す。男は虫に刺されたらしく赤くなった腕をぼりぼりとひっかきながら、脇の下に体温計を挟む。
「なんだろう、つんとくる甘い匂いだ」
男は、急に顔を上げて言った。
「何もないはずだけど」
房代は首を傾げた。
花の匂い、甘い芳香……しかしこの診療室に漂っているのは、消毒薬の匂いだけだ。
同じことを言う患者が、昨夜も来た。
三十を少し過ぎたくらいの女だった。頭が痛い、吐き気も少しする、と言った。医者は上気道炎という診断を下し、ここは応急処置しかできないから、明朝、近くの医院に行くようにと指示した。患者は帰りかけたが、少し頭痛が治まるまで休ませてくれ、と言って待合室の長椅子に腰掛けていた。
受付の窓から様子を見ていた房代は、患者の体がぐらりと揺れて長椅子に横倒しになるのを見た。慌ててかけ寄ると、女は目を開いた。
「すいません。眠っちゃって」と言った女の手は、少し前よりも熱く感じられた。
「夢というのか、すごくいい花の香りがしてきて、真っ白な光が、さーっとかけ抜けていったんです」
女は言った。様子がおかしいと気づいて、房代は彼女をもう一度、診療室に入れた。医者はその場で紹介状を書き、患者を市内の病院に送った。
そして病院へ行くタクシーを待ちながら、待合室で患者は独り言のように繰り返した。
「看護師さん、香水つけてる? つんつんくるような匂いだわ」
あの時は気にも止めなかったが、今考えてみれば、奇妙な言葉だった。
二晩続けて、幻の匂いをかいだ患者が来た。ささいなことだが、心にひっかかる。普通の医院と違い、ここは毎夜、派遣される医師が替わるので、こうしたことは看護師しか気づかない。
体温を計っていた男は、医者に呼ばれて再び丸椅子のほうに行った。熱は三十八度だ。医者はカルテを書くと、中村和子に薬の処方を指示した。
男は医者に向かい何度かお辞儀をして立ち上がり、診療室を出ていこうとした。しかし耳鼻科医が患者の診察をしている脇を通った瞬間、顔を背けた。ひどく不自然で神経質な動作だ。よほど見たくないものなのか、と思い、ふと気づいた。さきほど喉を見たときと同じだ。あのときはペンライト、そして今は患者の耳を覗き込んでいた医師の帯額灯の光が、何かの拍子に目に入ったのだ。この患者は、ずいぶん光に敏感だ。
なんとはなしに気になってその男のカルテを見たのは、その日の診療が終了した後だった。
「熱中症」とゴム印が押してある。四月とはいえ、この暑さだから熱中症が出てもおかしくはない。しかし「匂い」という奇妙な訴えをした患者二人が、昨日は急性上気道炎、そして今日は熱中症と診断された。医師が毎日替わる救急診療所では、こんなことはめずらしくはないが、それにしても何かおかしい。今日の男性患者の住所は「窪山町」とある。町とは言っても市域の西のはずれ、山の中だ。
「どうしたの?」
外用薬のワゴンに白い布をかけながら、和子が尋ねた。
房代は手にしたカルテをそちらに向けた。
「花の匂いがする、とか、昨日も同じことを言う患者さんが来たのよ。あたし、耳鼻科じゃないから、よくわからないんだけど」
「そりゃ、早くちゃんとした病院行ったほうがいいわね。匂いだから鼻とは限らないわ。脳腫瘍の初期症状でそんなのがあるからね」
一通りの作業を終えて、和子は額の汗を拭う。
「脳腫瘍?」
「別に脳腫瘍に限ったことじゃなくて、匂いを感じる鼻がおかしいこともあるし、その情報を処理する脳の部位に異常がある場合もあるから」
「へえ、なるほど」
「ただしあたしたちは、医者じゃないからね。大学出たてのヒヨコだって、医者は医者。彼らの診断に口は出せないわ。彼らが熱中症と言えば熱中症、上気道炎と言えば上気道炎、せいぜい薬を渡しながら、明朝になったらちゃんとした病院に行きなさいとしかいえないのが辛いところね」
和子は着替える時間も惜しいらしく、白衣の上にトレンチコートをひっかけた。長身で、所帯臭さのない和子には、バーバリーがよく似合う。
「あなた、帰らないの?」と房代のほうを振り返る。
「ちょっと昨日の患者さんが気になってさ」
よいしょと掛け声をかけてしゃがみ込み、ファイリングキャビネットの鍵を開けて分厚いカルテの束を取り出す。
和子はちょっと肩をすくめ「熱心ね」と
(第4回へつづく)
▼篠田節子『夏の災厄』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321411000060/